
春場ねぎ 『五等分の花嫁』 : 「誠実への愛」の物語
いささか遅ればせながら、テレビアニメにもなり劇場用長篇アニメにもなった人気漫画を読んだ。
なぜ今頃なのかといえば、それは昨年夏の劇場用アニメの予告編で、その存在を初めて知ったからである。
もともとラブコメには興味がなかったので、その時は「今はこんなのが流行っているのか」と思っただけだった。
ところが先日、おたくライターのにゃるらさんが、児童心理学系のベストセラー本・宮口幸治著『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)のレビューを書いており、これがたいへん素晴らしい文章だったのだが、その中で本作を、
『さて、唐突ですが途中で言及した「五等分の花嫁」は紛うことなき名作です。彼女たちは単純に頭が悪いのでケーキを等分できませんが、そんな彼女たちが恋愛や夢に向かって勉学に勤しむ姿は感動があります。』
と紹介していたので、読んでみる気になったのだ。
「このレビューを書いた人が、ここまでいうのなら間違いない」と思ったのである。
さて、本作『五等分の花嫁』については、前記のとおりの大ヒット作で、すでに多くの若い人がレビューを書いているから、いまさらこの年寄りがあえて付け加えねばならないことなどほとんど無いのだけれど、それでもいくつか気づいた点について、指摘させていただきたいと思う。
まずは、本作の紹介。
『貧乏な生活を送る高校2年生・上杉風太郎のもとに、好条件の家庭教師アルバイトの話が舞い込む。
ところが教え子はなんと同級生!! しかも五つ子だった!!
全員美少女、だけど「落第寸前」「勉強嫌い」の問題児!
最初の課題は姉妹からの信頼を勝ち取ること…!?
毎日がお祭り騒ぎ!
中野家の五つ子が贈る、かわいさ500%の五人五色ラブコメ開演!!』

典型的な「ハーレム型ラブコメ」である。
ただし、その完成度が、極めて高い。作者がタダモノでないというのは、一読明白だ。
作者と本作の、優れた点を列記すると、こんな感じになる。
(1)絵が上手い
(2)性格描写、感情表現が的確
(3)キャラクターの(性格の)描き分けが巧みで、しかも類型に堕さない厚みがある
(4)14巻にもなる長編でありながら、伏線回収型のかっちりと計算された作品
この中で、(1)と(2)は当然として、(3)と(4)が生半可ではない。
(3)について言うと、『五等分の花嫁』というタイトルどおり、主人公は「一卵性」の五つ子で、それぞれに個性的な姉妹が、一人の少年(上杉風太郎)を好きになって、あれこれ葛藤するラブコメなのだが、この五つ子の描き分けが実にしっかりおり、かつ「五等分」というタイトルに恥じない「平等に厚みのある性格描写」になっているのだ。
そしてそれが、(4)の必要条件となっている。
つまり、最後に「風太郎の花嫁となるのは誰か?」という「謎(フーダニット)」において、「5人の容疑者」の性格描写が実にしっかりとなされており、誰が(「真犯人」に当たる)「花嫁」になるのかを容易に窺わせないだけの「魅力的な描写」を、5人について「当分」になしえているのである。

当然、これは生半可な力量でできることではない。単に「描き分ける」だけではなく、それぞれを「同程度に魅力的に描く」必要があるからだ。(ちなみに、犯人を「当てる」だけなら、比較的容易ではあろう)
しかも、「5人を当分に魅力的に描く」にあたって、「1つのエピソードを、5人それぞれに視点から(繰り返して)ドラマティックに描く」ということを、何度もやっていて、これも物語を「立体的に組み立てて、厚みを持たせる」能力がなければ、到底できないことだというのは明らかだ。
Amazonカスタマーレビューでも、「M.A.」氏が『この作品は「ラブコメ風ミステリ」ではなく「ミステリ風ラブコメ」です』というタイトルの、レビューと言うよりもむしろ論文と呼ぶべき長文を寄せており、私はこのタイトルを見ただけで「やっぱり先に指摘されていたか」と、このレビューを読む気にもなれなかったのだが、ともあれ本作が、『ミステリ』的な造りの作品であるというのは、じつに本質的なものなのである。
そんなわけで、本作は、単に「ハラハラドキドキのラブコメ」というわけではなく、全体がきっちりと計算され構築された、じつに「堅牢な作品」に仕上がっている。
単に「面白い」だけではなく、じつに「よく出来た作品」であり、その点で、生半可な作品ではないのだ。
ただし、それで「完璧」かというと、もちろんそうではない。
点数をつければ「95点」となり、この「残り5点」というのは、本作における「計算された構築性」や「完成度の高さ」をこそ、超え出ていく「何か」が足りない、という点なのだ。
無論これは、本作が「稀有な傑作」だと認めた上で、あえて付した「注文」なのだが、この部分は「創作」において、きわめて重要な部分であるからこそ、あえて指摘させてもらった。
どういうことかというと、なべて「創作」というものは、「計算」を超えていってこそ「非凡な作品=恩寵を受けた作品」になりうる、という事実なのだ。
例えば、「バランスは悪いし、欠点を挙げれば色々とあるけれど、しかし、ある一点において、この作品は歴史的な作品になった」というような作品を、誰もがひとつくらいは知っているのではないだろうか?
本作のように「最初から最後まで、ずっと面白く、しかも、全体としてよく出来ている」というのとは真逆に「途中まではイマイチ盛り上がりに欠けた作品だったけれど、ある時点から異様な迫力を発揮しだして、最後は読者を呆然とさせるような作品になっていた」というような作品である。

そして、そのような作品というのは、多くの場合、作品が「独り歩き」していったものであることが多いのだ。つまり、作者の「才能や能力」や「計算」による、コントロールを超えていった作品だ。
言い換えれば、同じ作者が、いくら頑張っても、同レベルの作品を描けないような作品。
だからこそ、天の「恩寵」を賜ったかのような「奇跡的な作品」、ということにもなるのである。
こうした観点から見た場合、本作には、そうした「恩寵」が感じられない。
すべてが、作者の並外れた力量に支えられた「作者の計算どおりに作り上げられた傑作」なのだが、だから「すごい」と思う反面、一抹の「物足りなさ」も禁じ得なかった。
すべては「緻密に計算された設計図どおり」であり、そこから溢れ出すような「過剰な何か」が、本作には感じられなかったのである。
そして、私がこのレビューで指摘しておきたいのは、「どうして、そうなったのか?」という、その理由についてである。
○ ○ ○
本作は、こうした「よく出来た作品」によく見られるとおり、「悪人」というのがほとんど出てこない。
読者が「気持ちよく読める」のは、ひとつには、本作で描かれる喜びや悲しみは、そのほとんどすべてが「善意や誠実や愛」によって引き起こされるものだからである。
人を好きになったが故の苦しみ。仲良し姉妹でありながら、同じ人を好きになったがゆえの葛藤と対立。
例えば、ほかの姉妹を出し抜いてでも、自分が風太郎の彼女になりたいと画策してしまう自分への嫌悪と、姉妹への申し訳なさや罪悪感などなど。
五つ子姉妹や風太郎やメインの登場人物のすべてが、それぞれに「誠実」だからこそ、彼女・彼らは、葛藤を抱えることになる。
だから、読者としても、仮に彼女らが「卑怯な手」を使ったとしても、それが「風太郎への愛」のゆえであり「自分の感情に正直であろうとしたため」の止むに止まれぬものであると理解できるから、本質的に「反感や不快感」を覚えることがないのだ。

もちろん、こうしたことも、本作作者なら、意識的にか無意識的にかは別にして、計算してやっていることだろう。だから、すごいとも言えるのだが、しかし、それが「弱点」になっているとも、私には感じられる。
つまり「読者に気持ちよく読ませる」という枠内でしか描けなくなってしまっているのではないか、それが「限界」になってしまっているのではないか、ということだ。
しかし、ではなぜ、そうなってしまったのだろうか?
それは無論、作者が「その方が読者が楽しめる」と考え、そう「計算した」からではあろう。
だが、多くの作家が、そのように考えながら、それでもある瞬間にその「矩を踰え」てしまうのは、なぜだろうか。
それは、現実とは、「気持ちがいい」だけのものではないし、また人は「気持ちがいい」だけのものでは満足できず「それ以上の何か」を求めてしまう存在だからではないだろうか。
では逆に、本作作者は、どうして矩を踰えずにいられたのであろう?
それはたぶん、作者が人一倍「誠実であること」にこだわる人であり、言い換えれば「裏切ること」への憎悪を、深く抱えた人だったから、ではないか。それを「どうしても許せない」人だったからではないだろうか。
私がこのように考えるのは、まず本作が「誠実さ」を描いた作品であるというのが、ひとつ。
例えば、五つ子たちの「風太郎への誠実」「姉妹への誠実」であり、「自身の恋愛感情への誠実」。
この物語は、複数の並び立たない「誠実さ」を求めるところに「葛藤」が生まれる物語であり、もとより「強固な誠実さ」がなければ成立しない物語なのだ。
そしてそれは、「犯人の行動が、終始一貫して論理的」でなければ「本格ミステリ」は成立しないというのと、同じような事情なのである。
したがって、本作は、登場人物が「誠実だからこそ成立する物語」(誠実な登場人物がすべて救われる、気持ちの良い物語)だと言えるのだ。だが、その「例外」が、まったく存在しないわけではない。
例えば、最も露骨に「不誠実」な人物として描かれるのは、物語の終盤で登場する「五つ子の実父」である。かつて「五つ子とその母」を残して、去ってしまった男だ。
この男のために、母子は大変な苦労を強いられたのであり、その意味で五つ子は、母への深い愛を持つ反面、この男に対しての未練は持たなかった。
ところが、そんな男が、物語の終盤で登場して、五つ子に関わろうとするのだが、その描かれ方は、はっきりと「悪役」であり、作者には、この男に対する一片の同情もない。
また、長女「一花」の所属するタレント事務所の社長の娘で、要は一度しか登場しない幼女「菊ちゃん」に関する(本作で私の最も好きな)エピソード(第5巻所収・第38話)において、幼い菊ちゃんが、父をおいて去った母への、複雑な心境を吐露するシーンがある。
幼いがゆえに母を恋うる気持ちを持ちながら、しかし、愛する父を苦しめた母を許せないと感じている、菊ちゃんの「健気さ」が見事に描かれたエピソードだ。

で、私が、ここで指摘したいのは、「五つ子の実父」であれ「菊ちゃんの母」であれ、この人たちが、例外的に「悪役」的に描かれてしまうのは、たぶん作者が「信頼への裏切り」というものに対して、並外れた「こだわり」を持っているからだと思うのだ。
つまり、そうした「コンプレックス」において作者は、「読者を喜ばせる」という「エンタメの原則」から、そこでは例外的に、逸脱してしまっているのである。
それでも「五つ子の実父」の場合には「最後にギャフンと言わされる」のであるけれど、「菊ちゃんの母」については、ただ「過去の悲しい事実」として語られるだけだからこそ、その「悲しみ」が「エンタメ的に昇華」されることがない。また、だからこそ、この小さなエピソードは、忘れ難い印象を残すのではないだろうか。
私は、何も「エンタメに徹することが悪い」などと言っているのではない。
ただ、本作作者ほどの「並外れた力量を持つ才人」をしても、善かれ悪しかれ、その「コンプレックス」が「無意識の足枷」になっているのではないかと感じられ、それは惜しいことだと思うのだ。
五つ子が、愛する姉妹のために、自分の恋を諦めようとする描写が何度かあり、その一方で、そうした自制は「自分の恋心に対する不誠実」であると指摘されるシーンも何度かある。
そう。人は「愛するものに誠実であろう」とするならば、あえて「愛する人を裏切ることこそが誠実である場合もある」のだ。
だから、これを作者自身に適応するならば、作者が「読者」に、そして何よりも「自身」とその「作品」に誠実であろうとするならば、時には「不快な現実」を描かなければならないこともある、ということなのである。
この物語がそうであるように、そうした「矛盾葛藤」を抱え、それを超えたところにこそ、真の「誠実」と「愛」があると、そのようにも言えるのではないだろうか。
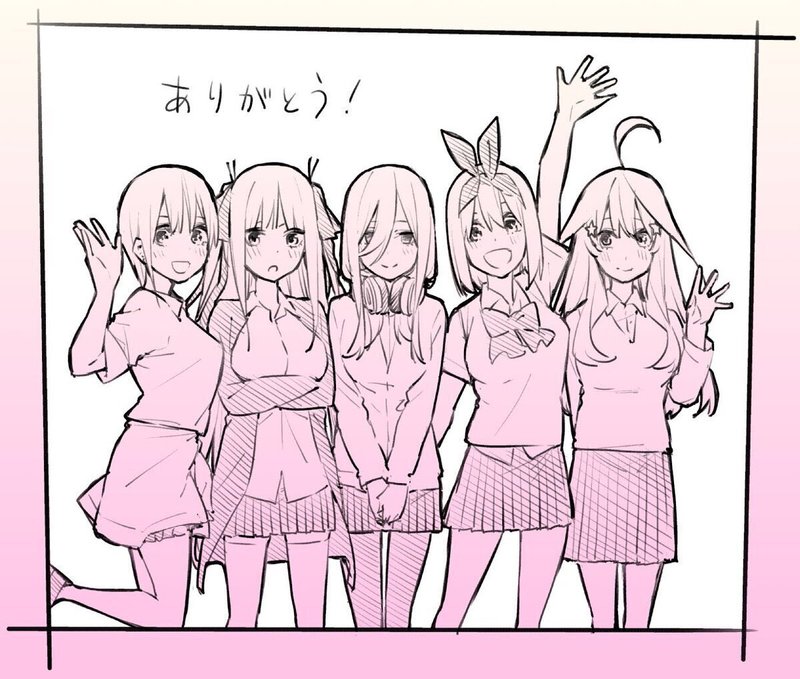
(2023年6月1日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
