
山田英生編『書痴まんが』 :〈書痴〉という聖なるもの
書評:山田英生編『書痴まんが』(ちくま文庫)
Amazonカスタマーレビューで、レビュアー「直いい親父」氏が「純粋に書痴に関する作品が少ないのでは・・・??!」と題して書かれているとおりである。
まったく適切な評価であり、かつ短文でもあるので、全文引用して紹介させていただこう。
『 純粋に書痴に関する作品が少ないのでは・・・??!
あとがきにもありますが、書物や書痴に関しての本は、フローベルを始め、けっこう出版されています。
アンソロジーで特筆すべきは、紀田順一郎の2冊があげられると思います。
漫画に関しては、筑摩文庫では「ビブリオ漫画文庫」に続き本書は2冊目になります。
全15編の作品が収録されています。
純粋に書痴に関する作品は、フローベルの作品を下敷きにした「愛書狂」くらいじゃないですかね?!
後は本に関するファンタジー系統の作品が多いように思います。
また、貸本、戦後の漫画創世記に作品も多いと思います。
諸星さんに関しては、「栞と紙魚子シリズー」(※ ママ)でもっと良い作品があるように思いますが・・・?』
「書痴」というのは、要は「書物への偏愛に狂った痴れ者」あるいは「書物への偏愛に狂った痴れ者状態」を指す言葉であり、普通に「本好き」「愛書家」「読書家」「作家」「(熱心な)出版関係者」を指す言葉ではない。
「好き」という当たり前の感情を逸脱して、「狂い」「痴れて」いなければ「書痴」とは言わない。
例えば、欲しい本を手に入れるために、散財して家財産を失うとか、人を殺すとか、文字どおり「気が狂う」といった状態か、それに近い「非常」の状態に達している者でなければ、「書痴」という表現は、大げさに過ぎよう。

たしかに、普通はあまり使わない言葉であり、人の目を惹くため、マーケティング的な意味合いでのネーミングなのだろうが、そういう「功利的=世俗的」な態度ほど「書痴」から遠いものもないのである。つまり、こんなことでは「書痴(処置)なし」なのだ(失礼)。
○ ○ ○
したがって、本書に「書痴」を期待してはならない。
あくまでも、普通に「本好き」「愛書家」「読書家」「作家」「(熱心な)出版関係者」にかかわるマンガ作品集だと考えて読むべきで、その分には、バラエティーに富んでおり、よほど熱心なマンガ読者でないかぎり今時は接する機会もないであろう古い作品も収録されているので、勉強にもなるだろう。
ちなみに、私は「書痴」や「愛書狂」ではない。「愛書家」であり「ビブリオマニア」くらいまでなら該当するだろうが、「書痴」や「愛書狂」と呼ばれるほどの、「豪の者」ではあり得ない。
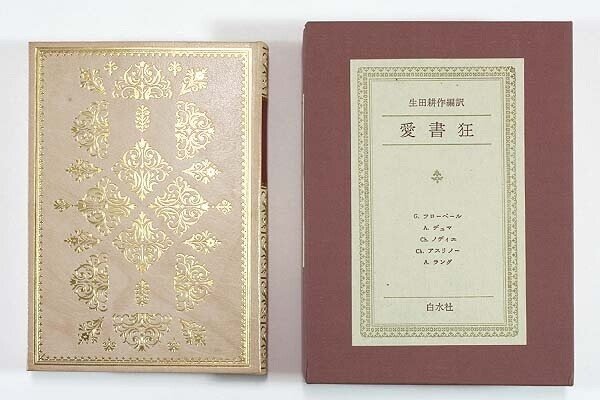
無論、私はここで「書痴」や「愛書狂」を見下しているのではなく、彼らを「突き抜けた稀種」として「特別扱い」にしているのである。
じっさい、「愛書家」や「ビブリオマニア」なら、世の中に掃いて捨てるほど存在するが、同じ「愛書家」や「ビブリオマニア」をして「狂気」を感じさせるほどの、突き抜けた「愛書家」や「ビブリオマニア」というのは、当然のことながら、めったにいない。
しかし、そういう境地に達していてこそ、「書痴=書物の痴れ者」「愛書狂=書物愛に狂った者」と呼ぶに値するのではないだろうか。
愛書家で知られる、フランス文学者で作家の鹿島茂の著書に『子供より古書が大事と思いたい』というタイトルのエッセイ集があるけれども、「書痴」か否かは、まさここがポイントなのだ。
つまり「子供より古書が大事」と思える者こそが「書痴」であり、そこまで行きたくても行けない「常識」が残っており、「痴れていない」のが「愛書家」や「ビブリオマニア」だと言えよう。
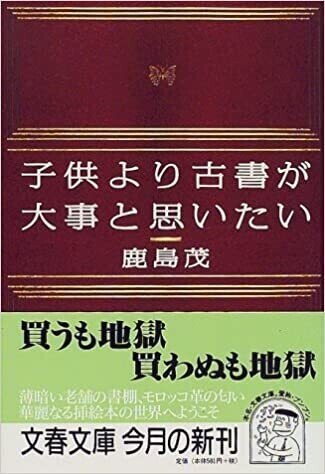
鹿島自身は、「書痴」の境地に憧れを感じつつ、しかし、そこまでは振り切ってしまえない自分に、一種の「物足りなさ」や「寂しさ」や「情けなさ」や「諦観」を感じているのだ。
言い換えれば、鹿島にとっての「書痴」とは、一種の「超越者」であり「悟りを開いた者(覚者)」であり、ある種の「憧れ」を持って鑽仰されるべき存在なのである。
一方、本書に登場する(作中の)人々は、たしかに「魅力的な人たち」であり、その意味で、おおむね「共感できる人たち」である。そして、そんな彼らを描いているからこそ、本書所収の作品は、いずれもそれなりに「愛書家」や「ビブリオマニア」の共感を呼ぶだろう。その意味で、それなりに「面白い」はずである。
しかし「書痴」という言葉にこだわりを持つような人間にとっては、本書所収作品に描かれた人は、所詮は「共感」可能な「人間=同類」でしかない。
だが「書痴」は、そうしたところから逸脱した存在であり、言ってみれば「アウトサイダー」なのである。
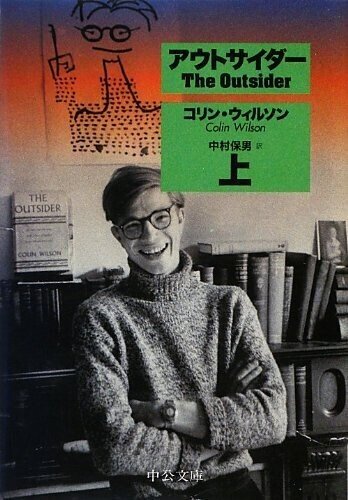
所詮は、無難に社会生活を営んでいる私たちとは違う境地に突き抜けてしまった人たちが「アウトサイダーとしての書痴」であり、私たち「本好き」が、「書痴」というものに惹かれる時、私たちはそれ(書痴)に「共感」したいのではなく、共感し得ない「圧倒的な存在」の前に「慄き」たいのだ。
言うなれば、私たちは、宗教学者ルードルフ・オットーが言ったところの『聖なるもの』としての「書痴」という存在に接する「非日常体験」をしたいのである。

だからこそ、その意味で本書は、決定的に「物足りない」のだ。
(2022年1月12日)
○ ○ ○
