
オタク・マニア・ファンの違い : ニコ・ニコルソン 『古オタクの恋わずらい』
書評:ニコ・ニコルソン『古オタクの恋わずらい』第2巻(KC KISS・講談社)
良い意味で裏切られた。第1巻よりも、ずっと面白くなっていたからだ。
見た目には、いかにも軽っぽい「ラブコメ」だが、作者の自伝的な内容が織り込まれているせいで、作り事ではない心理の機微の描写が素晴らしく、しばしば共感の感動で、うかつにも、うるっとさせられるシーンがいくつもあった。これは、間違いなくオススメだ。

この第2巻も、主人公・佐東恵の、42歳の現在時から、幕を上げる。
立派なオタクに育ってしまった恵の娘が、母が若い頃に作った、同人宣伝用の配布ペーパーを見つけ出してきて、恵が激しく動揺してごまかそうとする、コミカルなシーンである。
しかし、焦る恵に対し、娘はむしろその手描きのペーパーに感心しており、そしてじつに素直に「もう(※ マンガを)描かないの?」と尋ねる。
恵は「描くわけないじゃない」と答えながらも、心の中で「何かに夢中になることなんて、もうない気がする」とつぶやいたところで、本作の主たる舞台である、恵の高校生時代に移る。恵が「アニメとマンガ描きと同人活動に夢中になっていた、青春時代」へ。
じっさい、若い頃にマンガ同人活動をしていた人の多くは、就職や結婚、子供の誕生などとともに、そうした「趣味」を
、心ならずも捨ててしまったいるだろう。プロやセミプロになって金を稼げるようにでもならないかぎり、家庭を持った後も、趣味でマンガを描き続けるというのは、決して容易なことではないからだ。
しかし、かく言う私は、趣味の「文章書き」を、還暦を目前にした今でも続けている。そして、それが可能だった最大の理由は、私の場合は、結婚をせず、趣味第一に生きてきたから、ということになろう。
だが、もしも、私が「文章書き」の方にシフトせず、高校生の頃に少しだけ齧った「マンガ描き」を続けていたとしたら、それは今も続いていただろうか? いや、事実として、今「マンガ描き」をしていないのは、それ相応の必然性があったのだ。
私が「マンガ描き」を止めたのは、純粋に「才能がないと思い知ったから」である。つまり、客観的に「才能がない」だけではなく、それが自分でもよくわかってしまい、「この先も大して上達しない」「面白いものも描けないだろう」と、自身の才能と将来が見えてしまったので、描いていても、不満ばかりがつのり、少しも楽しくはなかったからである。
つまり私は、当時すでに、「マンガ描き」に関しては、完全に「眼高手低」だったのだ。
自他の作品を、客観的に評価する「眼」だけは持っていたのだが、それがマイナスに働いてしまった。いくら「描きたい」と思っても、ぜんぜん思ったように描けなければ、楽しくはないし、長続きしないのは当然である。
そしてこれは、「マンガ描き」以前の「趣味」であった「プラモ作り」でも、同じであった。
中学生の頃にはすでに、模型専門誌である『モデルアート』や『ホビージャパン』を不定期購読していたが、そこで紹介されているような作品が「自分には作れない、作る才能がない」と気付いて、やめてしまったのだ。
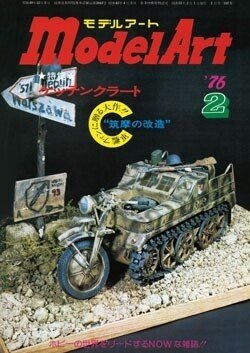
その点、「文章書き」については、最初からそれなりに満足のいくものが書け、書いていて楽しかったからこそ、今日まで続いているのであろう。
そしてこれは、私に「文才があった」ということではなく「文章に鈍感で、意図の伝達にしか興味がなかった」から、続いたのだと思う。「マンガ描き」に喩えれば、私は、自分の文章の「デッサン狂い」に気づく能力が無かったからこそ、楽しく書けた、というわけである。
マンガを描いていた頃の私は、自作について「デッサンが狂っている」「同じアングルばかりだ」「背景を描くのが苦痛なうえに、うまく描けない」「そもそも、ストーリーにオリジナリティーが無く、勢いもない」などと、描きながら、そんなふうに厳しく批評してしまっていた。だからこそ、まったく手が進まず、おのずと完成もせず、上達もしなかった。
そして、これは「プラモ作り」でも基本的に同じだったのだ。
ところが「文章書き」の場合、自分の下手さが、よくわかっていなかった。わかっていなかったからこそ「盲、蛇に怖じず」で、どんどん楽しく書いていき、そのおかげで、下手は下手なりに、読むに苦痛はない程度の文章を書けるようになっていったのだと思う。
私は、自分で「詩オンチ」だと公言しているが、そうした「繊細な言葉のセンス」が無く、ひたすら「洞察力・分析力・論理性・レトリック(比喩の的確さ)」で文章を書き、それで満足できたから、かえって良かったのだと思っている。
私が、「文章書き」の中でも「詩」や「小説」などの創作には進まず、もっぱら「批評・評論」ばかりを書いてきたのは、私の長所と短所が、そちら向きだったということだったのであろう。
つまり、何かに熱中できるというのは、ある意味では、他の何かが見えなくなる「才能」なのかもしれない。
○ ○ ○
さて、第1巻でも描かれたとおり、恵が好きになる、学級委員の梶政宗は、『死ぬほど嫌い』と口にするほどの、オタク嫌いである。
そのために、恵は梶くんに、自分がオタクだということを伝えられない。好きな梶くんに嘘をつくこと、本当の自分を知ってもらえないのは辛いことだが、同時に、これまで自分の幸福の源泉であった「アニメ好き=オタク」というものを隠すという行為には、大切なものに対する裏切りという後ろめたさがつきまとい、「二つの好きなもの」の間で、恵の心は揺れ動くのである。

さて、とにかく本当に「いいヤツ」である梶くんは、どうして「オタクが死ぬほど嫌い」になったのか。それが第2巻では描かれている。
要は、彼の母親が、家族の迷惑を顧みない、どうしようもないオタクだったのである。
梶くんの家庭は、父親の姿が見えないので、どうやら母子家庭のようだ。しかも、梶くんは長男で、その下に幼い弟妹が五人もいる。ところが、件の母親は、コスプレスナックを経営して生活費は稼いでいるものの、家事や子供たちの面倒は、すべて長男の梶くん任せっきりにしており、店に出ている時も含めて、いまだに「オタク生活」三昧なのである。
例えば、コスプレスナックだから、店にいる時に(アニキャラの)コスプレをしているのは仕方ないとして、店の宣伝だといって、街頭で、コスプレ姿で店の宣伝用のティッシュ配りをし、たまたま通りがかった恵と、その時のコスプレネタである『スレイヤーズ』で盛り上がるというのだがら、仕事というよりも趣味でやっているとしか思えない。また、幼い子供たちの保育園へのお迎えも、アニメを見なければならない時間だからと、梶くんに丸投げである。
これでは、いくら真面目で好青年の梶くんでも「オタクが死ぬほど嫌い」になっても仕方ないだろう。この母を許すことなど、できなくて当然である。

ちなみに、なぜ梶くんの家は、母子家庭状態なのか。父母は離婚しているのか、別居しているだけなのか。そのあたりはまだ描かれておらず、読者が当たり前に想像する「妻のオタクぶりに愛想をつかして離婚した」ということなのかどうかは、不明である。むしろ、このあたりに仕掛けがあって、ハッピーエンドへの伏線になっているのかもしれない。
○ ○ ○
さて、私がここで問題としたいのは、「オタクのイタさ」である。
今どきのオタクは、一般(大衆)化を経てソフィスケートされているから、「イタいオタク」というのは、ほとんど目につかないし、多くもないのかもしれない。

しかし、この作品の主たる舞台となる20年ほど前は、たしかに「イタいオタク」が少なくなかった。
ある意味で、当時の(そして、その少し前の)「オタク」とは、普通の人生を捨てたも同然の覚悟を持って、好きなことに没頭している、ある種の「エリート意識」を持った「少数者」だったからだ。
だから、身なりにかまわないだけではなく、もう人にどう思われようともかまわない。自分は「ゴーイング・マイ・ウェイ」で、自分の道を行くだけだ、という「アウトサイダー」意識すら持っている「豪の者」も少なからずいた。
したがって、彼らを「常識」を基準にして見れば、たしかに「イタい」のだから、当時の「オタク」が忌み嫌われたというのも、必ずしも無根拠なことではなかったのである(例えば、男性オタクの場合だと、現実の恋愛を捨てて、二次元の嫁に殉ずる、みたいな覚悟を語る者も少なくなかった。彼らは彼らなりに、二股を拒否する、おかしな倫理を持っていたのである)。

で、「第一次オタク世代」に属するであろう私(佐東恵は、第二次以降)は、「オタク」ではなかった。むしろ「オタク」に批判的だった。なぜか?
一一それは、私には「批評家」的な眼があって、「独り善がり」というのが、何より嫌いだったからである。
つまり「それしきのことで、エリートづらするな。そんな狭い範囲に限定すれば、くだらない瑣末な知識まで、持てて当然だろう。だが、そうではなく、当たり前のことは最低限当たり前に押さえた上で、そうした趣味的なものを持ってこそ、優れて趣味的なんだよ」と、おおよそそのように感じていたのだろうと思う。そして、こうした意識は、今でも「哲学(現代思想)オタク」などに向けられている。
私が「オタク(おたく)」が決定的に嫌いになったのは、1980年代後半、私が二十歳すぎの頃、大阪の中之島公会堂で開かれた、中規模の同人誌即売会を見物に行った時だった。
私は、高校の頃、漫画部に所属していたから、部誌や同人誌を作っていたが、即売会に出したことはなかった。まだ、関西では即売会は珍しいものだったし、そもそも私は、見知らぬ人に売ろうと思うほどの作品を描くことができていなかったので、売るものもなかったのであろう。
だから、この時は、雑誌などで知っている「同人誌即売会」なるものの見物に行ったのだが、そこで初めて、コスプレの実物を見て「ゲッ…」となり、そこにいられなくなったのである。
私が見たのは、高校生くらいのスレンダーな男子による、『ダーティペア』のコスプレだった。
ケイだかユリだかは記憶していないし、二人いたのか一人だったのかも記憶していないが、アニメ版のナンモ(ロボット)がいたことは覚えている。段ボール箱で作ったナンモの被り物を被っただけの、シンプルなネタコスプレだった。
このナンモから、私はこの『ダーティペア』のコスプレが、原作版ではなくアニメ版だとわかったのだが、それなりに似合っていたとは言え、男が『ダーティペア』の露出の多いコスチュームのコスプレをすることに対し、激しい拒否反応をおぼえた。「おまえ、そんなかっこうをして恥ずかしくないのか!」と思い、恥ずかしくなさそうなところが、余計に苛だたしかった。むしろ、こっちの方が、恥ずかしくて、いたたまれなかったのだ。
(ちなみに私は、早川書房が主催していた「DPFC」の会員であった)


(上が原作版の安彦良和画、下が土器手司デザインのアニメ版キャラ)
で、私は、オタクのこうした「自己相対視」能力の無さが、たまらなく嫌になったのだ。
「おまえ自身は楽しいかもしれないが、他人がお前をどう見ているのか、少しは考えろよ」、そう思った。オタクのそうした「自己満足」ぶりが、私にはたまらなく嫌だったのである。
だから私は、自身を「アニメファン」ではあっても「アニメオタク」ではない、と規定した。
「ファン」とは純粋に対象を「愛好する」者のことであり、「オタク」とは対象に没入して、それを私物化してしまう欲望に囚われた人種だと、おおむね、そんな「区別」をした。そして、こうした「区別=差異化」は、これが初めてではなかった。

(※ 「日本一のオタク」と呼ばれる庵野秀明も、「アニメファン」と「オタク」を使い分けている)
私は、自分と「行動様式」こそ似ていても、本質的に「別人種」だとして切り離した存在として、「オタク」以前に、すでに別のものがあった。それは「マニア」である。
今はあまり「マニア」という言葉は使われず、「オタク」のうちに含まれてしまっているようだが、私からすると「マニア」と「オタク」は、また違っている。
どう違うのかというと、「マニア」は「好きになった対象を研究し、誰よりもそれをよく理解しているという自負を持つことで、単なるファンとの差異を明確化したがる、一種の知的エリート志向が鼻につく人たち」であり、「オタク」の方は、もっと「即物的」に好きな対象に「耽溺」したがる人たちだ。
つまり、のちに評論家の東浩紀が定式化したように、「オタク」とは「動物化したポストモダン」であり、「マニア」とは、まさに「モダン(近代理性主義)」の範疇に止まった、その頽落形式なのである。
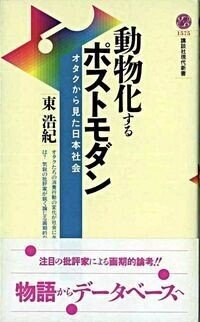
で、私は、「マニア」の薄っぺらな「知識偏重主義」が嫌いだったから、自身は「ファンではあっても、マニアではない。気持ちが大事で、知識の多寡など問題ではない」としていた。
ところが、そこに「気持ち」寄りの「オタク」が出てきて、それがまた「気持ち悪い」ということになると、「ファン」と「オタク」の違いも明確にしなければならない、となった。
そこで私の与えた「線引き」とは、「ファンは、捧げる愛」であり「オタクは、同一化する愛」だ、といったような差異である。
つまり、「ファン」は「プラトニック(精神的)」なのに対して、「オタク」は「肉欲的」なのだ。「オタク」は、欲望に身をまかせる、精神性を欠いた快楽主義者であり、そのために非理性的だが、そんなものは見苦しいし、汚らしいというのが、当時かなり潔癖症ぎみだった私の「線引き」であった。
で、歳をとった今は、昔ほどの潔癖症ではなくなったし、多少は寛容にもなったから、積極的に「オタク」を攻撃したりはしないし、人から「オタク」呼ばわりされても、わざわざ否定したりはしない。自分も、ごく大ざっぱに言えば「オタク」の一種だろうと認めてもいる。
一一だが、私には、「自己相対能力のない人間」への嫌悪は、今も抜きがたく残っている。
だから、梶くんの母親(不二子)の行状を、そのまま容認することはできず、梶くんが「オタク」を嫌いになるのも、やむを得ないものと認めるし、母親の不二子さんには、厳しく説教をしてやりたいとまで思うのである。「あんたみたいな人がいるから、アニメファンはバカにされ、白眼視されるのだ」と。
しかしだ、最初の方で書いたように、何かを盲目的に好きになるというのは、文字どおり、他の何かが盲目的に見えなくなる、ということでもある。そして、人間には「盲目的に好きになる」ということが、やはり、必要ではあろうと思う。それが無くては、人間として「大切な何か」が欠けているように思えるのだ。
つまり「人は、賢くなければならないけれど、賢いだけでは不十分だ」ということだ。
例えば「不倫」。
「不倫」は、論理的には「好ましくないこと」である。なぜなら、それは「他人のものに、手をつける」ということであり、その行為は、この社会を支えている「所有の論理」を、根底から揺るがすものだからである。
だが「好きになってしまったものは、仕方がないじゃないか」「好きになるのに理屈はない。気づいた時には、すでに好きになっていたのだから」という理屈も、現実として否定できない。
理屈としては「自制すべき」ことなのだが、それができないから「好きになってしまった」のだ。
では、どうすればいいのか?
結局、それに「正解はない」のだと思う。「一般解」などというものは無いのだ。
だから、人は、そのどちらか一方に開き直るのではなく、両立しえない両者の間で、誠実に葛藤するしかないのではないか。
そして、本作の主人公である高校生の恵は、こうした葛藤を、まさに誠実に生きているのではないだろうか。
「オタクとしての本性を、隠すか明かすか」といったことなど、つまらない問題だと思う人もいるだろう。
だが、人はそれぞれの立場で「あるべき自分」と「ありたい自分」の間で、揺れうごきながら生きているのであり、その葛藤があってこそ、まともな人間であれるのではないだろうか。
「ロボットのように正しく生きる、理性人間」でもなければ「欲望の追求のみに身を任せて生きる、動物人間」でもない。そんなところに、人間の「正しく生きる道」があるのではないか。
「二つの道」の間で揺れ動く、恵のこの先を、私は笑いながらも温かく見守っていきたいと、そう思っている。
(2022年6月26日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
