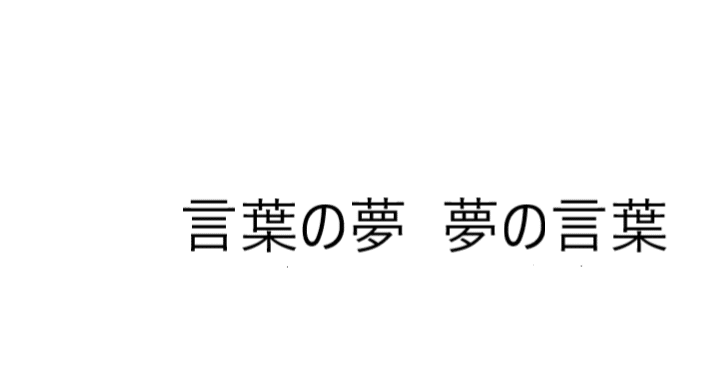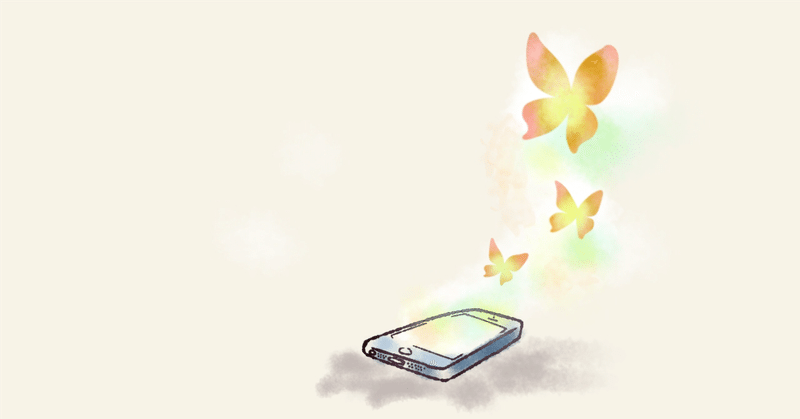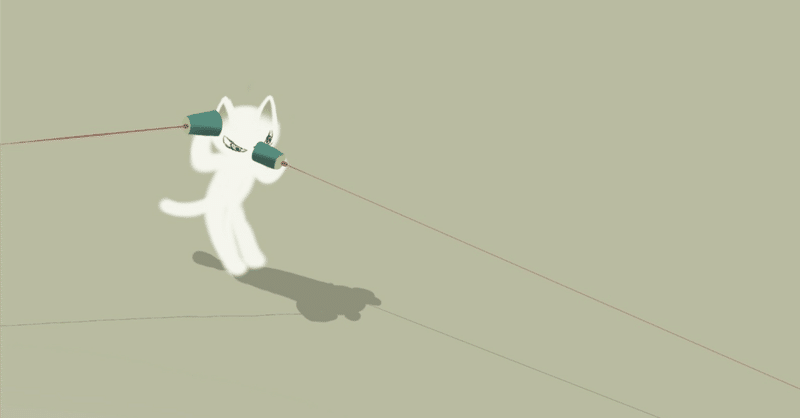2024年3月の記事一覧
蝶のように鳥のように(断片集)
今回の記事では、アスタリスク(*)ではじまる各文章を連想だけでつないでありますので――言葉やイメージを「掛ける」ことでつないでいくという意味です――、テーマに統一感がなく結びつきが緩く感じられると思います。
それぞれを独立した断片としてお読みください。
*
ない。ないから、そのないところに何かを掛ける――。
何かに、それとは別の何かを見る――。これが「何か」との出会い。遭
「読む」と「書く」のアンバランス(薄っぺらいもの・07)
◆第一話
文章を書くのは料理を作るのに似ています。天才と呼ばれる人は別なのでしょうが、私なんかはずいぶん苦心して文章を書いています。
勢いに任せて殴り書きする癖があるにしても、文章を書くのには手間と時間がかかるのです。
料理も手間隙かけてせっかく作ったのに、ぺろりと平らげられる場合があります。あっけないですが、作ったほうとしてはうれしいものです。
書くのに時間と労力を要するのに、さ
多層的で多元的なもの同士が、ある一点で一瞬だけつながる世界
「春」を感じるたびに連想するのは「張る」です。辞書の語源の説明には諸説が紹介してありますが、私は「張る」派です。
春になると、いろいろなものが張ります。木々や草花の芽やつぼみが膨らむのは張っているからでしょう。
山の奥でも雪解けが進み、川面が膨らんで見えます。道を歩く人たちの頬も上気したかのように見えます。細い血管が膨らんでいるようです。
山川草木、そして人が膨らみ張って見えます。膨張