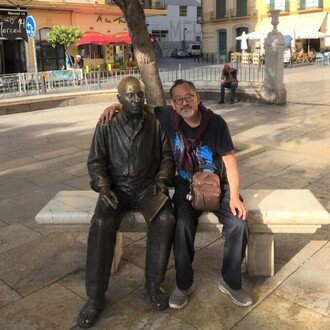#哲学
<書評>『水と夢 物質の想像力についての試論』
『水と夢 物質の想像力についての試論 L’Eau et les Reves: essai sur l’imagination de la matiere』ガストン・バシュラール Gaston Bachelard著 小浜俊郎・桜木泰行訳 国文社 1969年 原著は1942年出版
哲学者というよりも、夢想家的なイメージのあるガストン・バシュラールの主著である。多くの詩人や文学者さらに文芸研究家が、
<書評>『歴史の意味』
『歴史の意味―人間運命の哲学の試み― Der Sinn Der Geschichte, Versuch einer Philosophie des Menschengeschickes』ニコライ・アレクサンドロヴィッチ・ベルジャーエフ Nicolai Alexandrowitsch Berdjajew著 氷上英廣訳 白水社 1960年 『ベルジャーエフ著作集』の第一巻として発行された。原著は19
もっとみる<書評>『眼と精神』
『眼と精神 Eloge de la Philosophe L’oeil et l’esprit (原題を忠実に訳せば、「哲学をたたえて、眼と精神」)』 モーリス・メルロポンティ著 Maurice Merleau-Ponty 滝浦静雄・木田元訳 みすず書房 1966年発行 原書は、Editions Gallimard, Paris, 1953 et 1964 パリのガリマール書店が1953年及び1
もっとみる<書評>『ラスコーの壁画』
『ラスコーの壁画 La Peinture Prehistorique Lascaux ou La Naissance de L’Art』 ジョルジュ・バタイユ Georges Bataille 出口裕弘訳 二見書房 1975年 原書はGeneve, Suisse 1955年
原題を直訳すれば「芸術の誕生であるラスコーの原始絵画」。20世紀のフランスの哲学者であるジョルジュ・バタイユの名著の一つ
<書評>『悲劇の死』
『悲劇の死 The Death of Tragedy』ジョージ・スタイナー George Steiner 喜志哲雄 蜂谷昭雄訳 筑摩書房 1979年 原書は1961年
本書の内容は、もちろん本文が中心なのだが、スタイナーによる最後の解説的な第10章とそれを補足する訳者の解説は、最初に読むべきだと思った。最初に読んでいれば、本文の感じ方がかなり異なった気がする。
アメリカ人ジョージ・スタイナ
<書評・芸術一般>『デュシャンの世界』芸術とは生きること
『デュシャンの世界 Entretiens avec Marcel Duchamp(フランス語原題を直訳すれば、「デュシャンとの談話」)』Marcel Duchamp マルセル・デュシャン、 Pierre Cabanne ピエール・カバンヌ、Pierre Belfond ピエール・ベルフォン 1967年 Paris パリ。日本語版は、岩佐鉄男及び小林康夫訳 朝日出版社1978年。
20世紀最高
<書評>『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』
『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ Rosencrantz and Guildenstern are dead』 トム・ストッパードTom Stoppard 著 松岡和子訳 原著は1967年 翻訳は1985年 劇書房
20世紀を代表する不条理を描いた劇作家の一人、チェコ人ながら英語圏で成長した英語作家のトム・ストッパードによる、シェイクスピアの『ハムレット』に名前だけ登場する人物二人
<芸術一般・エッセイ>ナンデ君とダカラ氏との12の対話(そしてときどき、ワカッタ嬢の闖入)(後編)
6.ナンデ君「なんで、生き物を殺したらいけないのですか」
ナンデ君、少しわかったような顔をしながら、今日もダカラ氏の家を訪ねてきた。
ナ「死ぬことを避けなきゃというのは、なんとなくわかったんだけど、じゃあ、今度は殺すこと、もちろん人を殺すのはいけないのはわかっているけど、他の生き物、例えばハエや蚊、そしてゴキブリとかは、普通に殺していますよね。・・・これって、どうなんだろう?」
ダ「うん、
<芸術一般・エッセイ>関係の哲学
哲学というほどのたいそうなものではないが、この世の人と人とのコミュニケーションとか、人がどう生きているのかとか、なぜ私がここにいるのかなどの、いわゆる根源的な疑問・テーマについて考えることは、昔から哲学という名称を持っていたので、私もそのまま表題に使わせてもらう。
また、表題にある< >内の言葉は、noteマガジンの項目分けなのだが、そもそも<哲学>というマガジンを作っていない上に、私として