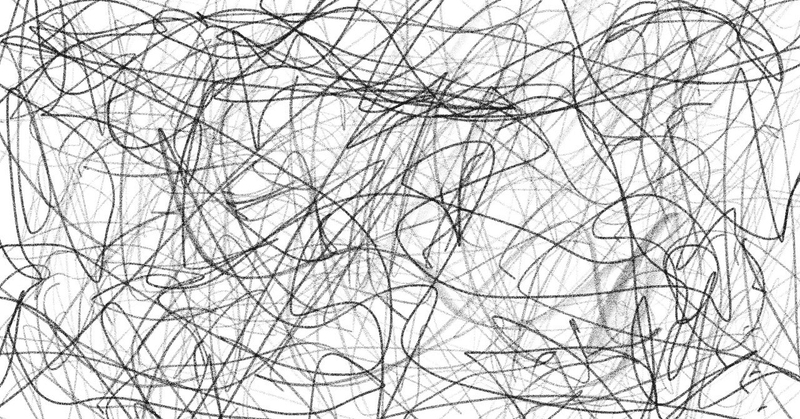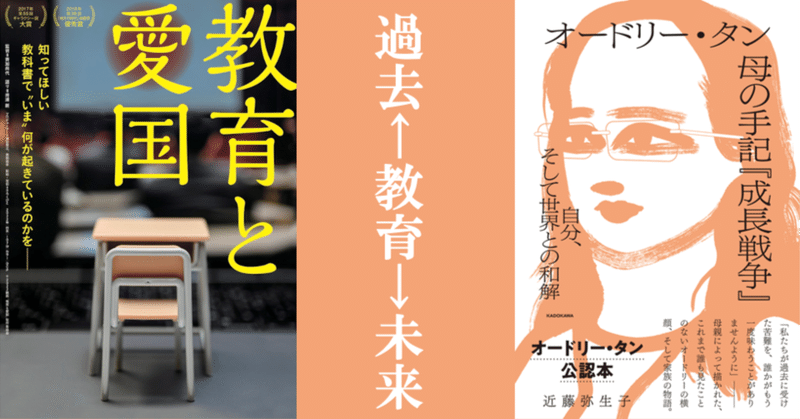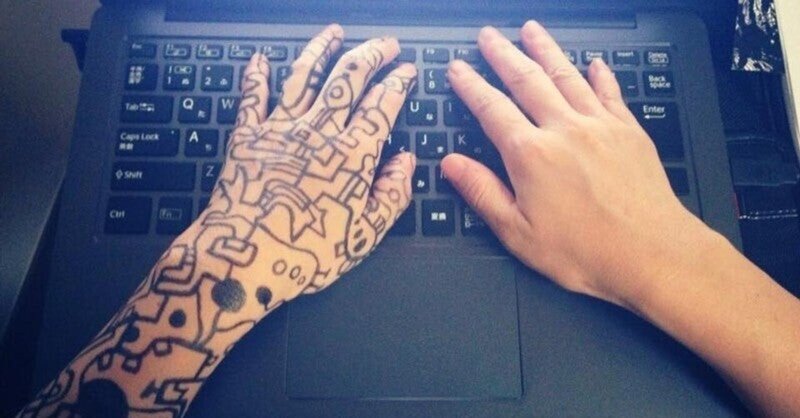- 運営しているクリエイター
#教育
子どもに怒るのと叱るのは違うと考えるのは危険
少し前に話題になっていてネットで目にしました。子どもが何か問題行動をした時に
怒るは感情が入っているからダメで叱るはしつけだけだから良い
みたいな話でした。色々な議論がなされていましたが、私はこういう考えはとても危険だと感じています。なぜなら一番大切なことが抜け落ちているからです。それは、
子どもから見たらどっちも一緒
っと言うことです。怒られようが叱られようが子どもからしたら一緒ですよ。
なぜあなたにメンバーはついてこないのか?
いつも記事を読んでいただきありがとうございます。
今回は「リーダーに求められる資質」について解説します。
リーダーに求められる要素皆さんはリーダーに求められる要素には何があると思いますか?
みんなを率いる統率力、みんなの心に火をつける情熱的な言葉など、他にも様々な要素があると思います。
しかし、真のリーダーは「リーダーシップ」だけ追及していてもなることができません。
それはなぜでしょうか?
上司は「天才」を「凡人」にしてはいけない
いつも記事を読んでいただきありがとうございます。
今回は「上司の役割」について考えてみます。
天才的な社員私の部下に入社1年目ですが、天才性を持った女性社員がいます。
彼女は学生時代に様々なことに挑戦し、一度自分が決めたことに関しては結果を残してきました。
大学院の時には突如アフリカに行くと言って、周りの反対を押し切り1年間アフリカで原住民と一緒に暮らしてきたというのです。
「女性一人で危な
部下のやる気を引き出したいなら、上司は「正論」を言うのは止めよう
もし、あなたに部下がいるなら、その部下から
「やる気出てきました」
「頑張れそうな気がします」
「仕事楽しくなってきました」
という言葉を聞くことができたら、きっとあなたは「嬉しさ」「安堵感」「期待感」「自己効力感」を感じるはずです。
今回は、あなたの部下からやる気を引き出すちょっとしたコツについてお話しします。
やる気が出ないのは、やらされ仕事だから「仕事でやる気が出ない」ことってありま
過去を向いた教育ではなく、未来の可能性のための教育にしていこう 〜『教育と愛国』と『成長戦争』の比較から
お疲れさまです。uni'que若宮です。
今日は久々に「教育」について書きたいと思います。
過去を向く『教育と愛国』の違和感先日、『教育と愛国』という映画を見てきました。
「愛国」という言葉があるように、政治的なテーマも半分入っていますが、日本の教育の問題について、改めて考える機会になりました。。。(教育に携わる方は是非みてほしいです。そして問題だと感じたらなにか変えるアクションをとっていき
組織は今いる戦力で最適化してはいけません
マネジャーの仕事の一つは、今いる戦力で最大の成果を出すことです。
そのためマネジャーは自分のチームで成果が最大限に出るように最適化します。
基本的にはこの方向性は間違っていないのですが、時として最適化しすぎることで弊害が出ることもあります。
今回は部分最適についてのお話しです。
社員は流動することを念頭に入れておく今いるスタッフを最適化するとは、例えば仕事を役割や、能力に応じて割り振って、
成長した姿を想像できるだけの感性を養うこと
どうも。藁科侑希(わらしなゆうき)です。
普段は大学教員やスポーツ現場でコーチやトレーナーをしております。
今日が444日目のnote投稿です。
本日はこちらの記事を読んで感じたことについて。
考える種が散りばめられているようで。
何度も繰り返し読んでいて、「あ、ここはこういうことかも」「もしかしたらもっと深掘りできるんじゃないか」などが想起されてきたんですね。
今日はそんな頭の中を書き留め
今いる社員だけでチームを最適化してはいけない
マネジャーの仕事の一つは、今いる戦力で最大の成果を出すことです。
そのためマネジャーは自分のチームで成果が最大限に出るように最適化します。
基本的にはこの方向性は間違っていないのですが、時として最適化しすぎることで弊害が出ることもあります。
今回は部分最適についてのお話しです。
社員は流動することを念頭に入れておく今いるスタッフを最適化するとは、例えば仕事を役割や、能力に応じて割り振って、
上司が身に着けておくべき、現場で起こる課題の解決手順
「(現場で)困ったことが起こっているので相談させてください」
私は障害者支援の仕事をしながら、企業に対して障害者雇用における困りごとを解決するための研修やコンサルティングの仕事を行っています。
その中でよく人事から相談を受けるのが「障害者を雇用している現場の管理者が対応に困っているので、何とかしたい」という内容です。
特に最近では精神障害、発達障害を持った社員の対応で相談をもらうことが多く、
129. 「嫌いな仕事をやってはいけない」違和感修正パワーアップ
パプアニューギニア海産の働き方を深く知ると「好きな日に出勤」よりも「嫌いな仕事をやってはいけない」のほうが人間の本質をとらえていて奥が深いと感じるようです。
人によって「好き嫌い」や「得手不得手」が違うなんて誰もが分かっているのに、なぜか一様に同じことをやらせようとする社会への違和感。