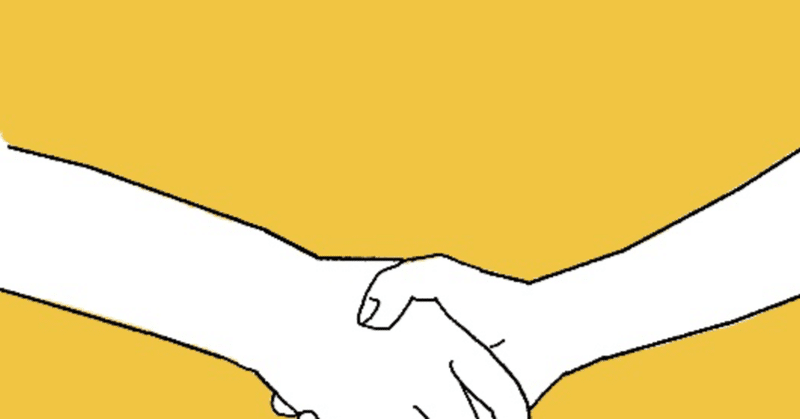
(小説)白い世界を見おろす深海魚 20章(帰り道)
【概要】
2000年代前半の都内での出来事。
広告代理店に勤める新卒2年目の安田は、不得意な営業で上司から叱られる毎日。一方で同期の塩崎は、ライター職として活躍している。
長時間労働・業務過多・パワハラ・一部の社員のみの優遇に不満を持ちつつ、勤務を続ける2人はグレーゾーンビジネスを展開する企業から広報誌を作成する依頼を受ける。
【前回までの話】
序章 / 1章 / 2章 / 3章 / 4章 / 5章 / 6章 / 7章 / 8章 / 9章 / 10章 / 11章 / 12章 / 13章/ 14章 / 15章 / 16章 / 17章 / 18章 / 19章
20
ほとんどの社員が平日よりも早めに退社する。午後10時を過ぎた頃、トイレに行くついでに広いオフィスを見渡した。デスクに着いているのは5人だけだった。
このペースでいけば12時前には仕事が終わりそうだ。
ぼくもデスクに戻り、明日の休日の予定を考えながら追い込みをかけた。
早足で歩く靴音が聞こえた。気にとめず、画面から目を離さないでいたが「いつまで働いているんだ」という怒鳴り声で、キーボードを叩く手を止めた。
社長だ。
電車に乗ることを嫌うため、彼の家はオフィスから500メートルも離れていない位置に建っていた。なんらかの用事でビルの前を通ったら、自分の会社の灯りが点いていたので様子を見に来たのだろう。
「今日は土曜日だぞ。いい加減に帰れ。働いてばかりいないで、週末ぐらい遊びに行けよ。ったく、若いヤツが仕事ばかりして」
先月で還暦を迎えたと言っていた。それなのに、こんなにも覇気が出るものだろうか。この会社にいる誰よりも怒鳴り声に力があった。緩んでいた空気が小刻みに震えだす。
社長は、後ろからぼくの肩を軽く叩いた。仕事に疲れた若手社員を労う言葉にも聞こえなくはないが……その裏側を誰もが知っていた。過剰な労働時間で労働監査から目をつけられているのだ。
最近は特にうるさいらしい。余裕のないギリギリの職場で働いている人間が、電車に飛び込む事件が多くなっている。コンプライアンス社会。過労が原因で死者でも出したら、この小さな会社は一発で潰れるだろう。そうならないためにも……もし、そうなったときのためにも言い逃れができるように、社長は社員に対して常に口うるさく「帰れ。休め」を連呼しなければならない。しかし、仕事量は減らない。手を抜くわけにもいかない状態。板挟みの社員はどうすればいいのだろう。
今、帰ると月曜までの仕事が仕上げられない。明日も休日出勤しなければならないのか……。諦めて、パソコンの電源を消した。圧倒的に仕事量の多いベテラン社員は、この災難に頭を抱える。社長に意見をしたのだろう。デザイン部の社員が社長に怒鳴られていた。
駅で塩崎さんと会った。先に見つけたのは、ぼくだった。
彼女は携帯電話になにかを打ち込んでいた。メールだろうか。画面を真剣な表情で見つめていたから、話し掛けようかどうしようか悩んだ。彼女は画面から目を離すと、ぼくに気づく。
「おつかれ」と近づいてきた。「無事に終わった?」
ぼくは笑って、首を横に振った。
「作らなきゃいけない資料が、まだひとつ残っているよ」
「ひとつでしょ? それならすぐに終わるよ。わたしなんて、シュゲンを10ページも残ったまま……」と痩せた肩を落とした。
「どこのクライアントの原稿?」
彼女は口元に手を当てて背伸びをする。内緒話の仕草。耳を寄せると、甘い匂いがした。こそばゆい息と共に日本橋にある製薬会社の名前がこぼれた。
あそこは月に一度、ドラッグストアに設置するパンフレットを作る。ひだまりの中で笑う家族の写真と健康法、季節の野菜を使ったレシピ等を掲載している。
「締め切りは、いつまで?」
ぼくの問いに彼女は答えなかった。しばらく前を向いたまま、一点を見つめている。視線の先には、白い光を放つ看板と看板。その間には不安になるほどの黒くくすんだコンクリートが貼り付いているだけだった。黙り込んだまま、そこだけに目を向けていた。
なにか悪いことでも言ったかな? いつのまにか泣く直前の子どものように唇をぎゅっと閉じている。その表情は悲しみと怒りが混じっている。
電車が入線する放送が響く。それでも彼女は足を地面にぴたりと付けたままだった。電車が止まり、扉が開く。休日のせいか吐き出される人の数は極端に少ない。ディズニーのイラストが描かれた袋を大量に抱えた家族が前を通り過ぎた。
「仕事の話しかないよね……」
ようやく塩崎さんの口が開いた。でも、ぼくはその言葉の意味が分からないで「えっ?」と聞き返す。
「わたしたちって、ほとんど仕事の話しかしたことないよね」
今度は強い口調。怒っているのか?
「うん、そうだね」
それしか話すことがないから……という言葉を飲み込んだ。彼女の機嫌をさらに損ねる気がしたから。
他の話題が欲しいのだろうか。趣味や好きな映画や、恋愛の話。人それぞれが抱えている柔らかい個人情報。そういえば、ぼくは彼女のことをなにも知らない。三日前に、キャスト・レオの関係者と食事をした際、休日の過ごし方を耳に入れた程度だ。
ぼくは今まで、こういった話題を避けていた。人間性を見られることを、どうしても隠したがるクセがある。多分、無意識に“つまらない人間”だと思われることを避けている。そんな評価をされて、人が離れていくのが怖い。それなら、最初から近づくための会話なんてしない方がいい。
「もう、同じ職場に勤めて1年以上になるのに、全然お互いのこと知らないんだよ」
彼女の責めるような言葉に「まぁ、うん……」と、自分でも情けなくなるほどの返事しかできなかった。
どうしたのだろう。
なにが彼女を不機嫌にさせてしまったのだろう。
その場から逃げ出したい衝動に駆られる。ぼくの態度に呆れたのか、彼女は唸るようなため息をついた。
高校生の頃からだ。ぼくは女性と会話すると、怒らせることがある。それは同級生だったり、デートに誘った女の子だったり、友達に紹介された女性だったり。
ほとんどの理由は分からない。ただ、喋りの上手い男のように女性を笑わせることができないから、せめて不機嫌にはさせないように気をつけている……にも関わらず相手の感情は“怒り”という、避けている方向へと向かっていく。そして、その感情は、ぼくに対して二度と変わることがない。塩崎さんも、か……。
早く次の電車が来ればいいのに。
今日は、もう誰とも話したくない。一人になりたい。
発車時刻を表示する電光版を見上げる。
あと、一分。
「お腹、空いている?」
予想していなかった塩崎さんの言葉に「えっ?」と聞き返す。
「ご飯、食べにいこうか」
列車の到着を知らせるアナウンスが流れる。彼女は、ぼくの腕をつかむ。
「交流会。おいしいものでも食べながら、今日は腹を割って話そう」と到着した列車の中へと引っ張る。
午前中の電話はなんだったのだろう。この後、予定があるのだと思っていたんだけど。ぼくは列車に乗り込む前に、もう一度今の時刻を確認した。
つづく
【次の章】
【全章】
序章 / 1章 / 2章 / 3章 / 4章 / 5章 / 6章 / 7章 / 8章 / 9章 / 10章 / 11章 / 12章 / 13章/ 14章 / 15章 / 16章 / 17章 / 18章 / 19章 / 20章 / 21章 / 22章 /23章 / 24章 / 25章 / 26章/ 27章 / 28章 / 29章 / 30章 / 31章 / 32章 / 33章 / 34章 / 35章 / 36章 / 37章/ 38章 / 39章 / 40章 / 41章 / 42章 / 43章 / 44章 / 45章 / 46章 / 47章 / 48章 / 49章/ 50章 / 51章 /52章 / 53章 / 54章 / 55章 / 56章 / 57章 / 58章 / 59章 / 60章 / 61章/ 62章 / 63章 / 64章 / 65章 / 66章 / 67章 / 68章 / 69章 / 70章 / 71章 / 72章 / 73章/ 74章 / 75章 / 76章 / 77章 / 78章 / 79章 / 80章 / 81章 / 82章 / 83章 / 84章 / 85章/ 86章 / 87章
リアルだけど、どこか物語のような文章。一方で経営者を中心としたインタビュー•店舗や商品紹介の記事も生業として書いています。ライター・脚本家としての経験あります。少しでも「いいな」と思ってくださったは、お声がけいただければ幸いです。
