
映画 『ある精肉店のはなし』 : 精肉と差別
映画評:纐纈あや監督『ある精肉店のはなし』
本作は、2013年の作品で、約10年ぶりのリバイバル上映だ。
こんなドキュメンタリー映画があったことなど知らなかったし、1週間の限定上映ということなので、この機会に観ることにした。
描かれるのは、大阪は貝塚市にある、精肉店「肉の北出」一家の仕事と生活である。
「肉の北出」のユニークなところは、牛を育てるところから、屠殺、解体、精肉、卸し、小売りまでのすべてを手がけている点だ。
さすがに子牛は買ってくるわけだが、それでも家族経営の店でこれだけやっているところは、10年前でさえ他にはなかっただろうし、今ではもう存在しないだろう。
この映画の冒頭で描かれるのは、「肉の北出」として最後となる屠殺・解体のシーンなのだが、この共用屠場が老朽化して廃止になるため、おのずと「肉の北出」も、自前での屠殺、解体は行えなくなったいうわけである。

では、現在、屠殺・解体作業が、どこで行われているのかと言えば、もちろん、今でも屠殺場は存在するわけだが、昔のような小規規模の共同施設などではなく、もっと巨大化しシステム化された、現代的で「工場的」な屠殺場において、一括大量生産的に行われるようになったのである。
この映画で描かれるわけではないが、こうした屠殺場の「巨大工場化」というのは、まず第一には「資本主義的競争原理による効率化」が進められたということであろうし、また文化的な側面からいえば「死の隠蔽」ということもあっただろう。平たく言えば、「屠殺」という「動物の命を奪う行為」の「見えない化」である。
そういえば、今では「屠殺」とは言わず、「屠畜」と言うようだ。あとで触れるが「殺す」という言葉を避けた結果であろう。
言うまでもないことだが、一見「残酷」とも映る「屠殺」という作業が「忌避される心理」は、わかりやすいものである。
学術的に「血穢の忌避」などと言ったところで、その内実は「生き物が殺されるところを見る」のは「怖い」ということに他ならない。
そして、なぜ「生き物が殺されるところを見るのは怖い」のかと言えば、それは無論「人間である自分も、いつかは死んで死体(物)になる運命であり、人間の生も永遠のものではない」という事実を、剥きつけに見せられることになるからなのであろう。そして、それ以降は「過剰な連想」による、不合理な忌避である。
しかし、当然のことながら、このようにして「動物の死」を隠蔽したところで、人間が他の動物を食べる以上は、どこかで動物が殺されているというの変わりのない事実だし、人間が食べるための動物を殺すことを職業にしている人もいるわけで、「肉の北出」が屠殺・解体をやらなくなったからといって、屠殺・解体が無くなったわけではない。
これは、「戦争」に関するニュース映像に「死体」が映らなくなったとしても、それで戦場における「死体」が無くなったわけではない、というのと同じことである。
むしろ、そうした「戦争」における「死の隠蔽」が、「戦争」の悲惨さに対する想像力を鈍らせ、「戦争」を「陣取りゲーム」感覚で捉えてしまう人を増やす結果となるのと同じで、「屠殺・解体」という作業の隠蔽は、私たちが「他の生き物の生命をいただいて生きている=殺して食うことで生きている」という事実を隠蔽するものでしかなく、私たちが「殺して食う」ことで生きている「動物」だという事実を忘れさせてしまう、問題のある行為だということにもなるだろう。
だから、私たちは「屠殺・解体」という、一見「残酷な行為」から、目をそらすべきではない。
「屠殺・解体」が残酷ならば、それは、それを必要としている「私たち自身が残酷」なのである。
だが、「他の生き物を殺して食う」という「生物としての、当たり前の営み」が「価値中立的なもの」であるなら、それは、「残酷」でもなければ、無論「心優しい」ものでもなく、ただ「必要なこと」でしかないことに気づくだろう。
「屠殺・解体」という作業は、「趣味」や「娯楽」でやっているのではなく、「生きるため」に止むなくやっていることだからこそ、「残酷」ではないし、許されることなのだ。

つまり私たちは、「見た目の残酷」だけで、それを忌避してはならない。そこから目をそらしてはならない。
「屠殺・解体」であれ「戦争における殺人」であれ、それは私たち自身の姿であって、「他人」の話ではない。「他人の残酷さ」ではないのである。
私たちが、今のところ「屠殺・解体」や「戦争における殺人」をやらないで済んでいるのは、良く言えば「それを他の人が引き受けてくれているから」であるし、悪く言えば「それを、一部の人に押し付けているから」に他ならない。
「屠殺・解体」と「戦争における殺人」を、ひとしなみに並べて語るな、というご意見もあるだろう。
だが、そうした意見は、たぶん何かを隠蔽して、「見たくない現実」をキレイゴトの中に回収しようとしているだけだと、私は思う。
「屠殺・解体」も「戦争における殺人」も、避けられるものなら避けたいのだけれども、やはり完全には避けられない現実的難問(アポリア)であるという点においては同じであり、どちらも「生存競争」における「生命」のかかった行為なのである。
○ ○ ○
本作冒頭の、屠殺・解体のシーンを見ても、特に残酷だとも思わなければ、ショックも受けなかった。その理由は、よくわからない。
もしかすると、私が40年間警察官をやってきた中で、人間の死体をいくつも見てきて、その中には腐乱死体や身体の潰れた墜死体といった、決して「きれい」とは言いがたいものが、いくらでもあったからかもしれない。
それに比べれば、屠殺場での牛の屠殺死体は、死んでいても「きれい」だったからなのではないだろうか。
牛を屠殺する場合、額のところをハンマーで叩くというのは知っていたが、私は、それで殺すのだと思っていた。だが、正確には、それで「気絶」をさせ、心臓が止まる前に解体作業を始めるのだと、この映画で知った。
心臓が動いている間に、喉のところを切開して頚動脈を切り、心臓が動いている間に素早く血抜きをするのである。
北出家での牛の飼育は、次男の北出昭さん(58歳・当時)が担当しており、彼が成長した牛を、家の牛舎から屠殺場まで、綱を引いて連れて行く。
せっかく、丹精込めて育てた牛に情の移らないはずはないが、しかし、彼はプロだ。彼は、食肉にするために牛を育てているのであり、それは誰かがやらなければならない必要な仕事なのだから、その時期が来れば、彼はその牛を屠殺場へと、自らの手で連れて行くのである。
その仕事から「逃げる」ことは、むしろ牛への背信行為なのかもしれない。

牛の額にハンマーを打ち込むのは、「肉の北出」の経営者である長男の北出新司さん(59歳・当時)の仕事だ。
この作業は、経験を積んだ新司さんであっても、いつも緊張すると言う。というのも、一発で気絶させるのは、牛に余計な苦しみを与えないためにも必要なことだし、一発で倒せないと、牛が暴れて危険だからでもある。
つまり、牛を屠殺場に入れ、ハンマーを構えた瞬間には、それまで感じていた「情」を振り捨てて、屠殺・解体作業に集中するのだ。そして、牛にハンマーを撃ち込んで倒した後は、すでに牛は、「肉」というものと化したのであり、後は、いかに良い肉に変えるかという、プロの作業が続くのである。
○ ○ ○
このように「精肉業」、特に「屠殺・解体」業というのは、リアルな仕事であって、「血穢」がどうとか、「可愛そうだ」「残酷だ」といったような、幼稚な話ではない。そこには、牛がいて、人がいて、肉ができる。それだけなのだ。
だが、そうした現実から、自らを無責任に切り離し、しかもそのことに自覚のない人たちが、「ファンタジックな理由」を捏造して、「差別」を生み出す。
「人間も生き物であれば、他の生命を食べて生きる」という当たり前の現実から目をそらして、「人間が、他の生き物の命を取る」ということに、なにやら「観念的な意味」を付与し、それで自分は何やら「次元の高い」ことを語っているかのような「勘違い」をする。
だが、それは所詮、人間が、そして自分自身が「他の生き物を食べなければ生きていけない、動物」であるという現実から目をそらすための、つまりは「現実逃避」のための「フィクション(虚構の物語)」でしかないだろう。
それは、人間が死んだら、「天国へ行く」とか「あの世へゆく」とか「西方浄土へ行く」といった「フィクション」と同根で、「人間も同じ動物であり、いずれは死んで土に還る」という物理的な現実からの、無用な怖れに発する、「逃避」でしかない。そんな「きれいごとの世界」が、あって欲しいという気持ちはわかるが、あるわけがない。しかし、人間は、それを求めてしまう。
そしてそれは、動物たちのための「慰霊碑」に掌を合わせる北出さんたちだって、多かれ少なかれ同じであろう。「人間に食べられるために死んでいく動物たちに、感謝しなければならない」というところまでは、合理的な心理なのだが、動物たちの成仏を祈るのだとしたら、それはもう「現実逃避」でしかない。
映画の中で、子供たちが北出新司さんに「牛を殺す」云々と質問した時、北出さんは「殺すとは言わへんねんで、鶏か
て、締めるって言うやろ。それと同じで ○ ○ と言うんや」というようなお話をなさっていた。
この「 ○ ○ 」の部分の言葉を失念してしまったのだが、私は、やはりその「言い換え」を好ましいものだとは思わない。どんなに言い換えたところで、「殺す」は「殺す」なのだ。
だが、屠殺の当事者である彼らには、やはりそれくらいの「ごまかし」は必要なのだろう。
いくら覚悟して引き受けていると言っても、この仕事に誇りを持っているとは言っても、誰もやらないで済む作業であったなら、何もすすんでやるわけではないはずだ。やはり、やらなくていいのならやりたくないだろうし、その意味でも、心理的な負荷は否定できず、だから「殺す」という剥きつけの言葉は避けたいのだろうと思う。「殺す」という言葉を「禁忌(タブー)」化するのだ。それに触れないよう、遠避けるのである。
○ ○ ○
この映画を観て「差別はいけない」といった感想を持つのは、当然ではあるが、思考停止でしかない。
そもそも、この映画を観に行く人の99パーセントは、自分が「差別反対者」だと自認しているだろうし、事実、差別に反対しているだろう。現に差別を受けている人(被差別当事者・差別被害者)もいるだろう。
だが、そんな私たちが考えなければならないことは、私たちの中にも「差別」を生む感情があり、北出さんたちの中にだって、それがあるという、事実である。
「差別感情」が、全く完全に無いような、「神様」のような人間は存在しないし、その「神様」も存在しない。しかし、私たちは、自分がその「存在しない神様のごとき存在」だと、容易に信じてしまえるのである。だから「差別は、永遠になくならない」のだ。
差別は「する人とされる人」に、二分されるのではない。
ある場面で「差別する人」が別の場面では「差別される人」になり、あるところで「差別されていた人」が別の場所では「差別する人」になる。それが現実だ。
だから私たちは、「差別に反対する、差別しない人」という自認ではなく、「差別しないために、差別に反対する人」という自認を持つべきだろう。私たちは皆「差別しながら生きている」人間という「生物」なのである。
○ ○ ○
この映画を観ていて感じたのは、そこに移されている町の風景が、10年ほど前のものでしかないにもかかわらず、私が子供の頃の、近所の風景に似ている、ということだ。つまり、50年も前の風景に似ていると感じられたのだ。
それはフィルムの性格による「色調」の問題もあっただろうが、しかし、北出家の古い家屋の室内の、いささかごちゃごちゃした感じだとか、北出家の人々の、いささか垢抜けない濃い顔立ちだとか、そういうこともあったはずだ。
私が子供の頃には、こういう室内が当たり前にあり、こういうおっちゃんおばちゃんが当たり前に歩いていたのだが、いつの間にか、そういう人たちを見かけなくなってしまった。みんな、妙に垢抜けしてしまったのだ。
だから、私は、こうした室内や、人々の顔を「懐かしい」と感じていたのである。

そう言えば、私が子供の頃には、あちこちに空き地があって、今から思えば、家から500メートルほどしか離れていない一級河川沿いの広い土地には、豚舎があった。
私たちはそれを「豚小屋」と呼んでいた。そして、日により風向きによって、豚舎の方から、糞尿の臭いがしてきて、私たち子供は「くさい、くさい」と言って、鼻をつまんでいた。だから、豚舎の方に近づくことはなかった。
また、これも家から200メートルほどしか離れていないところに、古ぼけた平家の町工場があり、表にはドラム缶が並んでいた。中まで覗いたことはなかったが、この工場の出入り口付近のコンクリート舗装された道路は、油染みで黒光りしており、その工場の周辺には、いつでもかなり強い異臭が立ち込めていたので、私たちは、その工場の横と通るときには、息を止めたものである。
たしかめたことはないのだが、今はもう存在しないその工場は、「石鹸工場」だという話だった。
石鹸と言えば、あんなに良い匂いがするものなのだから、こんな臭い工場で石鹸を作っているなどという話は眉唾だと思っていたのだが、この映画では、解体した牛から取れた脂身を石鹸工場におろしているという話だったので、実際、あの工場は「獣脂」をつかった石鹸工場だったのかもしれない。まだ、香料を混ぜ込む以前の、石鹸の原料を作っていたのではないだろうかと、今では後知恵で、そんなふうに考えることもできる。
それから連想したことがある。この映画での「屠殺・解体」シーンに、まったく臆するところのなかった私だが、実際に現場にいれば、少し違ったかもしれない、と思った。
現場で見れば「生々しい」とかいったことではなく、「臭い」だ。映画には「臭い」は無いが、現場には「臭い」がある。そして「臭い」は、「見た目」よりも、むしろインパクトが強いことも少なくないからだ。
私が警察官だった頃、変死現場の現場保存をした際、遺体が新しければ良いのだが、夏場で腐乱したりしていると、その臭いの方が、難敵であった。
現場保存といっても、要は、現場に人を立ち入らせないようにするだけだから、死体を見張っていなければならないというわけではない。だから、かなりキツイ死体であったとして、見なければ、どうということはない。
しかし、屋内ともなれば、臭いの方は、どっちを向いていようと、かなりの離れていようと、しつこく付きまとってくる。だから、同僚でも、死体の状態そのものよりも「臭いが苦手だ」と言う者が結構いた。
しかしまた、幸いなことに、私は鼻が利かなかったので、比較的、臭いに対しても強い方で、総じて、死体は平気な方だった。
検視をする刑事さんのように、ゴム手袋をするとは言え、死体に触るのは御免だったが、近くにいるだけなら、ほとんどまったく平気だったのである。
だから、刑事物のドラマで、新米の刑事さんが、惨殺死体を見て「えづく」みたいなのには、リアリティーを感じなかった。事実として、そんな人を見たことがない。私だって、「これは酷いな」とは思っても、たぶん気持ち悪くはならなかったと思うからだ。
幸い、そうした惨殺死体に向き合う機会はなかったから、実際にあったら、どうなったかは、わからないままなのではあるけれど。
で、話を戻すと、屠殺・解体の現場では、それなりに「臭い」がしたはずで、それが「生々しい」のではないかと想像した。
映画パンフレットによると、牛の腹を割いて内臓を取り出すときには、腸を結んでおいて、腸内の内容物が溢れ出さないようにするようだが、それでも多少は出るだろうし、その中には胃酸や糞尿もあって、殺したばかりの、まだ温かい死体から出てくる温かいそれらは、かなり臭うのではないかと想像する。
だとすれば、その臭いが、忌避感を強く喚起するのではないだろうか。
つまり、屠殺・解体は、見るだけなら、それなりに馴れることもできるだろうが、臭いがあると、二度と見たくないと思う人も少なくないのではないかと考えた。一一だから、この映画を見ただけで、屠殺・解体という作業の「実際」を知ったと思うのは、いささか早計なのではないかと考えたのである。なにしろ「臭い」は難敵なのだ。
たしか、中沢新一の『大阪アースダイバー』だったと思うのだが、皮革業に従事する部落の人たちが差別された理由の一つとして、皮革製造にともなう「臭い」の問題があった旨、書かれていたと記憶する。
つまり、観念的な「差別感情」だけではなく、「あの町は臭い」とか「あいつらは臭い」といった「生理的な嫌悪感」に発する差別も、かなり大きかったのではないかと推察するのだ。
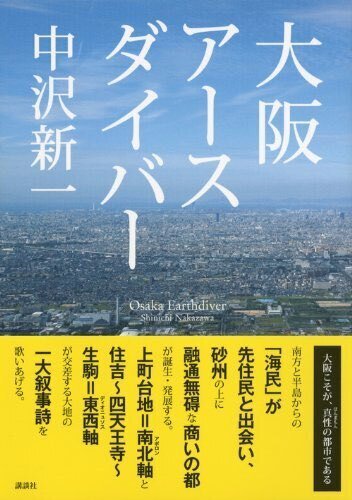
じっさい、この映画でも、北出さんたちが、亡き父から「継ぎの当たった服を着ていても恥じることはない。ただ、いつもきれいに洗濯された服を着ていろ」と言われていたという話だったが、これも、単に「気構え・心意気」の問題などではなく、「臭い」で差別されるという現実があったからではないだろうか。
例えば、電車に乗って、近くに立ったおじさんが「臭かった」としたら、あなたはその人を「見下す」ことはないだろうか?
「ちゃんと風呂に入っているのか?」「近くに寄るなよ、臭いな!」と、口には出さないまでも、そのおじさんが「低級な人間」ででもあるかのように、見下したりはしないだろうか?
私なら、するだろう。自分のことは棚に上げてでもである。一一私は、子供の頃からずっと、入浴を面倒がる人なのだ。
というわけで、「私は、人を差別したりはしない」と思っている人でも、たぶん「臭い」だけで、人を「見下す」ものなのだと思う。
「臭い」からといって、その人は「悪人」でも「品性下劣」なわけでもないと、それがわかっていても、「臭い」だけでその人を「見下し」、逆に「良い匂い」をさせている人には、どんな性格の人かもわからないのに、好感を持ってしまったりするのではないだろうか?
事ほど左様に、人間の「差別感情」というものは、本能的に抜きがたいものであり、簡単に頭をもたげてくるものなのである。
だから私たちは「私は、人を差別したりなどしない人間だ」などという、頭の悪いうぬぼれに、少しは自覚的であるべきだろう。自分自身の、抜きがたい「差別意識」も自覚できないような人間が、他人の差別意識を気易く云々するのは、まさしく烏滸がましいことだからだ。
私たちは、まだまだ「困った動物」である。その自覚が、まずは必要なのではないだろうか。
○ ○ ○
蛇足ながら、気づいたことについて書いておこう。
この映画の監督は、「纐纈(はなぶさ)」という苗字だが、私のような古いミステリファンは、この難しい言葉を見ると、すぐに国枝史郎の『神州纐纈城(しんしゅうこうけつじょう)』を思い出す。

そして、あの作品が、「血」や「差別」にかかわりのある作品だったと思い出して、ネット検索してみると、『神州纐纈城』の「内容紹介(河出文庫版)」は、こんな具合だ。
『武田信玄の寵臣土屋庄三郎は、夜桜見物の折、古代中国で人血で染めたという妖しい深紅の布、纐纈布に出遭う。その妖気に操られ、庄三郎は富士山麓の纐纈城を目指す。そこは奇面の城主が君臨する魔界、近づく者をあやかしの世界に誘い込む。“業”の正体に圧倒的な名文で迫る、伝奇ロマン不滅の金字塔』
そして「そう言えば、かつては染物業も、差別の対象だったんじゃなかったか?」と思い出して検索してみると、江戸時代に染め物屋を指した「紺屋」についての「Wikipedia」の説明に、次のような記述があった。
『非人との関係
柳田国男の『毛坊主考』によると、昔は藍染めの発色をよくするために人骨を使ったことから、紺屋は墓場を仕事場とする非人と関係を結んでいた。墓場の非人が紺屋を営んでいたという中世の記録もあり、そのため西日本では差別視されることもあったが、東日本では信州の一部を除いてそのようなことはなかった。山梨の紺屋を先祖に持つ中沢新一は実際京都で差別的な対応に出くわして初めてそのことを知らされたという。』
見てのとおり、全国的なものではなかったようだが、やはり「染色業」も差別の対象になっていたようだし、ここで前述の中沢新一とも繋がってきた。
中沢が『大阪アースダイバー』で「大阪の被差別地区」を扱ったのは、決して偶然ではなかったのであろう。
また、「纐纈(こうけち)」とは、
『絞とは纐纈すなわち布帛ふはくを糸で絞り込んで、染料の浸透を防ぐことによって文様を表わす技法である。』
という、サイト「日本服飾史」の記述も見つかり、赤い「纐纈」布も、人血で染めたものではないものの、実在するのである。

つまり、本作の監督、纐纈あやも、これまで人生の中のどこかで、自分の苗字が「差別」と接点を持つものだと知ったのであろうし、だからこそ「差別問題」に興味を持ち、本作を撮ることにもなったのではないだろうか。
この映画の中では、そうした事情は語られていないが、実際のところ、ほとんどすべての人間は、どこかで「差別される側」であったり「差別する側」の血を受け継いできたのではないかと思う。
だが、「血」なんてものに過剰な意味を見出すのもまた「現実逃避のファンタジー」でしかないと、私は思う。そんなもので、自分の存在が規定されては困るし、規定することを許してもならないとも思う。
「血」など「物理的な液体」に過ぎない。「天皇家」のそれであろうと、である。
(2022年12月7日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
