
野間宏 『青年の環』 : 長いくてしんどい物語
書評:野間宏『青年の環』(岩波文庫)
いまどき、野間宏の『青年の環』と言って通じる、30歳以下の人はいないのではないだろうか。
この物語の舞台となるのは戦前の大阪だが、紀伊国屋大阪本店の来店者に対し、年齢を問わない無作為抽出で「『青年の環』を読んだことがありますか?」と質問したとしたら、1000人に尋ねても1人もいないのではないか? もしかすると1万人でも。五十代以上なら、100人は無理でも、500人に1人くらいはいるかもしれない。
そんな具合だから、紀伊国屋商店大阪本店の店員全員に訊いても、1人もいないという結果も十分に想定しえるだろう。

もちろん「野間宏」という作家名なら、四十代以上の読書家ならば、それなりに知られているだろうが、『青年の環』という作品は、野間作品の中でも、今やマイナーな存在になってしまっているのではないだろうか。
その理由は、とにかく長くて、くどい描写やくどい会話の多い作品なので、誰も読もうとはしないからだろうと思う。
なにしろ『原稿用紙で約8000枚。文庫本の小さな活字で約4300頁』、おおむね900頁程ある、やたら分厚い文庫本で5巻にもなるのだから、この分厚さ・長さだけでも気圧されてしまう。
しかも、これがエンタメなら読めない長さではないが、何しろ純文学中の純文学作品であって、いわゆる「面白い」とか「ワクワクする」ような作品ではない。
もちろん、それでも「面白い」とか「ワクワクする」という読者も、ごくまれにはいるだろうが、普通は、そんなふうに読める作品ではないし、作者も、エンタメ性など、カケラも気にかけていない作品なのだ。だから、端的に言って、この作品は、読む通すに困難な、いわゆる「挫折本」のひとつだと言っても過言ではないと思う。だからこそ、なかなか読まれないし、読まれないから、忘れられてしまうのである。

野間宏と言えば、昔は「国語の教科書」にも、その作品名が紹介されていた、短編「暗い絵」が有名だろう。
その次に有名な作品は、映画にもなった、軍隊批判小説『真空地帯』。その次が、戦後文学アンソロジーなどによく収録される短編「顔の中の赤い月」、といったことになり、その次くらいに「読まれない名作」的な意味で有名な『青年の環』ということになるだろう。したがって、それ以外の作品になると、いまどき数千人に1人もいないかもしれない「野間宏ファン」以外、ほとんど誰も記憶していないのではないだろうか。
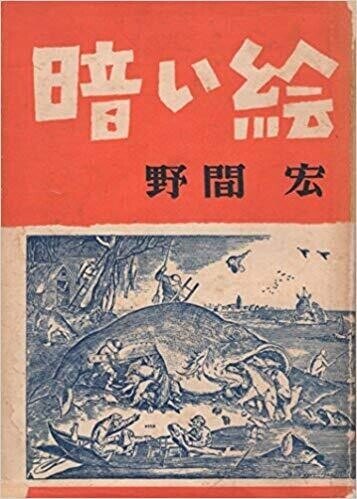


私は、そんな『青年の環』を、このたびの初挑戦で、なんとか読了することができた。しかし、少なくとも、私自身の「趣味」から言わせてもらうなら、お世辞にも「面白い」とは言えない作品だった。
では「文学的」な評価としてどうなのかと言えば、「興味深い」部分はあるけれども、「傑作」とまでは言えないだろう、といった感じになる。
もっとも、『青年の環』は、刊行当時に、谷崎潤一郎賞とロータス賞を受賞している作品ではある。
ロータス賞は、SFの文学賞で有名な「ローカス賞」とは別物で、1969年に創設された「アジア・アフリカ作家会議が主催する国際文学賞」であり、日本人作家ではこれまで、野間宏のほかには、堀田善衛、立松和平、小田実といった人たちが受賞しているようだが、個人的には、あまり興味のない日本人作家たちだ。
ちなみに、谷崎賞の方は、功成り名を遂げたベテラン作家の長編に与えられることが多いから、その受賞作が、その作家の作品の中でも、特に優れているという保証はなくて、作品評価的にはあまり当てにはならない「功労賞」なのではないかと、私は考えている。
そんな訳で、『青年の環』は、完成当時はそれなりに評価された大作だが、本当に「傑作」と呼べるのかどうか、それはいささか疑わしいと、私個人は思っているのだ。
『青年の環』は、1970年に完成して評判となり、1974年には、埴谷雄高編の『『青年の環』論集』が刊行されている。しかし、野間宏の以下のような「プロフィール」を見ると、埴谷は野間の、文学的かつ政治的「同志」であったから、この『論集』も、有力な仲間の代表作のために作られたもの、だったとも言えるだろう。つまり、そのぶんを差し引いて考えなければならない、ということだ。
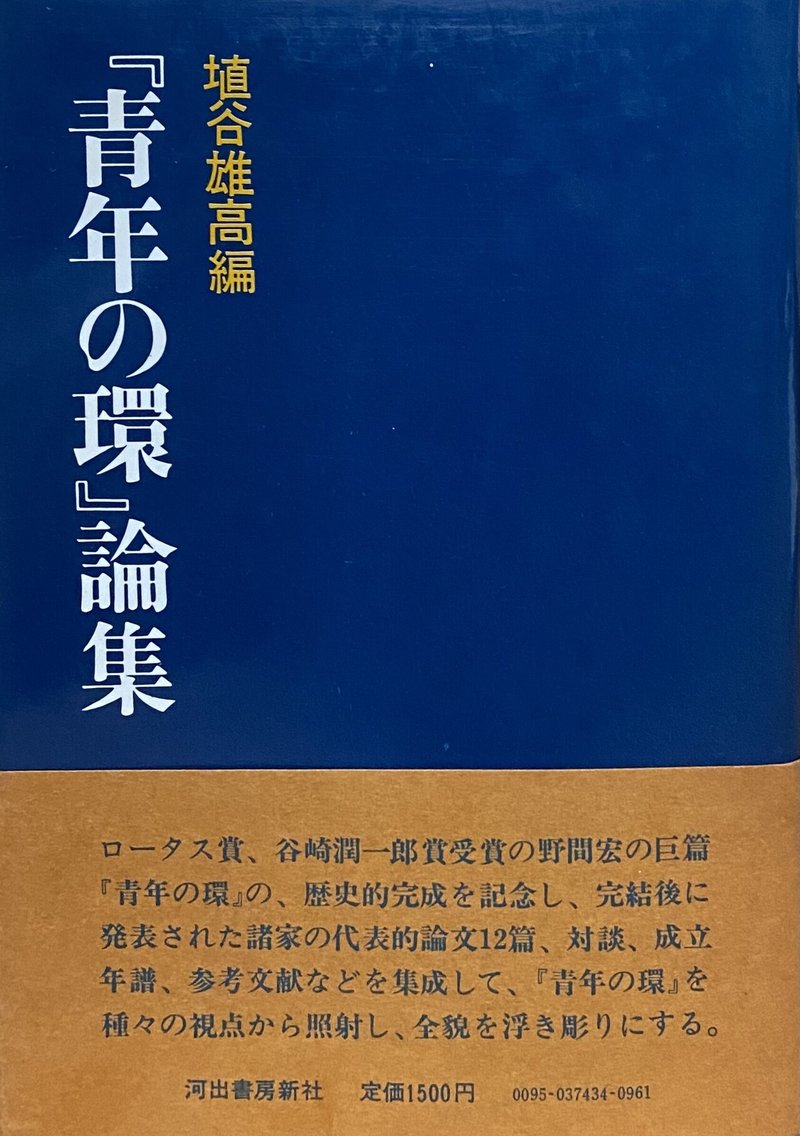
ちなみに「新日本文学会」とは、日本共産党系の文学者団体である。
戦後は、この「新日本文学会」に入会所属した作家が大勢いたが、中野重治の長編『甲乙丙丁』などに描かれたとおり、政治路線の問題などをめぐって内部的なトラブルがあり、大西巨人のように退会する(本人の弁では「いつの間にか除名になっていた」)人も増えていって、2005年に解散となっている。
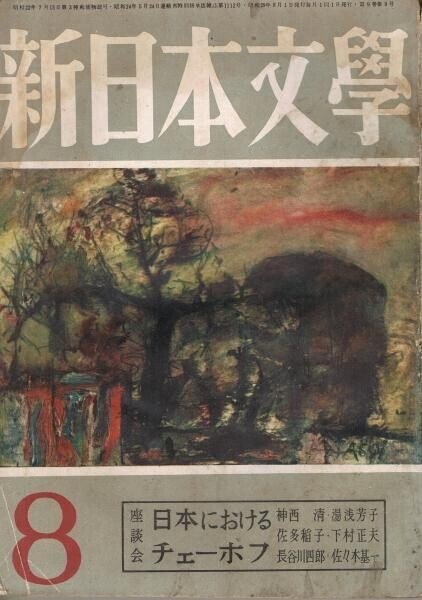
『兵庫県神戸市に生まれる。大正4年(1915)、神戸市長田区に生まれる。父・卯一、母・まつゑ。電気技師であった父は親鸞の教えを奉ずる在家仏教の一派を開き、教祖として自宅に説教所を設けていた。大阪府立北野中学校を卒業後、京都の第三高等学校文科丙類に入学。同学年であった桑原静雄、富士正晴を知り、詩人・竹内勝太郎の指導のもと、三人で同人雑誌「三人」を創刊。京大仏文科卒業後、大阪市役所社会部に勤務。融和事業などを担当し、被差別部落の実態を知るとともに、部落解放運動の指導者たちと接触して大きな影響を受ける。このときの体験から『青年の環』が生まれることになる。昭和21年(1964)処女作『暗い絵』を「黄蜂」に発表し、評論家の注目を集める。この年、新日本文学会に入会、翌年には花田清輝、埴谷雄高、佐々木基一、安部公房らとともに「夜の会」を結成し、「近代文学」「総合文化」の同人にも参加。また日本共産党に入党し、戦後芸術運動の推進にも力を注ぐ。』
(「地図に乗らない文学館 ネットミュージアム兵庫文学館」の「野間宏」より)
本作『青年の環』には、二人の主人公がいるが、この「プロフィール」を見ると、『青年の環』が、野間自身の経歴を大きく反映した作品であることは、一目瞭然である。
『矢花正行 大阪市役所社会部員として、貧しい部落の人々を対象に部落融和事業にあたっている青年。関西の友人たちがすすめている左翼運動グループに参加している。
大道出泉 正行の高校時代の先輩。かつて学生運動をすすめるうちに傷つき、思想的停滞におちいる。性病に蝕まれ、デスペレートな行動を通じて正行との対立点を見出そうとする。広告会社調査部に勤める。』
(岩波文庫「『青年の環』主要登場人物」紹介文より)
この二人が主人公だが、矢花正行の母よし江の設定は、次のようなものである。
『矢花よし江 正行の母。在家浄土真宗の熱狂的な信仰者。夫なき後、盛り場千日前にプレイガイドを経営し、闇切符を売って生計を立てている。』(前同)
このように、本作は、野間宏が自身の「経験と知見」をフルに生かして書いた作品なのだが、だからこそ苦労し、執筆に長い年月を費やすことにもなったのではないだろうか。つまり、本作を「面白く」書こうとすればするほど、「嘘」が混じる蓋然性も高くなることを、作者自身強く感じていたのではないか、ということである。

(大阪・戦前の被差別部落の様子)
けれども、本作はあくまでも「小説」であって「自伝」ではないのだから「作るべきところは作る」のが当然であり、むしろ、その困難とは、「小説(創作)」と「自伝(経験的事実)」のどちらか一方に徹した作品にはあり得ない、「経験的事実と創作的事実の兼ね合い」の難しさだったのではないかと察し得る。
同様に、この作品の「くどさ」は、作者・野間宏個人の個性であるのは無論だが、同時に、関西人の体質や大阪の土地柄を反映したものでもあったはずだ。
端的に言えば、スマートに理知的にシャープに書いてしまったら、大阪と大阪に住む人々の「リアル」が描けなかっただろうから、その「リアル」にこだわると、おのずとリーダビリティの低いものとならざるを得なかったのではないか。少なくとも、作者には、実感としてそう感じられていたのではないだろうか。
(日本の)文学の世界において、無意識化されたデフォルトとなっている「標準(語)的リアル」あるいは「首都的リアル」に馴染んだ私たち読者にとって、この作品における「大阪的リアル」は、ある意味で「小説的ではないもの」のように感じられるのではないだろうか。そしてこれは、生まれも育ちも現住も大阪である私ですら、「とても読みにくい」と感じられるほどのものなのだ。
私がこの作品に感じた「しんどさ」「合わなさ」は、主にその「鈍重さ」にあったと言えるだろう。
例えば、この二人の主人公だが、どちらも「察しが悪く、独り合点」である。つまり、端的に言って「あまり頭が良くない」のだ。
「本格ミステリ」ファンである私としては、「名犯人と名探偵」「欺く作家と看破する読者」的な、頭の良い者どうしが丁々発止でギリギリのやり取りをするような小説が読みたいのだが、残念ながら本作『青年の環』の二人の主人公は、二人ともそういう「主人公らしい主人公」ではなく、わざわざ物語を停滞させるような独りよがりに嵌まり込みがちだし、繰り返しの多い、くどい議論を執拗に繰り返してくれる。
それで、読まされるこちらは心底うんざりさせられるわけだが、しかし、そこには、今の「エンタメ小説」は無論、「今の純文学」にも存在しないような、「手段を選ばないリアリズムの追求」を見ることができる、のではないだろうか。
たしかに、「察しが悪く、独り合点」な「面倒くさい主人公たち」であり、その意味でおのずと「しんどい」「合わない」小説なのだが、しかし「こういうことって、よくあるよな」とも思うし「人間、だいたいこんなものだよね」とも思う。本作は、そういう「思い当たる節」を仮借なく突きつけてくるからこそ、読者を、少なくとも私を「うんざり」させるのではないだろうか。「そんなのは、現実の方で間に合っているから、小説でまで読みたくはない」と思わせるのではないか。
しかし、だとすれば、こうした小説には「現実逃避のためのエンタメ文学」とは真逆の、意味や価値があるとも言えるし、まして、大岡昇平の『筆取られぬ老残の身となるとも、口だけは減らないから、ますます悪しくなり行く世の中に、死ぬまでいやなことをいって、くたばるつもりなり』(『成城だより3』)という言葉を、長年くり返して引用しては、世の中に「いやなこと」を突きつけていくと公言している私としては、『青年の環』が描き出す「面倒くささ」の文学的価値を認めないわけにはいかないだろう。
たしかに、いまどき、こんな小説が読まれるわけもないとは思うものの、それは何も「読まれない作品は、ダメな作品だ」という意味ではない。野間宏に厳しかった、切れ者の大西巨人も、『勝てば官軍』ではなく、むしろ自分は「筋として正しい方に、自分の運命を賭ける」と、次のように語っていた。
『果たして「勝てば官軍」か。
果たして「政治論争」の決着・勝敗は、
「もと正邪」にかかわるのか、
それとも「もと強弱」にかかわるのか。
私は、私の「運命の賭け」を、
「もと正邪」の側に賭けよう。』
(大西巨人「運命の賭け」より)
ならば、私も、この「人間の、どうしようもない面倒くささ」を描いた作品の価値を認めなくてはなるまい。
無論、この作品の価値は、そんな部分だけにあるのではないけれども、例えば、この作品に描かれた、「差別」の問題、「思想と生活」の問題、「国家と権力」の問題、「戦争」の問題、さらには「信仰」の問題、一一これらが、別個の問題としてではなく、あちこちでくっついたり離れたりしながら流動してゆく、その結末のない物語に、「純文学」の価値(の多面性)を見出さなくてはならないのではないだろうか。
今はもう、失われたも同然の、そうした「文学的価値」とその可能性に、私は「運命の賭け」に値するものを見いだし得るのではないかとさえ思えるのだ。

「この小説は、どうしたって褒められない」と、そう思いながら、書き始めたこのレビューだが、最後は立派に「褒める」ことができたようだ。
だが、なぜそんな芸当ができたのだろう?
それは、本作が、やはりそれだけの作品であったということなのか、それとも、私がそれほどのへそ曲がりであったというだけのことなのか、あるいはその両方であり、その兼ね合いだったのか…。
今のところ、その真相は、私自身にもよくわからない。
(2022年5月9日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
