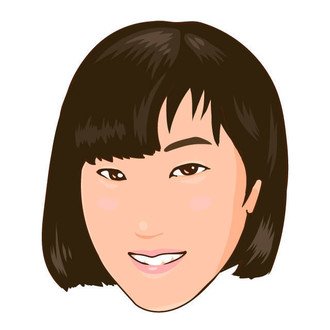#働き方
シングルマザーを働かせる社会の異常さ
生活保護や貧困問題に興味がある私は、2018年夏に放送されている関西テレビのドラマ、『健康で文化的な最低限度の生活』を毎週観ています。同名のコミックが原作で、新人ケースワーカーが生活保護の現場で奮闘する様子を描いた社会派ドラマです。ドラマなのでかなりわかりやすく描いているなぁとは思いますが、普段はまず光の当たらない現場、重いテーマに切り込んでいっている挑戦的な作品だと感じ、応援しています。
この
「母性喪失社会」と保健室の役割
前々から書きたいと思っていた内容をまとめてみたいと思います。ちょうど1か月くらい前に、『ルポ 保健室 子どもの貧困・虐待・性のリアル』(秋山千佳著)という本を読んでいました。記者の方が学校の保健室のリアルな現状を取材してまとめた本で、読みやすいけれども中身は非常に重く、看過できない内容だったのでご紹介したいと思います。保健室にやってくる子どもたち(中高生)の置かれた状況や、学校における養護教諭の役
もっとみる思い通りにならない世の中における優先順位
最近「世の中の人ってこんなに自己中心的な人ばっかりだっけ?」と思うようなことが多いなぁと少し悲しくなったりする時もあります。グローバル資本主義が自己中心的&エゴ丸出しな思想なので、人々の意識がそちらに向かいがちということもありますし、「引き寄せ」などのスピブームにより、願望成就や夢を叶える的な思想が流行っていることも背景にあると思います。「自分の思い通りに生きるために…」というのが人々の共通目標み
もっとみる「その先の○○」のために今を犠牲にする生き方
前回の就活や婚活も、「偏差値」至上主義?という記事でも少し触れましたが、幼い頃から人と比べられ、競争することに慣れすぎた私たちは、あとあとでいい思いができる(と信じている)ことをするために、今を犠牲にしてそれに捧げるような生き方をしているものだなぁと感じます。いい会社に入るためのいい大学、いい大学に入るための高校生活などなど、こういった類のものは無限にあります。「その先の○○」のために生きているの
もっとみる理念は「平等」、しかし性差は超えられない
前回まで、教育や大学進学について思うところを書いてきました。大学全入時代と言われて久しいですが、大学進学率のデータを見てみると確かに年々上昇していて、特に女性の大学進学率はここ数十年で急激に増加しています。私が大学に入るころのH18年には約40%、最新のデータでは約48%と、半数近くにも上っているようです(参考:平成29年版男女共同参画白書 概要版 )。女性が高い教育を受けられなかった時代から、女
もっとみる