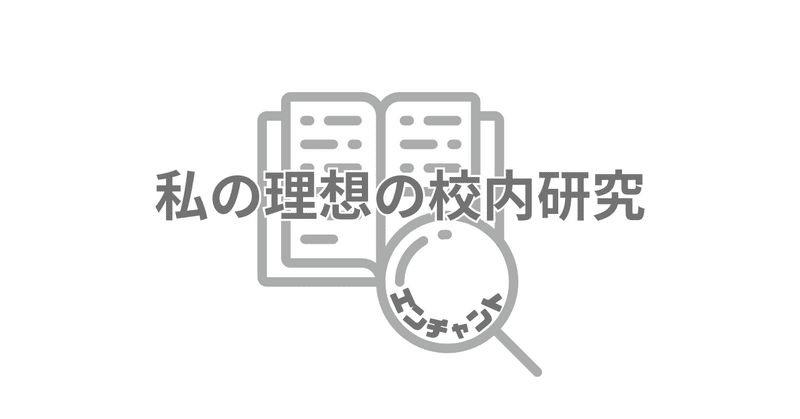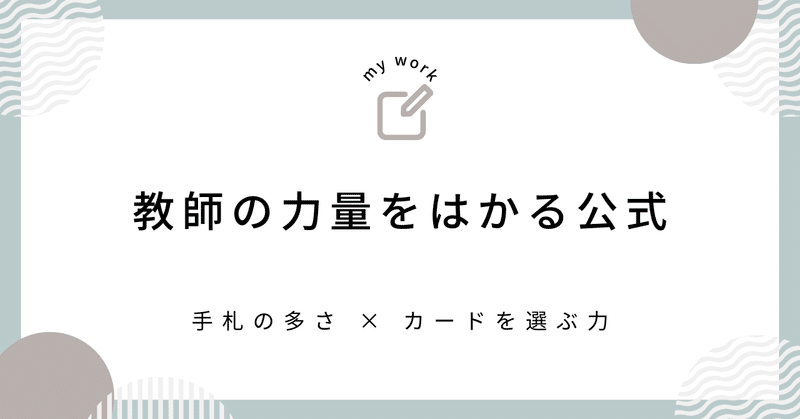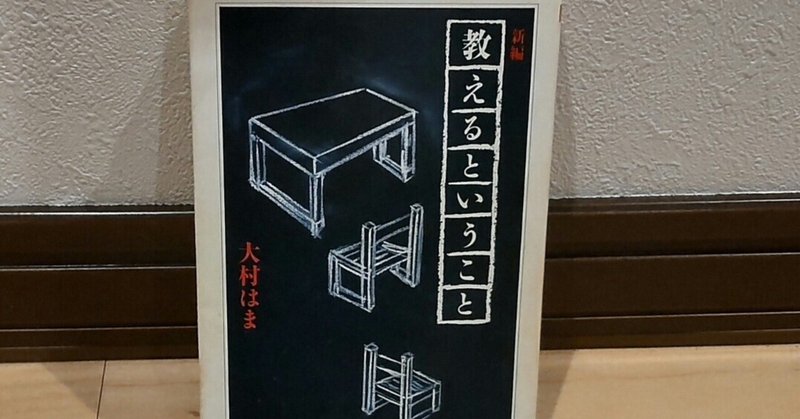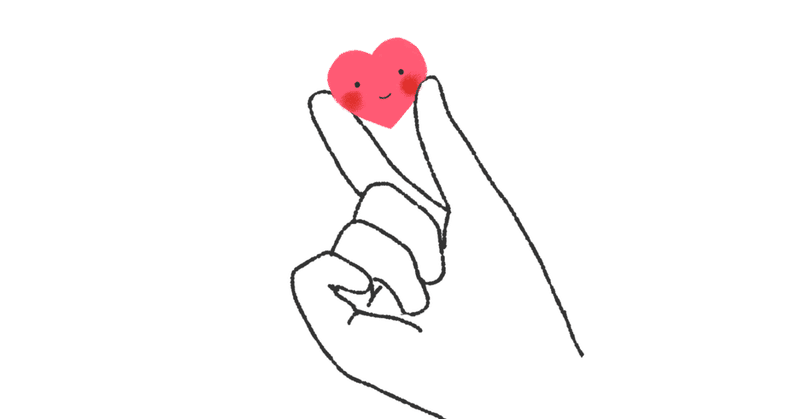#先生
授業でどう教えるかは手段だから、目的である子どもの成長を忘れないようにしたい
1293記事目
こんにちは、旅人先生Xです。
今日は「教える手段と子どもの成長という目的」について書いていきたいと思います。
良かったらぜひ、目を通していってみていただければ幸いです!
目次は、以下の通りです。
子どもの成長が学校の授業の目的だと思う
学校では、国語や算数といった様々な教科の授業があります。
子どもの頃から当たり前のように教科の授業を受けてきたし、教員になってからも当
ここ数年間の学校教育で悪くなった点
学校教育で、ここ数年で状況が悪化したことについてまとめてみました。
◯◯教育など学校の業務負担が増加した
文科省は教育を充実させようと、次から次へと新しい政策を打ち出し実施しています。新学習指導要領(小中学校:2021年実施、高校:2022年実施)にて、小学校英語教育の教科化(5〜6年生)、高校の学習内容を下ろし授業は英語で行うなどの英語教育の高度化(中学校)、プログラミング教育(小学校)、キ
🌈社会人先生になりませんか? 朝活7時 🌸#しゃかせん 記事紹介 ✅①こんな方に担任の先生になって欲しい✨ ✅②きしゃこく学院附属中学校@渋谷大翔 ✅③誰もが先生になれる社会に✨誰もが先生【「#先生DAO」DAO TDAO TeacherDAO note 発!仲間募集中⭐】
(きしゃこく先生🌈)
おはようございます!
さあ、きょうも朝活7時は、
「#先生DAO」、
TDAOプロジェクトの時間です!
こんな社会経験豊富な方たちが
「学校の先生」、
しゃかせん、社会人先生になってくれたら、
ガッコは、変わるだろうな🌈
そんな方達を
紹介したいなって思っています。
ファシリテーターは、
教育DAO 、
きしゃこく学院附属中学校の生徒会です!
(