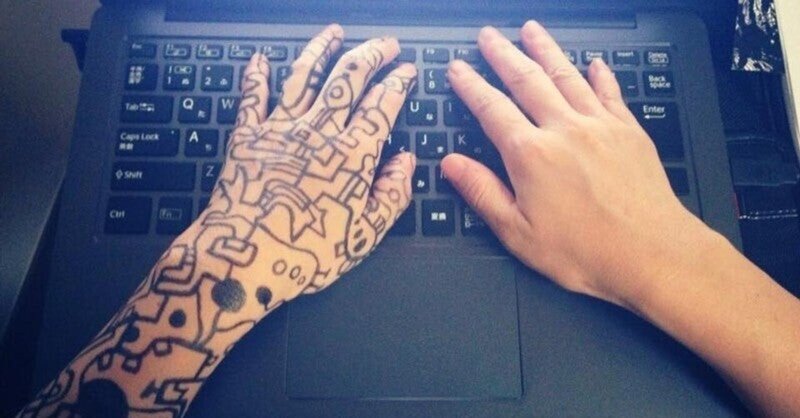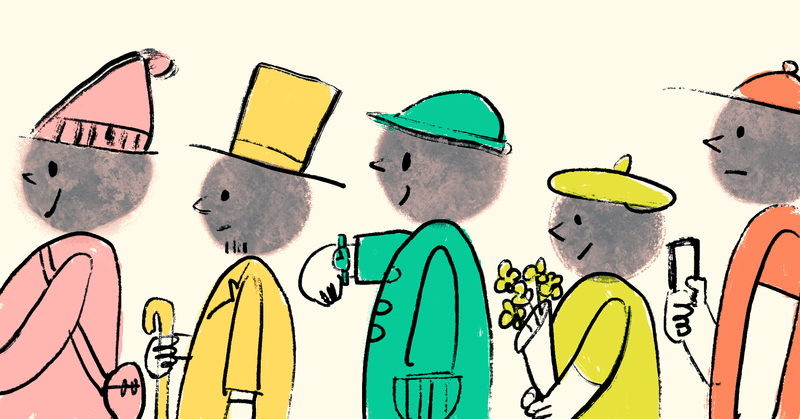- 運営しているクリエイター
2021年10月の記事一覧
成長した姿を想像できるだけの感性を養うこと
どうも。藁科侑希(わらしなゆうき)です。
普段は大学教員やスポーツ現場でコーチやトレーナーをしております。
今日が444日目のnote投稿です。
本日はこちらの記事を読んで感じたことについて。
考える種が散りばめられているようで。
何度も繰り返し読んでいて、「あ、ここはこういうことかも」「もしかしたらもっと深掘りできるんじゃないか」などが想起されてきたんですね。
今日はそんな頭の中を書き留め
「褒め」が組織を強くする。称賛文化を浸透・定着させる上で外せない“感情報酬”とは。
皆さん、こんにちは。今回は「社内表彰」について書かせていただきます。
記事の中に当社の事例をご紹介いただきました。サイバーエージェントは創業以来、「頑張って成果を出した社員にスポットライトを当てる」、「褒める時は盛大に褒める」という価値観を重要視してきました。
従業員のエンゲージメントをいかにして高めるかは、日本企業の近年の課題の一つである。エンゲージメントとは従業員が活力や熱意をもって仕事に
チームをつくり、プロダクトをつくる
こんにちは。
クックパッドの長野(@naganyo)です。
今回は、今年の始めに公開した↓noteのその後の話です。
前回は、プロダクトマネージャーの立場から、レシピアプリの買い物機能のリリースまでの道のりについて書きました。この時点では一つのプロジェクトとして開発を進めていましたが、今年の頭から正式にそのための新しい部署ができました。私は副部長という立場になり、プロダクトのマネジメント+組織
会社員を卒業したら正論嫌いになった話
正論とは「理にかなった正しい論」。今日は、呪術廻戦の五条先生なみに正論が嫌いになったというお話です。日々「経営者って何考えてるか意味わからんよね・・」とあきれている従業員の方やコンサルタントの方にむけての、ちょっとしたexcuseです。
正論バンザイの経営企画時代私はこれまでのキャリアの大半、会計・ファイナンス、経営企画と、表計算ソフトで数式を組みまくったり、ビジネススクールで経営学をやったり(