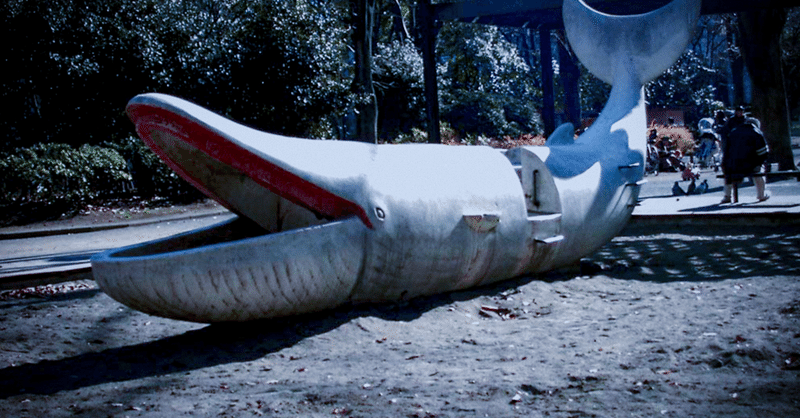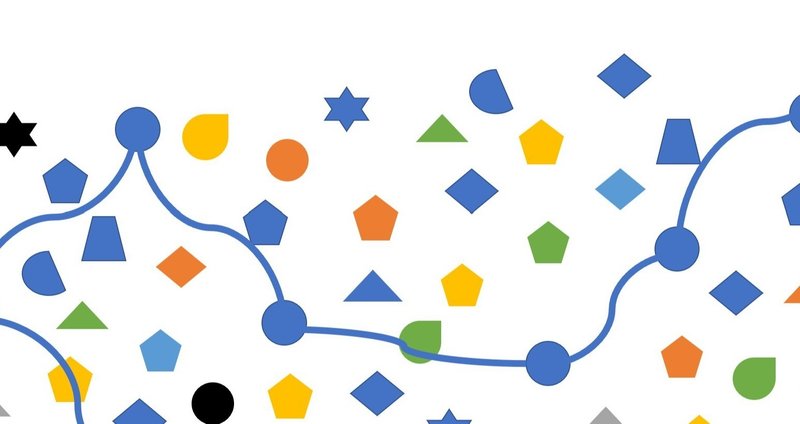
- 運営しているクリエイター
#イノベーション
VUCAのカオスから脱出するチカラ
VUCAの時代と言われます。そこから脱出するときに必要なチカラはラフティング・ボートの転覆から脱出したときのものに似ているかもしれない。
VUCA(ブーカ)はVolatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguityの頭文字から取られた言葉ですが、ざっくりいうと「変化の振れ幅が大きくて、不確実・複雑・曖昧で分かりにくい世界」、「カオス」ともいえると思います。
水難事
翻弄されている日本企業に役立つヒントはここにある
GAFAだ、DXだ、SDGsだ、ESGだと海外の動きに翻弄されている日本企業に役立つヒントは海外や日本の大手企業ではないところにある。マザーハウス代表である山口絵理子さんもヒントをくれるそのひとりだと思う。
昨日のobanote「日本企業の『看板』とチーズはどこへ消えた?」では、米国経営者が下した「株主第一主義」という「看板」に対して、日本の経営者が掲げてきた「看板」はそもそも何だったのか?を問
OODAをじっくり学び・検討するということ~気づく力と自分軸
最近、ビジネスパーソンの間でOODAが賑やかである。今の時代にOODAをじっくり検討することはどれだけの意味があるのだろうか?その思考・行動自体に問題はないだろうか?
機動戦を制す戦闘哲学OODA ビジネスに生かすには|ブック|NIKKEI STYLEビジネス街の書店をめぐりながら、その時々のその街の売れ筋本をウオッチしていくシリーズ。今回は定点観測している八重洲ブックセstyle.nikkei
イノベーションはどうしたら起こせるのか?
イノベーション創出に悩む企業は多い。格差問題の根っこを見ると、そのヒントがわかる。問題の根っこはいつも似ている。欧米の格差問題から日米イノベーションの「格差」を考えてみた。
#COMEMO #NIKKEI
様々な格差の問題は最終的には「情報の格差」に行き当たる。そこには「情報のアクセス」の問題が常にある。個人間の格差も企業間も国家・地域間も。経済も教育も同じだ。
そう考えたとき、GAFAのひ
職場にアートを、学校にアートを、人に笑顔を、全国にワクワク挑戦する場を♪
最近、アートが話題だが一過性で終わってしまったり、その効果に疑問を感じていたりする人も多い。アートを使った研修をする側として、「アートをビジネスに実装するうえで欠かせない視点~イノベーション創出を期待する前に必要なこと~」をお伝えしてみたい。
#COMEMO #NIKKEI
端的に言えば、今、アートが注目されるのはアートで感性を磨くことでイノベーション創出に繋がるのではないかという漠たる期待か
日本の経営学とITの向き合い方は似ている~舶来品珍重主義の弊害
海外の輸入・紹介に依存し、独創的な概念や理論がなぜ日本の経営学者から提供されないのか?そのことは日本企業にどのような影響を与えてきたのか?これらが語られることは少ない。ITの世界も同様だ。これらの根底には類似した傾向が窺えないだろうか?
#COMEMO #NIKKEI
野中先生の「私の履歴書」を共感しながら拝読している。先生は日本の経営学を「解釈学」としていたが、個人的には「意訳のない翻訳」と
「一億総障がい者社会」に向けて「障害」を再定義しよう
障害を他人事と思っている人は多いが、歳を取れば誰もが障害を抱える。一億総活躍の前に一億総障害の問題がある。「障害」を再定義することで、ビジネスチャンスを広げることにも繋がるのではないだろうか?
一般に身体や知的・精神の障害を抱える人を障害者と呼ぶ。
障害者は医療的・制度的支援を受けるうえで基準がある。しかし、発達障害などいろんな障害が明らかになるにつれ、状況は複雑に、対応は難しくなっている。
その「イノベーション」はどの「イノベーション」ですか?
「我が社に必要なのはイノベーションだ!」と上層部が言っているとき、「そのイノベーションとはどのイノベーションですか?」と尋ねる人は少ないだろう。イノベーションほど独り歩きし、曖昧なまま多頻度に使われている言葉もないのではないか?
およそ言葉というものはその理解や認識に差異が生じるのは当然としても、イノベーション創出を急ぐ企業がその議論の場で曖昧さを残したまま事を進めれば期待する効果はいくばくか。
社名から「製品」と「技術」が消える日~製薬業界から考える
トヨタ自動車や武田薬品工業など伝統的な製造業では、作っている製品(ex.自動車、薬品)や持っている技術を社名に冠していることが多い。この社名はいつまで続けられるだろう。
テクノロジーの進化、特に情報通信技術(IT、ICT)による大きな変化、昨今でいうDX(デジタル・トランスフォーメーション)がこれまでの業界構造を、産業のあり様を大きく変えているのだから、社名変更が時間の問題になるのは避けられない
変革期にこそ「Who am I?」
元日リリースのTV CM「トヨタイムズ」が面白い。クルマに興味なく、免許すら持たない筆者でも人間には興味がある。楽しそうな章男社長に釣られてCM用の短縮版ではなく20分強のロングインタビュー版を見た。章男社長の言葉には変革時代に自問自答する人や企業へのヒントがあると思う。
近年、「100年に一度の変革期」と危機感を訴え、メディア報道では笑顔をあまり見ないように思えた章男社長がまるでやんちゃ坊主の
Z世代とカニカマに見るアフターコロナ
テクノロジーの恩恵を一身に受け、「リープフロッグ(leapfrog:蛙飛び)」が可能なZ世代。リアルに比重がある上の世代とサイバーに比重があるZ世代がアフターコロナを共創するヒントをカニとカニカマで考えてみた。
#COMEMO #NIKKEI
上記の日経記事のなかで米国のZ世代が「2019年に最も関心が増したブランド」のランキング(米モーニング・コンサルト)が紹介されている。ドアダッシュなどの