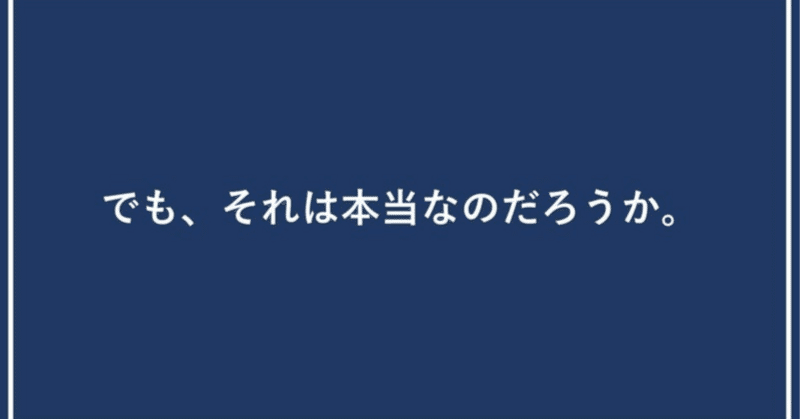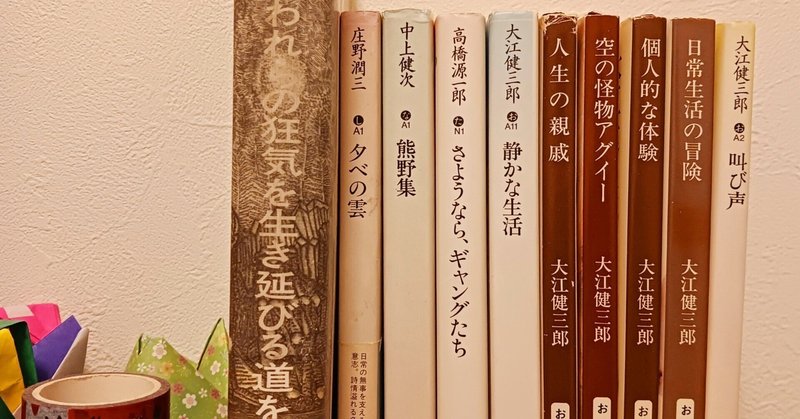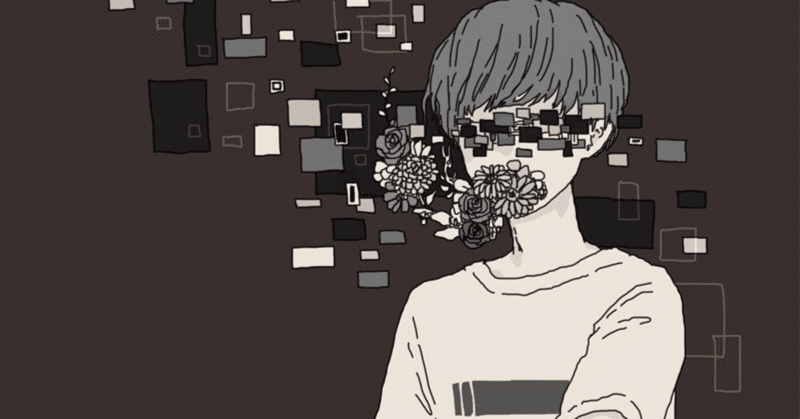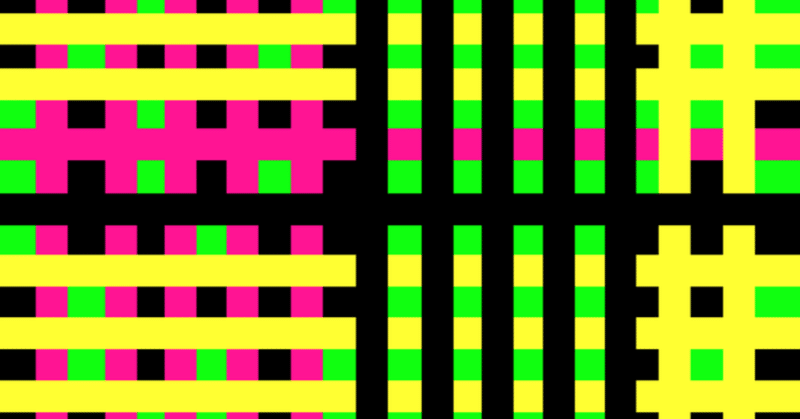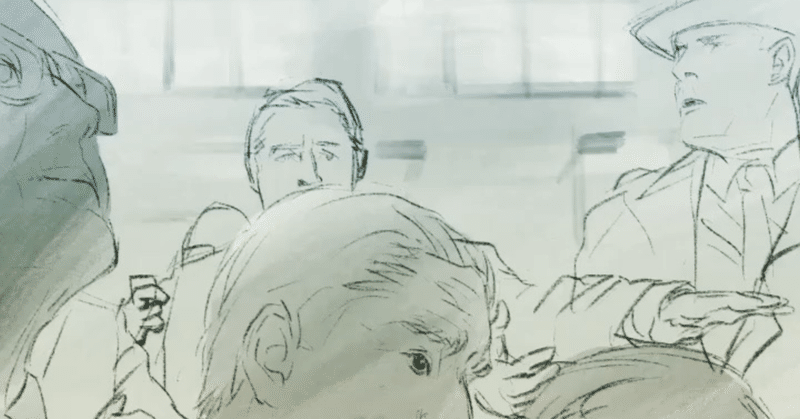#読書
拝啓 読書様。これが私の遊びで、続く葉脈になります。
私が貸した星野道夫の「旅をする木」を手に持ち、後輩が私のもとにやって来た。
「お返しします」
私は、この後輩を密かに読書好きにさせるように遊んでいる。遊んでいるというよりかは、遊んでもらっているのかも知れない。本に興味があると言った後輩は、彼女が読んでいるという伊坂幸太郎を好きかどうかを私に聞いてきたことが始まりだった。
Amazon.co.jp: 死神の精度 (文春文庫) 電子書籍: 伊
大江健三郎の作品を読む僕は、その感想だけに留めて置けない読書になる。
久しぶりの友人からの通知だった。
「大江健三郎を読むなら何から読んだらいいかしら」
その質問に僕は答えながらも、それとは別のことを感じていた。もう逝去されて半年以上経つのか。そのニュースを知った時から大江健三郎を読めなくなっていた。
大江健三郎は、僕にとって書くことへの議題をくれた人だ。それは、小説のようなフィクションに於いても文体に思想を入れると共振を呼ばせることが出来るということを初めて
もしかしたら、文芸サークルの一員として今後登場出来るかも知れないと考えたらサリンジャーを読まずにいられなかった。
ないものねだりは世の常である。
私は、今年に入って文芸サークルに物凄く憧れを持った。それは本というものを主人公にして議論を交わし、お互いに執筆をしながら高め合う。そんな活動が存在していることを初めて知ったからだ。それも部活やクラブ活動と同じような学生生活の一部、青春の一部として、存在していたことを知ったからだ。
ここに出てくる物語は、私の記憶でも何でもないのだが、初めて心の底から他人様の青春を
もし吉田知子と呑むならば、その機会と境界線を探りはしたが惨敗だった。
先日、年間読書量ゼロの先輩に言われました。
「君は、日本一の読書家だと思うよ」と。
うっすらと私もそうじゃないかと思っていたので今日から名乗ります。
日本一の読書家の私がこんなことを言うのはお恥ずかしいのですが、どっぷりと本に浸かれず、最近は短編や随筆を読んでいる。何が正しいのか分からないまま、フラフラフフフであります。
四十を越えても自己が定まらず、迷いに溢れている毎日が嫌いではない。た
恐怖から見つける自分への疑惑。続くのは、大江健三郎を再び読める日まで。
大江健三郎と古井由吉が、対談している。
大江健三郎は、「短編の文章の緊迫を復活して、日本の文学、表現の世界を再建する必要があるんじゃないか。」と言っている。
古井由吉は、「言葉がぼろぼろに崩れがちな時代ですし、これは敗戦に劣らぬ文学の危機ですね。」と言っている。
大江健三郎が亡くなって、大江健三郎を読めなくなった。どうすることも出来ない気持ちが続いていて、新潮名作選「百年の文学」を読みはじめ
1972年の時代評論は、めぐりめぐって私に届く
めぐりめぐってなんてお言葉は、都合の良いお言葉でございます。ですが、そういう場合も世の中には、めぐりめぐってあるんでございます。
まったく予定にない本を読みました。どうして私が出会うことになったのか。物語は複雑な経過を辿ります。
思い返せば2月下旬、一つの記事がアップされました。
私は、この記事の文字の裏にある夫婦の愛情の交換に思いを馳せ、半ば羨望の眼差しを向けながら、「共通の趣味でケンカ
小津夜景の暮らしに触れた一日に。
「梅雨が明けた頃でいいかしら」
「梅雨が明けた頃会いましょうね」
その日、同じ時間を共有したのであろう2人から、別々に写真やメッセージが私宛てに届いたのは偶然ではないのだろう。
ふいに届く言葉にふと、その時間を想像し、想いを馳せる事が出来るありがたさを感じた。
「楽しみにしてます」と文面を一言で返信しようとしていた自分に、これはキッカケだ。逃すな。と踏みとどまった。
好きな作家が亡くなり
私にも語らせて欲しい。BLUE GIANT のこと。
私は、小説に自己の内面を求めて、マンガに理想と解放、感情の揺さぶりを求めているのかも知れない。
読むという行為が好きだ。生粋の怠け者で怠惰な暮らしをしている私は、一歩も動かずにその世界の何処でも飛ばしてくれる読書が好きなのだ。
BLUE GIANT ずっと好きなJazz 漫画だ。
もう、何年も追いかけている。主人公はその年月の全てをかけてサックスを吹き続けてその音を届けてくれている。
映画
谷崎潤一郎の「刺青」により、その理想の嗜好を探る。
表現により、実体を体験したかの錯覚を起こす事がある。それは、その作家の技量というよりも作品における自己の内面との一致によるものである気がする。
想像しやすい、そして理解したいというような、こちらが迎え入れて作品を感じる時は、全てが合わさりとても幸福感が充足する。良い時間だったと感じるからだ。
私は、谷崎潤一郎にその救いを求めた。私が知る限り、読書をしながら女性の美を知れるのは、私の記憶において
開高健が僕に伝えたものに、本当のことを追いかける。
文学が駆り立てる物は何か。今年初めのイベントで開高健が、純文学からのスランプでノンフィクションを書くようになり、それでも純文学にまた戻って「輝ける闇」を書いた事を知った。
僕は、開高健が純文学を書けなかったという時期のルポルタージュ、「ずばり東京」を読みつつ、その語り口や文体に引き込まれる事を是とし、心地よく沈んでいた。
だが、こんなに面白い文章を描けるのに、それでも本人が描きたかった文学。純
手紙になるような一日を終えて、自己を知る。
その日の約束は、昨年の9月からの約束になる。僕は、逸る気持ちを抑えきれずに待ち合わせの40分程前にそこに着いた。伊勢佐木町のBOOK・OFF前が待ち合わせ場所だったのは、きっと僕が早く到着しても大丈夫なようにという気遣いからだろう。
僕に渡したい本がある。
そう言っていただき、実際に会うまでに5ヵ月。聞きたい事、話したい事が積もりに積もっていた。
大江健三郎という一人の作家がいる。僕が大江健