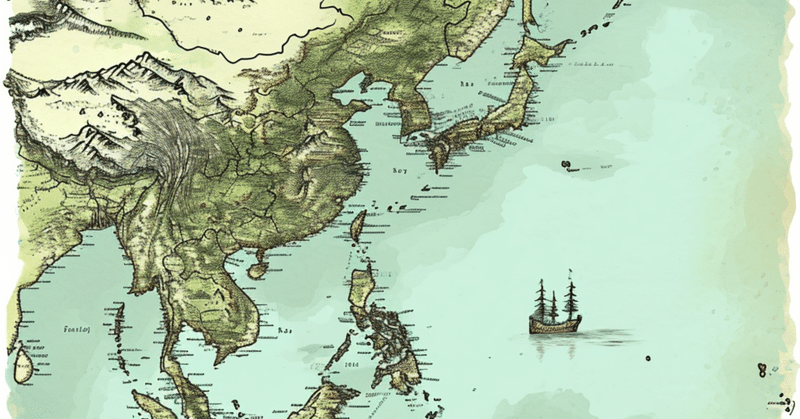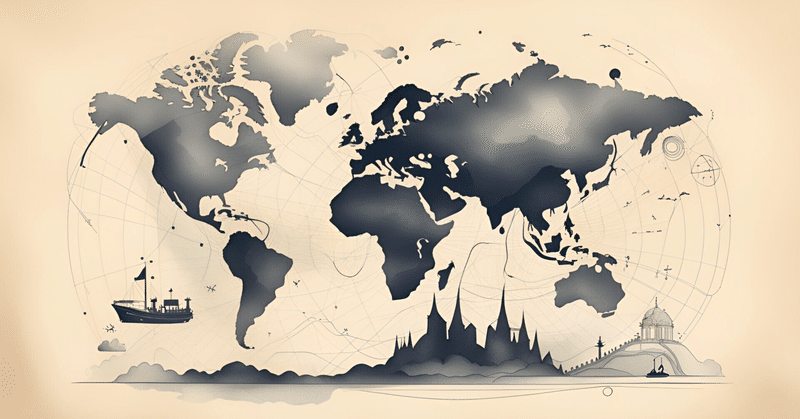#日本
受動と能動の教育思想史 ~個々それぞれ~
受け身で学ぶ。自ら進んで学ぶ。
色んな方法がありますよね!
人間は千差万別、という前提に立てば
学び方もまた千差万別で、
強制的にでも学んだほうが良いケースもあれば
能動的が良いケースもある…と思われます。
一方だけには決められない。
受け身で学ぶから、100%良い/悪い。
能動的に学ぶから、100%良い/悪い。
それは極論、言い過ぎ。
実際には両方ある。混ざっている。
ただ、そのどちらか
ジャガイモが動かす世界 ~アンデスから月面まで~
ジャガタラのイモ、略してジャガイモ!
庶民の味方、ジャガイモは
江戸時代前後に日本へやって来ました。
出身はアンデス、南アメリカ。
経由はジャガタラ、今のジャカルタ。
…しかしカボチャやサツマイモと違い、
淡泊な味のジャガイモ栽培は
江戸時代の日本ではそこまで広がりません。
本格的に栽培されたのは、明治時代です。
「いも判官」とも呼ばれた
湯地定基(ゆちさだもと)は
クラーク博士の下で農業を
インドネシアと南海の女王
海岸に緑色の服を着ていってはいけない…。
そんな言い伝えが
インドネシアの南の海岸にはあるそうです。
「ニャイ・ロロ・キドゥルの伝説」。
直訳すれば「南の(海の)女王様」です。
彼女の好きな色は緑色。
海岸で緑色の服を見つけると、
この女王は「自分の召使い」と思ったり、
「マイカラーを使われて嫉妬」したりして、
海にひきずりこむ、と言われています。
ジャワ島の南部、インド洋の海岸で
緑色の服
「一国一城の主」精神 ~日本の自営業者の推移~
日本の総雇用のうち、約1割は自営業者。
逆に言えば、約9割は自営業者ではない。
雇用されている、と言えます。
2024年の総人口は約1億2千万人台。
そのうちの労働人口は約6千万人。
この約1割、ですから、
「約6百万人」が自営業者です。
(ただし、家族従業者を含む数ですから、
真正の自営業者はもっと少なくなる)
読者の皆様はどう思われましたか?
思ったより多い? それとも少ない?
では、他
歴史の描き方、生まれ方 ~世界史の誕生~
個人、集団、一国、世界の歴史とは?
この四つを仮定してみます。
パーソナル・ヒストリーは、
ある一個人の歴史。
自分のヒストリーならマイ・ヒストリー。
「個人史」「自分史」になります。
これが集団ならワンチーム・ヒストリー。
「ある集団」のヒストリー。
家族、会社、学校、市町村、コミュニティ…。
個人ではなくなっていきます。
さらに広げると「国」単位。
日本で言えば「日本史」ですね!
ナシ