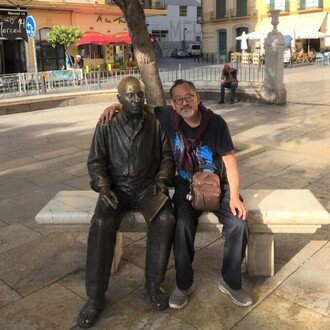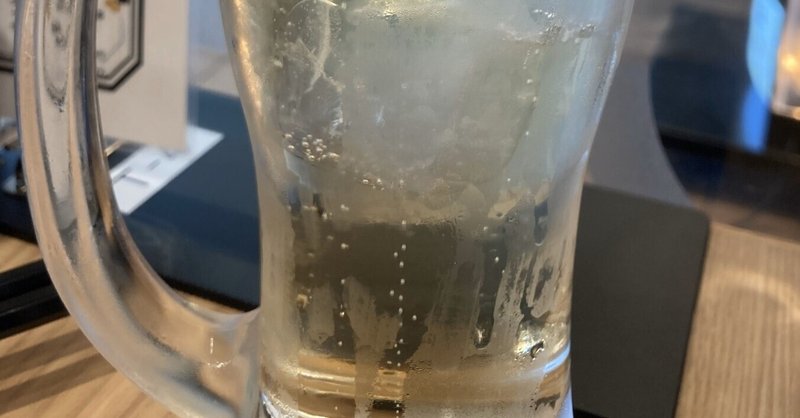#文学
<書評>『悲劇の死』
『悲劇の死 The Death of Tragedy』ジョージ・スタイナー George Steiner 喜志哲雄 蜂谷昭雄訳 筑摩書房 1979年 原書は1961年
本書の内容は、もちろん本文が中心なのだが、スタイナーによる最後の解説的な第10章とそれを補足する訳者の解説は、最初に読むべきだと思った。最初に読んでいれば、本文の感じ方がかなり異なった気がする。
アメリカ人ジョージ・スタイナ
<書評>『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』
『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ Rosencrantz and Guildenstern are dead』 トム・ストッパードTom Stoppard 著 松岡和子訳 原著は1967年 翻訳は1985年 劇書房
20世紀を代表する不条理を描いた劇作家の一人、チェコ人ながら英語圏で成長した英語作家のトム・ストッパードによる、シェイクスピアの『ハムレット』に名前だけ登場する人物二人
<書評>『デカメロン』
『デカメロン Decameron』 ジョバンニ・ボッカッチョ Giovanni Boccaccio著 平川祐弘訳 2017年 川出書房文庫全三巻 原著は、1351年のイタリア、フィレンツェ
翻訳者曰く、ダンテ・アリギエリ『神曲』に並ぶ、イタリアルネサンスが生んだ世界的かつ歴史的な名著である。そして、巷間に流説している艶笑物語集だけではないことが、実際に全文を読むことでわかる。多くの人が、まった
自由律俳句(その8)
〇 2023年9月27日。酷暑の夏が終わり、久々に公園を散策する。季節的に花は少ないが、曇天の中に見える太陽が力強い。そして、トンボが飛び、鈴虫が草の中で音楽を奏でる。ふと見ると、大木の下に草花の芽が大きく出ていた。私もようやく芽が出るのか?散歩をすると、詩作が浮かぶ。不思議だ。
腰が伸びない私を 傍で見守るトンボよ お前よりは長生きしているぞ
無視すれば近寄り 探せば逃げるトンボ お前の名は
<閑話休題>2022年のまとめと2023年の抱負
明けましておめでとうございます。旧年中のご愛顧を感謝申し上げますとともに、引き続き本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
2022年4月以降は、定年退職して時間ができたこともあり、読書及び創作活動に勤しむことができた。そこで、2022年のまとめと2023年の抱負を書きたい。
1.読書
(1)2022年のまとめ
なんといっても、ダンテ『神曲』を邦訳ながら読了できたこと。翻訳しているせいも