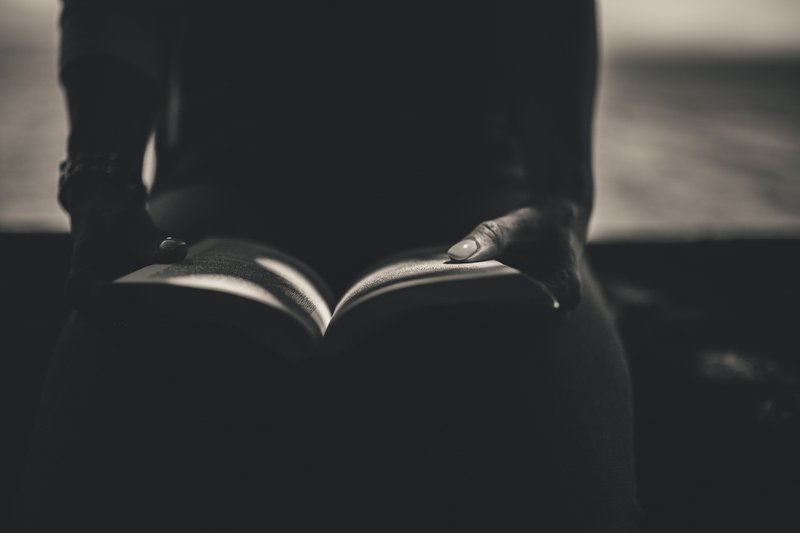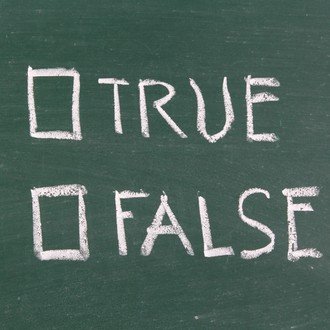#ニュースで語る
宮本常一に学ぶーー「文化」「芸術」を支えるのは「自ら功を誇らない」人々
▼東京の府中に、日本一大きな太鼓がある。宮本常一は、その太鼓は会津で作られた、という話から、「復興と文化」について、忘れがたい話を語っている。今号は、その講演を紹介したい。
「民衆文化と岩谷観音」という講演が、1978年の冬、山形県東村山郡中山町の中央公民館で行われた。
この講演は、いま手に入る本としては、河出文庫の『日本人のくらしと文化 炉辺夜話』と、農文協の『宮本常一講演選集2 日本人の知
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(6終) ゾーニングの知恵
▼アレックス・カー氏と清野由美氏の『観光亡国論』を読むと、「ゾーニング」という言葉の意味について考えるきっかけになる。
▼「ゾーニング」と「分別」とについて言及している箇所を、大切なところなので、再度引用しておく。
〈清野 日本で「ゾーニング」というと、都市計画法で定める住居専用地域とか、商業地域、工業地域といった「用途指定」のこと、という理解が一般的ですが。
カー それはごく狭義のもので、
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(5) ゼロドルツアーの恐怖
▼アレックス・カー氏と清野由美氏の『観光亡国論』を読んでいる。
両氏の対談で、日本の観光産業の問題点が浮き彫りにされている。
カー氏いわく、
〈日本の観光業では、全盛期の高度経済成長期の「クオンティティ・ツーリズム(量の観光)」が、いまだに根を張っており、今の時代に通用する「クオリティ・ツーリズム(質の観光)」については浅い理解になっていることです。〉(168頁)
▼20世紀の「量」と、2
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(4) ユネスコサイド
▼「ユネスコサイド」という物騒(ぶっそう)な言葉がある。
ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が悪い、というわけではない。
〈最近のヨーロッパや東南アジアでは、ユネスコの世界遺産登録を受けて、観光業で汚染された場所を「ユネスコサイド」という言い回しで表現するようになっています。〉(『観光亡国論』154頁)
▼本書では中国の雲南省にある「麗江(リージャン)」という町や、ミャンマーの「バガン遺跡
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(3) 黒門市場の成功
▼前号は京都の観光名所の2つの悪例、「二条城の襖絵」と「錦市場」の惨状について触れた。キーワードは「稚拙化」。
▼アレックス・カー氏の『観光亡国論』から。
▼スペインはバルセロナの「ボケリア市場」は、〈自撮り棒を持った観光客で埋め尽くされるようになっています。〉ということで、〈地元の人たちは「もうボケリアには行けない」と嘆いているのです。〉(151頁)
▼いっぽう、「なにわの台所」たる大阪の
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(2) 京都の「稚拙化」
▼アレックス・カー氏は『観光亡国論』で、日本の観光が「ゾンビ化」したり、「フランケンシュタイン化」したりしている、と指摘している。
「ゾンビ化」とは、「昔の様式をそのまま守っていくやり方」で、「フランケンシュタイン化」とは、たとえば観光名所の観光名所たる勘所(かんどころ)を見失ってしまい、お化けみたいな代物に変わり果ててしまうことを言う。
ということを前回、紹介した。
▼アレックス・カー氏は
『「いいね!」戦争』を読む(19)人間が「フェイク」化しつつある件
▼ロシアが、たとえば「トランプを熱烈に擁護するアメリカ人」のアカウントを捏造してきたことは、国際的な大問題になったから、すでによく知られるようになった。
筆者は『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」を読んで、2017年にツイッターに登場した「アンジー・ディクソン」という有名な女性女性が、〈ツイッターを侵食し、アメリカの政治対話をね
『「いいね!」戦争』を読む(18) SNSが「グローバルな疫病」を生んだ件
▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」では、人間の脳がSNSに、いわばハイジャックされている現状と論理が事細かに紹介されている。
▼その最も有名な例であり、その後の原型になった出来事が、2016年のアメリカ大統領選挙だった。それは、何より「金儲け」になった。本書では
「偽情報経済」(216頁)
という術語が使われているが、フランスでも、ドイツでも、スペイ
『「いいね!」戦争』を読む(17)SNSは「承認」が最大の目的の件
▼前号では、「フェイクニュース」という言葉が広まっただけでなく、「フェイクニュース」の「定義」そのものが変えられてしまったきっかけが、アメリカ大統領選挙であり、なかんずくトランプ氏の行動だったことに触れた。
「フェイクニュース」は、もともとの「真実でないことが検証可能なニュース」という意味から、「気に入らない情報を侮蔑(ぶべつ)する言葉」、つまり、「客観的」な言葉から、とても「主観的」な言葉に変
『「いいね!」戦争』を読む(16) 「フェイクニュース」誕生の論理
▼ここ数年、ネットの中で「嘘(うそ)」が蔓延(まんえん)するスピードが、やたら速くなった。
すでによく知られるようになったある常識について、『「いいね!」戦争』がわかりやすく説明していた。
ちなみに2019年7月10日の21時現在、まだカスタマーレビューは0件。
▼MIT(マサチューセッツ工科大学)のデータサイエンティストたちが、ツイッターの「噂の滝(ルーマー・カスケード)」(まだ真偽が検証
『「いいね!」戦争』を読む(15) 「アラブの春」が独裁に繋がった理由
▼「アラブの春」が、なぜ独裁主義に吸収されてしまったのか。『「いいね!」戦争』は、「確証バイアス」や「エコーチェンバー」現象などの知見を使って絵解きしている。
▼毎度おなじみ、カスタマーレビューはまだ0件だ。2019年7月10日10時現在。
▼以下の引用箇所を読めばわかるが、この経緯から引き出せる教訓は、「アラブの春」だけに限った話ではない。ジョージ・ワシントン大学公共外交・グローバルコミュニ
『「いいね!」戦争』を読む(14) 「確証バイアス」は脳の最悪の衝動の件
▼「インターネットと戦争と生活」について考えさせられる名著『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」は、人間の「脳」をめぐるネット戦略の中間報告になっている。
▼2019年7月8日現在で、まだカスタマーレビューは0件。0件のまま半月も経つと、なんだか面白くなってきた。
▼前回は、記事が真実であるかどうかは重要ではなく、「なじみがあるかどうか」で判断が分かれる、と
『「いいね!」戦争』を読む(13)記事は「真実」でなくても構わない件
▼今号で紹介するのは、「オンラインの生態学」とでもいうべきものだ。
『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」の続き。
▼前号は、最近よく目にする「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」の簡単な解説だった。
▼ところで、『「いいね!」戦争』には、まだアマゾンでカスタマーレビューが1件もつかない。2019年7月7日現在。
▼先に「オンラインの生態学」と書いた