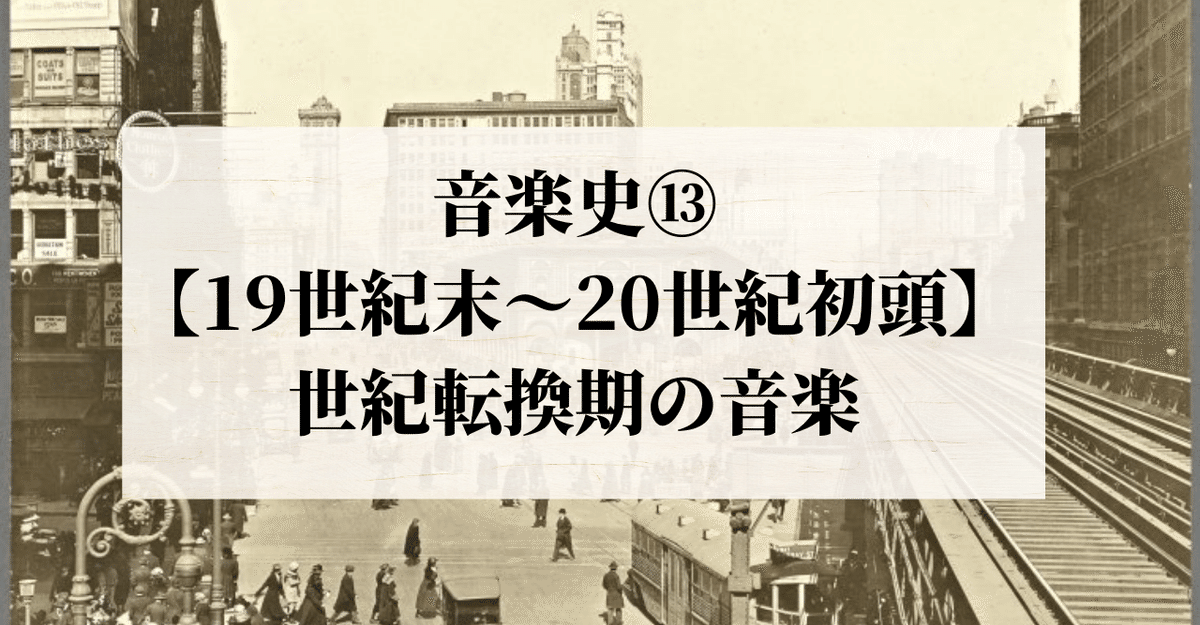
#18 音楽史⑬ 【19世紀末~20世紀初頭】世紀転換期の音楽
クラシック音楽史とポピュラー音楽史を並列でつなげる試みです。このシリーズはこちらにまとめてありますので是非フォローしてください。
これまでの記事↓
(序章)
#01「良い音楽」とは?
#02 音楽のジャンルってなに?
#03 ここまでのまとめと補足(歴史とはなにか)
#04 これから「音楽史」をじっくり書いていきます。
#05 クラシック音楽史のあらすじと、ポピュラー史につなげるヒント
(音楽史)
#06 音楽史① 古代
#07 音楽史② 中世1
#08 音楽史③ 中世2
#09 音楽史④ 15世紀(ルネサンス前編)
#10 音楽史⑤ 16世紀(ルネサンス後編)
#11 音楽史⑥ 17世紀 - バロック
#12 音楽史⑦ 18世紀 - ロココと後期バロック
#13 音楽史⑧ フランス革命とドイツ文化の"救世主"登場
#14 音楽史⑨ 【19世紀初頭】ベートーヴェンとともに始まる「ロマン派」草創期
#15 音楽史⑩ 【1830~48年】「ロマン派 "第二段階"」 パリ社交界とドイツナショナリズム
#16 音楽史⑪【1848年~】 ロマン派 "第三段階" ~分裂し始めた「音楽」
#17 音楽史⑫ 【19世紀後半】 普仏戦争と南北戦争を経て分岐点へ
〈今回〉#18 音楽史⑬ 【19世紀末~20世紀初頭】世紀転換期の音楽
前回は19世紀後半の特にヨーロッパの普仏戦争(1870~71)後、そしてアメリカの南北戦争(1860~65)後の音楽を取り上げました。今回は19世紀末からスタートし、20世紀に入り、第一次世界大戦が勃発するまでの「世紀転換期」です。
ラテン音楽の趨勢
19世紀後半、アルゼンチンで発生したミロンガは、ウルグアイのアフリカ系民族の踊りであるカンドンベや、スペイン系のハバネラと融合することによって、19世紀末にタンゴが誕生します。1900年代になり、バンドネオンや弦楽が導入されました。1900~20年代まで、「ダンスミュージック」として数多くのタンゴスタンダードが作られ、「グアルディア・ビエハ(古いタンゴ、古典曲)」と呼ばれています。(「ラ・クンパルシータ」など。)
パリなどに持ち込まれたタンゴは「ヨーロピアン・タンゴ」として人気になり、日本では「コンチネンタル・タンゴ」と呼ばれ1910年代に流行しました。
また、ヨーロッパで誕生したバンドネオンという楽器がこの時期アルゼンチンに持ち込まれ、タンゴの伴奏楽器として急速に普及しました。バンドネオンはヨーロッパでは定着せず、今でも「アルゼンチン音楽のための楽器」という立ち位置だと言っていいほどになっています。
19世紀後半、キューバで誕生したソンは、キューバの基幹音楽として発展していました。19世紀末、スペインから伝わったコントラ・ダンサ(舞踊)が「ダンソン」として流行します。
ダンソンの要素やアフリカ音楽の要素を吸収しながら、「ソン」は発展していきました。ボンゴやギロなどの楽器が追加されていき、1910年代より、アメリカ全土へ広まっていきます。
「ソン」の特徴は「クラーベ」というリズムです。もともと西アフリカをルーツとする、鍬(くわ)を打ち付けて演奏されていた3連符のリズムが、カリブ海諸国で3連符でないものと合体し、「ルンバ・クラーベ」「ソン・クラーベ」が誕生しました。
ブラジルでは19世紀末ごろ、かつて黒人奴隷が多く投入されていたバイーア地方で、複数の打楽器によるバトゥカーダ(バトゥーキ)という音楽が形成されていました。その後リオに持ち込まれ、ポルカ、ハバネラや、19世紀後半に生まれていたショーロなどと融合していきます。ショーロは、ピシンギーニャ(1897~1973)によって近代的なハーモニーが当てられ、発展していきました。
ショーロは1910年代にサンバの誕生にもつながっていきました。
(※「ラテン音楽」として混同されがちですが、ポルトガル語圏のブラジリアン音楽は、スペイン語圏のキューバン音楽とは基本的に異なっており、ラテン音楽には入らない、との意見まであるほどです。)
劇場娯楽産業・大衆演芸の隆盛・・・ヴァラエティー、ヴォードビル、レビュー、ミュージカルコメディ、アメリカンオペレッタ
ロンドンで一大娯楽産業となったミュージックホールですが、徐々に出し物に対する規制が緩和されていき、1880年代後半~、アクロバット、手品・奇術、パントマイム、寸劇、レビューなどの「ヴァラエティー」へとシフトしていきつつありました。特に寸劇やコントがブルジョア階級の客層を招くことのできる健全な娯楽として大幅に取り入れられるようになりました。ミュージックホールでは火災が相次いだために、安全性や建築の観点から規制が強まったほか、新たなロンドン州議会がライセンス制を掌握して規制を強め始め、ミュージックホールは変革を迫られます。結果、ミュージックホールの出し物の多様化を当局が認める形で、同時に泥酔や深酒の抑制がなされました。これまで「酒を飲みながら歌や踊りを楽しめるところ」だったのが、「ヴァラエティを観ながら酒も嗜めるところ」へと変わっていったのです。
さらに、上流層を引きつける「レスペクタビリティ」を徹底するため、座席料金に差を設ける、演し物中の出入りや移動の禁止など、客の「観客化」が進められたほか、「宮殿(パレス)」と呼ばれる豪華な建物、換気機能や安全面の改善、邪魔な柱を無くす、など、徹底した洗練化が行われ、1879年エジソンが発明した白熱電球などによってさらに舞台照明も改善されました。
この時代になると、鉄道網の発達により「旅行」「観光」がブームになっており、1900年までには主要な各地点に駅ができ、「観光コース」もうまれました。そしてロンドンの観光コースに各ヴァラエティーシアターが組み込まれるようになります。街灯によって子連れや女性客も夜の外出が安心してできるように。旅回りの一座を「待つ」時代から、演し物を観たければ「観に行ける」時代になったのでした。
こうしたイギリスの「ミュージックホールからヴァラエティシアターへ」の変遷に相当するのが、アメリカでの「ミンストレルショーからヴォードビルへ」の変遷です。
エジソンの白熱電球の発明による舞台照明や舞台装置の変革、街灯の増加とニューヨーク・ブロードウェイの劇場街の発展、鉄道網の発達によるサーカスなどの巡業の大型化が進んでいき、劇場娯楽産業が隆盛を極めます。ミンストレルショーは初期の人気のピークは過ぎ、内容がヴァラエティ化していきました。
ヴォードビルの父と呼ばれるトニー・パスター(1837~1908)が、1881年にニューヨークに開いたフォーティーンス・ストリート劇場で、ミンストレルショーやイギリス由来のヴァラエティーといった従来の野卑なものに対して、本格派の歌手、コメディアン、曲芸師などを使った正統的で洗練されたショーを公演して成功、以後この種のものが主流となり、1890年から20世紀初頭にかけて全盛期を迎えます。1883年、バファロー・ビルが「ワイルド・ウエストショウ」という大型ショーを始め、ベンジャミン・フランクリン・キースが自分の大型ヴァラエティショーに「ヴォードビル」と名付けたのも1883年。これらが世紀末にはミンストレルショーに代わって人気となりました。
また、フランスではレビューという、年の終わりに一年の出来事を回顧(レビュー)する時事的な風刺劇が生まれ、やがて歌とダンス、コント、スケッチなどを組み合わせて豪華な装置や艶やかな衣装で観客を楽しませるショーの意味に転じました。(このレビューが、日本の宝塚歌劇団の生成に影響を与えます。)「レビュー」も、1894年にブロードウェイに渡ります。雑多な芸の寄せ集めだったヴォードビルと異なり、レビューではショー全体に統一されたコンセプトが存在していました。ここから、劇場演芸全体が統一されたスタイルへと変容する兆しが見られるようになります。
ニューヨーク市の中心部マンハッタンは、南北がアヴェニュー(番街)、東西がストリート(丁目)と名付けられており、7番街と42丁目の交差点で斜めに交わる通りがブロードウェイです。現在、劇場が集中する42丁目から北側には、19世紀末は劇場はなく、42丁目より南側でミンストレルショー、ヴォードビル、オペレッタが連日、客を集めていました。42丁目界隈は「テンダーロイン」と呼ばれ、猥雑なショーを見せる一大歓楽街を形成していました。20世紀に入るとブロードウェイには白熱電球による看板が掲げられます。1898年のボストンに次いでアメリカで二番目の地下鉄がニューヨークに1904年に開業、1910年には現劇場街にも地下鉄が通り、大きく発展します。同1904年、7番街と42丁目の交差点に、ニューヨーク・タイムズ新聞社本社ビルが移転してきたことから、交点の広場が「タイムズ・スクエア」と名付けられ、ブロードウェイの中心地として賑わうようになりました。
19世紀後半のパリやウィーンで、オッフェンバックやスッペらによって栄えたオペレッタは、イギリスでは「コミック・オペラ」「サヴォイ・オペラ」という名で流行しており、それらがブロードウェイにも伝播していました。さらに19世紀末~20世紀初頭にかけて、ヨーロッパから数多くのオペレッタがブロードウェイへ輸入されます(「フロロドーラ」「メリー・ウィドウ」「チョコレート兵士」など)。
こうした輸入オペレッタと並行して、アメリカ・オリジナルの創作オペレッタも作られるようになっていき、それらを担ったのがヴィクター・ハーバート(1859~1924)、ルドルフ・フリムル(1879~1972)、シグムンド・ロンバーグ(1887~1951)の3大オペレッタ作曲家でした。3人ともヨーロッパ出身で、クラシック音楽の基礎を学んだあとアメリカに渡って大成しました。
19世紀末のヨーロッパ的なオペレッタは、20世紀に入るとアメリカらしいスピード感ある口語的な音楽劇へとシフトしていく傾向になります。ジョージ・M・コーハン(1878~1942)が、歌って踊れる俳優として、さらに作詞・作曲・脚本・演出・興行師としても一人ですべてこなす才能として活躍しました。「ブロードウェイの父」と呼ばれ、タイムズ・スクエアに銅像が立っています。
このころ、コミカルな音楽劇に対して「ミュージカル・コメディ」という言い方が登場したといいます。その後、コメディの枠組みに収まらないものは「ミュージカル・プレイ」と呼んだり、総称して「ミュージカル・シアター」という言い方も出現し、こんにちの「ミュージカル」の語源になったとされます(諸説あり)。
こうして、ヴォードビル、アメリカン・オペレッタ、レビュー、ミュージカル・コメディなどを中心に、ニューヨーク劇場街ブロードウェイが繁栄のときを迎えました。
こうした劇場音楽は、興行が終わればストーリーではなく楽曲のみが残る、という考え方だった時代。楽曲が残されるメディア・ツールは、クラシック音楽と同じく「楽譜」でした。1877年のエジソンの円筒形「フォノグラフ」や、1887年のベルリナーの円盤型「グラモフォン」など、蓄音機の発明によって産声を上げた録音メディアの歴史ですが、1900年前後には1分間に78回転のSPレコードが標準になり、コロムビアとビクターの2台レコード会社が中心となって録音活動を活発化させていきます。しかし、前回書いた通り、電気を使わないアコースティック録音の段階では音質はまだまだ劣悪で、録音メディアが一般的に普及段階になるのはもう少し先になります。
19世紀後半、ブルジョワ階級の一般家庭にピアノがだんだんと普及していっており、憧れ・ステータスとなっていました。ミンストレルショウの段階から、その上演曲や民衆のヒットソングは家庭で気軽に演奏できる形での「シート・ミュージック」として出版されていましたが、他のクラシックの楽譜や讃美歌集と同じように、ヨーロッパ的な教養のもとの「文化」としてとらえられており、宣伝にはあまり力を入れてはいませんでした。ところが世紀転換期になると、シートミュージックに特化した音楽出版社が数多く誕生します。劇場や娯楽施設で歌われる楽曲を「商品」として管理する新しい形態は、都市の音楽的需要にあわせて勃興した、まったく新しい産業でした。はじめは各所に乱立していた音楽出版社ですが、次第に一つの地区に場所が集中するようになります。各出版社は自社の楽譜を売り込むため、ドアを開け放ち、アップライトピアノの蓋も取っ払い、朝から晩までプレゼンテーションをし続けていました。この激しい宣伝合戦は音の洪水を呼び、まるで鍋釜でも叩いているような賑やかな状態を揶揄して、この地域のことを人々は 「ティン・パン・アレー」(日本語訳すると「ドンチャン横丁」「どんがらがっしゃん通り」など)と呼ぶようになります。
「音楽出版社」は、楽譜をただ出版するだけでなく、「曲を作って楽曲を買い取らせる」という音楽ビジネスを誕生させました。各出版社が専属の作曲家を雇い、曲を作らせる。宣伝のために劇場のスターやシンガーにも売り込み、歌ってもらう。こうして人々に親しまれた楽曲が楽譜として売れる。このような「作曲家と演者」の分業システムがアメリカ流のビジネスとして成り立ち、アメリカン・ポップスの伝統となっていきます。ティン・パン・アレーでは、工場の商品生産のように、流れ作業で楽譜や楽曲を量産していき、聴衆の心をつかむポピュラー音楽のフォーマットが確立されていきました。いつしか、この地域で誕生するポピュラー音楽そのもののことが「ティン・パン・アレー」と呼ばれるようになりました。
ラグタイムの人気
19世紀後半に誕生したラグタイムは、1893年のシカゴ万博をきっかけに爆発的に流行し、1910年代まで全米で大流行します。なかでもスコット・ジョプリン(1867-1917)、トム・ターピン(1873-1922)、ベン・ハーニー(1872–1938)が有名です。間違えがちですが、ラグタイムは即興音楽ではなく、ピアノ曲として楽譜に書かれた作品です。アンサンブル用に編曲した楽譜もあり、ジャズとは音楽的な影響はあれど性格を異にしています。
ニューオーリンズ・ジャズとディキシーランドジャズ
クレオールによる西洋的な音楽に黒人のフィーリング・即興性が加わり、ニューオーリンズ周辺で産声を上げた黒人たちの演奏を総称してのちにニューオーリンズ・ジャズと呼ぶことになるのですが、その実態はブラスバンドの影響を受けた即興的で力強い黒人音楽もあれば、クレオールによるクラシックの室内楽的な白人向けのものもあるというふうに、さまざまでした。
1897年に、ニューオーリンズには「ストーリーヴィル」という売春容認地区が置けられ、黒人たちの仕事場が数多くでき、白人に受け入れられる演奏をする機会が数多く生まれます。さらに、街灯や広場のパレードが当たり前だったこの時代、街にはブラスバンドがたくさんありました。その中でコルネット奏者 バディ・ボールデン(1877~1931)が編成したバンドが人気を得ます。音響設備が無くマーチングバンドなどでも音量のためにその編成は常に20人以上が必要だった時代、バディ・ボールデンはコルネット、クラリネット、トロンボーン、チューバ(or ウッドベース)、バンジョー(or ギター)、ピアノ、ドラム、で構成される総勢7~8人の少人数バンドで人々の話題を集めたのでした。これが史上初のジャズバンドとされます。また、それまでクラシックでは打楽器奏者は小太鼓、大太鼓、などと複数人に分かれていたのが、ディー・ディー・チャンドラーと言う小太鼓奏者が、右足で大太鼓を打ち鳴らすフットペダルを考え出し、小太鼓と大太鼓を同時に演奏して話題を呼びます。ここからドラマーは椅子に座る様になり、そうなると左足ではシンバルを鳴らそう、とハイハット・シンバルの原型が考え出され、複数人数が絶対条件だった打楽器がドラムという一人で演奏可能な楽器に進化を遂げました。バディボールデンはここに目をつけ、少人数バンドを実現し、名声を挙げたのです。このころ、ジャズやブルースでコントラバスが使われ始め、ウッドベースと呼ばれるようになります。
当時、南部一帯を指してディキシーランドという俗称が付いていたため、ニューオーリンズジャズは別名をディキシーランド・ジャズとも呼ばれた、という話があります。しかし、やがて白人の中にも黒人のジャズを真似て、同じような編成で演奏するバンドが出てくるようになり、こちらを黒人のニューオーリンズジャズと区別してディキシーランド・ジャズと呼ばれた、とも言われています。ディキシーランドジャズと呼ばれるようになってから、アメリカ全土やヨーロッパへも広まっていきました。
このころのストーリーヴィルで人気のジャズピアニストだった、ジェリー・ロール・モートン(1890~1941)は、ラグタイムピアノの進化形といえるピアノソロのスタイルをつくるなど、最初期のジャズの偉人とされています。しかし、自分の名刺に「ジャズとスウィングの創始者」と記すなど、派手な性格で、自慢話で話題を呼ぶのが好きだった彼は誇大表現も多く、「ホラ吹きモートン」とも呼ばれていました。現在のポピュラー音楽での共通言語であり記譜の前提であるコード表記はモートンが考案したと言われていますが、真偽のほどは確かではありません。しかし、いずれにしてもニューオーリンズジャズの発達したこの時期にコード表記が生まれたということは確かなようです。
ニューオーリンズ出身の白人ジャズ・バンド、「オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンド(Original Dixieland Jass Band)」は、1917年に世界で初めて、ジャズのレコード音源を発表したバンドとして知られています。これを起点に「ジャズの誕生」と捉え、2017年にはジャズ生誕100年が祝われたりしました。どうやら、それ以前にもニューオーリンズジャズ的な音源は存在していたようですが、当時まだJazzという語が無く、Jass House Music(売春小屋音楽、Jass=性交を意味するスラング)など言われていたり、ラグタイムやブルースなどと未分化だったり、という理由があるようです。ジャズの語源には諸説ありますが、ともかく1917年の初のジャズ音源の発売をもってジャズの正式な誕生と位置付ける考えが主流となっています。
1917年、アメリカの第一次世界大戦参戦にともない、ストーリーヴィルは突如閉鎖されてしまいます。これにより、黒人音楽家たちは職を失って当てのない暮らしが始まり、ニューオーリンズを離れてシカゴやニューヨークへと離れていき、ジャズの新たな段階へと進んでいきます。
「ブルース」の伝播
奴隷時代のフィールド・ハラーから発達し、ミシシッピ州デルタ地帯にて産声を上げたとされるブルースですが、W.C.ハンディ(1873~1958)というミュージシャンが紹介したことで、全米に「ブルース」の語が広まっていきました。ハンディは「ブルースの父」と呼ばれていますが、実は彼の功績は黒人たちの土着の音楽を楽譜に起こして紹介したということなのです。
ハンディはクラシック音楽の訓練を受けたミュージシャンで、ミンストレルショーなどのバンドリーダーとして活躍していました。活動を続けながら南部を旅していたあるとき、1903年に、弦に押しつけたナイフをスライドさせながらギターを弾く男を目撃し、衝撃を受けます。楽譜など無かったこのような音楽をハンディは分析・採譜し、楽譜出版したことで大成功をおさめたのです。「彼らの音楽は、音階の3番目と7番目の音が下がっている(ブルー・ノート)」「セブンスの和音を基礎とした3コードで12小節をひとまとまりにする」など、西洋音楽的視点からブルースを解析・体系化し、1910年以降ハンディ自身もブルースの作曲に専念します。「メンフィス・ブルース」「セントルイス・ブルース」など多数のヒット作を生み出しました。
このようなブルースのヒットは、ティン・パン・アレーのシートミュージックを通じて広まったのです。つまり、ハンディの広めた「ブルース」は、ヴォードビル音楽と同じように、都会的な洗練された音楽として拡大していったのです。このもう少しあとに、原始的なイメージを持ったブルースの人気が起こることになります。一般的なブルース史観では「原始的ブルースから都会的ブルースへ」という、逆の順番のイメージで語られることが非常に多いのですが、実は逆なのです。クラシック音楽史と同じように、「原始的なものから複雑なものへ」という一直線の歴史観で体系化するとわかりやすくはなるのですが、そこにはかならず、時系列的に不可解な疑問が発生してきます。実際のところは、ヴォードビルやラグタイムやジャズなどの同時代音楽と相互作用を起こしながら、ブルースは発展していきました。
先述したとおり、現在ニューオーリンズジャズと呼ばれている音楽も当時まだ「Jazz」というスペルでは無く、「Jass(売春宿音楽)」などと呼ばれる、音楽の正式ジャンルではなかったのですが、その「初期ジャズ」とは、ブルースや黒人霊歌などの黒人音楽を演奏するための、演奏スタイルの一つだった、という言い方もできるのです。初期ジャズの曲名に『~~ブルース』というタイトルが非常に多いのもこのためです。このあとジャズは、音楽のジャンルとしての地位を高め、ブルースから独立して別の発展をしていくわけですが、ともあれ、20世紀初頭のアメリカのポピュラー音楽は、ティンパンアレーの楽譜出版を軸に、ヴォードビルの音楽、ブルース、ジャズがすべて渾然一体となって「都会の音楽」というイメージで広まった、と考えるのが一番妥当でしょう。
映画の誕生
1877年に蓄音機を発明したエジソンは、「音」の次に「映像」に関心を向け、動画記録装置の研究を進めました。そして発明を完成させ、1891年に内輪向けに公開します。ヴォードビルやヴァラエティの芸人を読んでは演し物を撮ったり、芝居の一場面、ボクシングの試合、ダンスなどを撮ったりしました。その後「キネトスコープ」として1893年に一般公開します(シカゴ万国博覧会に出展)。この地点では、映像を見るには箱の中を覗き込む〈のぞき穴〉型だったため、多数に向け上映するということはできませんでした。エジソンはその後、他の発明に関心を移してしまいますが、そのあいだにヨーロッパでは、パリのリュミエール兄弟が1895年にスクリーン投影型の 「シネマトグラフ」の発明を成功させました。一般にこれが映画の起源だとされています。リュミエール兄弟は「工場の出口」など計10本の短編映画を商業公開しました。
初めは祭りや定期市など人の集まる場所で上映されるうち、さらに当時の市民の馴染みの場所だったミュージックホールやヴォードビル劇場の演し物の一部として上映されるようになり、大人気となります。
やがてヴォードビルを真似て、店先をやっつけで改良したような上映ルームや、芝居小屋を無理やり押し広げたような即席ホールが次々と登場し、映画専門小屋として大ヒットします。こういった小屋は入場料が5セント(ニッケル硬貨)だったため、「ニッケルオデオン」と呼ばれ親しまれました。ニッケルオデオンは、貧しい庶民の社交場となり栄えました。
「音」に関して、一説によれば1895年からの5~6年間は本当に「音無し」だったといわれますが、別の説によれば、映画が生まれて2~3年で劇場では音を付けていたとも言われます。このあたりはハッキリ無いのですが、20世紀になると同時くらいに、どうやらサイレント映画に上映現場で音を付けることを試み始めたようです。ヴォードビルやミュージックホールといった場では「鳴り物」は必須でした。
そもそも演劇などにつく「付随音楽」は、紀元前5世紀ごろの古代ギリシャの劇音楽にその歴史を遡ることができますが、ルネサンス後のシェイクスピア劇などを経てバロック期に誕生したオペラやバレエなどもルーツといえるでしょう。クラシック音楽のロマン派への変化とともに、劇音楽も音楽の表現分野を広げると思われましたが、やがて「マトモ」に取り扱われなくなってしまいます。音楽というものは「文学・演劇」というジャンルに付随するものではなく、「音楽」という独立した中での「個」の主張として存在するべきだ、という風潮になったのです。「道具としての付随物ではなく、音楽そのものの表現」というベートーヴェン由来のドイツ音楽美学に起因したこの考え方は、ブラームス派の「絶対音楽」とワーグナー派の「標題音楽」「楽劇」の両方の前提となりました。
そして、20世紀に入り、映画の時代が訪れたのです。「オペラ」「オペレッタ」「楽劇」などはいずれも音楽表現と文学表現・劇そのものが一体で考えられる芸術であるので、映画の誕生により「映像」と「音楽」が一度分離したことによって、完全な「付随音楽・BGM」としての役割の音楽の歴史が、ここから始まったといえるでしょう。
初期の映画音楽のつけ方には、大きく2パターン存在しました。
①映画館ごとに、その場の音楽家が適当な音楽を現場でつけるパターン
②映画製作者側が専用の音楽(スコア)を用意したパターン
①映画館ごとに、その場の音楽家が適当な音楽を現場でつけるパターンでは、大半はピアノかオルガンで自己流で演奏され、一部のキュー・シートの指示には従ったものの、映像に合わせて自己のインスピレーション、音楽知識と技術を総動員して、即興での制作活動ともいえる演奏を行っていました。〈シネマオルガンの時代〉と言われ、「やってみよう」精神を盛んに、効果音を考えたり、スクリーンの裏でいろんな音を出してみたり、セリフをしゃべってみたり、とあらゆる方法が試され、その中でピアニストやオルガニストが大きく注目されました。1909年にはトーマス・エジソン・カンパニーが自社の映画に「よく合う音楽」の楽譜を売り出したり、1913年にはオハイオ州の音楽出版社が「戦いのシーン」「ラヴシーン」などパターン化された音楽を用意した「Sam Fox Moving Picture Music」を売り出し、人気となりました。また、ドタバタコメディ全盛期の1910年代には、チャップリンなどの短編に対してラグタイムの音楽もよく演奏されていたようです。
②映画製作者側が専用の音楽(スコア)を用意したパターンでは、大型の劇場にフル・オーケストラが付き、既存のクラシック曲から書き下ろし曲までがスコアに揃えられ、それを演奏したそうです。選曲された作品としては、ロッシーニ、ベートーヴェン、ヴェルディ、ワーグナー、グリーグ、チャイコフスキー、サン・サーンスなどのクラシック曲から、フォスターなどのアメリカ民謡などまでを総動員して組み立てられました。1908年のフランス映画「ギース公の暗殺」はサン・サーンスが映画のために音楽を担当しました。初期映画界はアメリカではなくフランスの存在感が強く、音楽としてもこの後の時代もしばらくフランスのクラシック作曲家が映画界に比較的積極的に関わることになります。
末期ロマン派
さて、ヨーロッパの学術的な芸術音楽界に話を戻す(?)と、ワーグナーを継承するドイツ美学的「芸術音楽」の系譜として、19世紀末の「末期ロマン派」とも言える段階に入ります。この段階の特徴は、とにかくダイナミックで大仰だということです。転調や和声の複雑化、様式や形式を限界まで汲みつくす傾向も現れ、これ以上の肥大化が不可能なほどの規模の拡大が行われました。
・マーラー(1860~1911)[オーストリア] ・・・ブルックナーに影響を受け、巨大な交響曲や管弦楽伴奏付き歌曲を作った。
・フーゴー=ヴォルフ(1860~1903)[オーストリア] ・・・ピアノ伴奏による歌曲をつくり、「歌曲のワーグナー」と呼ばれた。ブラームスに対し、「シューマン・メンデルスゾーンの亜流」「太古の遺物」などと酷評。
・リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)[ドイツ]・・・リストやワーグナーの流れを受け、交響詩やオペラを作った。
ヴェルディ、ブルックナー、チャイコフスキー、ドヴォルザークら『古参』も、最後の踏ん張りを見せていましたが、総じて和声法が極めつくされ、徐々に「新しい」手法の開拓が困難になっていました。
ブラームスの音楽傾向が“保守的”、ワーグナーやリストが示した和声拡張傾向が“革新的”、という風潮によって形成されたドイツの「わかりやすいものは古い。新しいものはより複雑でなければならない」という音楽美学的史観に芸術音楽界は縛られ続けます。
そもそも、ドイツ的なクラシック音楽には、バッハの時代にはあった即興演奏の文化から、ベートーヴェン以来の「楽譜に設計されたものが芸術作品であり、一音たりとも変えてはならない」という方向への「進歩」の前提があるため、綿密に楽譜に設計されたものではないシートミュージックや即興音楽などの新しいポピュラー音楽は「新しい芸術」ではなく、議論の対象ではありません。さらに、オペレッタからの手法をそのまま継承しているはずのアメリカのブロードウェイ音楽や、クラシックピアノ曲を黒人的に発展させた恰好であるラグタイムなどすら、音楽の進歩史観的には「新しくなかった」ため、クラシック音楽史から完全に無視されています。音楽全体を「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → ・・・」という一方向的な複雑化のストーリーに当てはめて考えると、アメリカ音楽はただ「"古い"音楽」をやっているだけであり、問題ではなかったのです。問題とすべきは「“新しい”音楽手法」の追求であり、それが音楽の学問としての「正解」になっていました。
クラシックとポピュラーの違いをポピュラー側から安易に批判する時に、この点がよく間違えられがちなのですが、クラシックを「古いもの」、ポピュラーを「新しいもの」と位置付けてしまうと、クラシックの美学感覚とは話が合わず平行線のままになってしまいます。クラシック音楽を対象にした批評や学術書にも「古い」「新しい」というふうな表現が多々登場しますが、そこに価値観の分断の落とし穴が潜んでいるのだと思うのです。そこを解き明かすには、この記事シリーズで試みているような、ドイツ美学を外側から眺めた、音楽史の視点の相対化が必要です。
フランス『近代音楽』
従来の音楽史では、音楽理論や形式の複雑さの進歩に沿って、バロック → 古典派 → ロマン派 → 近代音楽 → 現代音楽 の順で「時代」が描かれますが、実際には前述のマーラーらによる後期ロマン派の同時代現象として、フランスで起こった潮流が「近代音楽」であり、第一次世界大戦まで共存していました。
国民音楽協会を中心とした「ドイツに負けない"正統的"な器楽文化をフランスにもつくろう」運動により、フランク、サンサーンス、フォーレ、シャブリエらが、交響曲・協奏曲・室内楽の名作をうみ出しましたが、世紀末になると、後期ロマン派の行き詰まり傾向も相まってアンチテーゼが起こります。
そのはじまりがドビュッシー(1862~1918)です。ワグネリズムは受け継ぎつつ、ドイツ風を拒否してフランスのアイデンティティを確立しようとした動きといえます。ドイツで確立された機能的な和声理論ではなく、和声そのものを「音色そのもの」と位置づけ、ペンタトニックスケール、ホールトーンスケール、中世の教会旋法などを用いることで、「メジャー/マイナー(長短)」中心の調性システムを離れた、浮遊感のある音楽語法を獲得しました。(用語の是非はありますが、同時代の画家 モネ の「印象 - 日の出」やマネらの作品にも共通する美的感覚から、「印象派音楽」とも呼ばれます。)

同じ傾向の作曲家としてラヴェル(1875~1937)が挙げられますが、ドビュッシー的な浮遊感とは異なる精密さで理知的な作品を作り、フランス音楽に新しい風をもたらしました。
「国民音楽協会」の世代との違いは、「独特のダンディズム、スノビズム、通俗性と洗練」だといわれています。ショパンやリストのサロン音楽の伝統も参照していました。かつてサロン音楽は上流社会のためのものでしたが、19世紀も後半になるとカフェやカジノ、キャバレーなどでワルツ・アリアなどの編曲をBGMとして音楽が演奏されるようになっていました。(ドビュッシーやラヴェルの華々しい活躍の陰で無名時代を過ごしていたサティも、キャバレー奏者をやっていました。)
フランスの音楽家はこういったものに興味を示しつつ、さらにエキゾチズム(異国趣味)が加わることで美的感覚が形成されていました。絵画でいうところのドラクロアやゴーギャンの、異国趣味や日本の浮世絵への関心とリンクします。

ドビュッシーの交響詩「海」の楽譜の表紙には、葛飾北斎の冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」の模写が採用されています。
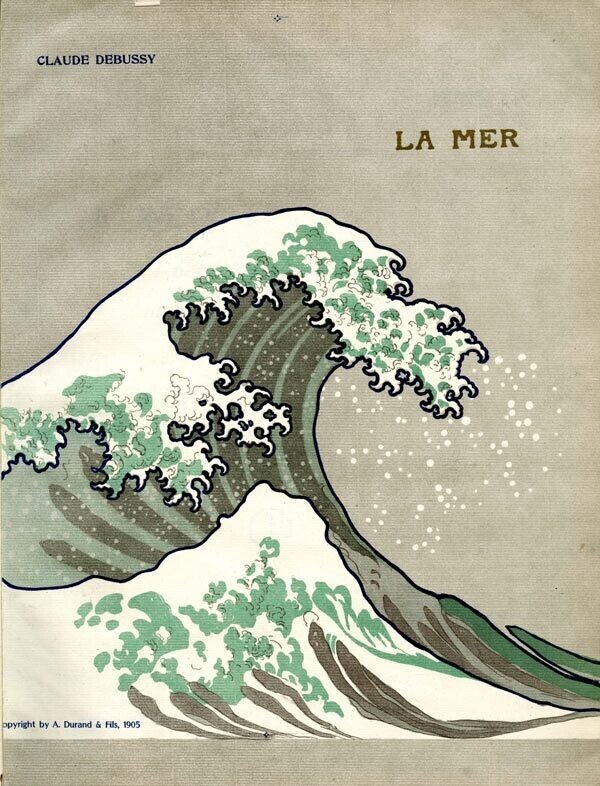
さらにドビュッシーは、アメリカのケークウォークやラグタイムにも関心を示し、「ゴリウォーグのケークウォーク」という曲も残しています。
こうした動きはドイツから見ると、「フランス的軽薄」として非難されていました。ドイツ語圏では、芸術音楽と娯楽音楽の間に厳格な線を引いていたからです。さらに、ドイツは「普遍性」を求める「純血主義」でもあったため、異国趣味との相性も悪かったのです。
蔑まれた国民主義・ロマン派音楽
ヨーロッパ各地方では、20世紀になっても、ロマン主義的な感覚で活動した音楽家も多いのですが、ドイツが中心となっている西洋芸術音楽界は、前進性の無い作曲家を評価しません。あと数十年早ければさらに評価されていたかもしれない人たちが「時代遅れ」と位置付けられ、この段階の時代区分よりも一つ前の「ロマン派」「国民楽派」に分類されてしまいました。
【イタリアオペラ】
演劇史としてはイギリスやアメリカのオペレッタに天下を取られ、芸術音楽としても前時代のものとされてしまったイタリアオペラは、これが最後の栄華といえます。
マスカーニ(1863~1945)
プッチーニ(1858~1924)「蝶々夫人」「トゥーランドット」など
⇒ドイツ楽壇から “聴衆の低俗な本能を助長” “お涙頂戴”と酷評。
国民楽派
【イギリス】
エルガー(1857~1934)「威風堂々」「愛の挨拶」など
ホルスト(1874~1934) 組曲「惑星」など
【フィンランド】
シベリウス(1865~1957)
【ポーランド】
シマノフスキ(1882~1937)
【スペイン】
アルベニス(1860~1909)
グラナドス(1867~1916)
【アメリカ】
マクダウェル(1860~1908)
【ロシア】
ラフマニノフ(1873~1943)
ここで、ロシアには、不思議な和音を操るスクリャービン(1872~1915)という作曲家が登場します。スクリャービンの和音は「神秘和音」と名付けられ、「ロシア神秘主義」としてフランスと同じように「近代音楽」に分類されました。しかし、スクリャービンと同年代であるラフマニノフは、一貫してロマン主義的音楽を作り続けたため、あたかも前時代の音楽家のように扱われてしまいました。ラフマニノフは第一次世界大戦後も活動を続けますが、ことごとく「古い音楽」として扱われ、まともに評価されませんでした。同じ国、同じ年齢の2人の作曲家が、片方はロマン派、片方は近代音楽、とされているさまは、クラシック音楽史の時代区分が、実際の「時代」に沿っておらず、一方向的な進歩史観に沿って分類されている、ということがわかる顕著な例ではないでしょうか。よっぽど特殊な興味を持って生年を調べない限り、ドビュッシーよりラフマニノフのほうが年下で、ラヴェルと同世代である、という事実は信じがたいと思います。
「前衛音楽」の誕生
このように、「ロマン派」に戻ることが許されない空気の中、ロシアではストラヴィンスキー(1882~1971)がさらに過激な音楽を作ってしまいました。従来の調性システムから離れていったのはもちろんのこと、リズム法の面からもアプローチし、変拍子の乱舞と継続する不協和音で、それまでの音楽の「一定性」を破壊しました。1913年発表のバレエ音楽「春の祭典」が賛否を渦巻く大反響を呼びます。初演時の客席が称讃とブーイングの入り乱れる大騒動になったといいます。
また、これによって、時代遅れとなったオペラに代わってバレエ音楽は「新しいもの」とされ、ロシア音楽が芸術音楽界で国際的に「前衛」の位置として認められるようになります。同時代の絵画での「フォービズム」「表現主義」「抽象絵画」と結びつけられ、「表現主義音楽」とされました。


イタリアでは、前衛芸術運動「未来派」が起こります。文学美術、建築、音楽、と広範な分野で展開され、過去の芸術の徹底破壊と、機械化による近代社会の「速さ」が讃えられました。1909年、イタリアの詩人マリネッティによる「未来主義創立宣言」が起草されてスタートし、音楽分野ではルイジ・ルッソロ(1885~1947)が、1913年に雑音を鳴らす楽器「イントナルモーリ」をつくり、騒音芸術を開始します。
『戦争は美しいものである。なぜなら、ガスマスクや威嚇拡声器、火炎放射器や戦車、人間の力が機械を支配していることを証明できるからだ』
『音楽はやがてノイズへと行き着くだろう。ノイズは音楽の豊かさをもたらしてくれる。ベートーヴェンやワーグナーが私たちの心を動かしてきたように、今度はエンジンの出すノイズや群衆のざわめきが私たちを楽しませてくれるだろう。』
イタリア未来派はこのあと、ファシズム・軍国主義と結びついて崩壊してしまいますが、この方向性はこのあとクラシック音楽がたどる道を予言していたととることもできます。
そして、ここまで歩んできた西洋音楽の既成の音楽理論的枠組みを根底から覆そうと実験した作曲家が、シェーンベルク(1874~1951)です。
「中心音」を断固として拒絶し、曲の中から一切の協和音を締め出しました。これにより、「調性」が破壊され、不協和音しか認めない「無調音楽」が始まります。1911年の「6つのピアノ小品」などはその顕著な例で、それまで後期ロマン派や近代音楽が限界まで拡張して保っていた調性がついに否定されてしまいました。
こうして、1910年代に入り、ここから先がクラシック用語でいう「現代音楽」の時代になります。
音楽に詳しくない人が現代音楽という語を「現代の音楽」という意味で使うことがありますが、「現代音楽」は21世紀の我々にとってもはや「現代の音楽」ではありません。ここまで解説してきた通り、ドイツ音楽史として「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → シェーンベルク」という音楽理論の一方向的なストーリーに当てはめて時代区分を分類した場合の、シェーンベルク以降の音楽が音楽用語として「現代音楽」と言われます。いわば「20世紀の前衛・無調音楽」という意味になるので、現代の音楽を指し示そうとしたときは「現代音楽」という語は控えるようにしなければなりません。
そして第一次世界大戦へ
1914年の夏、第一次世界大戦が勃発。ヨーロッパ本土で40年ぶりに戦争が起き、人類史上初めて近代兵器(戦車、ダイナマイト、潜水艦、軍用機)が使用され、前代未聞の大量殺戮が行われ、ヨーロッパ中が焦土と化した戦争でした。音楽でも絵画でも前衛主義が登場した時代、芸術家たちはキナ臭さを敏感に感じ取って、破壊的な作品を残したということなのでしょうか。
第一次世界大戦を経て、ヨーロッパは悲惨な状況となってしまいました。クラシック音楽文化を支えてきたヨーロッパのブルジョワ階級は崩壊します。今日のクラシック演奏会のレパートリーの中心となっているのはこの段階までです。芸術音楽は「現代音楽」の段階になり、「わかりやすいものは悪である。」という形で、聴衆に向けて音楽を作らなくなり、「音楽」全体の中でクラシック音楽の優位は知らず知らずのうちに形骸化していったのではないでしょうか。一方で戦争を経て「世界の強国」にのし上がり、覇権国家の道を歩み出したアメリカではこのあと「ローリング・トウェンティーズ(狂騒の20年代)」と呼ばれる繁栄の道を歩み、経済的繁栄と都市文化の開花、ポピュラー音楽の消費が渦巻く時代へと進んでいくことになります。
次回は第一次世界大戦から第二次世界大戦までの「戦間期」の音楽を紹介します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138783555/profile_c84af2a23c59f9583876f3c8dba39814.png?width=60)