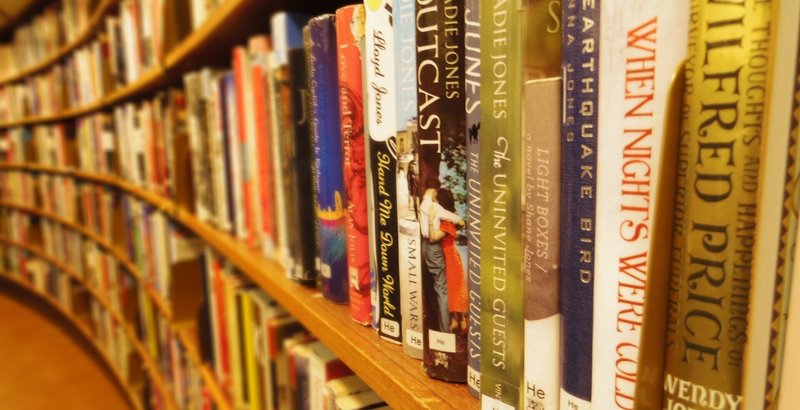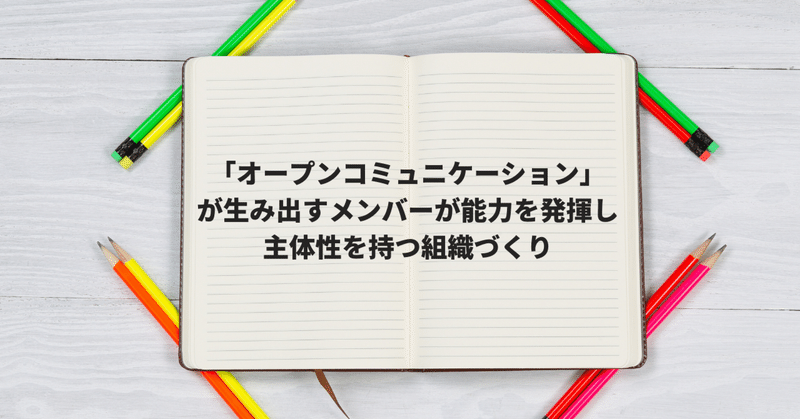- 運営しているクリエイター
2022年2月の記事一覧
リーダーは作られる、という話
令和の価値観は変わってきている。
昭和や平成初期は、マネジャーやら部長やら、のタイトルがあるとか、或いは、有名な〇〇社で働いているから、等の理由で、人を統率したり、良く見てもらえたりしたかもしれないけど、最近は変わってきている。
俺は社長だから、部長だから、有名企業で働いているから、というような、表面的な肩書に、迎合しない人が増えてきているのは確かだ。
なぜこういう話をするか、というと、先日
褒める時は「具体的に褒める」
「毎週必ずひとつは褒める」
3年前から自分に課している習慣です。
当時、マネージャー向けの研修を受けた際に、マネジメントは「叱る」より「褒める」方が部下の力を引き出すということを学びました。
私の会社では毎週月曜日に課内ミーティングをしています。当時は「反省会」と称して、前の週の「良く無かった点」や、「やり残した課題」を指摘するダメ出し中心のミーティングになっていました。
今思えば、ダメ出
メンバーの目標を設定する
プロジェクトは、メンバー1人1人の成長の場でもあります。
プロジェクト責任者がオモチャを与えられて好き勝手できるというものではありません。また、売上/利益をあげさえすればそれでいいと言うものでもありません。
企業において、従業員と言うのはいずれ新人→若手→中堅→一人前→ベテランへと育っていってくれなければならない存在です。
これを無視して目先の『金』だけしか見ないのであれば、人の成長機会を無
たった30分の「ゆるふわ」が生み出すチームビルディングのすすめ
コロナ禍、というか、閉塞感の方が蔓延しているような心地もしますが、2022年が始まって、劇的な(外部)環境改善が起きない中、2月中旬へと突入してきました。
僕自身は、1月に転職をしたので、まぁまぁ大きい変化はありました。そこでのオンボーディングと実務の中で、「いまどき」なチームビルディングを体感しております。今回のCOMEMOのお題はこちら。
まったくカルチャーの異なる企業に転職してきた(つもり
「言わずもがな」をあえて書く ー組織の知識を貯めるポイント
組織・チームの力を発揮するうえで、「ナレッジ・マネジメント」の方法に注目している人は昔も今も多いのではないでしょうか。
花王の沢田会長と、一橋大学の野中氏の対談でも、社員の『暗黙知』を組織の力に変えていく重要性が指摘されています。
ここでの知識とは、必ずしも高度な専門知識のみをさすわけではないでしょう。コミュニケーションの小さなわざや、デザインにおける素朴なコツなども、言語化されていない「暗黙
「オープンコミュニケーション」が生み出すメンバーが能力を発揮し主体性を持つ組織づくり
リモートワークが中心の状況が2年以上続いている中、企業におけるチームのコミュニケーションも大きく変化しました。コミュニケーションの変化に伴い、チームビルディングの方法も変化が見られているのではないでしょうか。
今回は「テレワーク環境下でのチームビルディング」をテーマに書きたいと思います。
チームビルディングとは「チームビルディング」という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。基本的には組織
#チームビルディング おすすめのやり方【日経朝刊 投稿募集】あなたの体験/ご意見 お待ちします
こんにちは。COMEMOスタッフの山田です。今回は「働き方」について、新しいご意見募集のお知らせです。
今回のテーマは「チームビルディング おすすめのやり方」です
新型コロナウイルスの感染が続きテレワークが普及するなか、改めて浮上してきたのチームワークの見直しですね。そんななか、いま、チームビルディングが注目されているといいます。ビデオ会議や研修に取り入れる企業が増えているそうです。チームの生
部下の成長を止める上司
From 安永周平
イエローハットの創業者である鍵山秀三郎さん曰く、人間には3つの幸せがあるそうです。最初は「してもらう幸せ」です。典型的なのは子供です。子供は、親から何かをしてもらうと幸せに感じるでしょう。オモチャを買ってもらったり、洋服を買ってもらったりすると、子供は誰でも喜びます。誰もが子供の頃には「してもらう幸せ」の段階だったのではないでしょうか。
次に、もう少し成長すると「自分ででき
ビジネスは「ととのう」が主流に
column vol.560
職場で「心理的安全性」を保つことが非常に重要になってきています。
そんな中、個人的に気になっているのが「スローワーク」という考え方です。
〈lifehacker / 2022年2月3日〉
仕事をがんばることはプロとして当然とはいえ、自身の健康、あるいは家族や恋人との関係を犠牲にしてまで手にしたその成功は、果たして真の成功とも言えないのかもしれません…。
「ス