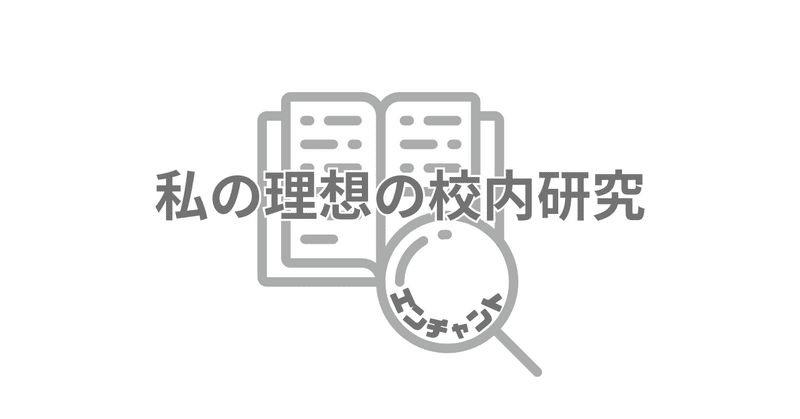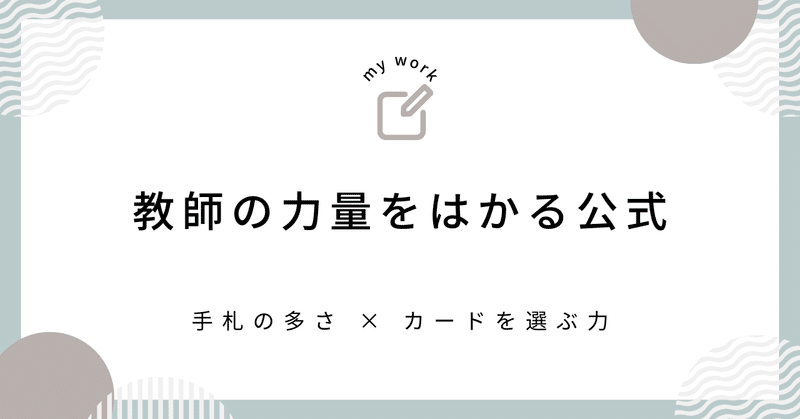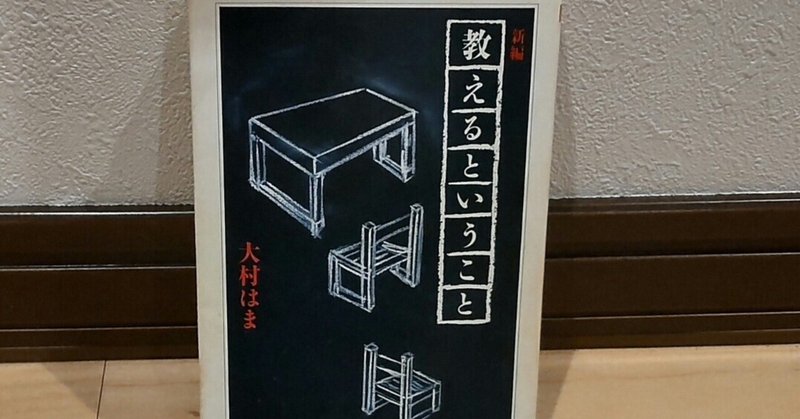#教師
【体育授業の微細技術】跳び箱運動の基礎感覚づくり
こんにちは。
今回は「跳び箱運動」における基礎感覚づくりの運動についてお話していきます。
跳び箱運動で広げていきたい感覚と、そのための運動について、少しでもお読みのみなさんのお役に立てられたらとまとめました。使えそうなものはぜひどんどん使ってください。
1.跳び箱運動で育てたい感覚マット運動で育てたい感覚については、以下の記事にまとめました。
跳び箱運動も基本的には同じです。そこに加えて、「フ
授業でどう教えるかは手段だから、目的である子どもの成長を忘れないようにしたい
1293記事目
こんにちは、旅人先生Xです。
今日は「教える手段と子どもの成長という目的」について書いていきたいと思います。
良かったらぜひ、目を通していってみていただければ幸いです!
目次は、以下の通りです。
子どもの成長が学校の授業の目的だと思う
学校では、国語や算数といった様々な教科の授業があります。
子どもの頃から当たり前のように教科の授業を受けてきたし、教員になってからも当