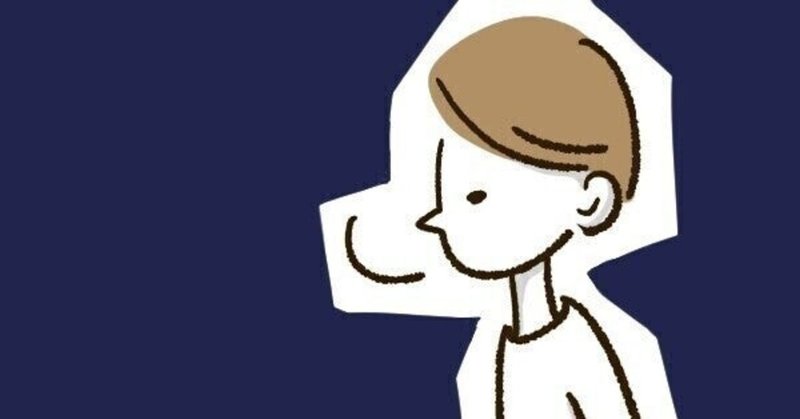2022年11月の記事一覧
🌈社会人先生になりませんか? 朝活7時 🌸#しゃかせん 記事紹介 ✅①こんな方に担任の先生になって欲しい✨ ✅②きしゃこく学院附属中学校@渋谷大翔 ✅③誰もが先生になれる社会に✨誰もが先生【「#先生DAO」DAO TDAO TeacherDAO note 発!仲間募集中⭐】
(きしゃこく先生🌈)
おはようございます!
さあ、きょうも朝活7時は、
「#先生DAO」、
TDAOプロジェクトの時間です!
こんな社会経験豊富な方たちが
「学校の先生」、
しゃかせん、社会人先生になってくれたら、
ガッコは、変わるだろうな🌈
そんな方達を
紹介したいなって思っています。
ファシリテーターは、
教育DAO 、
きしゃこく学院附属中学校の生徒会です!
(