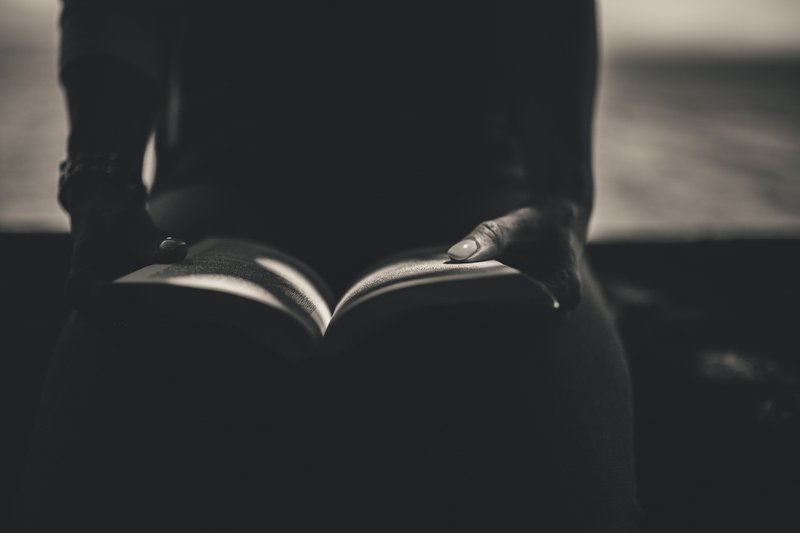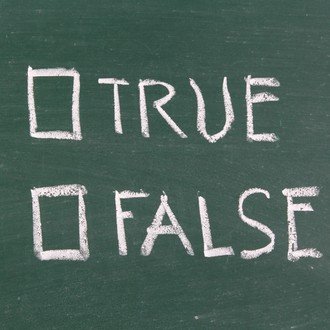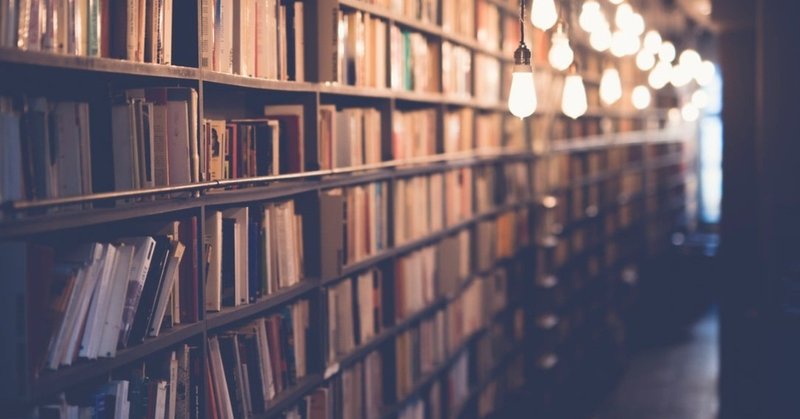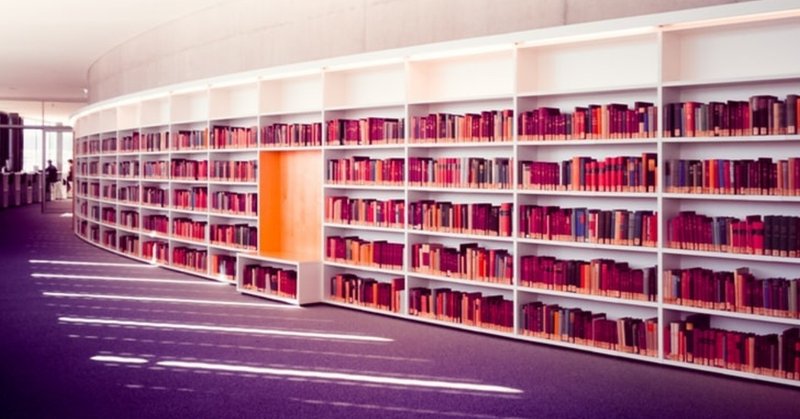#推薦図書
アメリカのあちこちに「反マスク法」という法律がある件(3)
▼アメリカで、どれだけ経っても黒人差別がなくならないのは、人類学的な理由がある、という話について、もう少し続ける。
興味のある人は、前号、前々号もどうぞ。
▼さて、トッド氏の『移民の運命』では、イングランドから輸入された家族システムや、プロテスタントの教義が、アメリカの差異主義と骨絡(ほねがら)みである、という仮説が示される。
いちいち辿(たど)るのは面倒なので、トッド氏本人が簡単に4つの項
アメリカのあちこちに「反マスク法」という法律がある件(2)
▼先週の金曜日(2020年5月15日)、下高井戸の駅前で中国製のマスクが「50枚入り1500円」で売っていた。
もともと「50枚入り3000円」のものを、タイムセールということで半額にしていたのだが、タイムセールはしばらく続いていた。この数カ月で、マスクの値段が乱高下している。
▼アメリカのあちこちに「反マスク法」という法律がある、というコラムから、トッド氏の『移民の運命』を思い出した話の続き
アメリカのあちこちに「反マスク法」という法律がある件(1)
▼新聞を読んでいると、世の中、自分の知らないことだらけだということがよくわかるが、思わず声をあげてしまった記事があった。2020年5月10日付の読売新聞から。中島健太郎アメリカ総局長のコラム。
〈マスクで浮かぶ差別の影〉
〈そもそも、米国の多くの州では理由なしに公共の場でマスクをつけること自体が違法だ。少なくとも18州に「反マスク法」と呼ばれる法律がある。その多くは覆面での白人至上主義団体の活
終戦記念日の新聞を読む2019(4)毎日新聞「余禄」~アジアから見た日本
「終戦記念日のコラムを読む」は、(1)では特攻した少年と親の物語、(2)では原爆被爆者の一言、いわば「虫の目」で見た戦争を、(3)では気候変動などの「鳥の目」で見た戦争や国家を、取り上げた。
▼今号で取り上げるコラムは、気候変動などと比べたら「低空飛行の鳥」の目で見た戦争かもしれない。
▼「戦争を知らない人間は、半分は子供である」という有名な言葉は、大岡昇平がフィリピン戦線の日本軍を描いた傑作
終戦記念日の新聞を読む2019(2)愛媛新聞「地軸」~言葉の底を読み解く
▼読み解く、という言葉の意味を考えさせてくれるコラム。2019年8月15日付の愛媛新聞「地軸」から。
▼冒頭は〈わが子を胸の下にかばい守ろうとした母親の姿は、皆の脳裏に焼き付いていた。広島市の原爆資料館には黒く焦げた親子の遺体の絵が何枚もある。〉
このコラムでは、広島市立大広島平和研究所教授の直野章子氏の知見が紹介されている。直野氏は「『原爆の絵』と出会う」(岩波ブックレット)の著者。
〈被
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(6終) ゾーニングの知恵
▼アレックス・カー氏と清野由美氏の『観光亡国論』を読むと、「ゾーニング」という言葉の意味について考えるきっかけになる。
▼「ゾーニング」と「分別」とについて言及している箇所を、大切なところなので、再度引用しておく。
〈清野 日本で「ゾーニング」というと、都市計画法で定める住居専用地域とか、商業地域、工業地域といった「用途指定」のこと、という理解が一般的ですが。
カー それはごく狭義のもので、
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(5) ゼロドルツアーの恐怖
▼アレックス・カー氏と清野由美氏の『観光亡国論』を読んでいる。
両氏の対談で、日本の観光産業の問題点が浮き彫りにされている。
カー氏いわく、
〈日本の観光業では、全盛期の高度経済成長期の「クオンティティ・ツーリズム(量の観光)」が、いまだに根を張っており、今の時代に通用する「クオリティ・ツーリズム(質の観光)」については浅い理解になっていることです。〉(168頁)
▼20世紀の「量」と、2
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(4) ユネスコサイド
▼「ユネスコサイド」という物騒(ぶっそう)な言葉がある。
ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が悪い、というわけではない。
〈最近のヨーロッパや東南アジアでは、ユネスコの世界遺産登録を受けて、観光業で汚染された場所を「ユネスコサイド」という言い回しで表現するようになっています。〉(『観光亡国論』154頁)
▼本書では中国の雲南省にある「麗江(リージャン)」という町や、ミャンマーの「バガン遺跡
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(3) 黒門市場の成功
▼前号は京都の観光名所の2つの悪例、「二条城の襖絵」と「錦市場」の惨状について触れた。キーワードは「稚拙化」。
▼アレックス・カー氏の『観光亡国論』から。
▼スペインはバルセロナの「ボケリア市場」は、〈自撮り棒を持った観光客で埋め尽くされるようになっています。〉ということで、〈地元の人たちは「もうボケリアには行けない」と嘆いているのです。〉(151頁)
▼いっぽう、「なにわの台所」たる大阪の
「観光のための文化」から「文化のための観光」へ(2) 京都の「稚拙化」
▼アレックス・カー氏は『観光亡国論』で、日本の観光が「ゾンビ化」したり、「フランケンシュタイン化」したりしている、と指摘している。
「ゾンビ化」とは、「昔の様式をそのまま守っていくやり方」で、「フランケンシュタイン化」とは、たとえば観光名所の観光名所たる勘所(かんどころ)を見失ってしまい、お化けみたいな代物に変わり果ててしまうことを言う。
ということを前回、紹介した。
▼アレックス・カー氏は
『「いいね!」戦争』を読む(19)人間が「フェイク」化しつつある件
▼ロシアが、たとえば「トランプを熱烈に擁護するアメリカ人」のアカウントを捏造してきたことは、国際的な大問題になったから、すでによく知られるようになった。
筆者は『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」を読んで、2017年にツイッターに登場した「アンジー・ディクソン」という有名な女性女性が、〈ツイッターを侵食し、アメリカの政治対話をね