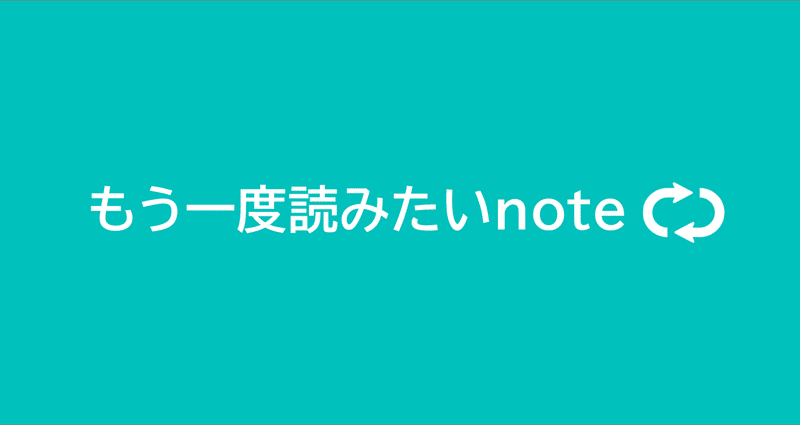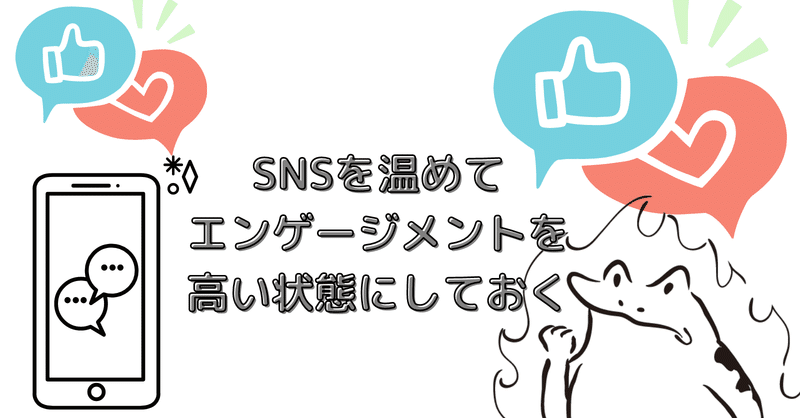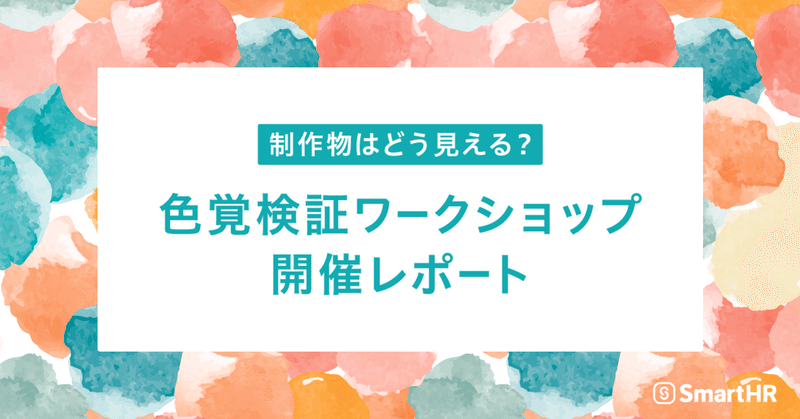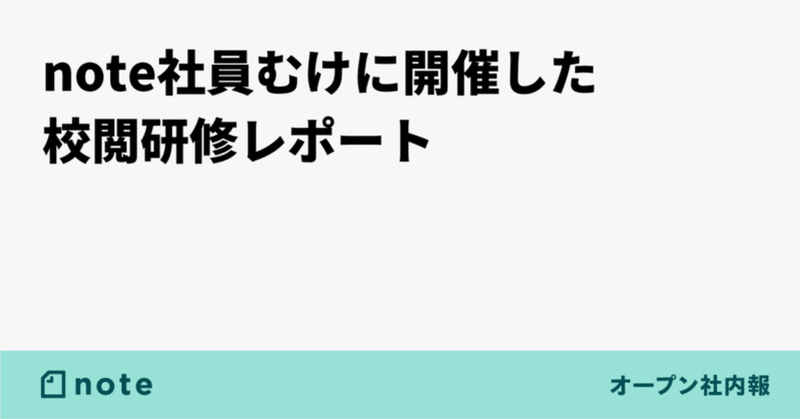2021年7月の記事一覧
SmartHRの制作物はどう見える?「色覚検証ワークショップ」開催レポート
SmartHR、コミュニケーションデザイングループのみやもとです。
2021年5月に第一回、6月に第二回と、2回にわけてグループ内で作ったデザイン制作物の色覚検証ワークショップを開催したのでレポートしたいと思います。
この会は、具体的なデザイン修正や制作進行の改善を求める場ではなく、みんなで色覚に関する意識を高めよう、多様な見られ方があることを知ろう、という目的で実施しました。
マーケティング
大盛況だったnote社員むけ「校閲研修」を振り返る
こんにちは。公共教育ディレクターの中野です。
季節はすっかり夏ですが、4月に開催した研修について、このオープン社内報でご紹介します(遅筆すぎてすみません)。
2021年4月、校閲会社の鴎来堂さんにご協力をお願いし、社員向けに校閲研修を開催しました。
オープン社内報とは?
一般的には社員しか見ることのできない「社内報」をだれでも見られるように公開することで、会社の中の様子を感じとってもらう記事
病気としての色覚障害と人としての色覚の多様性
ご縁があって私も出演させていただいた「竹田と山口の時々お役立ちラジオ」。オンデマンド配信なのでいつでも聞けるのがいいところ。
第49回ではご自身も色覚の多様性のある方がゲストに出演。色覚障害は男性の20人に1人ぐらいの割合で出現するのだが、実は色覚障害だけでは視覚障害には入らない。
さて、私が番組の中で印象的だったこととして、学校における色覚異常をスクリーニングする検査をどのように考えていくべ
やらないことを決める勇気 | オンライン秘書日記
~「0→1」と同じぐらい「1→0」も大切~
作業に対して、実施に違和感があるものに関しては
「これってやる必要ありますか?」と、躊躇せずにズバリと聞くことにしている。
もし、当初の目的が薄れてきてしまったり
費用対効果が悪かったなら、見直しをするタイミング。
この機に、見直せばいい.
もちろん、やるならやるでOK!
意図を共有していただき、お互いの感覚を共有していきたい。
忘れがちなのは「
頂(いただき)を示してもらえることの幸せ
少し前にしょこらさんのツイートに触発されてこんなことをツイートした。
お陰様でずいぶんと反応があった。せっかくなので、ここを少し深掘りしてみたい。今回はそんな話。
師匠とは?コトバンクによると師匠とは「学問、芸術、または武芸などを教える人。先生」と定義されている。定量化されにくい芸事の中で何かしら秀でていて、それを生徒に教えている人だ。学校の先生とも違うし、会社の上司やメンターとも違う。そして
#361 目線の先に、飛んでいく。
むかーし読んだ本の一節をふと思い出して、メモ。
1、ハンググライダーのレッスンで。今となってはどの本か思い出せないのですが、節目節目で思い出す、昔読んだ本の一節があります。
前後関係もすっかり抜け落ちているのですが、著者がハンググライダーのレッスンの初回、座学の講義を受けた際の一番最初の講師の以下のような言葉です。
「最初に最も大事なことを伝えます。これから話すこと全てを忘れたとしても、これ
「アンラーニング」(学びを手放す)感覚が大切
知識や情報を得るうちに、自分の中に根づいてしまうモノや人への見方。
先入観、固定概念、思い込み…。
賢くなってるつもりで、微妙にやっかい。
私は、特にインタビューで対峙するとき、相手の職業や属性に惑わされず、なるべくまっさらな状態で話を聞くように心がけている。
著名人の場合は、公表しているプロフィールや実績という「表向きの情報」を一通り確認するものの、その情報で判断したりせず、質問のヒント程度に