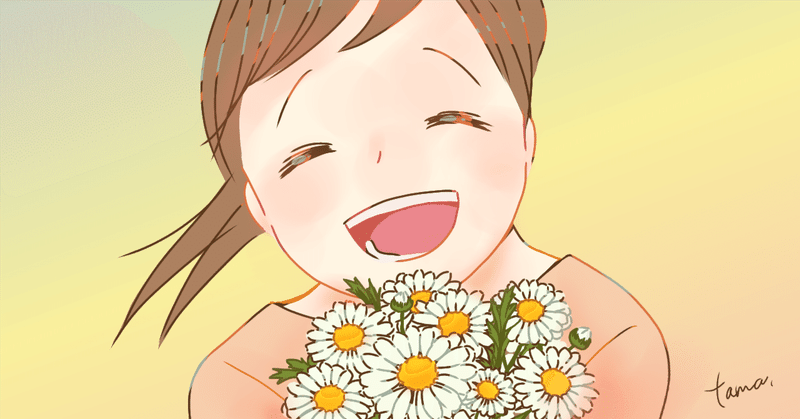記事一覧
幽霊って見える人もいます。
蒸し暑い日が続いていますね。今回はちょっと異質なテーマでお話しします。少しは涼しくなるかもしれません。
私は小さいころから不思議なものが見えます。火球というバレーボールくらいのオレンジ色の火の玉、俗に言われる幽霊なるもの。おそらく遺伝だと思います。
むかし、祖母がこんな話をしてくれました。祖母の家の近くに公民館があります。その横に細い下り坂の路地があります。その路地の2軒目に友達が住んでいたそ
生き方 心の内側を素直に話してみる
人には自分のことを自ら話すタイプの人と、自分のことはかたくなに話さないタイプの人がいます。私はこういう人だと早く知ってもらいたいので前者のタイプです。こういう人は何を考えているのか比較的わかりやすいと思うのですが、後者のタイプは、どんな人なのか最初はわかりづらいのかもしれません。
自分のことを進んで話さない人は少しプライドがあって、軽く見られたくないという気持ちがどこかにあるのかもしれません。ま