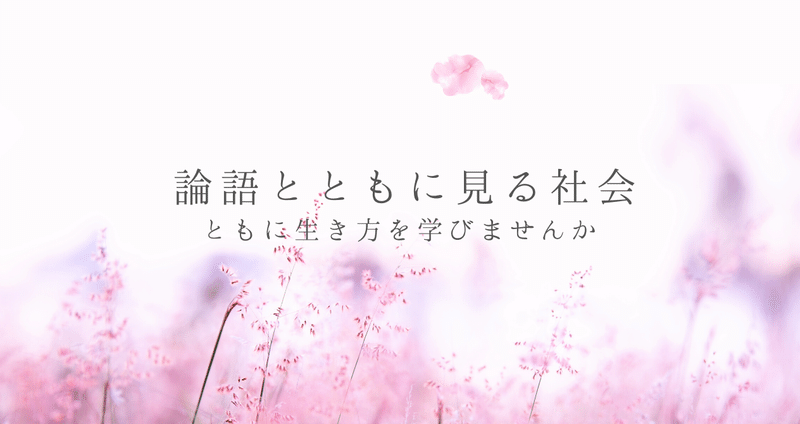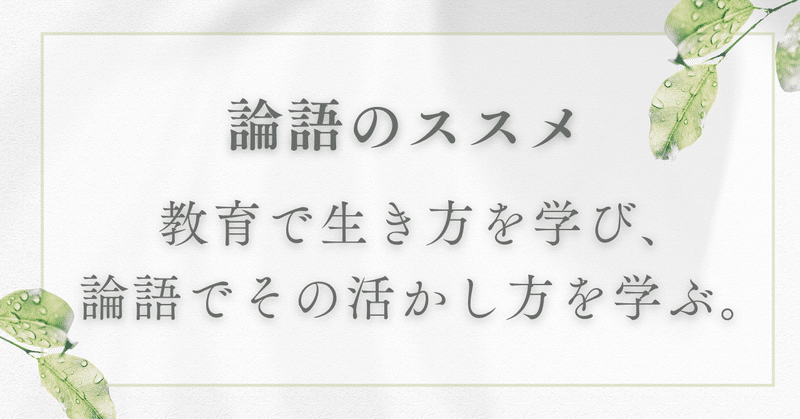記事一覧
論語のススメ...論語入門編まとめ①
①人と社会のみちしるべ……論語とは
論語は、今から約2500年前に中国でできました。
論語をあまり知らない人からすると、
孔子が書いた本というイメージの人もいるかもしれません。
実は、論語は弟子達がまとめた語録なのです。
孔子(紀元前551~479年、春秋時代末期の思想家・教育者・政治家)が亡くなった後、孔子と優れた弟子達が言ったこと、行ったことを書き記しました。
孔子、直弟子、孫弟子達は、
成功者のバイブル…論語を愛し、活用した偉人達
新一万円札の顔となった「近代日本経済の父」渋沢栄一も論語を愛した一人です。
彼が著した『論語と算盤』は非常に有名です。
彼は論語でいう「君子」を「紳士」ととらえ直し、
自らの生き方と当時の日本を成長させるうえでのバイブルとしていました。
論語から生き方、人と社会の導き方を学び、
己を支える拠り所とし、
明治維新後の日本経済と、
500もの企業の発展に尽力しました。
現京セラ㈱の設立者・稲盛和
人不己知...人が自分を認めてくれないのを気にすることはない。
子(し)曰(のたま)わく、人の己を知らざるを患(うれ)えず、其の不能を患(うれ)うるなり。
(憲問第十四、仮名論語二百十七頁)
先師(孔子)が言われた。
「人が自分を認めてくれないのを気にすることはない。
自分にそれだけの能力がないのを気にすることだ」
昨年、荊妻に難しい病気が見つかり、
手術までの一ヶ月は本人より私の方が沈んだ。
普段は朝からクラシック音楽を聴いている。
作曲家はシベリウ
不欲勿施...自分が人からされたくないことは、人にしてはいけない。
己の欲せざる所は人に施すこと勿(なか)れ。
(顔淵第十二、仮名論語一六二・一六三頁
衛霊公第十五、仮名論語二三七頁)
先師(孔子)が言われた。
「自分が人からされたくないと思うことは、
人もいやなのだから、それを人にしてはいけない」
いつも持ち歩く小銭入れに、
一センチ強の化石が入っている。
五億年前のカンブリア紀三葉虫の化石である。
小銭を出す度に、五億年という時間の長さ、
殆どの動物の門