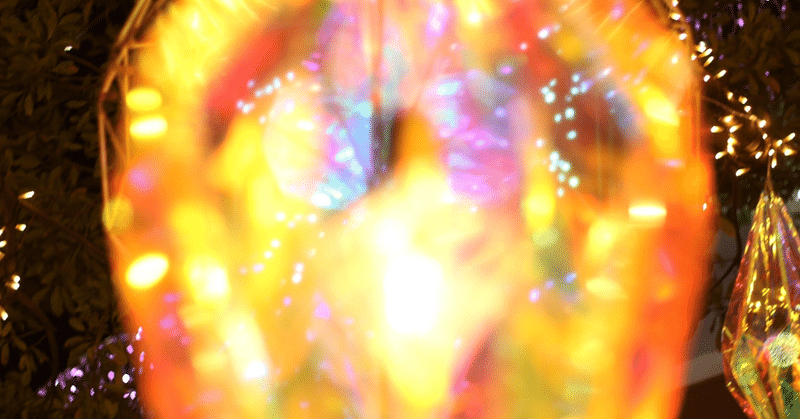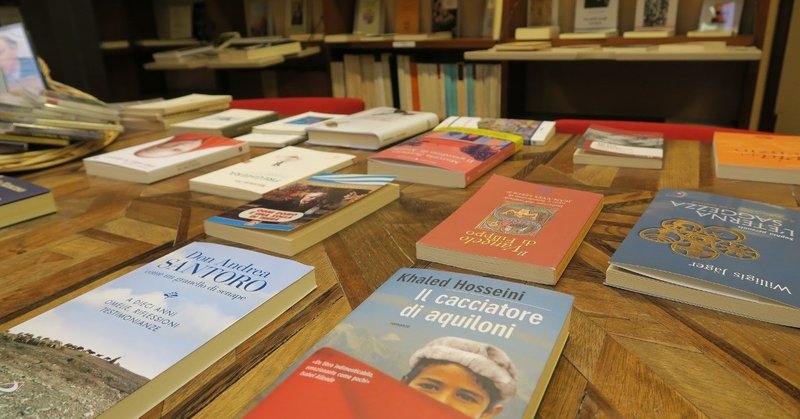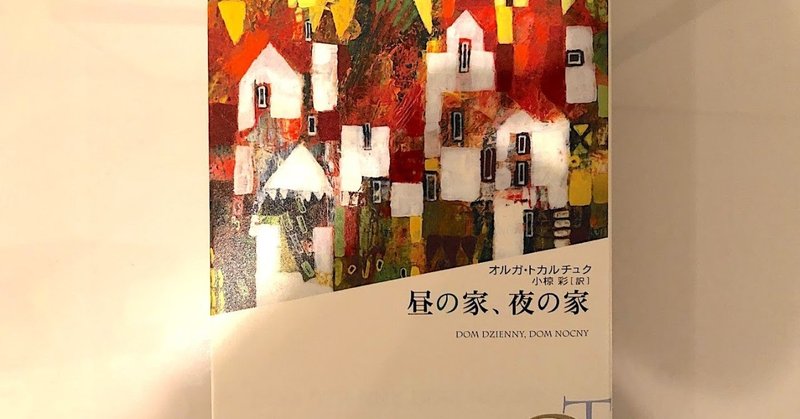#日記
気づかずに通り過ぎることだけは避けたい愛を書き連ねる
・夏の早朝の透き通った空気
夏の朝はやく、5時でも6時でもいい。
まだ暑くなる前の透き通った空気、騒音のない静かな雰囲気、誰にも汚されていない時間帯。まだ鳥も人間も目が覚めていないような、世界中がまだ眠っているような、そんなぽっかり穴があいたような空間にただひとり、起きる。この世界をはじめるのはわたしだ、と高らかに宣言しても誰も聞いていないような、そんな見放された時間がとにかく好きだ。
・ヨー
巡礼路、大地を踏みしめて歩いたことの確かな記憶。
今日、NHK BSプレミアムで「聖なる巡礼路を行く 〜カミーノ・デ・サンティアゴ 1500km〜」という番組が放送されていた。
全三回放送のこのシリーズは、1ヶ月ほど前すでにBS8Kの高画質でヨーロッパの大地、青空、草花、石垣、教会、巡礼路を美しい色合いそのままに視聴者に届けていたらしい。反響があったことからBSプレミアムで放送、初回が本日だった。フランス国内のLe Puy-en-Velay(ル
主体性と、個人主義と、相互作用。
今日、渋谷の街を歩いていたら、百貨店の入口の扉に貼られた「当面の間」まで営業を中止するという案内を見かけた。シャッターは降ろされ内部の様子はうかがうことはできないが、いつもの賑やかさは遠く記憶の向こうに追いやられている。当面の間という言葉の解釈、その具体性、判断は各自に委ねられているのだろう。当面、当分、いつまでかはわからないけれど一定期間。
フランスのカフェやレストランでの張り紙では閉店を顧客