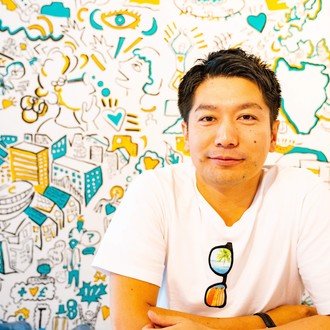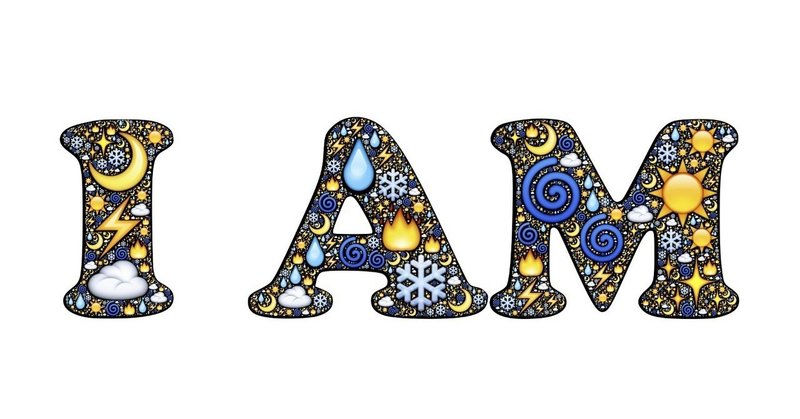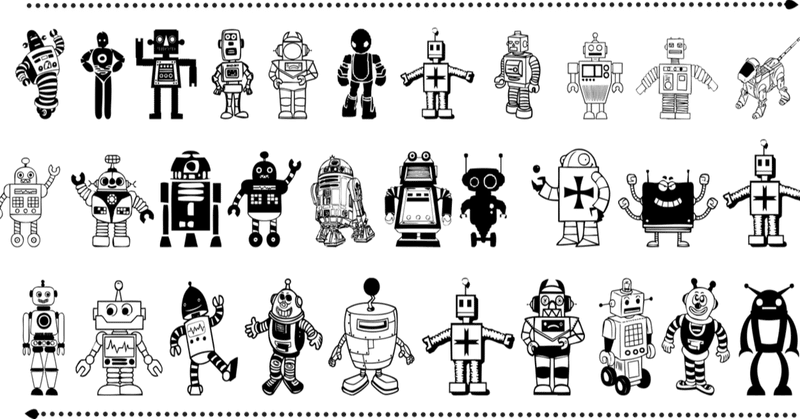- 運営しているクリエイター
#デザイン
暮らしと仕事のウェルビーイングというのにやっと腹オチしたという話。
今頃かよ!!という突っ込みを社内外から受けてしまいそうですが、タイトル通りの話を書いてみたいと思います。
2019年に「何気ない日常をより豊かに Augmentation for Well-being」ということを目標にAug Labというバーチャル組織を立ち上げました。
コンセプト段階のプロトタイプから積極的に発信してきたので、結果的に社内外の多くの方から意見を頂きました。特に、発信してきた
「エスノグラフィー」って元はデザインシンキングではなく、文化人類学の言葉だったのね
2019年にデザインシンキングというものに触れるようになって以来、ちょこちょこ聞くようになった「エスノグラフィー」。
そもそもエスノグラフィーって??ネットで調べると、
と書いてありました。感覚的には、ユーザというか、対象者の日常に入り込んで、困りごととか特徴とかを何気ない行動とかから紐解いていく、みたいな印象です。
業務の中で必要なところで活用するという感じの接し方だったなので、あまり深く
ヒトより1000万倍大きい地球と1/1000万小さいウイルス。
『マルチ・スピーシーズ・デザイン』ーーー。
この言葉を初めて聞いたのは10月頃。そこから2ヶ月くらいで、違う人から5回ほど聞いた。流行っている???
これまでの人類は人のことを主に考えてきたけど、人以外の動物はもちろんのこと、植物や微生物など複数の生物種との共生をしっかりと考えて行きましょう!というのがざっくりした概念かと思います。
マルチスピーシーズ海外だと「Multispecies sus
ユーザが消費者から生産者になるとき持続的なWell-beingが生まれる
今月のDIGITAL Xでのコラムは、『偏愛』が感性価値の高いプロダクト/サービスを生むということで、書かせて頂きました。
今週のNoteはこのコラムの補足的な記事を書いてみたいと思います。コラムの中では、偏愛からプロダクト/サービスの開発のプロセスとして、
(1)偏愛マップの作成
(2)偏愛マップの共有・対話
(3)偏愛情報の拡張
というのを紹介しました。この中で、一番難しいのは、(3)の
共に育ち、共に創る。オープンイノベーション、共創、リビングラボのハブとしてのSTEAM教育。
昨日、パナソニック センター東京に"AkeruE"というクリエイティブミュージアムがオープンしました。
博物館と美術館と工房が混ざったような体験型のその施設は、本当に素敵で、子供だけでなく、大人も楽しめること間違いなし!のオススメスポットです。
そんなAkeruEのオープニングイベントのトークセッションに参加させてもらいました。
テーマは、未来の教育。特に、STEAM教育。
ということで、
ロボット開発者が京都市美術館で現代アートに出会い、『で??』と思った話。
「考えるな、感じろ!!」
そんなことを昔、言われた気もする。もしかすると、アートというのはそういうものかもしれない。
でも、そんなこと言われたって考えちゃうんですよね。
『アートとは何なのか??』
初めての美術館展示きっかけは京都市美術館。リーダーを務めるAug Labでコネルさんと作った『ゆらぎかべTOU』を展示させて頂ける機会を貰えた。
12/6まで展示中なので、もし宜しければ是非!
慶應大学・コネル社のBTC人材と連携してWell-beingのための技術と社会実装に挑む
11月18日にパナソニックの"Aug Lab"において、「Augmentation for well-being~何気ない日常をより豊かに~」というコンセプトを一緒に目指して頂ける共同研究パートナーの公募結果発表させて頂きました。
まず、短い公募期間にも関わらず、多くの研究者、クリエータの方々から応募を頂きましたこと、感謝申し上げます。公募に応募するということは何度もありましたが、公募する側にな
ロボットエンジニアがデザインに足を踏み入れた1年:Who am I? Who are you? Who are we?
2019年度も最終週になりました。今回はこの1年を振り返った感想を書いてみたいと思います。今年も基本的にはロボット関係の仕事がメインなわけですが、会社の人のオススメで7月にNoteを始めた一発目の記事で書いたように「人手不足が加速する中で自動化により生産性を向上させていく取り組みと、個人がしたいことをし続けられるように支援する取り組みを両立する」ということを目指し続けた形です。
人手不足解消へ少