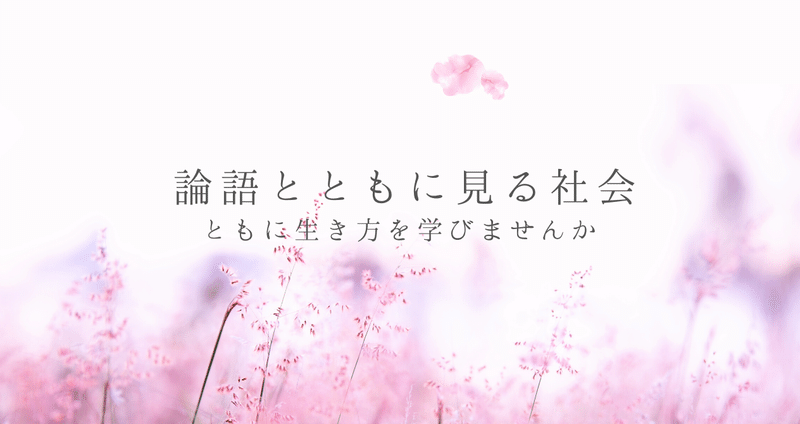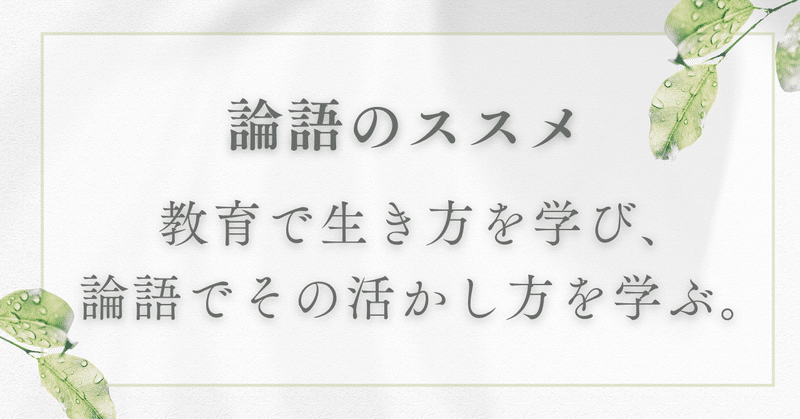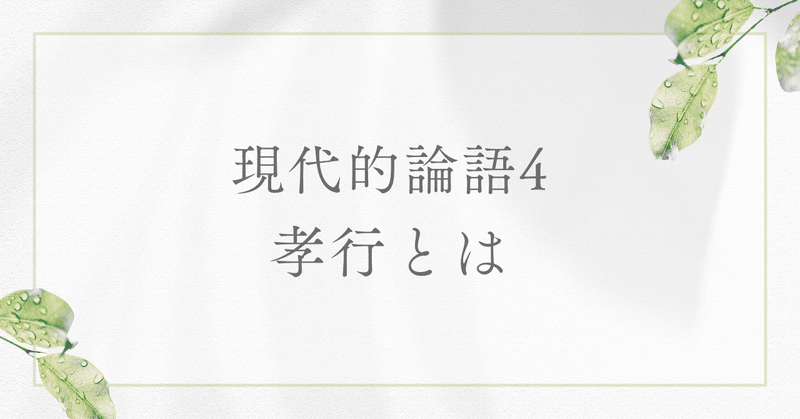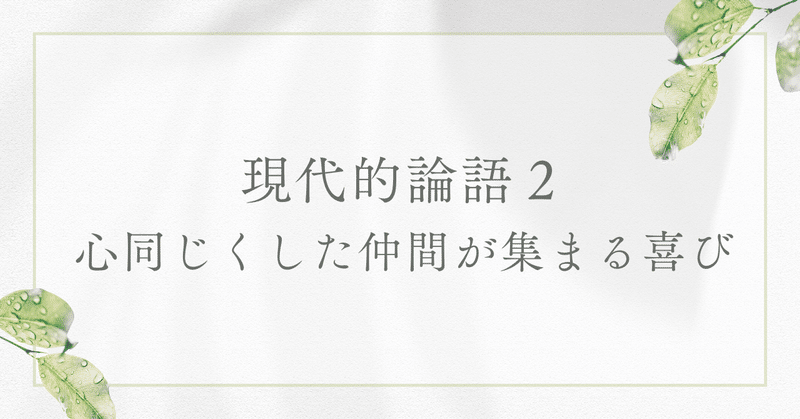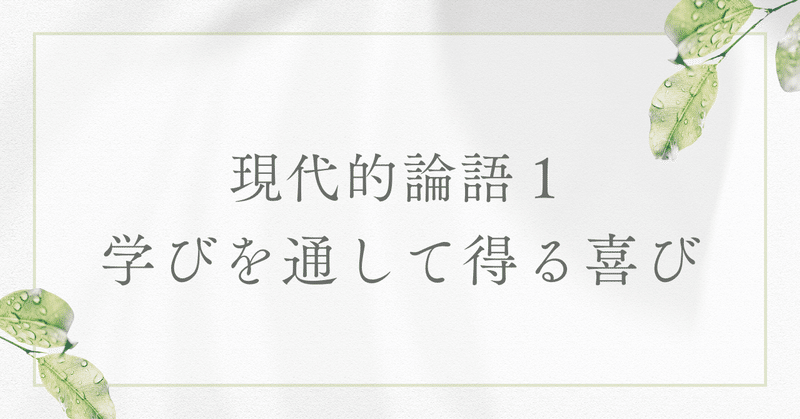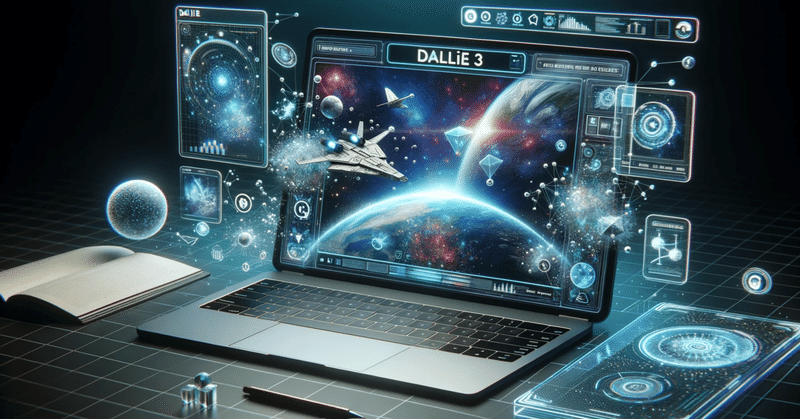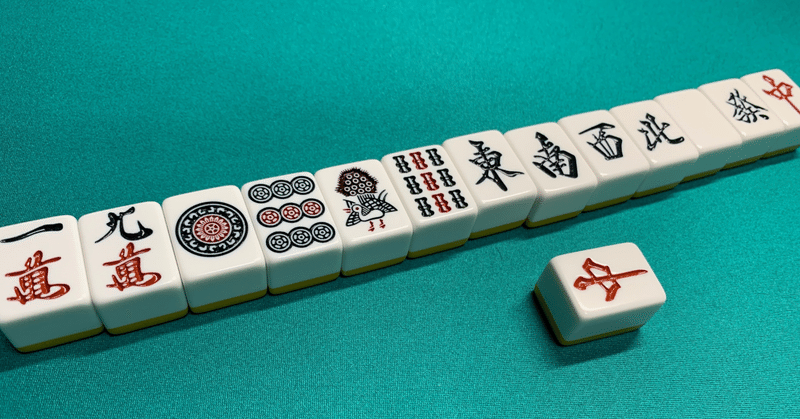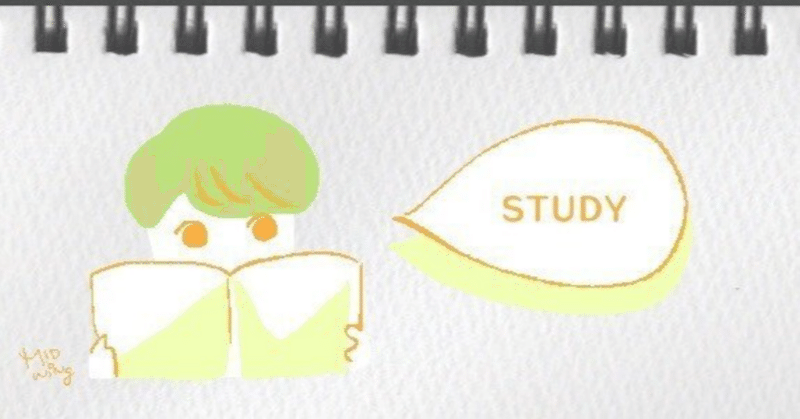#学び
論語のススメ...論語入門編まとめ①
①人と社会のみちしるべ……論語とは
論語は、今から約2500年前に中国でできました。
論語をあまり知らない人からすると、
孔子が書いた本というイメージの人もいるかもしれません。
実は、論語は弟子達がまとめた語録なのです。
孔子(紀元前551~479年、春秋時代末期の思想家・教育者・政治家)が亡くなった後、孔子と優れた弟子達が言ったこと、行ったことを書き記しました。
孔子、直弟子、孫弟子達は、
現代的論語1 学びを通して得る喜び
私は論語を学んでいる者です。
論語との出会いは、約3年ほど前。
開業する際に、昔からお世話になっている税理士さんから「経営者になるなら論語を学べ」と言われたことがきっかけでした。
当時は論語についてはさっぱりで、
『どんな勉強なんですか?』と尋ねたところ、
「孔子だ」と一言。
何のことか結局よく分からないまま、税理士さんが参加する論語の勉強会に一緒に参加しました。
そこにおられた方々は、人生