
内田樹 『日本辺境論』 : 読んで楽しい 「自己啓発本」
書評:内田樹『日本辺境論』(新潮新書)
本書は『新書大賞2010 第1位』を獲得した、当時のベストセラー本である。
ちなみに、この「新書大賞」というのは、中身云々ではなく、「よく売れた新書本」に与えられる賞だ。
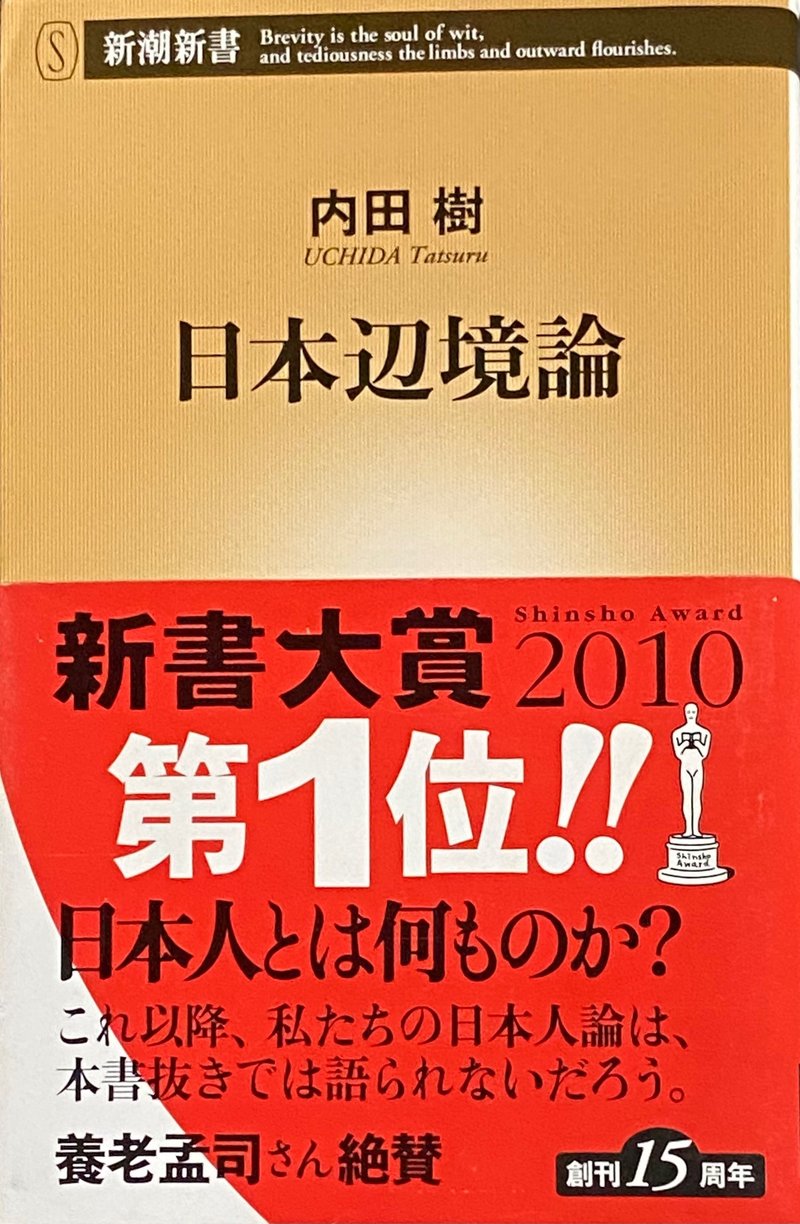
なんで10年以上も前のベストセラー本を読んだのかというと、最近読んだ本の著者が本書を褒めていたからで、「それなら、やっぱり良い本だったのかな?」と思ったからである。
ちなみに、何という本で誰が褒めていたのかは失念した。いつも書いているとおり、自慢ではないが、私は記憶力が弱いのだ。
さて、書き手である内田樹についての私の評価だが、これがいささか微妙なものである。
「書ける人」だというのは間違いないのだが、どうも、いまいち信用しきれないところがある。
平たく言うと「口のうまい、世渡り上手な男」という印象が拭いきれない。
もちろん、書ける人なのだから、書いたものについては、その内容によっては褒めることもあるのだが、「これは、真に受けられないな」というようなものも少なくない。
内田樹については、2002年刊行の第4著書『寝ながら学べる構造主義』がすごく面白かったので、第1著書『ためらいの倫理学』、第2著書『レヴィナスと愛の現象学』、第3著書『「おじさん」的思考』、第5著書『期間限定の思想 「おじさん」的思考2』と、鈴木晶との共著『大人は愉しい』(2002)などを読んだ後、しばらく遠ざかっていた。
『『ためらいの倫理学』(2001年)以来、レヴィナスをはじめ思想の簡明な解説や、知的エッセイを数多く執筆。少子高齢化、成熟した資本主義経済の末路への予測から、消費を基盤とした経済システムが終焉を迎えつつあるとし、今後は共同体による相互扶助、共生的な考え方を基盤とした社会を目指すべきだとしている。ネットにおける匿名性の危険性についても、警告を発しており、著書の多くは、ブログから発信した文章がもとになっている。
映画、武道に関する批評活動でも知られ、自身も合気道や居合道の有段者である。合気道については、大学を退職後、道場兼能舞台である「凱風館」を完成させて、そこで師範として合気道の指導を行っている。』
とあるとおりで、大学の先生であった当時、学生の運営による自身のブログに掲載していた文章が話題となり、それが書籍化されるようになった人である。

したがって、文章は読みやすく、わかりやすい。
その意味で、たしかに「面白い」のは面白いのだが、少々つっこんで読んでいくと、引っかかるところが目につくようになる。
例えば、この人には、一般に「リベラル」と呼んで良い立場なのだが、「フェミニズム」に対しては攻撃的で、私は当時から、そのあたりにかなり引っ掛かりをおぼえた。
たしかに、当時のフェミニズムは、かなり先鋭で攻撃的なものではあったけれども、それは歴史的な価値観が揺るがされる「過渡期」のものとして、ある程度は仕方がないんじゃないかと、古い型の男性フェミニストである私などは、そう思っていた。だが、内田は意外に、「寛容」ではなかったのだ。
内田のフェミニズムに対する書き方には、多分に感情的なものが籠っているように、私には感じられた。
詳細は忘れたが、「それはどうかな?」と引っかかる部分があって、内田のブログのコメント欄に「この部分は、こうこうだからおかしいんじゃないですか」というような「懇切丁寧な長文」のコメントを、何度か書き込んだ。
だが、無名の素人の、しかも批判的なコメントに、意を尽くした回答など与えられなかったし、こちらとしても「荒らし」だと思われるのは業腹なので、そこそこで切り上げておいた。
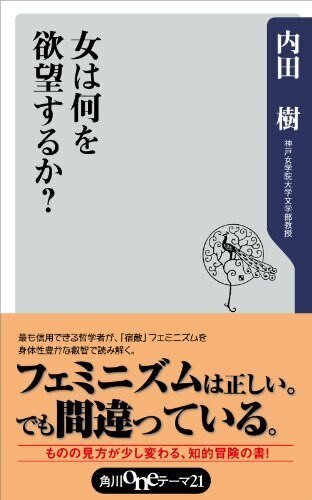
こんなことを書くと、「そこでも、やってたのか」と呆れられそうだが、私は、おかしいと思ったら、相手を選ばず議論をふっかけるので、これは通常運転だと思っていただきたい。別に、相手が有名人だからといって、遠慮しなければならないとは、寸毫も思っていない。
内田だって、公式には、そんな差別など設けていないはずだが、気分が悪いだけで、銭にもならない議論につき合う気はなかったようである。
そんなわけで、私は、内田について「自分のファンや支持者には、フランクで親切だが、そうでない者に対しては、無視を決め込むタイプ」だという印象を受けた。
実際、その後の内田の著書を見ても分かるとおりで、仲の良い者どおしで褒め合う「お友だち本」が多いように思うがいかがだろうか(このあたり、佐藤優なんかと共通点がある)。
この人は、基本的に、人を「名指し」で批判したり、真正面から議論したりはしない人のようなのだ。
事実、本書でも「広く誤解されているようだが、天下無双とは、いちばん強いという意味ではなく、敵を作らないということだ」という趣旨のことを書いている(P173〜181)。
一一相手のいないところでは、皮肉めいた書き方くらいはしてもである。
そういうわけで、内田が「リベラル」で「反・安倍晋三」といった側面では、意見を同じくするものの、人としては、どうにも信用しきれない。
この人の文章のうまさは、多分に「人を煙に巻く」技巧として働いているように感じられてならないのである。
だから、もちろん、個々の意見については是々非々で評価はするし、支持し評価できる意見の持ち主なのではあるが、「人としては信用しきれない」という印象が、ずっと拭えないでいるのだ。
しかしまた、それでも2007年の『下流志向』だったかを、(刊行当時にだったかどうかは忘れたが、とにかく)評判を聞いて読み、素直に感心したし、2021年の「日本学術会議問題」に関する論文集『学問の自由が危ない 日本学術会議問題の深層』に寄せた文章については、
『学術会議の会員ではないが、今回の問題に「学問の危機」を感じて、本書の編者の一人となった、ご存知、内田樹先生の文章は、さすが手練れの「批評家」だけあって、他の先生方では真似のできない、思いもかけない「逆説的な洞察」を開陳している。これは、抜群に面白いので必読だ。』
と書いて、推薦までしている。
だが、やはりこれとても、その技巧(切り口)に対しての『面白い』という評価であった。
○ ○ ○
さて、肝心の本書『日本辺境論』だが、率直に言って、期待を大きく下回って「うさんくさい」、という印象であった。つまり、低評価。
いまさら読もうと思ったのは、この本を推薦していた人の評価を信用したからで、内田の人柄はともかく、その著作に優れたもの、面白いものがある、というのは確かなことなのだから、本書はベストセラーにもなったことだし、「面白い」本になっているのではないかと、そう本気で期待していた。だからこその、期待はずれなのである。
本書の内容を簡単に紹介すると、次のような感じだろうか。
「日本は、中国に朝見していた邪馬台国の時代以来、「(中華に対する)辺境国」という意識が抜けない国であり、そのために、他所を気にせず自分の意見を持って、自分が先頭に立って「理想」を示すといったことができない。かつての「中心」である中国が、西欧先進国に変わったところで、その意識は何も変わらない。いつも、よそに中心があって、それに対して、自分がどういう位置どりをするか、という発想しか持てないでいる。
そのための難点がいろいろとあるわけだが、しかし、こうした日本人の「辺境国意識」はもはや骨がらみのものであり、いまさら変えることはできないと考えるから、私(内田)はむしろ、その欠点を意識しつつ、欠点の裏返しである長所を生かす方向で考えたい。世界の中でも、最も徹底的に辺境国意識のしみついた国であり、その国民として、我々にしかできないことがあるはずだ。」

本書は、「はじめに」において、くどいくらいに「本書にはオリジナリティーはない」と強調される。
本書で語られるのは「日本論」なのだが、日本人ほど「自国論」が好きな国民もいないのではないかというくらいに、次から次へと「日本論」が書かれ、消費され、忘れ去られ、また書かれて消費されるということを繰り返しているので、自分が書くものも、決してオリジナルではなく、先人の議論を塩梅したものに過ぎないのだが、どうしてわざわざ、そんなものを書くのかといえば、年に一度は側溝や雨樋の掃除をしてゴミをとり除かなければならないのと同じように、日本人がどういうものなのかというのは、繰り返し確認反省されなければならないことだからで、私(内田)は「側溝掃除」を引き受けるような気持ちで、これを書くのだ。一一というような趣旨だそうだ。

なるほど「立派な志」だとは思うのだけれど、そんなに、くりかえし「日本論」が書かれ読まれるのならば、「何もあなたが、そんな汚れ仕事を引き受けなくても、他に似たようなものを書く人が、必ず出てくるでしょう」と思うのだが、内田は「自己犠牲精神」の陶酔に浸っているのか、そうした疑問は持たなかったようである。
が、ともあれ、その「犠牲的精神」のおかげで、本書は、内田の著書の中でも最も売れた本になったのだから、期せずして、一一かどうかは別にして、まあ書いて良かったのではないだろうか。今となってはもう、ほとんど読まれない本だとしてもである。
著者自身が本書の中で書いているとおりで、本書は「長編論文」的な著作ではない。あらかじめ明確に認識された「結論」があって、それに向かって、論理的に、手順を踏んで書かれたような、構築的な本ではない。
平たくいえば、本書は「日本は辺境国意識に支配された国である」というガイドラインに沿って、思いつくままに書かれた「長編エッセイ」であり、書いている内田としても楽しいしだろう、読む方にとっても肩のこらない本なのだが、いささか散漫な印象は否めない。しかしまた、これは最近の私の書き方と似てもいて、その気持ちは理解できる。
ともあれ、『日本辺境論』などという硬目のタイトルだから、もっとかっちりした「日本論」かと思ってしまうが、そうしたものではない。
これまでに何度も書いている「教育論」とか「武道論」「宗教論(霊性論)」といったことを、「辺境国意識」と絡めて書いているので、内田の著作をある程度読んできる読者には、いささか新味に欠ける印象が否めない。
なにしろ、「日本人論」としては「オリジナルではない」と最初に断じるのだから、本気で「日本人論」を書きたいのか、その「切り口」にかこつけて、いつも書いていることを変奏的に書けると思っただけなのか、そのあたりが少々あやしい。

前述のとおり、本書は「日本人には、こういう難点があるから、ここをこういう方向で正していきましょう」というようなものではなく「それは無理だから、難点・欠点の裏返しである、長所を生かそう」という内容なので、結局のところ日本人としての「自己正当化」臭が否めない。
なるほど、こうした書き方なら、世の中を改革改善しようとする「左翼」が弱った時代の「日本人論」として、本書がベストセラーになったというのも、うなづけるところだ。
結局のところ、多くの読者が本書から受け取るメッセージとは「我々にも欠点はあるけれど、それはどこの国の国民だって同じで、それぞれに欠点もあれば長所もある。ならば、我々はその長所を伸ばせばいいし、その長所とはこういうものなんだよ」という内容で、「日本人の特性」讃美に近いものになっているのである。
そしてさらに引っかかるのは、その「日本人的辺境意識の肯定」が、内田自身の「自己肯定」にもなっている点だ。
先にも触れたとおり、内田は、それまでにも何度となく書いている「教育論」や「武道論」あるいは「宗教論(霊性論)」といったことを、本書でも繰り返しているのだが、本書ではそれが「日本人の辺境国意識」と「肯定的」に結びつけられて、持論の「補強」となっている。
つまり、内田は、自身も分かち持つ、日本人としての辺境国意識を、全面的に肯定しているわけではなく、その弱点を認めつつも「しかし、それは骨がらみのもので変えようもないから、その弱点を長所として生かすことを考えよう」と提案し、それを持論と結びつけ、結果として、自己の方法論を「優れて日本人的な方法」のように語っているのである。
だからこのあたりが、「結局、それかよ」という感じで、我田引水するレトリックとしては大したものだが、やっていること自体は、かなり胡散くさいのだ。
例えば、本書でも、過去の話として「フェミニズム」に対する自身の見解を述べている部分があるのだが、この書き方が、いかにも「内田樹的にレトリカル」なものなのである。
『 以前別の本でも取り上げたことですが、九〇年代に日本にフェミニズム言語論というものが入ってきたことがありました。そのときはずいぶん勢いがよくて、一時期、文学研究はほとんど「ジェンダー論」一色に染まったことがあります。その基幹的な主張の一つは「女性に固有のことばを奪還せよ」というものでした。
あらゆるテクストは「性化」(sexualize)されている。無性の、あるいは中性のテキストというものは存在しない。これまで女性たちが読まされてきたテクストはすべて「男性の書き手、男性の主人公、男性の読者」という三重の拘束によって、男性中心的に編成されてきたものである。だから、すべての人間は一一男であろうと女であろうと一一男として書き、男として読むように訓練されてきている。フェミニストはそう主張しました。そして、そのような仮説に基づいて、文学のカノンが次々と「男性中心主義的イデオロギーのプロパガンダ装置」として告発されていったのでした。
私はこのときに、「女性に特化した言語を創出しなければならない」というリュス・イリガライらの論をそのまま日本の言語状況に適応して怪しまないフェミニストの「世界標準準拠主義」の徹底ぶりに驚きました。現に、日本語には「女性語」があるわけで、そのことをこの人たちはどう考えているのか。私たちの国語には、女性に特化した人称代名詞があり、 活用語尾があり、単語がある。それが土着の、コロキアルな、本音の言語であり、男性語に「斜めから」切り込むことで、男性語が語る命題の硬直性や空語性を暴露する批評的機能を果たしている。その女性語の果たしている役割をまったく無視して、主語人称代名詞を一つしか持たず、女性に特化した動詞も女助詞も持たない英語やフランス語の話者が自国語の文法構造を「世界標準」に見立てて作り上げた言語理論を無批判に受け容れている。
外来の知見を「正系」と掲げ、地場の現実を見下す。これが日本において反復されてきた思想状況です。フェミニズム言語論では、この構図がそのまま忠実に反復されました。ですから、このときは外来のブランニューな理論を掲げて、地場の「遅れた」文学を俎上に乗せて批判したフェミニストたちは「男性ジェンダー化」していたのです。そして、それに対して「なんだか、現実離れしたことを言っているなあ」と物陰でぶつぶつ文句を言っている私のような人間の言葉は「女性ジェンダー化」していた。
別に私はフェミニストが間違っていて、私が正しかったと言っているのではありません。日本語では、いつだって「外来の高尚な理論=男性語」と「地場のベタな生活言語=女性語」の二項対立が反復されていることを申し上げたかっただけです。そして、その相剋のダイナミズムのうちに、私たちの言語が豊穣化する契機もまた存在する。私はそう思っています。』(P245〜247)
つまり、フェミニズムに『ぶつぶつ』言っていた頃の内田樹は、「反フェミ」のネット右翼などに歓迎された、「バックラッシュの論客」の一人だった、ということである。
そもそも、この文章を読んで『別に私はフェミニストが間違っていて、私が正しかったと言っているのではありません。』なんて「自己申告」を真に受ける人というのは、日本語を語る資格のない文盲だと断じてもいいだろう。
むしろ、この文章には、内田樹という人の「人間性」が、とてもよく表れていると思うのだが、いかがだろうか。
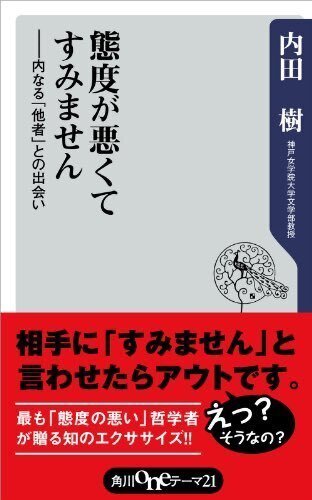
そもそも、第二次だか第三次だかのフェミニズム運動が衰退した後に、それに抵抗していた内田による、この一方的な「まとめ説明」を真に受けるのは、あまりに軽率だ。
内田のこの論法は、例えば、イギリスの政治家で、同時代の「フランス革命の暴力的な側面」を強調して描いた『フランス革命の省察』で名高い、「保守思想の父」エドマンド・バークの手つきに、そっくりなのである。
たしかに、フランス革命に「過酷な現実」があったのと同様、フェミニストの中にも、レベルの低い人は大勢いただろう。
しかしそれは、内田の読者の中に、フェミニストの文章をまともに読んだこともないのに、内田の一方的な「説明」を真に受けてしまうような人が多いという事実と、ほとんど同じことである。
つまり、私がいつも引用して紹介しているように、SF作家のシアドア・スタージョンの言う『SFの90パーセントはクズである。ただし、あらゆるものの90パーセントはクズである』ということなのだから、内田がここで、さも、当時のフェミニスト言語論者は「みんな、このレベルで語っていた」かのように「まとめ」て見せるというのは、眉に唾して聞くべき話なのだ。
また、そういう「低レベル」のフェミニストを批判するのであれば、せめてその人物を「名指し」て(特定して)、検証可能なかたちで、批判すべきではないだろうか。
だが、内田樹という人は、もともと学者としての厳密さよりも、エッセイストとしての「レトリック」に秀でた人だから、いつだってこのように「斜めから」斬りつけるのを得意として、決して「真正面から」立合うことなどしない武道家なのである。

上に引用した部分だけでも、私が内田樹に感じている「信用ならなさ」は、十分に伝わると思うが、これだけでは信用できないという人は、是非とも本書を読んでみるべきであろう。
たかだか300ページにも満たない、読みやすい長編エッセイの新書本だし、大いに売れた本だから、今では、ブックオフオンラインで220円、店舗販売なら百均の棚に並んでいる蓋然性も十分にある。
どんなに評判の良かったベストセラーも、過去のものになってみればこそ、それが、顧みられ読み直される価値のあるものかどうかは、むしろわかりやすいのではないだろうか。
何にしろ、読書家としての私の直観でいうならば、内田樹の本は何も残らないと思う。
読んで面白くはあっても、思想的な影響を残せない文章だ、ということだ。
しかし、私は何も、だから「内田書に価値がない」と言っているのではない。どんな時代にだって、気散じのための「教養書」というのも、やはり必要だと思うからだ。
そういうものは、繰り返し書かれ、繰り返し消費され、また新たに似たようなものが書かれていくものなのだ。
一一無論これは、内田先生に倣って、「斜めから」語ってみただけなのではあるが。
(2023年7月3日)
○ ○ ○
○ ○ ○
