
池上彰・佐藤優「日本左翼史」三部作:〈転向左翼〉の知ったかぶりと自己正当化
書評:池上彰・佐藤優『漂流 日本左翼史 理想なき左派の混迷 1972-2022』他三部作(講談社現代新書)
端的に言うなら、本稿タイトルのとおりで、池上彰と佐藤優による対談「日本左翼史」三部作は、「〈転向左翼〉の知ったかぶりと自己正当化」の書だと、そう総括することができよう。

そして、この「対談三部作」をありがたがる読者とは、基本的に「日本左翼史」に無知な、言うなれば「初心者」か、著者らと政治的立場を共有する「転向左翼」(あるいは、人気者に無節操に擦り寄る、時流迎合の文筆業者)だけである。
無論、誰でも最初は「初心者」なのだから、こういう「読みやすい本」から「入門」すること自体は、決して悪いことではない。
しかし、この程度の「薄っぺらい本」を読んで、「日本左翼史」を理解したような気になる人間は、このシリーズと同様に「薄っぺらで偏頗だ」ということになる(キリスト教書に例えるなら、本書は、清涼院流水の『どろどろの聖書』みたいなものだ)。
「思想」や「イデオロギー」ということを、少しでも「原理的に」考えたことがある者なら、「思想史」が非常にセンシティブな扱いを必要とするものであることくらいは、当然のこととして理解しているはずだ。
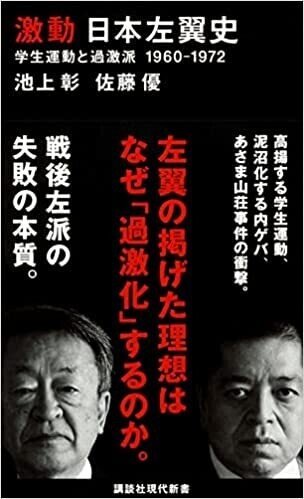
ところが、本シリーズをありがたがるような「一般読者」というのは、ナイーブにも、そういうことを考えたことがなく、「有名な知識人が言っているんだから、間違いないだろう」くらいの考えで、「ひととおりの知識」さえ得られれば、それで「知ったかぶり」できてしまうような「薄っぺらい」人たちなのである(Amazonのカスタマーレビューを参照)。
こういう「一般読者」のために、あえて分かりきった説明をさせてもらうが、「思想史」というのは「思想の歴史」を扱う学問であり、「思想の変遷を、歴史として描き出す」ものだと言えるだろう。
ここで問題となるのは、もちろん「著者の視点」である。
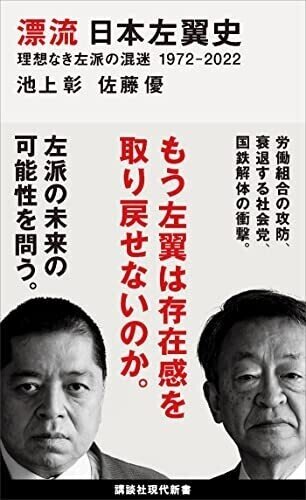
例えば、その人が、(あらゆる人間に対して)完全に「公正中立な立場」、言うなれば「神様」か「宇宙人(異星人)」のような立場にあるのならば、「人間の思想史」を「客観的に描く」ことも可能であろう。
ただし、「神様」の視野には、「人間」だけではなく「他の生物」、あるいは「宇宙人」などの立場も入っているから、「人間の思想」というのも、もちろん「左右上下」に色々あるとはいえ、全体から見れば「左右を問うまでもない、下」だと、そう、にべもなく評価するかもしれない。「人間の思想」など、「左右上下」を問題にするまでもなく、すべて引っ括めて、もう本当に「クソのような生物の、目糞鼻糞を笑うようなシロモノでしかない」ということにもなりかねないのだ。
これは「宇宙人(異星人)」の視点にしても同じだ。「地球人類の思想」など「地球蟻の思想」と「大同小異」でしかないと見られるかもしれない。遥か彼方の外宇宙から飛来した、高度な文明を発達させた「宇宙人」からするなら、「地球人類と地球蟻とは、すべてにおいて大差ない下等生物」でしかない、かもしれないのだ。
しかし、これでは「人間の思想史」にはならないから、「神様」や「宇宙人」のような「高みの存在の視点」ではなく、同じ地平に立った「人間の視点」で「思想史」を描くしかないとなると、今度は、その「視点人物=思想史を描く人」の「立ち位置」が問題となる。

つまり、その人が、極端に「右」に振れた立場に立っていれば、大概のものは「左」に見える。例えば、「新右翼」団体である「一水会」の鈴木邦男を「左翼」呼ばわりする、「右寄りの人」は少なくない。大きく「右」に振れた人たちであれば、鈴木邦男が「左」に見えるというのは、理の当然なのである。
また、その人が、極端に「左」に触れた人であれば、大概のものは「右」寄りに見えてしまう。当然、鈴木邦男は立派な「右翼」だと評価されるだろう。
ことほど左様に、「思想史を描く」と簡単に言っても、その「視点人物=思想史を描く人」の立ち位置によって、その「風景」は、ガラリと色合いを変えてしまうのだ。
だから「思想史」を書くのは難しいし、それでも「人間」が「神の視点」を採り得ず、「どこかの地点」に立って「思想史」を描かなければならないのだとしたら、その人がいかに誠意を持って「中立=中央・中間地点」に立つ努力をしたとしても、やはり原理的に「客観的な評価」などあり得ない、というのがわかるはずだ。
つまり、この程度のことは、「当然、考えていて然るべきこと」であり、そうでなければ「思想史」を語る資格など、その「読者」にもない、ということなのだ。

ところが、池上彰と佐藤優による対談「日本左翼史」シリーズを読んで、多少の「知識」を得ただけで、もう「左翼に関して、一人前の知識を得た」かのように思ってしまうような「一般読者」とは、言うまでもなく「当然、考えていて然るべきこと」考えていない人、「考えておかなければならない」ということにすら気づくことのできない、馬鹿だ、ということになる。
では、当たり前に「当然、考えていて然るべきこと」を「考えておかなければならない」と考える人なら、どうするだろう?
それは無論、当たり前のように「中立」を装っている、本シリーズの著者である、池上彰と佐藤優の「立ち位置」を厳しく検討し、その検討結果を勘案して、彼らが「中立的判断によるもの」として語っていることの裏側に隠された「思想」や「イデオロギー」に配慮して、「話半分」に聴く、というスタンスに立つだろう。
そして、その上で、この二人と意見(見解・解釈)に「対立するであろう立場の人たちの意見(見解・解釈)」を付き合わせ、さらに、この両者と意見対立する「第三項」あるいは「第四項」といった立場の意見にも耳を傾けて、その上で「精一杯、総合的に公正たらんとする、自分の良心」に基づいて、公正に判断しようと努力する「しかない」のである。
言うまでもなく、「自分」自身もまた、決して「公正中立」ではないけれども、少なくとも「心から公正であろう」とすることなら出来るのだから、最後の判断は「自分の良心」しかないのだ。
ところが、馬鹿な人たちは、こうした「個々が引き受けるべき判断責任」を、安直にも「世俗的権威」に、平たく言えば「有名人・人気者」に預けてしまう。
「あの人が言っているのだから、正しいに決まっている」とか「大丈夫」だと、広く情報を集めた上で自分で判断するという努力を放棄し、またそれが無責任だと気づく知性すら持たないのが、私の言う「馬鹿」なのだ。
そして、そんな「馬鹿」が、本書(本シリーズ)だけを読んで満足し、本書をベストセラーに推し上げる。

こうした「馬鹿」は、「ベストセラー」になって「多くの人から支持されている」ものならば「それが正しい」と信じられるほどに「馬鹿」なのだ。ヒトラーを支持した多くのドイツ国民もまた、ヒトラー自身も言うとおり、この手の馬鹿であり、現在の日本人の、少なくとも99パーセントは、こういう馬鹿なのだ。
なにしろ、このシリーズを読んでいる人の、8割がたが、本書に満足している馬鹿なのだが、しかし、この程度の本すら読まない(何も知らないでも、正しく判断できると思い込んでいる)というのが、日本国民の9割なのだから、日本人の99パーセントが「馬鹿」だという私の判断は、決して過大なものでもなければ、故なきものでもないはずなのだが、いかがだろうか?
じっさい、本シリーズに満足した人のうちの何パーセントが、本書著者たちが批判し否定的に評価した人たちの意見に耳を傾けようとして、そうした人たちの著書を手に取っただろうか?
しかし、「一般読者」とは、書店に並んでいるような本以外、つまり「マイナーなもの(不人気なもの)」を、探してまで読もうとはしないものだ。所詮はその程度の、「知ったかぶりたいだけの馬鹿」でしかない、ということなのである。
○ ○ ○
私が、ここで書いたようなことなど、ひと昔前なら「常識」に類する話でしかなかった。
事の善し悪しを判断するためには、まず「いろんな角度から」その問題を検討し、いろんな見方に虚心に耳を傾けた上で、出来うるかぎり客観的に判断しなければならない。一一これは、そんな「当たり前の話」でしかない。

しかし、今は、その「当たり前」が通用しない。何もかもが、じつに「お手軽」になった。
ちょっと、小腹がすいたら、マクドナルドにでも行けば、手軽に美味しいものが食べられる。
材料から買い揃えていって、手間暇かけて調理して、それでも、さほど美味しくもないものしか作れなかった「昔」に比べると、今は「お手軽」に、それなりに「美味しいもの」が食べられるようになった。
だが、私たちは、そうした「ファスト文化」によって、多くのものを失った。
「舌」を失い「耳」を失い「目」を失い、「頭」も失って、「心」まで失ってしまった。
本書、池上彰と佐藤優による対談「日本左翼史」三部作とは、要は、そんな「ファスト読書」の時代の「ファスト思想史」であると言えば、「ファスト文化」に 漬けこまれた人たちにも、比較的わかりやすいのではないだろうか。
いや、きっと、これはこれで、彼らには難しすぎるに違いない。
(2022年7月30日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
