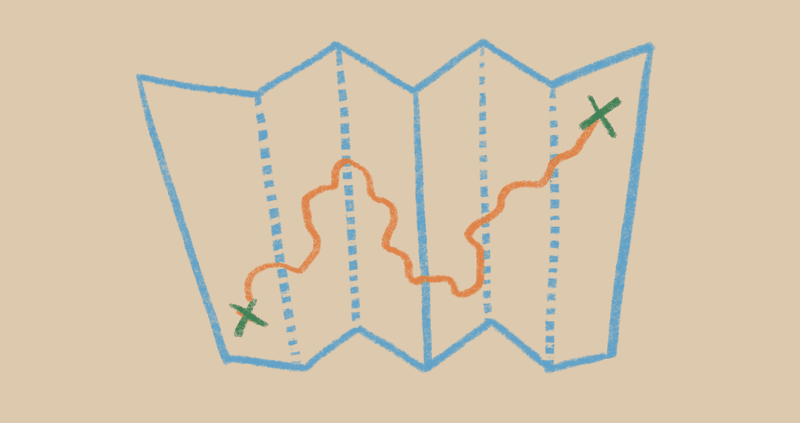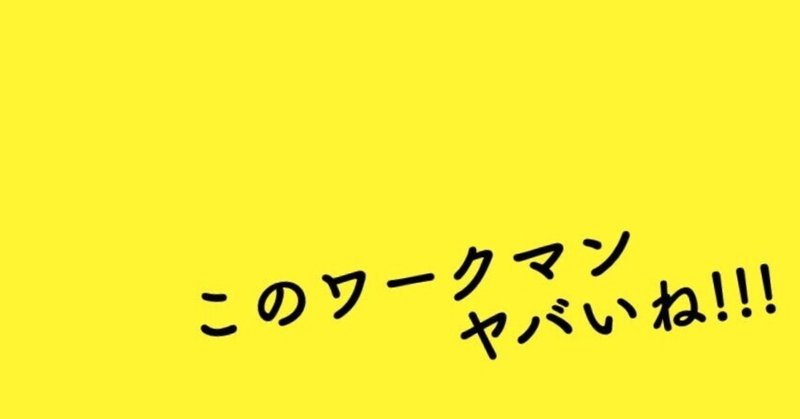ビジネスを通して人間は形成される。そういっても過言はないかもしれません。本の棚のなかでもかなりのボリュームを占めるビジネスコーナーは古典的なもの〜最新の情報まで幅広く並べていきま…
- 運営しているクリエイター
#経営者
本の棚 #154 『負けてたまるか!リーダーのための仕事論』
前著『若者のための仕事論』を
入社当時から何度も読み返した。
まずはアリ、そしてトンボ、最後はヒト。
そんな働き方をしなさい、という
丹羽さんの仕事論。
サラリーマン(商社マン)としての
リアルな体験談をまじえながら
偉い人なのに全然偉そうじゃない。
そんな文章に、また惹かれる。
−−−−−−−−−−−−−−
リーダーとなる、つまり部下ができたら
気をつけなはれ。
上司が部