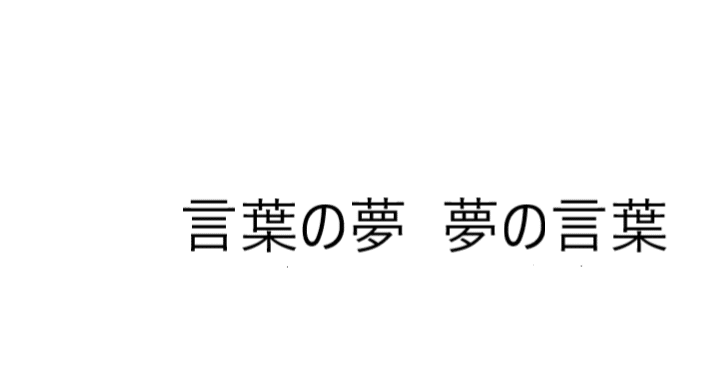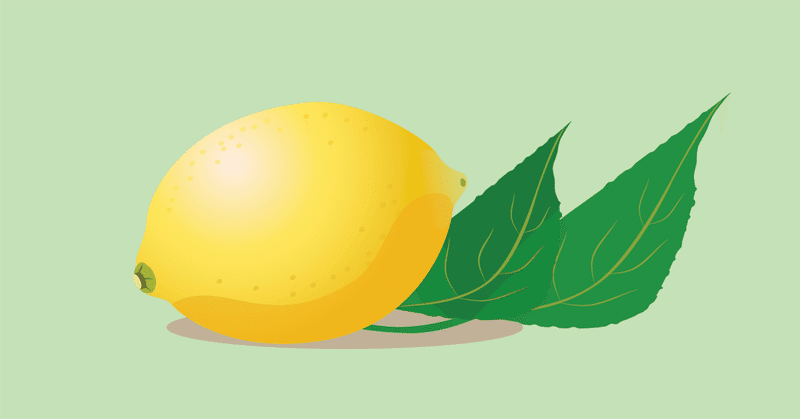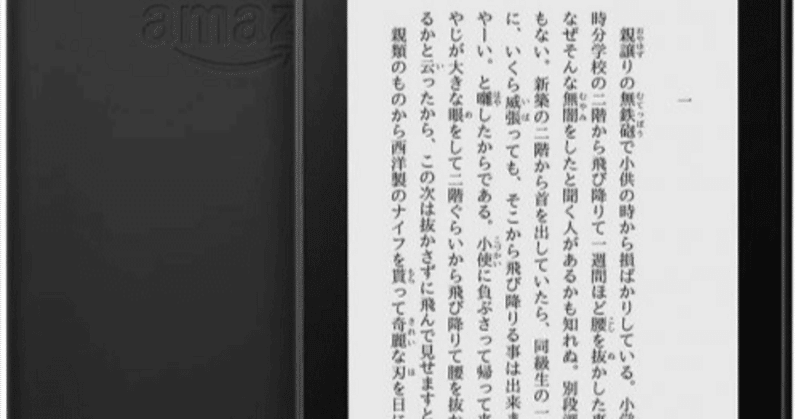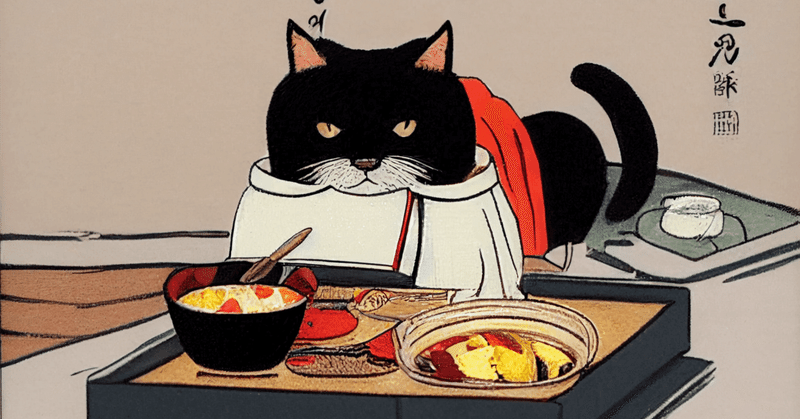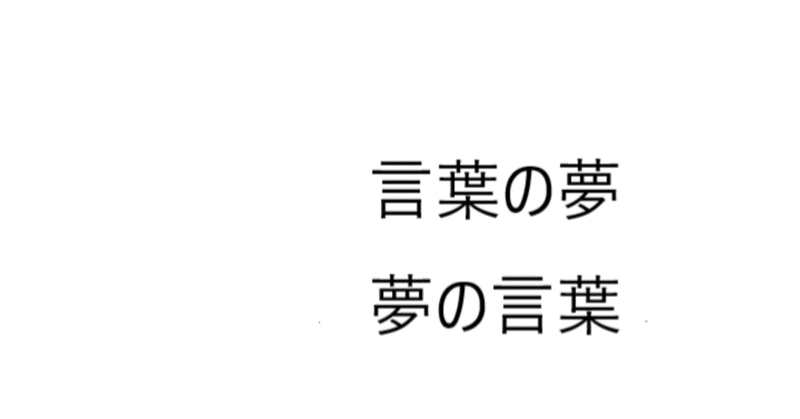#読書
「読む」と「書く」のアンバランス(薄っぺらいもの・07)
◆第一話
文章を書くのは料理を作るのに似ています。天才と呼ばれる人は別なのでしょうが、私なんかはずいぶん苦心して文章を書いています。
勢いに任せて殴り書きする癖があるにしても、文章を書くのには手間と時間がかかるのです。
料理も手間隙かけてせっかく作ったのに、ぺろりと平らげられる場合があります。あっけないですが、作ったほうとしてはうれしいものです。
書くのに時間と労力を要するのに、さ
音読・黙読・速読(その3)
シリーズ「音読・黙読・速読」の最終回です。
・「音読・黙読・速読(その1)」
・「音読・黙読・速読(その2)」
◆センテンスが長くて読みにくくて音読しにくいけど素晴らしい文章
まず、前回に取りあげた文章を再び引用します。なお、あえてお読みになるには及びません。ざっと目をとおすだけでかまいません。
(Ⅰ)
(Ⅱ)
*節のある竹のような文章
上で見た、井上究一郎訳によるマルセル・プル
小説が書かれる時間、小説が読まれる時間(小説の鑑賞・06)
「小説が書かれる時間」と「小説が読まれる時間」には「ずれ」があります。さらには「小説に書かれている時間」とのあいだにも、「ずれ」があります。
時間は一直線に進行していると感じられますが、そのなかに生きる人間にとって、時間は「ずれ」だらけ。人は時間の「ずれ」のパッチワークのなかで生きているのではないでしょうか。
小説は料理に似ている
小説は料理に似ています。つくるのには時間も労力もかかるのに
くり返すというよりも、くり返してしまう
創作と読書と夢に耽っているとき、人は似た場所にいる。自分以外の何かに身をまかせている、または身をゆだねているという点が似ている。
そこ(創作、読書、夢)で、人は自分にとって気持ちのいいことをくり返す。気持ちがいいからくり返す。というより、くり返してしまう。
創作であれば、その「くり返してしまう」が作家のスタイルになり、読書であれば、そのこだわりが読み手の癖になる。夢はその人の生き方と重な