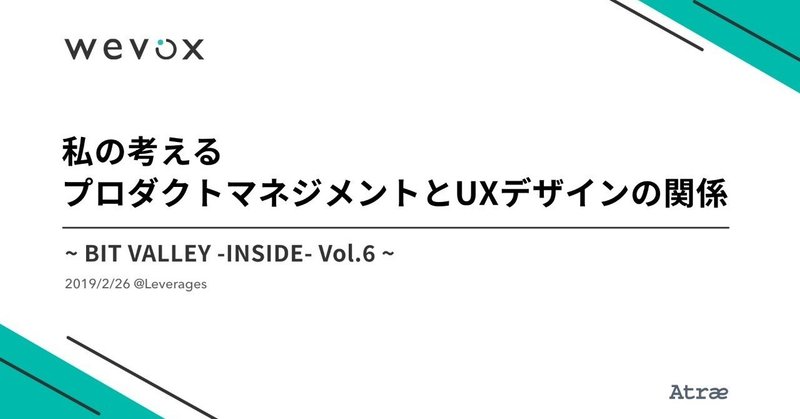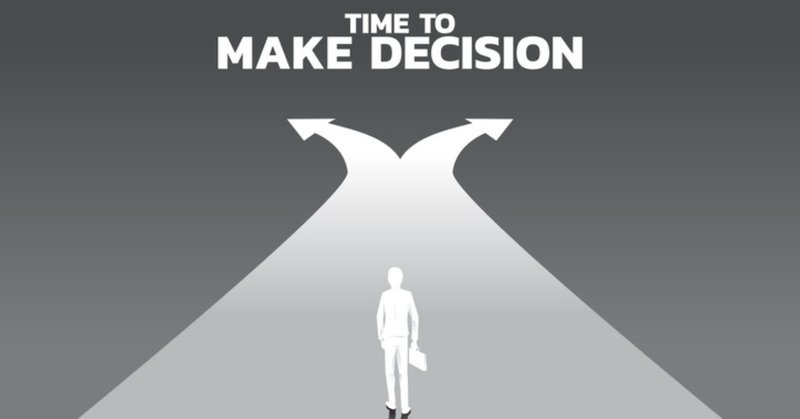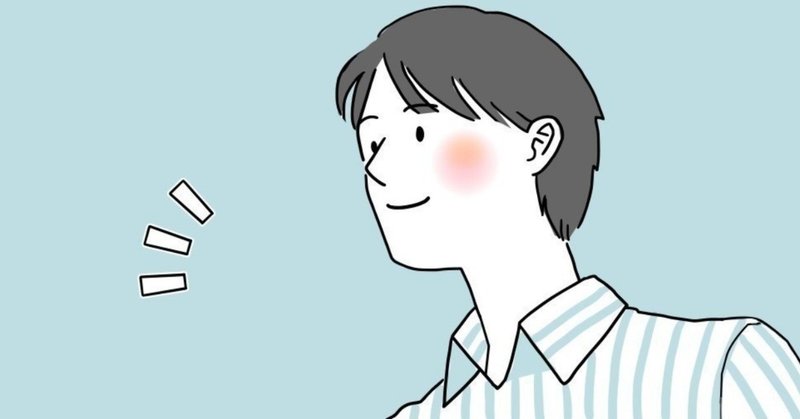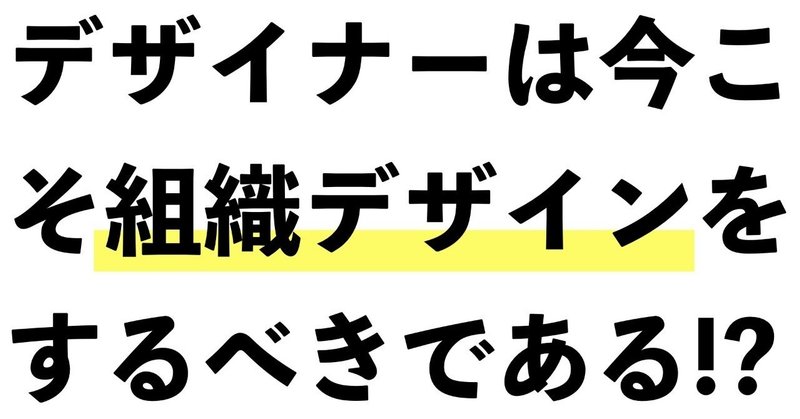- 運営しているクリエイター
2019年3月の記事一覧
集団で意思決定するのと、個人でするのとではどちらが有効なのか?
※この記事は有料マガジンの特別無料版です。
日本企業の停滞が長い間続いています。僕はかつてはこれ、意思決定者たちが昭和の成功体験を引きずっているからだと思ってたんですね。でも、アップルに務めたり自分で起業したりするうちに、これは単に意思決定のやり方の問題なんじゃないかと思い始めたのです。そして、最近ネットを騒がせている「『印鑑なしで法人登記』法案提出を見送り」のニュースを見て、あ、これはやっぱり
1人の方がアイディアが出やすいことと、3月10日の日記
※この記事だけを100円で買えますが、こちらのまとめマガジンを購入すると、1ヶ月約30本で400円で買えるので、1本約13円なのでそちらがお得です。
お店のカウンターで「お悩み相談」を受けることってあるんですね。まあnoteなんかで質問を受けているから、「だったらカウンターで」っていうお気持ちなんだと思います。
でも、どういうわけか、カウンターで質問されると、「うーん…」って感じで「良い解決
企業文化が「宗教」から学べることは一体何なのか?|カルチャーデザイン
行き過ぎた慣習や偏狭的な熱量は、時として「宗教」と呼ばれる。
それは「企業文化」というコンテキストにおいても同様で、パッと思いつくもので例を挙げればGMOさんで行われるスピリットベンチャー宣言の唱和は、定められた"教典"や"戒律"そのものだけでなく、唱和という"儀式"も合間って「宗教」的な輪郭を見るものに意識させる。実際、創業者の熊谷さんは宗教的な要素を意識的に取り組んだとも明言している ーーー
優れたチームは一度死ぬ
僕たちはこれまでたくさんの"チーム"に所属してきた。
例えば、
自分自身と向き合い、好きな仕事を見つけ、狭い門をくぐり抜け、ようやく入社した会社。これからは大人同士で好きな仕事に向き合える。
でも…
配属されたチームでは、勤続年数が多い社員が実権を握り、経験が浅い僕たちは、喉の奥に溜まった本音を言えないまま、かけがいのない時間を過ごすこともあるかもしれない。
例えば、
優秀な監督の元、
034. 「嫌いな仕事はやったらダメ」のルールをゆるくしたら、問題がおきた
「好きな日に働く」「嫌いな仕事はやったらダメ」などのパプアニューギニア海産の働き方はこちら。
昨年5月に一人のパート従業員が「むき作業」に✖(嫌い)をつけました。この「むき作業」は全作業の5割以上を担うメインの作業です。さすがにメイン作業を「やってはいけない」にすると問題が生じるような気がして、作業の流れによって「やったらダメを解除する」という何とも中途半端な決断をして10か月(詳細は「嫌い
これまでの発言、そしてこれからの発言は、全てこの3937文字に通ずる。
時々私は、自分は動物園にいる動物だったのではないだろうかと思う時がある。特に外国に住み始めてからというもの、この人たちが野生の動物であるならば、日本人は“動物園にいる動物”なのかもしれないと、確かにそう思う。もしくは、野生の動物に近い環境で飼育されている動物だろうか。
それが良いか悪いかは一度置いておいて欲しい。全く正解を言える自信がないし、その必要もないように思う。
ただ、日本人は、いつから
なぜ彼らは異常なまでに「見た目」に気を配るのか——。“弱い”と“ダサい”は比例する
人は本を表紙で判断する。最高の製品、最高の品質、非常に有益なソフトウェアなどを備えていたとしても、見せ方がいい加減であれば、いい加減なものにしか見えない。創造的で洗練された見せ方をすれば、望ましい特性を持たせることが出来る——。
▼Vol.3
*
冒頭の文章は「本の売り方」について書かれた書籍から引用したものではなく、ニュージーランド代表ラグビー集団「オールブラックス」について書かれた著『
組織にはなぜ「嫌われ者」が必要か
巨人の上原についてのこんな記事があった。
「時代の流れかもしれませんが『あれ、違うな』というのは感じていました。やっぱりみんな仲良すぎるんじゃないかな。勝っている時は別にいいんだけれど、負けている時に傷のなめ合いをしているような感じがね。このチームには嫌われ役がいないんですよ。はっきり物を言う人がいない。勝っている時は別にいいんだけれど、負けた時にどうするか、というのが強いチーム。負けに慣れると
シリコンバレーのデザインリーダーから学んだ6つのこと
本記事は、Chris Lee氏がMuzliに寄稿した記事『6 Things I Learned Interviewing Design Leaders From the Valley’s Top Companies』を公式に許可をいただき翻訳したものです。
プロダクトデザイナーとして働く上で、私はピープルマネジメントにも関わっている。
ただ、私はこの領域の専門ではない。そこで、世界のトッププレ
就活に、いや採用に透明性を #ES公開中
「対策してくる学生って、何か嫌なんですよねぇ」
2年前、僕が今の会社で営業をしていたときに、商談相手の新卒採用担当の人に言われた言葉を、今でも覚えている。
その時は何を言ってるのか理解できなかった。今は、悲しいかな、理解できるようになった。
その人は、対策する学生が嫌なんじゃなかった、進化することが嫌だったんだ。
今は、そう解釈している。
新卒採用マーケットは、何十年間、ずーっと進化が止