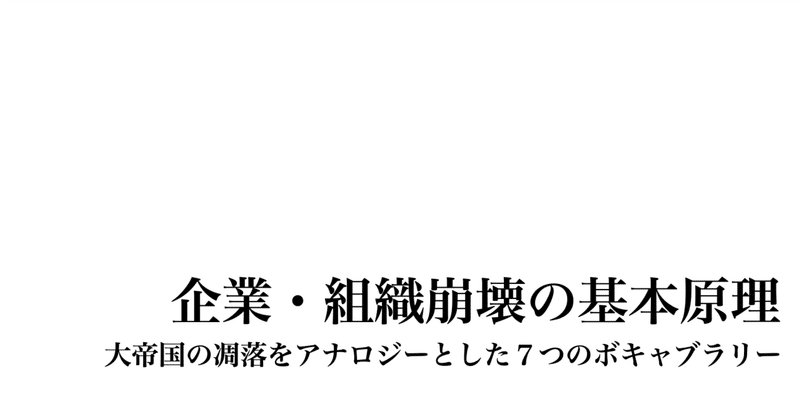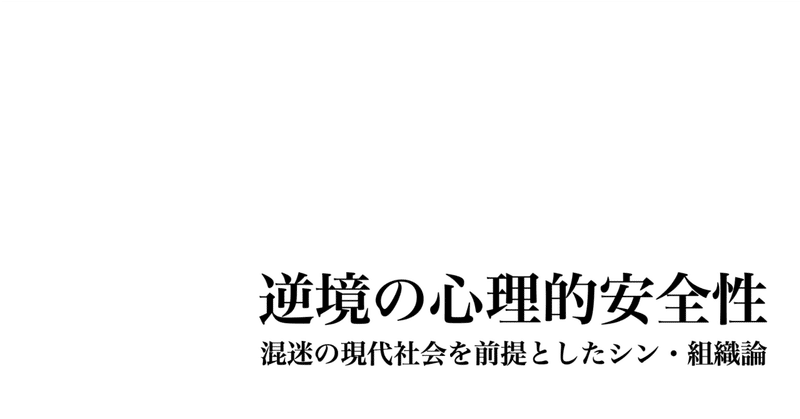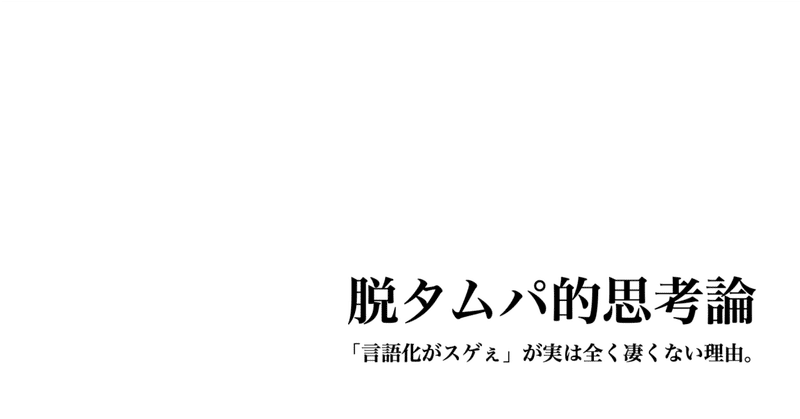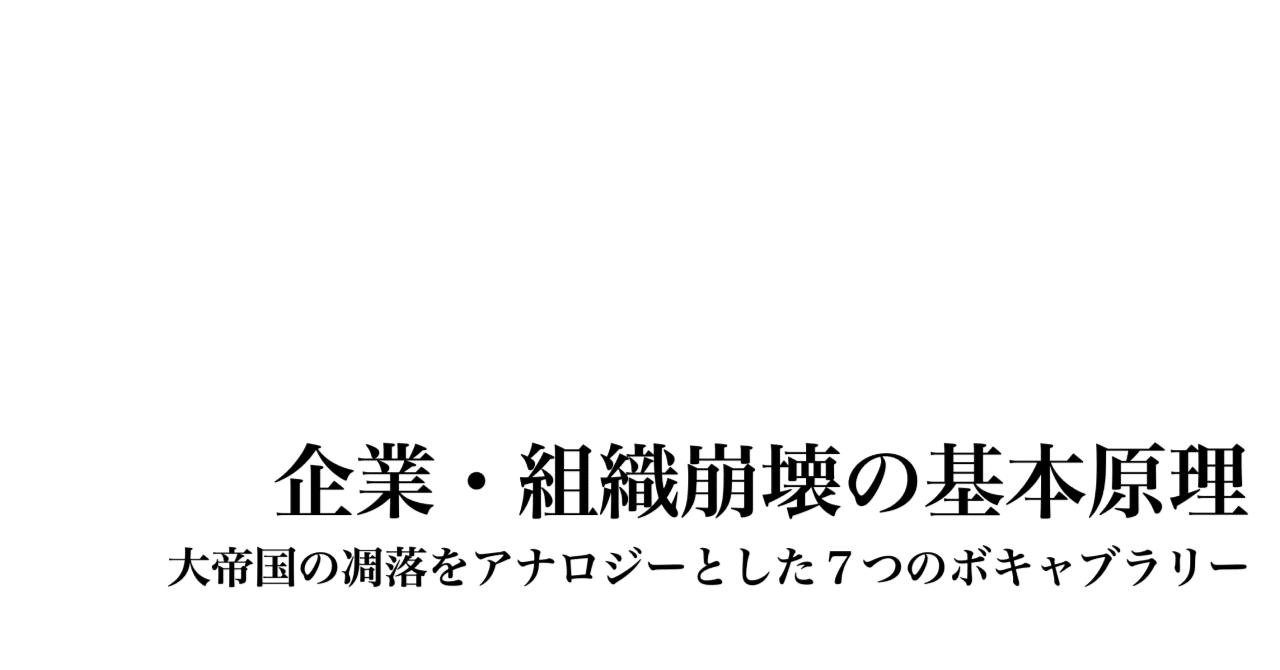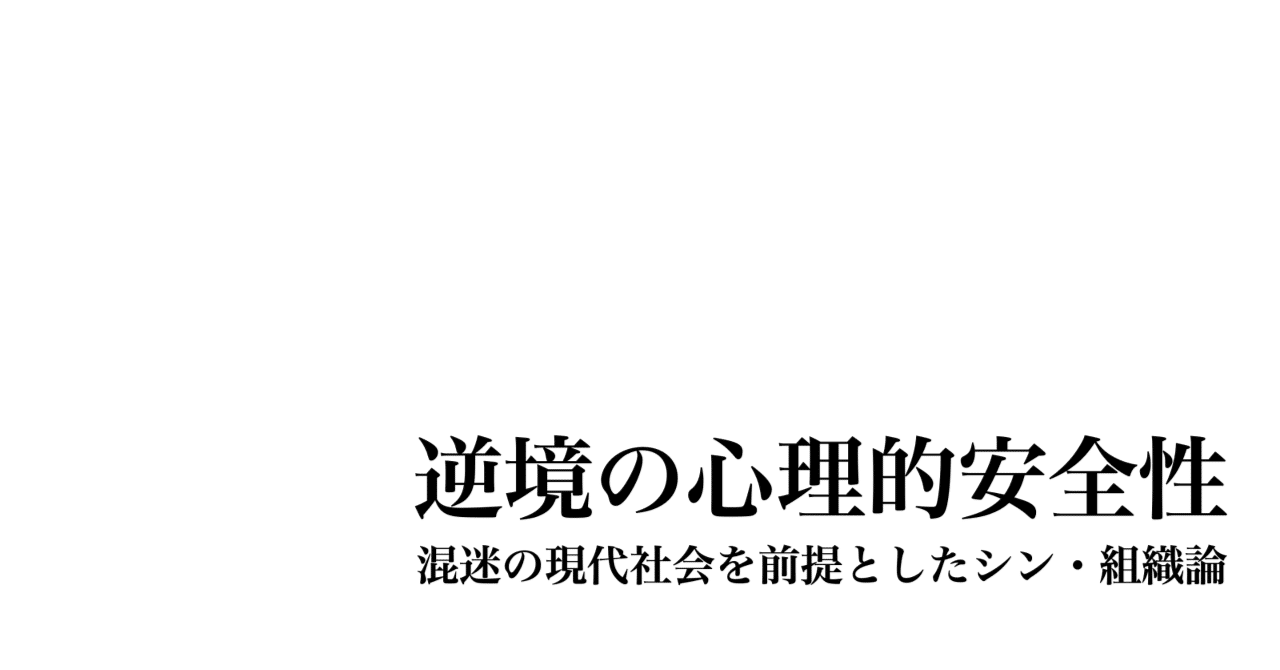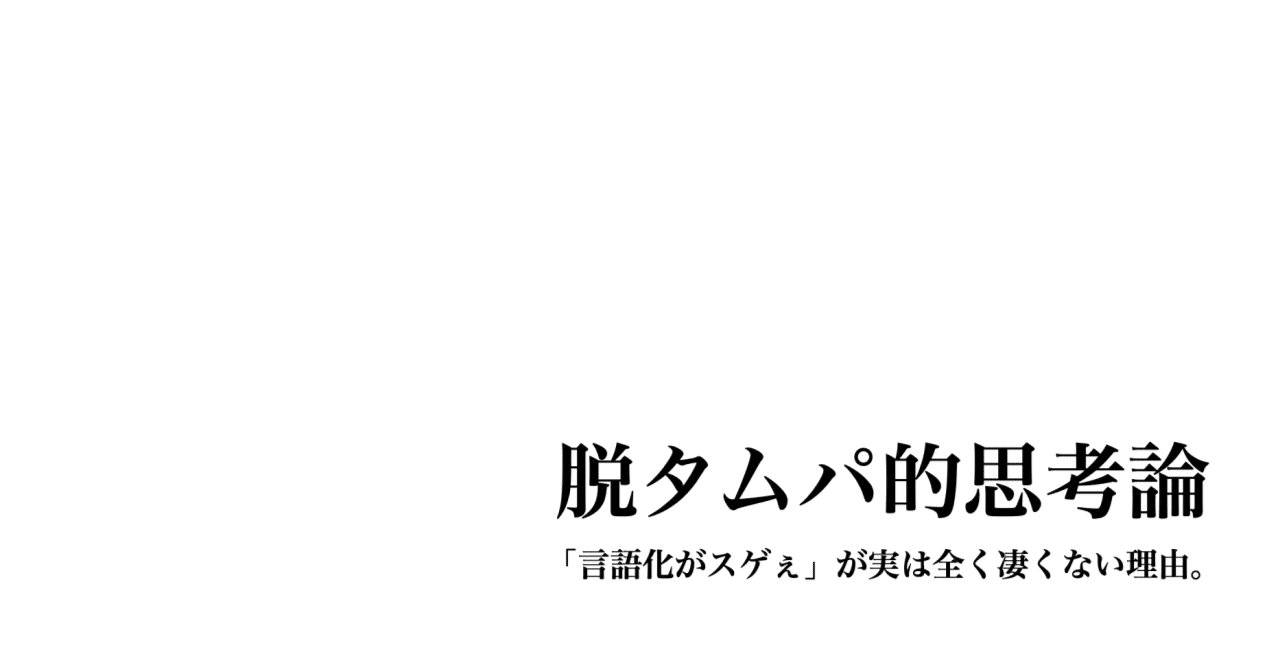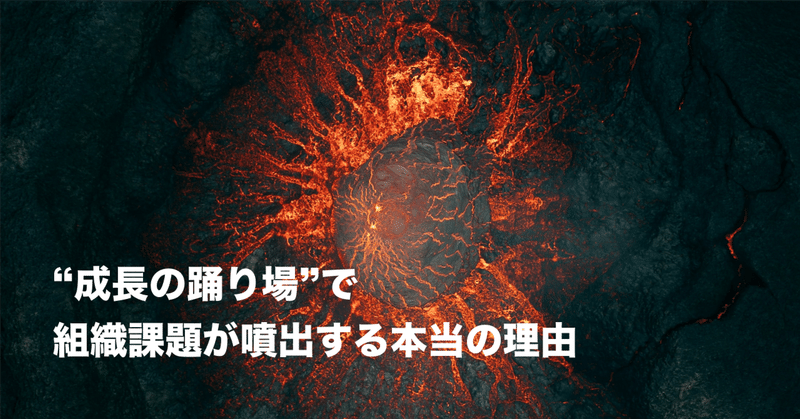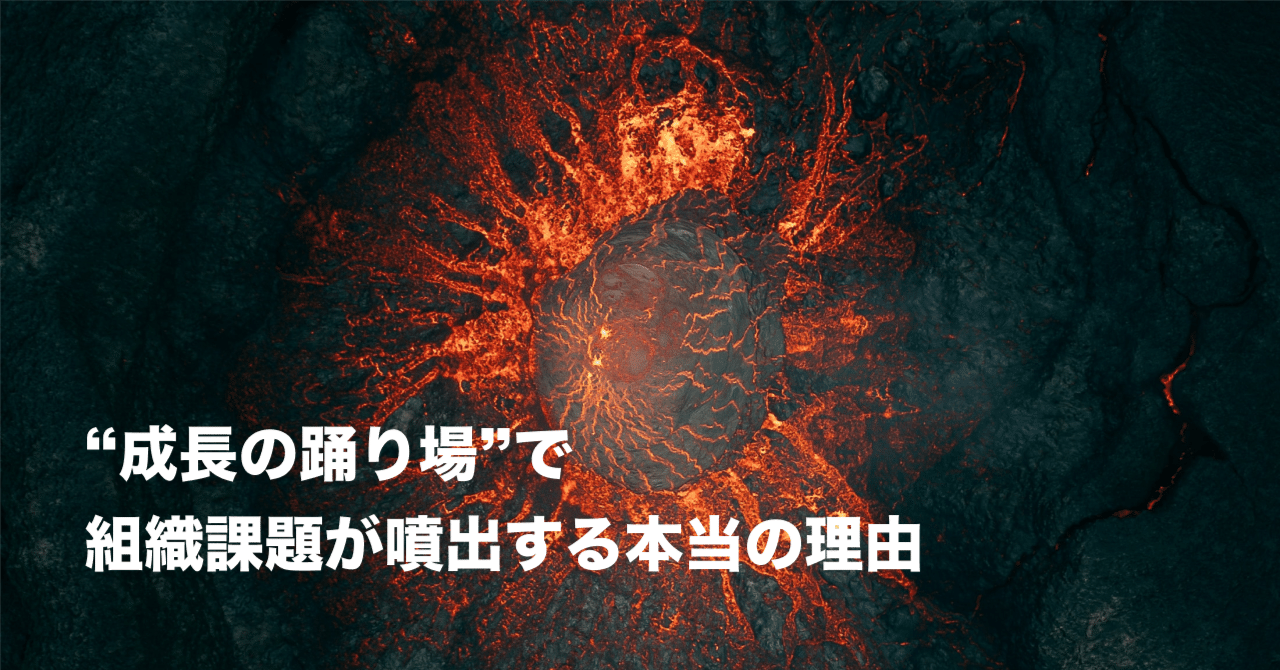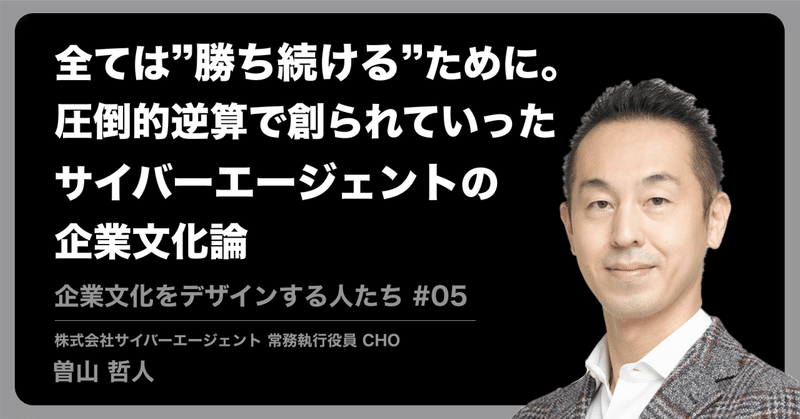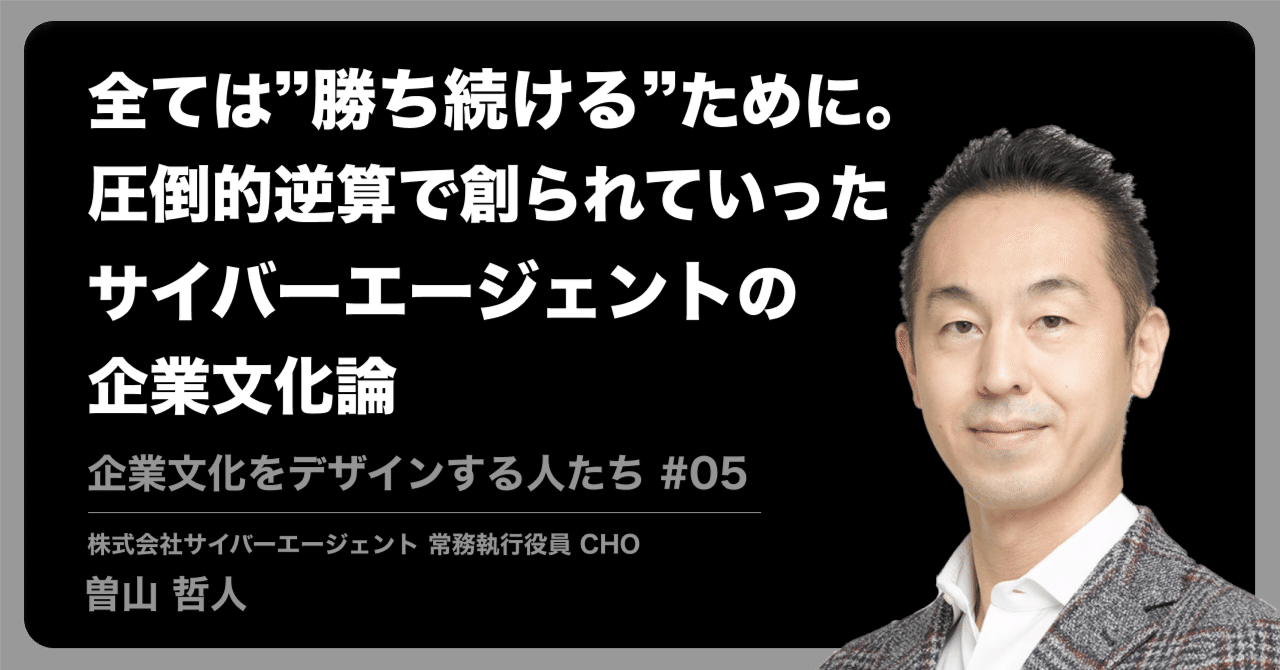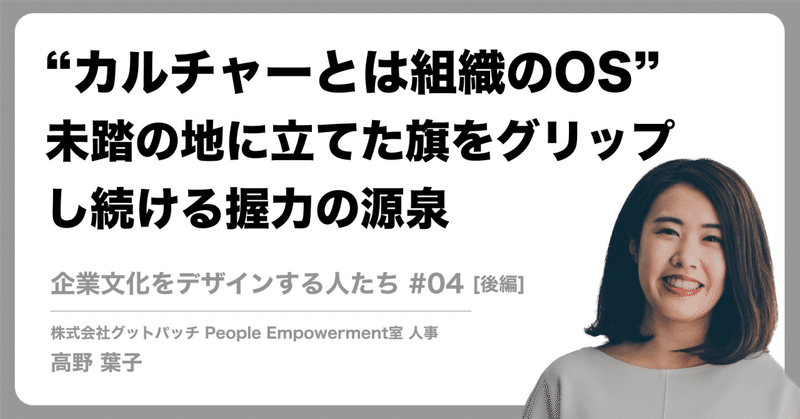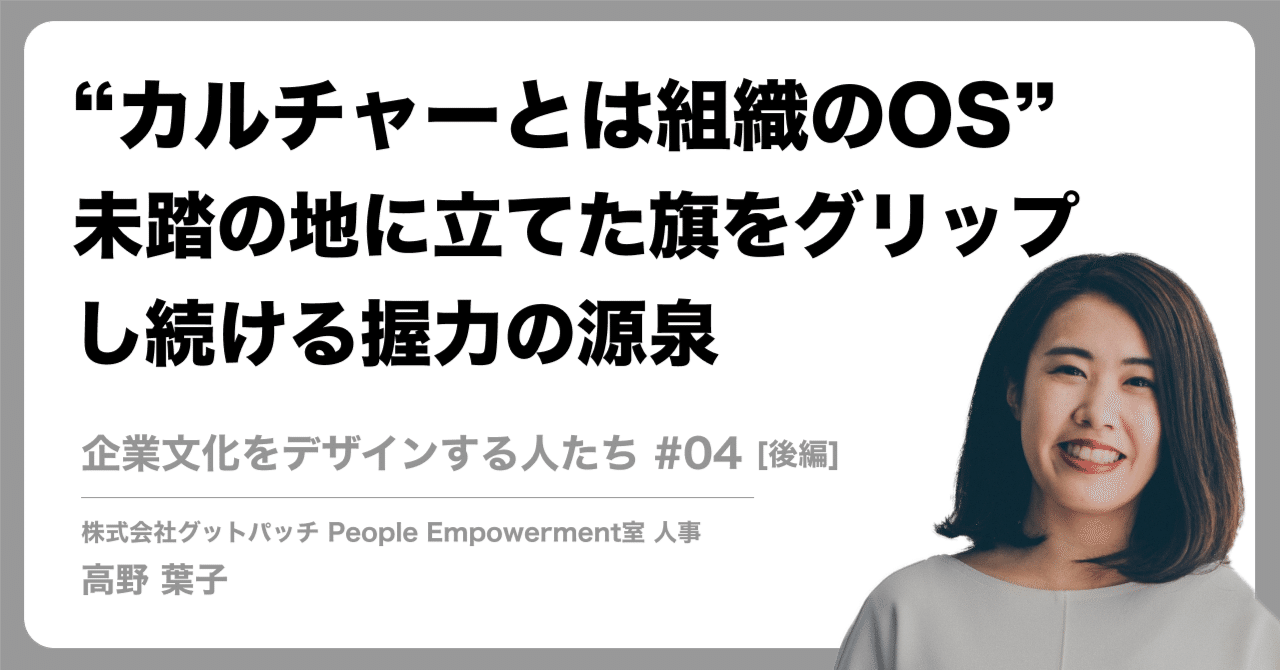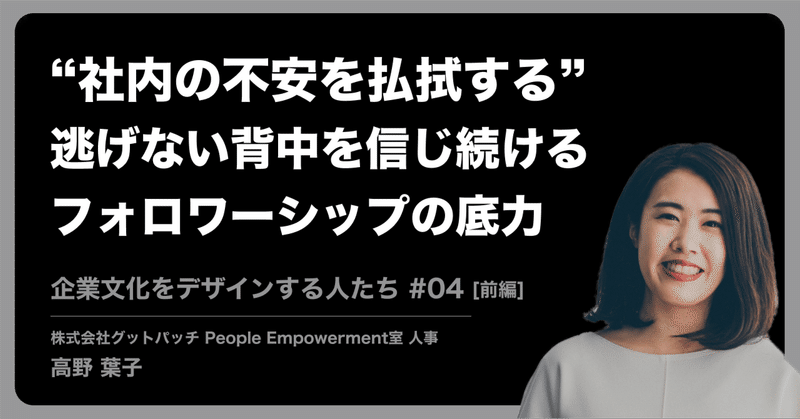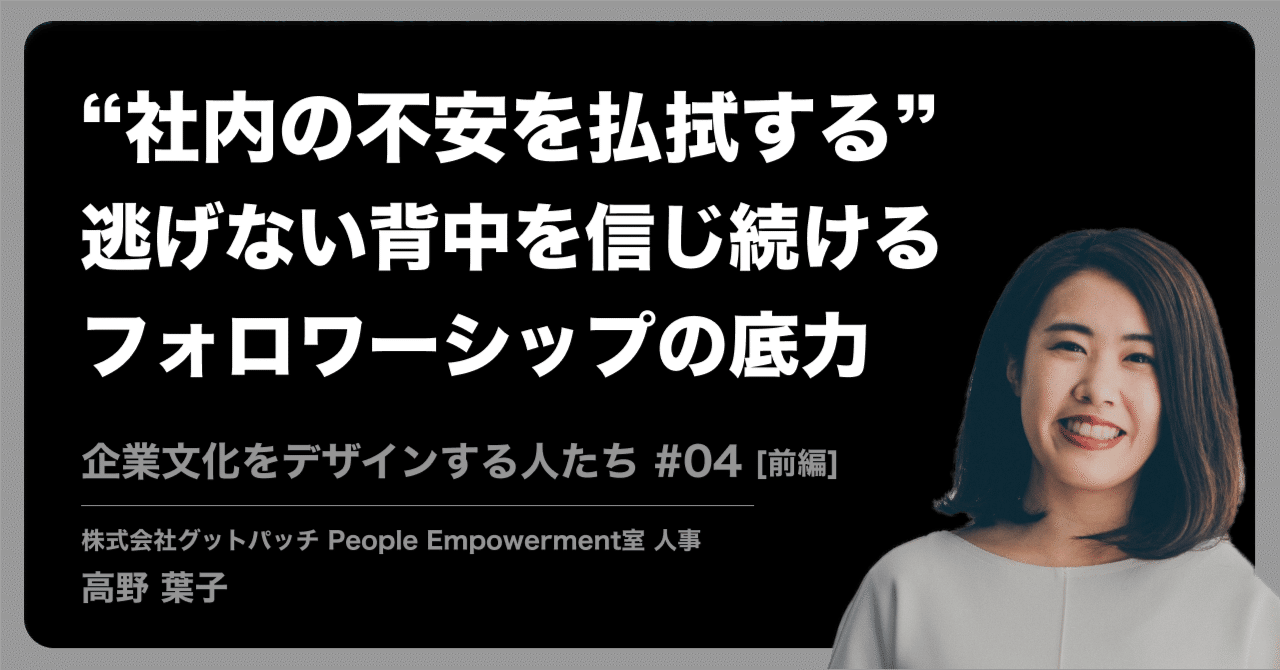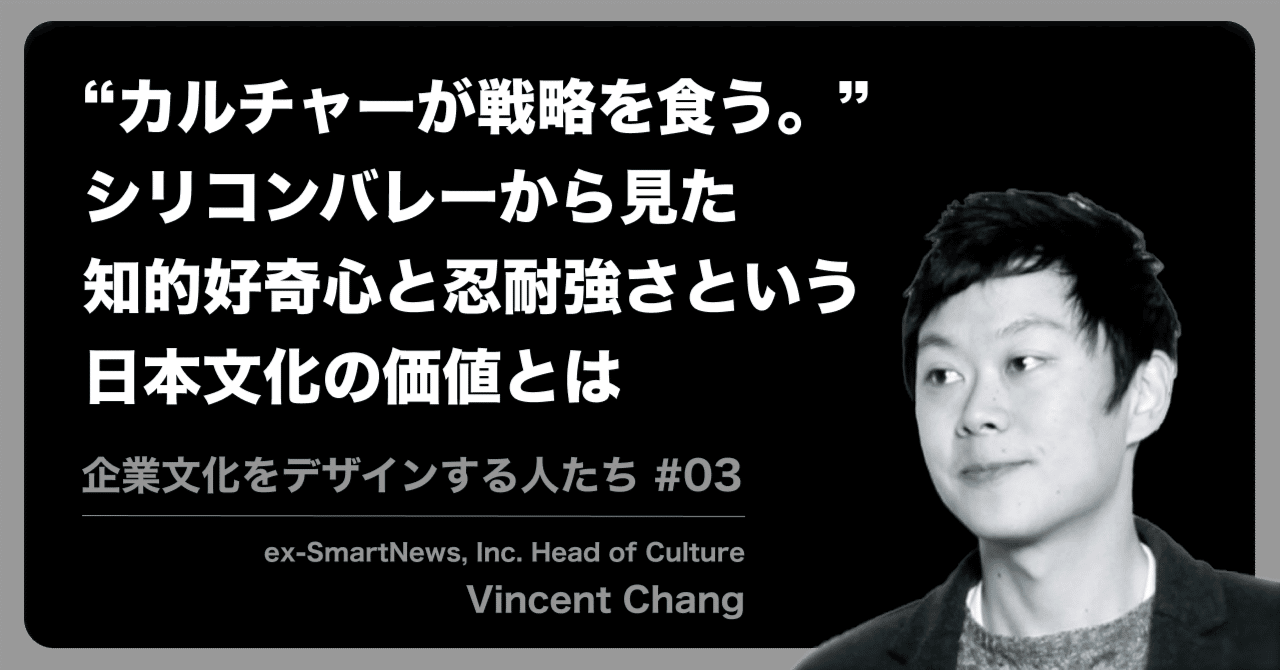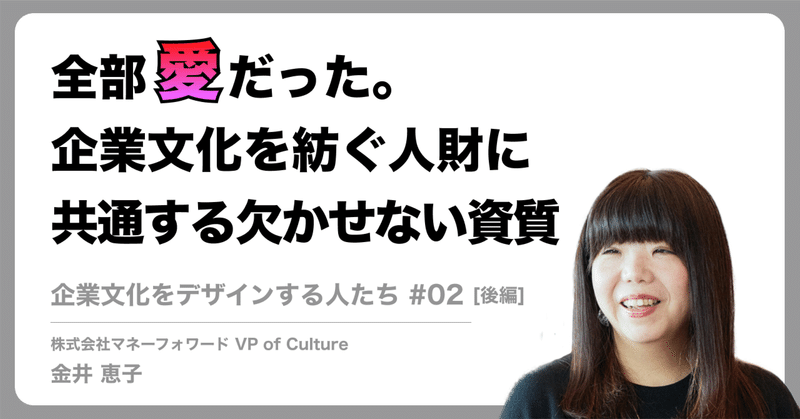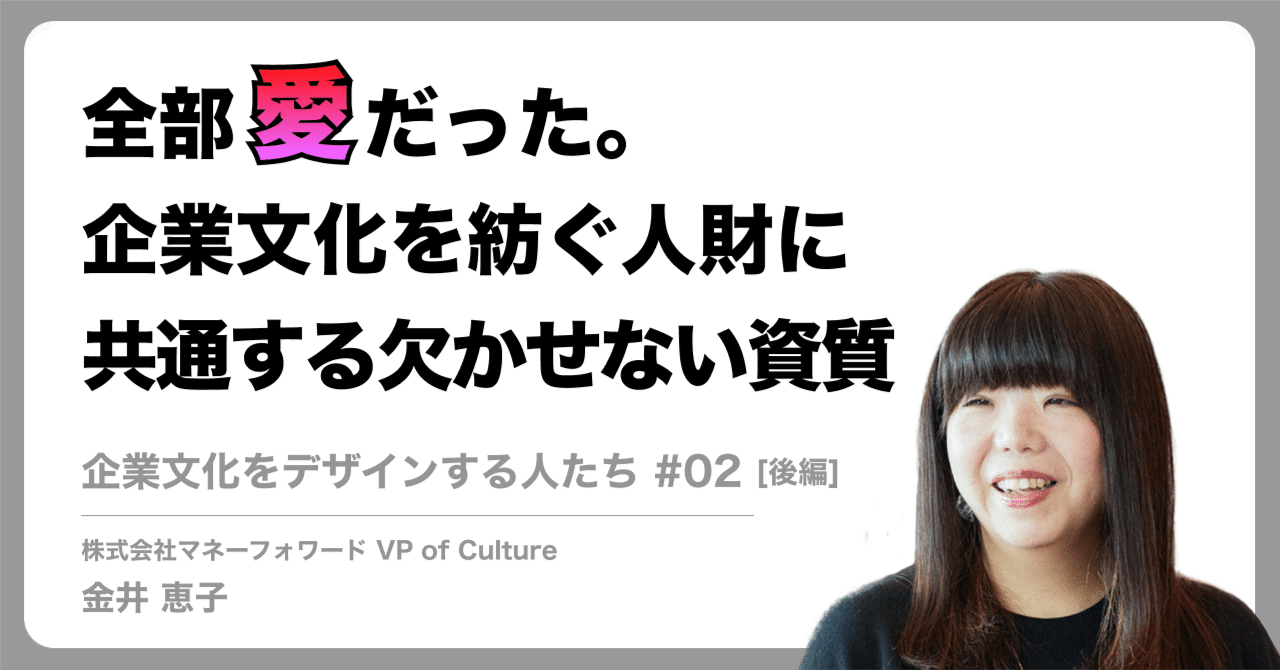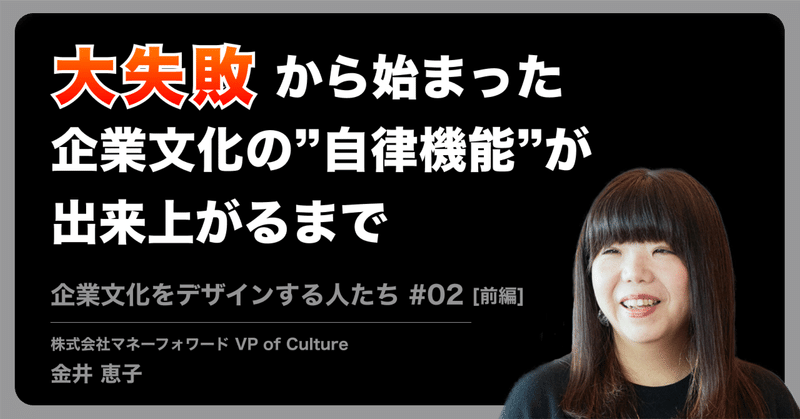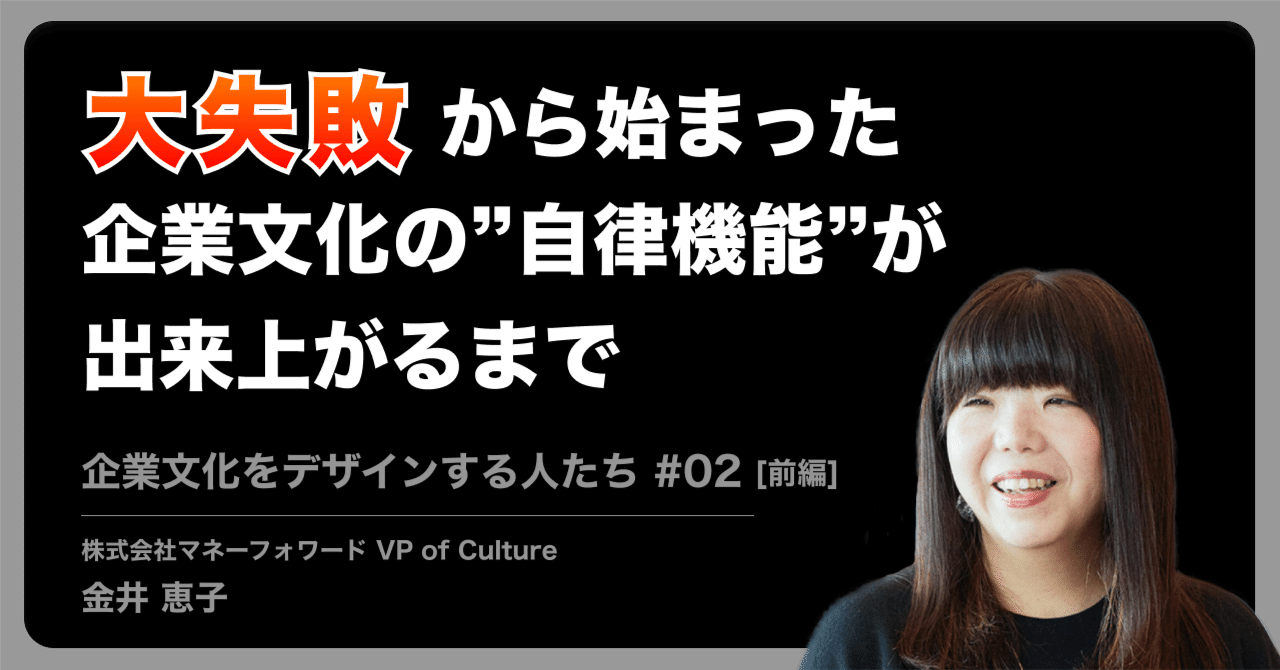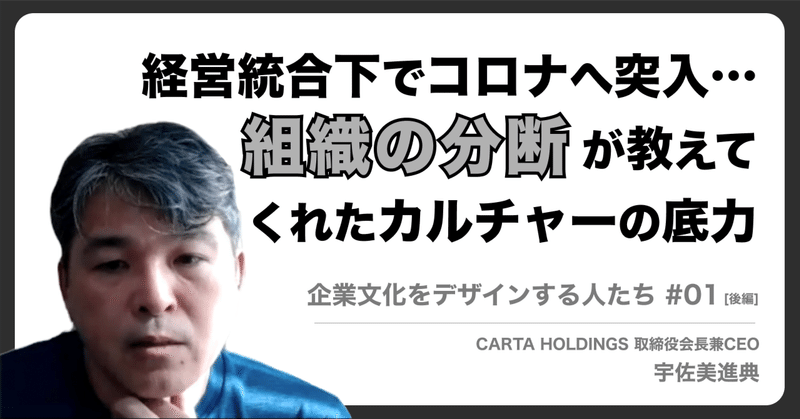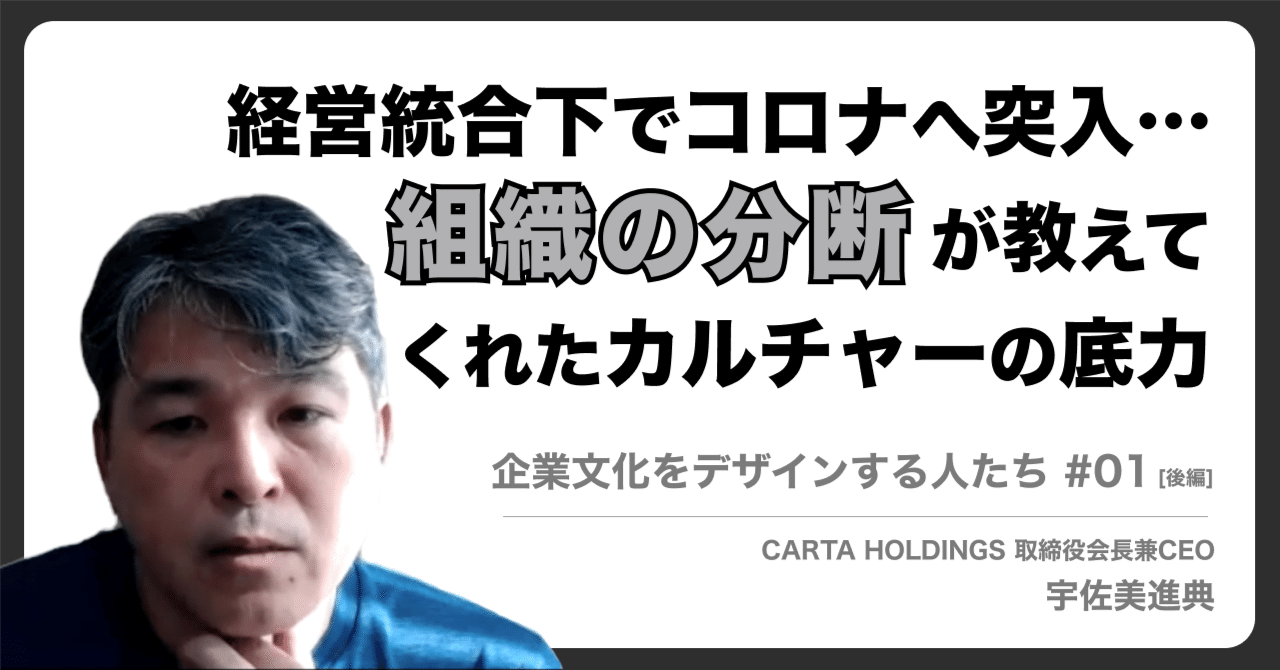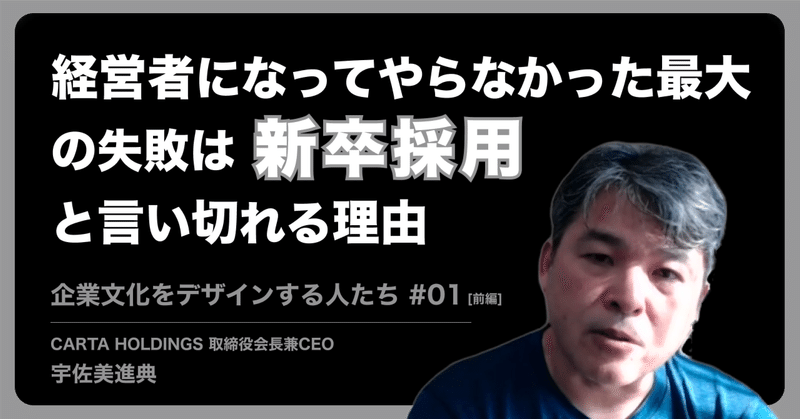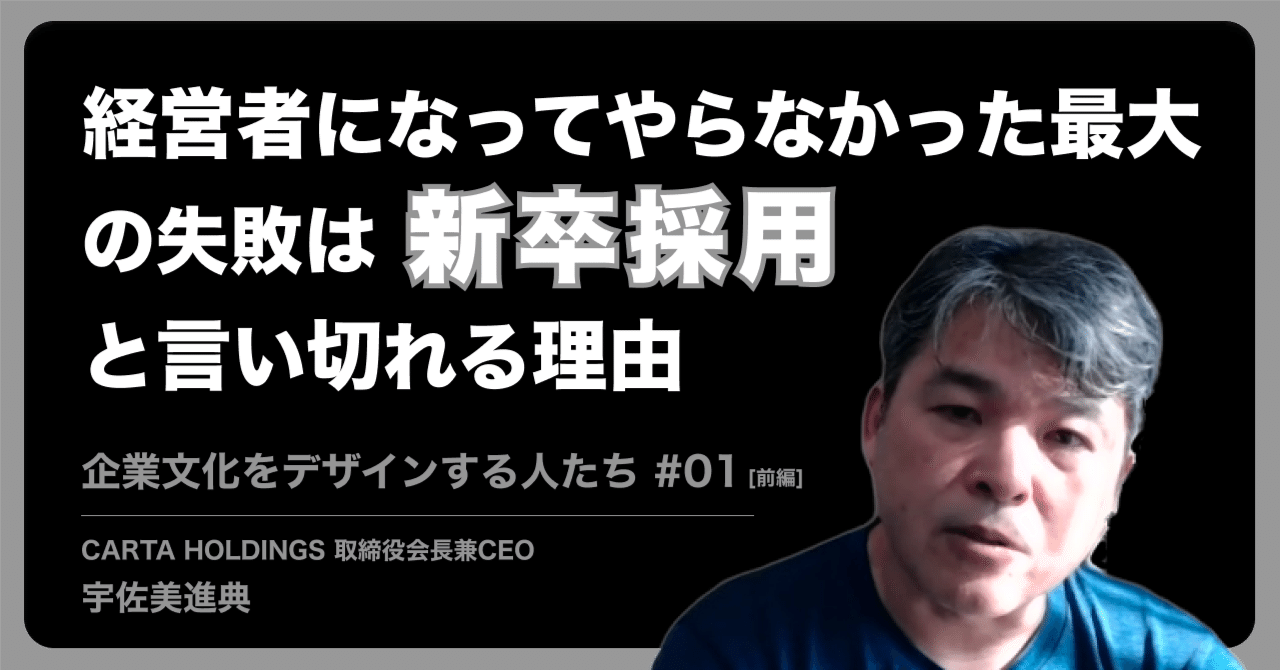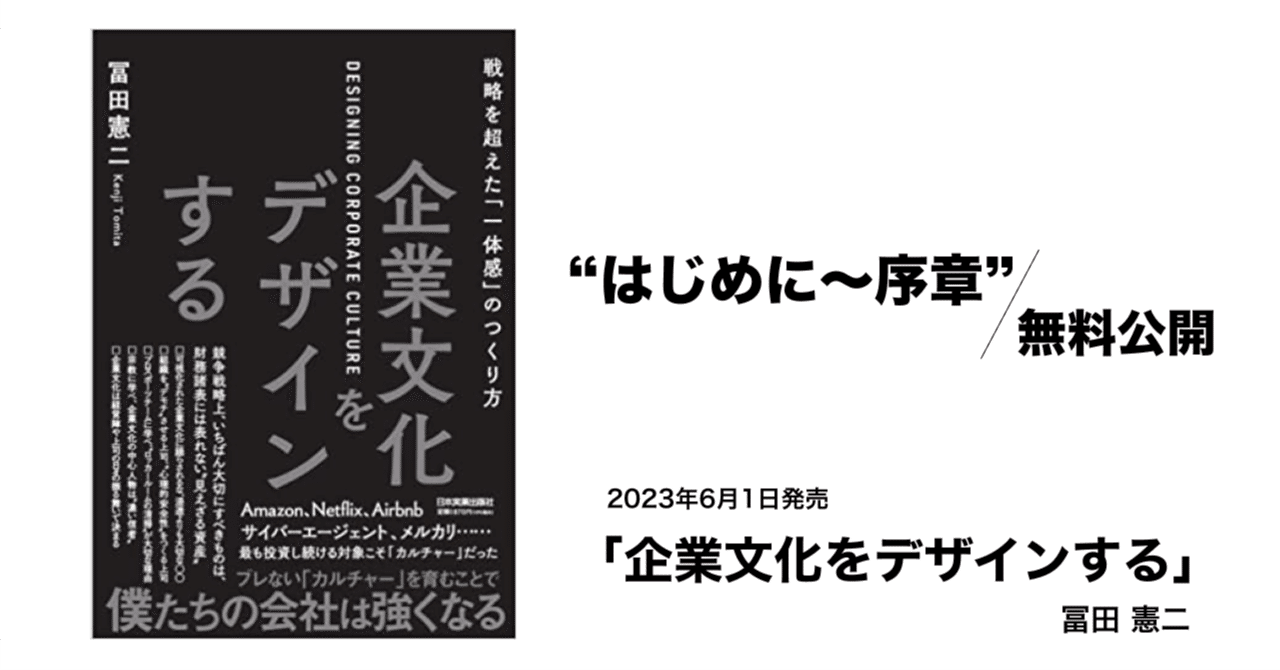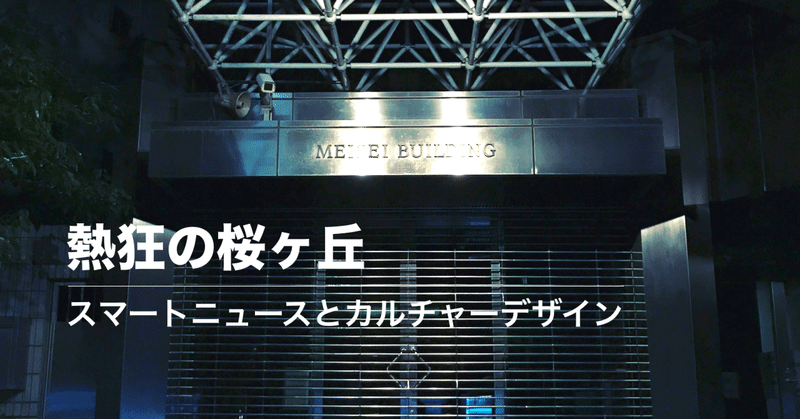Kenji Tomita / 冨田憲二
Runtrip, Inc. 取締役。前職はSmartNews8番目社員-組織200人ま…
最近の記事
- 固定された記事
- 固定された記事
マガジン
記事
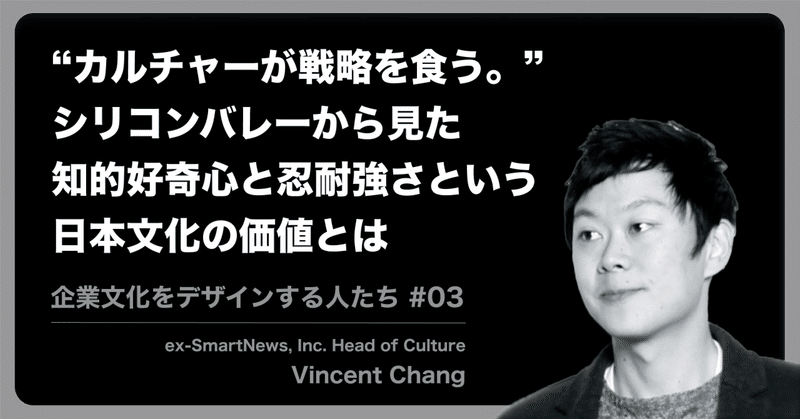
"カルチャーが戦略を食う。"シリコンバレーから見た知的好奇心と忍耐強さという日本文化の価値とは|企業文化をデザインする人たち#03
2023年6月1日に出版される「企業文化をデザインする」を執筆する過程であらためて実感した「企業文化」の底知れぬ奥深さと影響力。 そんな「企業文化」をさらに深め、多くのビジネスリーダーにとって「デザインする価値があるもの」にすべく、「企業文化」と常に向き合ってきたIT業界・スタートアップのトップランナーにインタビューする短期連載企画。 ーー「企業文化をデザインする人たち」 第3弾となる今回は、SmartNews, Inc. US拠点の立ち上げメンバーで、今年まで「Hea