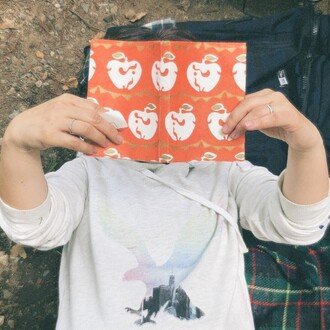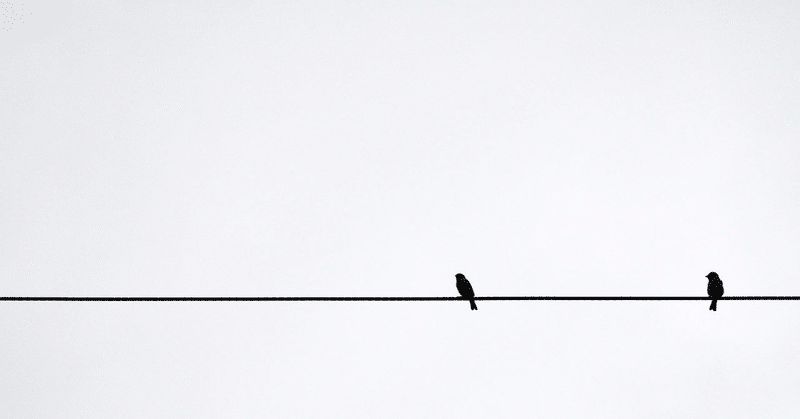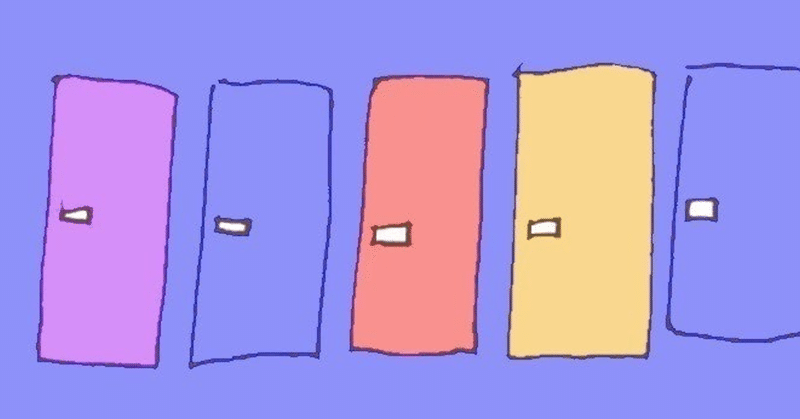#親
「ごんぎつね」を忘れない
子どもの頃、勝手に人のことを決めつけて叱る大人が嫌いだった。そんなつもりない、って子どもの立場では言えない関係性を作っておいて、頭ごなしに叱る。とんでもない話。
しかし大人になってみて、その大人の事情もわかる様になってしまった。大人としての責任を背負い過ぎている時こそ、その状況に陥りがちだ。大人を背負い過ぎている人は、子どもからバカにされないか、なめられないか。いつもドキドキしてる。そして、
家庭というシェアハウス
私は寮母さん
子どもが大きくなったら家族がシェアハウスの住人みたいになったらいいな、って思っていた。家事をする人、勉強する人、仕事する人、みたいな分担ではなく、みんながそれぞれ「生活する人」として生きる場所。
そしてこの空間は、リラックスして話せる人が集う場所。一人でいるにはちょっと淋しい時に気軽にリビングに集まって話せるし、一人になりたい時はなったらいい。
家族とは言え人同士。距離感も大
不登校でお悩みの方へ〜初期対応に関して〜
不登校と呼ばれる子たちについて。おうちの方々の初期対応が遅れてしまう要因として、それまでの間に「不登校は悪い」という概念が植えつけられていることだと思います。そこで「うちの子に限って」や「どうせ一時的なものだろう」と思って軽くあしらってしまう、というケースも多く見られると思います。私自身がそうでした。
私は英語教室を運営していますが、そこでは保護者の方々との語らいを大切にしています。そこ