
燃焼する垂直の言葉/音楽。螺旋形の階梯を、生成する白い光の言葉、あるいは、四方田犬彦「いまだ人生を語らず」
/2023/8/24/19:17/
/書かれてはいけないこと、書いてはいけないこと/燃焼する螺旋形の階梯としての言葉/書物が燃え上がることについて/

書かれてはいけないこと、書いてはいけないことがある。それを書いてしまうとそれが書かれた場所が発火し燃焼してしまうからだ。燃え上がる書物。真夏の正午の時間。書物が、白い光の中、宙を切り裂くように燃焼の炎を旋回させ螺旋形の階梯を生成させながら燃え上がる。書物に書かれた/書かれてしまった言葉の言葉自身が内包する言葉の核を発火点として炎に包まれる。書かれてはいけない、書いてはいけない、燃焼する階梯としての言葉。
自然発火すること、燃焼すること、螺旋形であること、階梯を形作ること、そのことに拠ってして、それは垂直の音楽となる。燃焼する垂直の言葉/音楽
論理にして倫理の誕生。事件として、必然として、宿命として。垂直の音楽とは論理にして倫理であり倫理にして論理である。いかなる意味に於いても、像/イメージになることが禁止される。想像してはいけない。描写してはいけない。記録してはいけない。そんなことをしてしまうと、その者の身体の内部から火が噴き出したちまちの内に人の形をした炎と化してしまうだろう。燃焼する人間。沈黙の中、人形の灰の塊が直立することになる。だから誰一人として垂直の音楽を伝聞することはできない。立ち会う以外、遭遇することができないこと。古い言伝えの破片の中で灰の残滓が漂うことになる

目撃し記憶すること。垂直の音楽を前にして人ができることはそのことだけとなる。耳を澄まし、目を凝らせ。真昼の透明な時間の中、書物が炎に包まれ燃焼する。無数の言葉の核が連鎖的に複層的に分裂と融合を重合させ、光が解放される。白いひかり。向こう側からこちら側へ到来するひかり。時間は反転と正転の最中で宙吊りとなり旋回を開始する。垂直に螺旋形が生成され階梯となり、書かれてはいけない言葉/書いてはいけない言葉が燃焼する。それらのことばたちは燃焼することでしか世界に存在することができないからだ。書かれてはいけない、書いてはいけない、言葉/書物が燃え上がる。

燃焼し旋回する言葉たちを読むためには階梯を昇るしか方法は存在しない。さあ、真夏の昼の時間、地上の光が氾濫する中、燃え上がる書物の中へと進もう。燃焼の白いひかりの内部へ踏み込み、螺旋の階梯を昇ることにしよう

/No.1//四方田犬彦「いまだ人生を語らず」//獰猛にして優しきその知性/肉体と伴に滅びゆく知性の最後を/
わたしの前に四方田犬彦の「いまだ人生を語らず」という本が置かれている。帯には「歳を取ろうとしているわたしは/はたして聡明になったのだろうか。/幸福になったのだろうか」とあり、装丁には四方田犬彦自身が撮影した帽子が並ぶ。七十歳を迎えた四方田犬彦の人生の回顧録、あるいは、老いたる者の幸福と後悔と希望と絶望の記録。まるで人生の指南書のような仕草。


しかし、それが見せ掛けの仮装にすぎないことは明白だ。殊勝な振りをしたところで四方田犬彦は、ルイス・ブニュエルの四方田犬彦であり、ピエル・パオロ・パゾリーニの四方田犬彦なんだ。四方田犬彦は四方田犬彦以外ではない。獰猛にして優しきその知性は衰えてはいない。でも部分部分で少しばかり柔らかくなっていて、わたしは茫漠とした哀しい気持ちの中に一人取り残されてしまった。四方田犬彦が老いる。そして、四方田犬彦はそれを隠さない。信じ難いのだが信じてよいことだとも思う。わたしたちは受け止めなければならない。知性が肉体と伴に有り肉体と伴に滅び行く知性の最後を。
/No.2//咆哮する生者・四方田犬彦の声を/語りえぬものたちを語ろうとしてきたその声を///追悼でも鎮魂でも思い出でもなく、四方田犬彦の言葉について書くこと/

わたしがこの文を書いている理由は、四方田犬彦がいままだ生きているからだ。四方田犬彦が生きているこの現在の時間の中で、彼の叫び声を四方田犬彦以外の者が書くこと、そのことに意味がある。と思うからだ。死によって四方田犬彦が生者・四方田犬彦と異なる存在として変貌する前に、これを書かなければならない。咆哮する生者・四方田犬彦の声を正確に言葉にすること。わたしにできるはずもない。しかし、出来るか否かを問うてはいけない四方田犬彦はいついかなる時も語りえぬものたちを語ろうとしてきた。だからわたしもそれに倣って生きて/吠えて/走る/四方田犬彦の姿を刻み込もう。

わたしが書くそれは誤り多きものかもしれない。しかし、書かないではいられない。わたしは四方田犬彦に多くの大切なものを与えてもらったからだ。かけがえのない幸せな時間がそこには含まれている。追悼でも鎮魂でも思い出でもなく、四方田犬彦の言葉について書く事。言い訳と慰めと感傷と醜い自慢話はこれくらいにして、俊敏に手早くさっとやり遂げることにしよう。

/No.3//四方田犬彦の「いまだ人生を語らず」とは、箴言集、寸鉄、であり、四方田犬彦版・〈旧約聖書〉、あるいは、〈約束の言葉たち〉

目次を見ればこの本がいかなるものなのか判明する。はじまりと途中と後書きこそ、それらしきタイトルがアリバイ作りのように並んでいるが、他の各章のタイトルを読めば、この本の本性は別の処にあることが分かる。「いまだ人生を語らず」の〈いまだ〉に騙されてはいけない。四方田犬彦とは永遠の現在進行形の知性であり、彼が人生を語ることなどこれからもありえない

四方田犬彦の「いまだ人生を語らず」とは、箴言集であり、四方田犬彦版・〈旧約聖書・知恵〉であり、寸鉄である。「寸鉄人を刺す」まさに人を刺す。ことばによって人が刺されることになる。だとすれば、触れれば皮膚が裂け血が滴り落ちることになる塩の結晶の言葉/寸鉄を、したり顔で解説する様ほど醜悪なことはない。愚者のわたしでさえも目を背けてしまう愚行なり
だからわたしにできることは編纂することだけだ。箴言集として。四方田犬彦の「いまだ人生を語らず」を〈約束の言葉たち〉として組み換えること。人生の回顧録として読まれることを、一旦、拒否し破棄し、燃焼し旋回する発光する言葉として再編集すること。吠えろ!走れ!跳べ!四方田犬彦!

/あとがき/03//『ソドムの市』(Salò o le 120 giornate di Sodoma, 「サロ、或いは、ソドムの120日」)ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の映画について

/あとがき/03/が四方田犬彦・箴言集の前に置かれる必要がある。ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『ソドムの市』と善と悪、そして、〈悪霊的なるもの〉についての文。ピエル・パオロ・パゾリーニの四方田犬彦の言葉を読むために必要であり、わたしが何者であり、四方田犬彦の言葉を読む理由についての文。四方田犬彦が四方田犬彦であり、わたしがわたしである理由。
わたしは、時折りピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『ソドムの市』の[Blu-ray]を真夜中の暗闇の静謐の時間の中、一人で、観ることがある。わたしは日々のあれこれとあれこれの日々の、重大でありながらも些細でもある混沌とした希望と絶望の濁流を泳ぎ溺れる。そんな時『ソドムの市』を観る。
飲み込むことができないそれでも飲み込むほかにない、汚穢を飲み干し、体内を満たす汚穢の残虐なる香りに陶酔し狂気の淵を彷徨うように回遊する。誰もいない真夜中の闇、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『ソドムの市』

わたしの中の奥深い秘密の場所に檻が存在している。檻は厳重に施錠され、内部に存在するものは決して檻から出ることはできない。そこに存在している〈悪霊的なるもの〉。絶対的な悪としての〈悪霊的なるもの〉。その場所に存在する悪は、相対ではなく普遍であり、絶対的な悪なんだ。絶対の悪。

善悪が相対的なるものとして、時と場所によって、それらは転倒し入れ替わる。目に見えて耳に聞こえる現実の現象として発生する。だが、その交替は〈悪霊的なるもの〉が詐術を尽して人々に見せる巧妙な仮面劇の一場面でしかない。「あなたの善は他人の悪であり、他人の善はあなたの悪でしかない。善悪は季節の風景のように移ろうものでしかない。昨日の善は今日の悪であり、今日の悪は明日の善として。さあ、わたしといっしょに善人も悪人も皆殺しに!」善悪の黒白が交じり合う灰色の混沌の人間の世界に君臨する〈悪霊的なるもの〉。わたしたちは絶対悪に翻弄され永遠に殺戮を繰り返す

時と場所を超越する普遍的なる絶対として、悪は実存する。人が受け入れることが最も困難な事柄のひとつだ。信じられないほど多くの人々が受け入れを拒否する。灰色で世界が塗り潰され覆われているからといって、世界に光と闇が存在していないわけではない。光と闇はわたしたちの内部に確実に存在している。静かに手を胸に当ててその鼓動を感じ確かめなければならない
わたしがピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『ソドムの市』を観るのは、わたしの内部の檻の中に閉じ込めているはずの〈悪霊的なるもの〉を確認するためなんだ。そして、それに餌を与えてやるためなんだ。凄く凄く危険な。

でも、そうしなければ〈悪霊的なるもの〉は激しく暴れ檻を壊し、わたしの外部に出て行くことになる。それは〈悪霊的なるもの〉が現実へ解き放たれることを意味している。惨劇。現実の中の破壊。わたしはわたしではなくなり、質量と形と色彩を持つ〈悪霊的なるもの〉に変貌して、現実を物理的に論理的に倫理的に破壊する。炎が渦巻き夥しい量の血が氾濫し無数の叫び声の後、わたしは崩壊することになるだろう。〈悪霊的なるもの〉は存在する
だから慎重に檻の中のそれを檻の中で生かすしか術はない。誰であれ。偉大なる者たちの創造が〈悪霊的なるもの〉に向き合う方法をわたしに教えてくれた。ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『ソドムの市』もそのひとつだ。
映画の終わりに狂乱の後の静寂の時間として不可解な空白が訪れる。それは絶対の彼岸のようにして、わたしたちの前に横たわる。ここが今現在だと。

わたしは、わたしの内部の檻の中に、絶対の悪〈悪霊的なるもの〉を宿す者なのだ。
わたしたちの内なるそれの声と姿を確認せよ!

/No.4//人の言葉を編纂する。四方田犬彦版・〈約束の言葉〉、あるいは四方田犬彦箴言集・〈塩の結晶の言葉/寸鉄〉

他者の言葉を編纂することは、自己の言葉を自身が書くことと異なることなのだが、他者の場所に存在するひとつの風景の光と影を自己が切り抜き、自身の白地の場所に自分の手で書き写し、そこにもうひとつの風景が作り出されると、それはまるで、自己の中の他者の言葉、あるいは、他者の中の自己の言葉のように見えてしまうのだ。言葉が他者と自己の間を自由自在に飛び交うものだということ。当然のこととして現れるその当然に驚くほかない。

そして、わたし/わたしたちは知ることになる。言葉は、自分事のためにあるのではなく、他人事のためにあるのでもなく、人の事のために、存在するということ。わたし/わたしたちの言葉とは、自己/他者を超える人間の言葉。だから、耳を澄ませ目を凝らさなければならない。人のことばを聴くために

四方田犬彦版〈約束の言葉〉、あるいは四方田犬彦箴言集〈塩の結晶の言葉/寸鉄〉を編纂する。それは単に四方田犬彦の言葉を編纂するということではなく、人間たちの言葉の編纂ということになる。論理的に倫理的に現実的に
わたしたちがこれから読むことになる言葉は、人が人のために人によって書かれた、人が人であるための、約束、誓いの言葉。それは、終わることのない現在進行形のことばとして、わたしたちの中と外に、今この瞬間ここに。

/No.5//忘却について、あるいは、わたしが、わたしの記憶を忘却すること、幸せと不幸せ
/わたしの記憶と、わたしの内側に存在し、わたしがどうしても、考えることのできない部分/
「わたしとはわたしの記憶だ。はたしてそう断言してしまっていいのだろうか。わたしは考える。だが、わたしの内側にあって、わたしがどうしても考えることのできない部分もまた、強烈にわたしを作り上げているのではないか。わたしはその懸念から自由になることができない。」
/だが忘れてしまうというのは本当に不幸なことなのだろうか。/
「生きるにあたって何よりも重要なのは過去についての記憶であり、わたしとはわたしの記憶だ。多くの人がそう考えている。だが忘れてしまうというのは、本当に不幸なことなのだろうか。記憶が甘美なものであるか、悲惨なものであるかは、ひとまず問わない。忘れることのできない記憶、癒しがたい記憶を携えながらこれからの生を生き続けることが、はたして幸福なのだろうか。だれがそれを受け合ってくれるのだろうか。」

/No.6//記憶について、あるいは、記憶から、歴史へ、歴史は人を幸福にするのか/わたしの眼前にぶら下がっている、解答を得ることない問い/

/記憶について/「見たものは見たものだ。」
「わたしとはわたしの記憶である。ひとたび見てしまったものは、見なかったふりをすることは許されない。「見たものは見たものだ。」これはドラクロアが『ファウスト』の一枚の挿絵につけた表題である。わたしは高校時代から、この言葉に捕らわれてきた。」
/記憶するというのは闘いなのだ。/ すべてを想い出すことが必要なのだ。/
「お前がこれまでの人生で立ち会ってきた残酷な光景は、苦痛に喘いでいる人々との出逢いは、それではどこへ行ってしまうのか。それらを一括りに現世の記憶と呼んで忘却に付すことで、お前は重大なものを喪失してしまうのでないか。」
「記憶するというのは闘いなのだ。わたしに向かってジョスリーンはいった。放っておくと、何もかもが想い出せなくなってしまう。心はすべてを忘れてしまうのではないかという恐怖に囚われ、無気力に陥り、自分が敗北してしまったことすら考えられなくなる。だから全力をもって忘却に抵抗しなければならない。すべてを想い出すことが必要なのだ。」
/抗わなければならない。忘却に対して、全身全霊をもって/
「わたしたちは癒しがたい記憶を前に、懸命に忘れようと努めた。そして一度は忘れたと信じた。しかし忘れるべきではなかった。記憶を保ち続けなければならない。忘却に対し、全身全霊をもって抗わなければならないのだ。」

//怒り、その神聖なるもの、怒り、その正しきもの// /怒りを侮辱し怨恨を擁護する、邪悪なるものたちの憎しみの魔都 踏み潰された、怒りの無数の破片の中、氾濫する憎悪//
「怒りとは神聖なものである。ある不正義が眼前で起きたとき、怒りを抱くことは正しい。怒りを訴え、闘争を呼びかけることはさらに正しい。なぜならば、怒りを無理に鎮静させると、それは容易に怨恨に転じてしまうからだ。」

/抑圧された怒りが、怨恨へ転化する。//遍在する怨恨 / 怨恨を基軸とする現代の中で、怒りが憎悪として回帰する。//
「怨恨は遍在している。見渡すかぎり怨恨を基軸として運行されているのが現代という時代だと、わたしは考える。憤りをいつまでも押さえつけていると、それが屈折して、自分だけがいけないのだという「良心の呵責」に陥ってしまう。だが、それでは問題は解決しない。「良心の呵責」が反転すると、ときに途轍もない憎しみを引き起こしてしまうからだ。憎悪とは抑圧された怒りの回帰したものである。回帰するものはつねに不気味でグロテスクだ。そして周囲をメランコリアに染め上げる。」
/怨恨の虜となることを免れるための、聡明さとしての怒り/ / リア王、透明なる狂気を生き延びるために//
「怒りは愚かなことだと見なされている。だがリア王は愚かだろうか。彼は自分が狂って愚かであることを充分に知っていたし、それゆえにもはや愚行を怖れてはいなかった。リア王は最後まで、その死の瞬間まで聡明であったと、わたしは思いたい。彼は怒りゆえに怨恨の虜となることを免れえたのだ。」

/怒りを滅却しても怨恨の誘惑に打ち勝つ方法、歴史という観念//歴史は人を幸福にするのか、それとも、さらなる苦悶の中へか/
「とはいうものの、怒りは長くは続かない。悲しみが長く続かない以上に、早々と委縮してしまう。怒り続けるためには膨大なエネルギーが必要なのだ。怒りを滅却しても怨恨の誘惑に打ち勝つには、歴史という観念を持たなければならない。とはいうものの、その歴史ははたして人を幸福にするのか。これまで幸福にしたためしがあっただろうか。歴史という観念は逆に人をさらなる苦悶のなかへと陥れてきたのではないだろうか。」
/心臓の右半分はつねに記憶を、心臓の左半分は真逆の忘却を/
「わたしの心臓の右半分はつねに記憶を訴えている。人間は歴史のなかでしか生きることができない。ひとたび歴史が存在すると知ってしまった以上、それに目を閉じながら生きていくことはできない。だから目の当たりにしたことのすべてを記憶として携えつつ生きていくことだと主張する。
心臓の左半分はまったく逆のことをわたしに示唆する。記憶とは後悔と苦痛でしかない。人は忘却を通してしか心の安息に到達することができない。忌まわしい思い出から解放され、浄化された空に向かって飛び立つことが重要なのだ。」
//歴史の存在の意味、それはいまだに解答を得ることなく、 わたしの眼前に、ぶら下がっている。//
「どうすればよいのか。歴史が悪夢の連続だと理解してしまった者は、その歴史に対しどのように処していけばいいのか。この問いは、かつて上海で魯迅を悩ませた問いでもあった。それはいまだに解答を得ることなく、わたしに眼前にぶら下がっている。」

/No.7//読むことについて、あるいは、悪徳、罰せられることなき/

/書物はそれを手に取るたびにまったく異なった相貌を見せる。 読もうとするこちら側がそのたびごとに違った人間になっているからである。/
「これまでいくたびとなく読み返してきた書物とは、もはや書物の域を超えた何ものかである。優れた書物はそれを手に取るたびにまったく異なった相貌を見せる。理由は単純で、読もうとするこちら側が人生のさまざまな局面にあってそのたびごとに違った人間になっているからである。たまたまの偶然からこれまで想像もしていなかった体験を重ねてしまった者は、これまでになかった関心に捕らわれ、以前とは異なった角度から昔馴染みの書物に接近する。書物もまた予期していなかった顔を見せ、まったく未知であった表情で微笑しながら読む者を魅惑する。」

/次々とわたしの記憶を吸収し膨らんでいく書物、その記憶の層を捲りあげていく歓び/
「書物は他人が書いたものではあるが、次々とわたしの記憶を吸収し膨らんでいく。それを繰り返し読むことの歓びは、その記憶の層を捲りあげていくことにあるのではないのか、今のわたしはそう思っている。」
/書物の海を漂流する。/
「わたしは次から次へと書物を相手に漂流を続けている。これまでもそうだったし、これからもそうだろう。」

/No.8//書くことについて、あるいは、救済のために、ただひたすら自分一人の/

/〈わたし〉にとり憑いて離れない問題を、終わりにして、 新しい場所へ、自由の場所へ、と移行するためのエクリチュール/
「わたしは何のために書いているのだろうか。わたしは人に尊敬されないために、また同情されないために書いている。偉大な人物だなどと、間違っても人に誤解されないために書いているのだ。わたしは机に向かうのはただ偏(ひとえ)に、〈わたし〉という問題から解放されたいからに他ならない。自分にとり憑いて離れない問題を終わりにして、新しい場所へ、より自分が自由を感じられる場所へと移行できるようにすること。それがわたしのエクリチュールの目的である。」

/救済としての書くこと/自分「一人がため」に/
「書くことはただひたすら自分の救済のためにある。困難な救済に希望を与えるためにある。」
「ひとたびは宿命のように見えていた問題を丹念に解きほぐし、自分にとって本質的なものと偶発的なものをより分け、後者を取り除いて自分の思念をより浄化されたものに変えること。」
「わたしもまた、自分「一人がため」に書いている。書いたものを通して人を啓蒙教化しようとか、社会を動かしてみせようなどといったことは、微塵も考えていない。短くない文筆生活のなかで、エクリチュールにはそのような権能などないという真理を思い知らされてきたからだ。」

/No.9//音楽について、あるいは、「好むと好まざるにかかわらず、暴力的な陶酔へと誘っていく何ものか」

/バッハとヴィヴァルディ/
/長い間、午前中はバッハを流しながら食事をしたり、小さな雑事を片付けたりしていた。それをヴィヴァルディに切り替えた。/
「長い間、午前中はバッハのCDをずっと流しっぱなしにしながら食事をしたり、小さな雑事を片付けたりしていた。六十歳を超したころからそれをヴィヴァルディに切り替えた。
バッハには人間を超越したところがあり、人間が世界から消滅したとしてもいささかも動くことない無限の諧調が世界には存在しているという心理を指し示しているようなところがある。わたしの死後もバッハは何も変わることなく世界に流れ続けるだろう。
ヴィヴァルディはまったく違う。そのvivaという音の響きからもたやすくわかるように、生きることの悦びそのものだ。わたしは忘れられていた彼のヴァイオリン曲を発掘し、ムッソリーニの前で演奏してみせたオルガ・ラッジの録音を聴いてみたいと思う。もしそれが今でもどこかに残っていればのことであるが。」

/音楽について/事件としての音楽/
「本当の音楽は最初、わたしを驚かす。自分の内側にあることなど予想もしていなかった未知の感情が一瞬にして眼前に実現され、自分を誘い込もうとしていることを、わたしに告げ知らせる。それはわたしを拉致し、わたしを包み込み、そして突然に放り出してしまう。わたしは茫然自失のまま、元の場所に引き戻される。」

/音楽は容易に人を道徳的倒錯へと導いていく。あるいは、彼らが歌うとき、わたしは歌わない。彼らが戯れに笑いあうとき、わたしは笑わない。/
「音楽は容易に人を道徳的倒錯へと導いていく。わたしが想い出すのは、ミラン・クンデラの話だ。」
「音楽はそれに心酔する者、群れだってそれを唱和するもののイデオロギーを、容赦なく体現している。同じひとつの歌を歌い合う者たちは、それだけで信頼できる「同志」である。逆に異なった歌のもとに集う者たちは、互いに敵同士である。その意味でわたしは人とともに、声を合わせて歌うことのできる歌をもってはいない。」
「とはいうものの、わたしは誰かといっしょに声を揃えて、同じひとつの歌を歌うことがない。他の人たちが声を合わせて歌っているとき、わたしは一人、憂鬱な気持ちを抱えて黙っていることだろう。彼らが歌うとき、わたしは歌わない。彼らが戯れに笑いあうとき、わたしは笑わない。もしわたしにとって不条理が存在するとしたら、にもかかわらず、彼らが死ぬようにわたしもまた死に赴くということだろう。」

/音楽を根拠づけている感傷性、あるいは、世界の悲惨の表象に対する純粋な音の結晶体/クセナキス/
「常軌を逸した野蛮を前にしたとき、人は容易に感傷へと流されてしまう。ラジオはひっきりなしにチェコの誇りとするスメタナを流し、感傷を駆使して眼前の破局を手なずけようとしていた。クンデラはプラハに蔓延するセンチメンタリズムの嵐に耐えがたいものを感じ、あらゆる音楽が聴けなくなってしまったという。そのとき彼はたまたま作曲家の名前を知らないままに、クセナキスの音楽を知った。数学のふるい理論を援用し、いっさいの感傷を拒否して成立している音楽に彼は深い悦びを感じた。毎晩のようにクセナキスを聴き続け、一時はそれ以外の音楽を受け付けないまでになったという。
わたしにはこのクンデラの気持ちがよく理解できる。ある種の音楽を根拠づけている感傷性がときとして不潔に感じられ、その粘着的な性格に耐えられなくなるといったことがある。」
「しかし外側から不用意に感傷的な過去の流行歌をもちこむだけで、はたしてそれは事足りるものだろうか。大惨事が起きたときにこそクセナキスを聴くべきではないか。世界の悲惨の表象に対してどこまでも無関心を標榜し、純粋な音の結晶体として存在しようとする彼の作品に耳を傾けるべきではないかというのが、わたしの考えである。」

/No.10//犬について、あるいは、「犬はわたしのダルマにして他者なのだ。」

/今度こそわたしは傍らにいて、犬の最期を看取ることにしよう。予行演習ではない。わたしの死の傍らに誰かがいるという保証は、どこにもないのだから。/
「わたしは考える。蘇鉄丸は死をいかに迎えることだろうか。それがいつになになるかはわからないが、今度こそわたしはその傍らにいて、犬の最期を看取ることにしようと思っている。
おそらくもう犬は何も求めないだろう。ただ、わたしがいっしょにいるだけで、満足していることだろう。わたしはわたしのダルマが消えていくのに立ち会うことになる。犬の終焉を看取ることは、人間のそれへの予行演習であるという人もいるかもしれない。だがわたしには、少し違うような気がしている。わたしが死に赴こうとするとき、傍らに誰かがいるという保証はどこにもないのだから。」

/犬について/「犬はわたしのダルマにして他者なのだ。」
「そう、犬はわたしのダルマにして他者なのだ。/犬はわたしといっしょに走っている。彼はわたしが自分ほどに速く走ることができないと知って、どう思っているのだろうか。ダルマはわたしを導くが、わたしがときおり付いていくことに疲労し、歩みを緩くしたとき、どのような眼差しをわたしに向けるのだろうか。」

/No.11//信仰について、あるいは、赦すことのできない者を、赦すこと、その極限の可能性

祈り、信仰、あるいは、世の中には二種類の人間しか存在しない/
「信仰という行為にとって重要なのは、世の中に信仰を抱いている人間と、信仰に何の関心も抱かない人間の二種類しか存在していないという事実である。ある超越的な対象に向かって祈りを唱える人間と、祈りという行為をそもそも理解できない人間の二種類だといい換えてもいい。とりあえず超越的な存在の呼称はさほど重要ではない。重要なのはその存在を見つめながらまったき自分を帰依するか・しないかの問題である。」

/神聖なる怪物たち/ 信仰と懐疑の両極を見つめてきた者たちの存在/
「だがわたしを魅了してやまないのは、みずからの精神が危機的な場所に赴こうとしていることを自覚しながらも、つねに信仰と懐疑の両極を見つめてきた者たちの存在だ。
小説の中で神がいればすべてが許されると書いたドストエフスキー。神は死んだが、神を殺したのはわれわれだったのだと説いたニーチェ。カトリックの神を深く信仰したのちに棄教し、神などいるわけがないわと痙攣的な笑いをしてみせたジョルジュ・バタイユ。神が不在であるにもかかわらず、その虚無の神を待ち望むのだと宣言したシモーヌ・ヴェイユ。彼らは揺るぎなき信仰に身を置いて、安定した市民生活を送ろうなどとは考えてもいなかった。一歩踏み間違えればたちまち奈落に転落するという場所に身を置きながら、困難な思考を続け、ために精神と肉体が犠牲になろうとも意に帰するところがなかった。わたしはこうした神聖なる怪物たちを遠くに認めながら、大学で宗教学を専攻した。」

/許されざることと許されること/神の存在と不在によって/
「神がいないからすべては許されているのだろうか。それとも神がいるからすべては許されているのだろうか。ドストエフスキーに発するこうした問いを突き付けられたとき、素朴な自称無神論者たちはどのように答えるだろうか。」
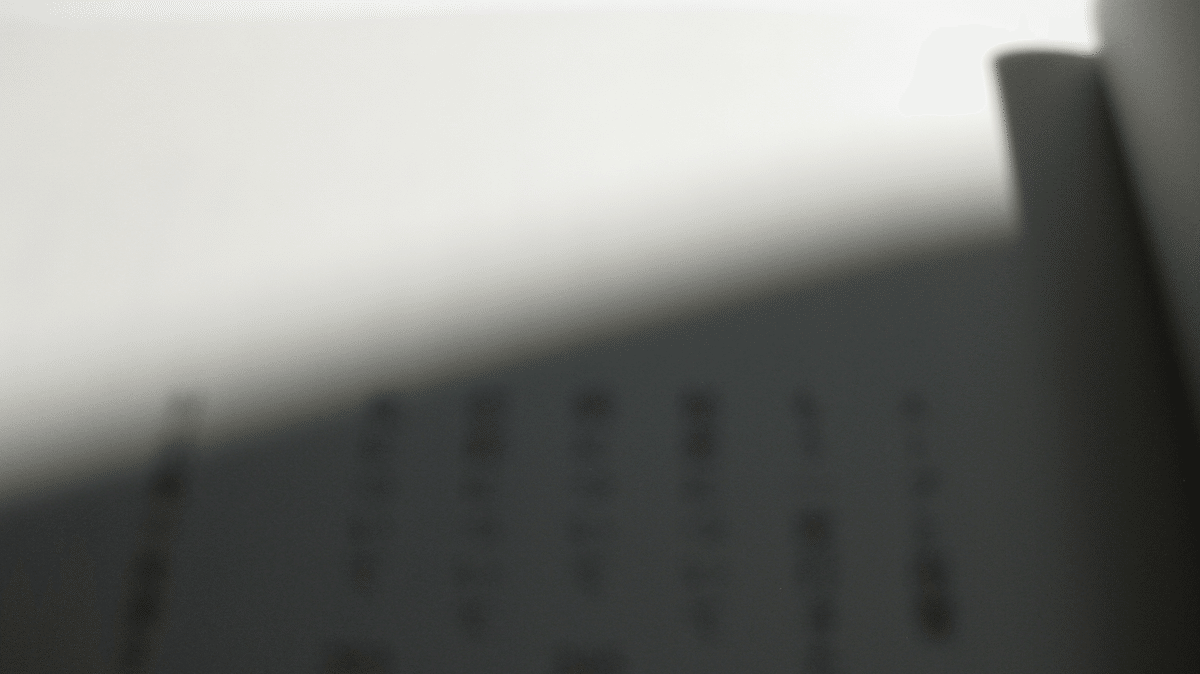
/無神論/キリスト教の影、分身として/
「無神論というのはキリスト教に特有の現象である。少し強い表現になるが、キリスト教の影、分身だといってもいい。それがキリスト教にのみ可能な言説、立場であることを理解するためには、たとえば無仏論というものを想像してみるだけで十分だろう。」
「そう、キリスト教だけが無神論者を生み出し、それに敵対することで護教論を発展させてきた。異端を創り上げ、異端を執拗に批判することを通して、教義をより堅固なものに変えてきた。高度に洗練された無神論とは、実のところ神学の分身に他ならない。」

/仏とは人間によって到達が可能な生の階梯であり、超越的存在ではない。仏教とはすでに高度に洗練された無神論の体系である。/
「無仏論なるものは、歴史的に存在したためしがなかった。仏教という宗教の性格を考えると、原理的にも考えることが不可能である。仏教は、明恵が法然を教義的に批判するように宗派によって対立することはあるかもしれないが、仏の存在を否定することはありえない。というのも仏とは人間(凡夫)によって到達が可能な生の階梯であって、それ自体は超越的存在ではないためである。仏教徒は神のような超越物を必要とせず、西洋風にいうならば、すでに高度に洗練された無神論の体系である。」

/時が到来すれば、神はおのずからわたしの前に顕現するだろう。
/神とは、証明によって存在が示されるものではない。体験されるべき何ものかである。体験が欠落している限り、知性、理性では到達することができない。/
「とはいうものの、神の存在は証明によってなされるものではないことを、すでにわたしは知っている。神とは体験されるべき何ものかであって、その体験が欠落しているかぎり、どのように理性と知性を働かせても到達できないものなのである。
もしわたしが神を必要とするような事態に陥ったとすれば、神はおのずからわたしの前に顕現するだろう。わたしを招き寄せることだろう。必要がないと判断すれば、神はわたしの前に出現しないだろう。」
「聖パウロがコリント人に宛てた手紙のなかにある一節は、長い間わたしの導きの糸であった。その時が到来してわたしが神に出逢うのであれば、それで充分ではないか。何もその存在を否定したり肯定したり、知的遊戯に情熱を注ぐ必要はあるまい。」

/われわれの眼前にある自然が今、このように存在しているということ自体が神である。/スピノザ/
「現在のわたしにとってもっとも寛容になれる立場とはスピノザのそれである。スペインを追放されたユダヤ人の後裔であるこの人物は、われわれの眼前にある自然が今、このように存在しているということ自体が神であると説いた。」

/信仰、人の生の苦痛に意味を与えてくれるそれ、しかし、無際限の欲求/
「麻酔や投薬の役割とは、人が身体に受けた苦痛を軽減することである。だがそれは、苦痛に意味を与えることはできない。自分が現下に苛まれている苦しみが無意味なものであると判明したとき、人は絶望し、より深い苦しみに苛まれる、人間は意味を糧として生きる者であり、無意味には耐えられないからだ。苦痛に意味を与えてくれるものは信仰しかない。
信仰とは、いつかは生きることの意味に到達できるのではないかという期待である。またその意味を求める欲求でもある。だが、それには果てがない。人は歴史から解放されることがあるかもしれないが、内面の信仰には解放がない。信仰とは文字通り、無際限なものである。」

/いかなる自力をもってしても動かしようのない現実/自分の意志と情熱の無力を徹底してわたしに教えるもの/こと/
「わたしの自力礼賛の哲学が少しずつ変化していったのは、五十歳を超えたところである。文化庁の派遣で半年をイスラエル/パレスチナに、もう半年を旧ユーゴスラビアのセルビアとコソボ自治区の大学に滞在し、日本文化を教授するということを行い、戦争の惨禍と敗戦直後の社会の混乱を目の当たりにしたときであった。わたしの眼に次々と入って来る悲惨は、自分の意志と情熱の無力を徹底してわたしに教えるのだった。いかなる自力をもってしても動かしようのない現実が、そこには展がっていた。」
/悪は実在する。自分の外側に存在している脅威として、そして、悪はそれを認識する者の内側にも存在する。//それをどのように解決すればよいのか。/悪の救済としての赦し/
「悪は実在する。それは単に善の欠如privatio boniでもなければ、自分の外側に存在している脅威であるだけでもない。悪はそれを認識する者の内側にも存在する。ではそれをどのように解決すればよいのか。もし赦すことが悪の解消であり、悪の救済であるとすれば、それはどのようになされるべきなのか。わたしを捕らえたのは、それまで一度も真剣に向き合ったことのない問題だった。」

/赦すことのできない者を、人はいかにすれば、赦すことができるのか。赦し乞われたからといって、ただちに赦しを与えることができない事態が転がっている。/
「赦すことのできる程度の悪人は、赦すことができる。だが赦すことのできない者を、人はいかにすれば赦すことができるのか。
謝罪という言葉がある。フランス語ではpardonner,つまり赦しを与えてほしいdonner un pardonという意味である。謝るというのは赦し乞うことなのだ。だが赦しを乞われた側は、乞われたからといってただちに赦しを与えることができるだろうか。謝られたからといって、はい、わかりましたと返事をして、すますことなどできない事態が、世の中にはいくらでも転がっている。」
/赦せない者を赦すことはできない。しかし彼らを赦さないわけには先に進まない。その矛盾について考える枠組みを作り、矛盾する行為を、実践すること。矛盾の向こう側の極限の行為の可能性/
「赦すことのできない者を赦すというのは、言葉の矛盾である。だがこの矛盾を重々承知の上で赦しを与えなければならない状況というものが、確かに存在している。」
「親鸞は回り道に回り道を重ね、恐ろしく長い物語の末に結論を語る。どうしても赦すことのできない悪行の者が存在する。だがその者たちにしても浄土に向かうことができるのだ。絶対に赦されない者すら、赦されるということがありうるのだ。
難解な漢文を読み下した『教行信証』を読み進み、ついにこの一節まで読み進んだとき、わたしはパレスチナとコソボで垣間見た残虐と悲惨について考える枠組みに、ようやく到達できたような気がした。赦せない者を赦すことはできない。しかし彼らを赦さないわけには先に進まないとすれば、どのようにその矛盾する行為を実践することができるのか。」

/絶対に赦すことのできないものが、世界には存在しているのだ。
「あるときわたしは金石範(キム・ソクボン)に訊ねたことがあった。赦せない者を赦すことはできますか。済州島の惨事を小説で描くことに人生のほとんどすべてを費やした作家はただちに答えた。赦すことはできない。絶対に赦すことのできないものが、この世界には存在しているのだと。」
/信仰からはるか遠いところに留まっている者は、赦すことからも赦されることからも、放逐されたままなのだろうか。/
「わたしは失語に見舞われる。赦すことができるためには何かしらの信仰に帰依しなければならない。それでは信仰からはるか遠いところに留まっている者は、赦すことからも赦されることからも放逐されたままなのだろうか。」

/No.12//死について、あるいは、未来から、止めどもなく流れ到来する時間の外側へ/ 巡りゆく季節の円環の時間の中で/

/わたしとは時間の内側に生起する現象であり、わたしは死んだときには、時間の外側へと行く。/
「物質が存在していないところに時間はない。物質が運動を開始したとき、はじめて時間が発生する。宇宙が開闢する以前には物質はなく、時間はなかった。いや、もとい、「以前」ということすらなかった。」
「わたしとは時間の内側に生起する現象である。だとするならば、死を定義することはさほど困難ではない。わたしが生まれる以前には時間の外側にいたとすれば、わたしは死んだときには時間の外側に飛び出してしまうだろう。要するに、本来いた場所に戻っていくだけのことではないか。時間の外側とは何か。それは物質の存在しない空間であり、空間さえも存在しない場所である。簡単にいえば無だ。」

/時間は未来から到来するものである。// 時間はまだ存在もしていない未来から止めどもなく流れて来て、一瞬、現在という状態に達し、次の瞬間に消滅してしまう。/
「時間は過去から未来へと進んでいくわけではない。未来から到来するものである。時間はまだ存在もしていない未来から止めどなく流れてきて、一瞬ではあるが「現在」という状態に達したかと思うと、次の瞬間に消滅してしまう。過去という、もはや存在しないものに属してしまうのである。われわれは結局のところ、現在という須臾(しゅゆ)の時間しか認識することができない。」
「ただ、ここで気に留めておかなければならないのは、時間には繰り返しがないという事実である。ひとたび過去となってしまった時間は、もう二度と回帰してくるわけではない。時間の進行は線的である。未来が現在になり、それが過去へと押し流されていく。わたしとはその奔流のなかで狼狽している小さな魚にすぎない。わたしは時間のなかに生れ落ち、時間のなかで揉みくちゃにされながら、時間を飛び出して死の領域に到達することになるだろう。」

/死から逃れることはできない。だが、死が携えてきた物語を切り替えることはできる。/巡り反復する季節の円環の時間の中で、/
「どの花々も季節に応じて蕾を膨らませ、花を咲かせると、種子を残して枯れていく。とはいうものの、翌年も、さらにその次の翌年も、同じように蕾を膨らませ、花を咲かせては枯れていく。庭仕事をするとは、こうした植物の持っている時間のリズムを読み取り、それに従って生きることであり、線上に進行する時間とは別の秩序にある時間に触れることだ。」
「繰り返しいうことになるが、死から逃れることはできない。だが、死が携えてきた物語を切り替えることはできる。人生には初めと終わりがあり、その間はただ一直線に時間が進行していくばかりであるという思い込みから一歩退き、時間の本質は反復にあるという認識へと進むことだ。土を掘り返して球根を一個ずつ植えこんでいくわたしは、そのたびごとに植物が本来的に携えている再生の力を分有することだろう。枯れて死滅することが生まれ変わることであるという教えを、チューリップやクロッカスから学ぶことだろう。わたしが想い出すのは、ヴォルテールが『カンディード』の最後に書きつけた言葉、「汝の庭を耕せ」である。」
/矛盾に満ちている生が、死という雷の一撃によって、その意味が統合され理解可能なものとなるというわけではない。/
「なるほど生は矛盾に満ちているかもしれないが、かといって死という雷の一撃によってその意味が統合され、理解可能なものとなるというわけではないのだ。生はただいつまでも繰り返しの途上にあり、始めも目的も定かでないまま、あるとき偶発的に終わりを告げる。それは時間という秩序からの脱落に他ならないのだが、はたしてその脱落を悦びをもって受け容れることができるかどうかが、これからのわたしの主題だろう。
薔薇を剪り棘をののしる誕生日 三鬼」

/あとがき/00//少しばかりの、あとがきを/ 自分「一人がため」の、救済として/

四方田犬彦の言葉たちはここまでとする。あらためていうまでもないことだが、編纂された四方田犬彦の言葉たちが描写する風景のかたちと色彩は、わたしにも部分的に理由がある。引用され再構成され短い文が挿入されたそれは、四方田犬彦の「いまだ人生を語らず」とは似ていないのかもしれない。しかし、これは〈四方田犬彦の言葉について書くこと〉のわたしの応答だ。
それでも、少しばかり、あとがきを書きたいと思う。 自分「一人がため」の、救済として、書く。

/あとがき/01//燃焼する言葉について// 別の仕方で//垂直的なるものたちについて/

それがそこに出現する。顔を真上へ上げ覆い尽くすものたちの彼方へ視線を向ける。しかし、昇ろうとした途端に頭部は一瞬身震いし硬直し石化する。静止後、頭部は力なく弱々しく崩壊し身体の上部から流体となり、四方へと流れ落ち平面の地面を濡らす。それでもそこかしこに現れる上へ向かう者たち。地平線の向こう側へでもなく水平線の向こう側でもなく、この場所のこの地点からの飛翔を企てる者たち。なぜ、彼ら彼女ら、あるいは、彼ら彼女らではない者たちがそうするのか? 理由は平面の果てを示すそれらが無限に後退することを知っているからだ。地平線/水平線の向こう側に存在するのは、遠くに地平線/水平線を見渡す見通しの良い場所でしかない。世界の外部へ向かう者たちが、視線を水平ではなく垂直へ向けることは当然の事なのだ

だが、すべてが垂直的なるものとして存在できるわけではない。前後左右を埋め尽くす垂直的ならざるものたちの無惨な残骸たち。わたしたちが日々を暮らす都市は、崩れ落ちた垂直的ならざるものたちの破片で象られている。

人の生、つまり人生とは、水平の言葉の海を航海することであり、「人生を語る」とは航海日記を朗読することを意味することになる。そこには垂直の言葉は存在しない。なぜなら垂直の言葉とは世界の外部に存在する言葉であり、世界の外部で遭遇する言葉であり、世界の外部から飛来する言葉だからだ。航海の中で、時折り、何かしらの誤りとして、あるいは、偶発的な事件として、水平の海に垂直的なるものが落下/上昇してしまうことがある。波立ち小さな混沌が生まれるが、海面を揺り動かすことはない。再び、海は凪ぐ

世界の外部に存在する言葉を求めて、孤独の中、異形の者たちだけが(その者たちを〈知性を持つ者たち〉と言い換えてもいい。)〈知性を持つ者たち〉を異形の者と呼ばざるを得ない、現在の時間の中で、燃焼する垂直の言葉/音楽を読み書き聴き演奏するために、神聖なる怪物として世界を切り裂いた、偉大なる創造者たちの後を追い、白いひかりの螺旋の階梯を昇って行く

あとがき/02/長編小説『すべての鳥を放つ』、あるいは,「抵抗と反撃としてのレクイエム」
長編小説の形式の言葉で語られる四方田犬彦の言葉たち。だがこれは映画でもあり漫画でもあり歌でもある。
「抵抗と反撃として、/それは死者たちに向けた花束であり、生き残った者たちへの警告ではないか/そして、レクイエム」

語りえぬものを語ろうとする、全ての異形の者たちのために、そして、神聖なる怪物へ〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
