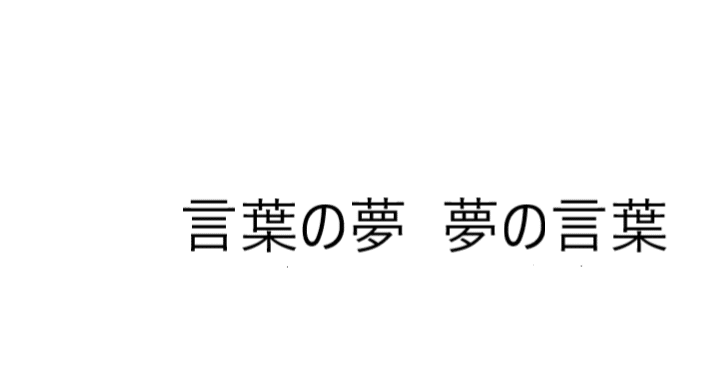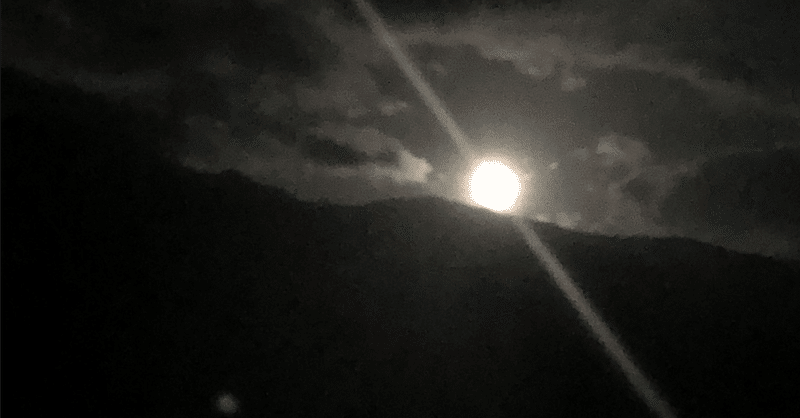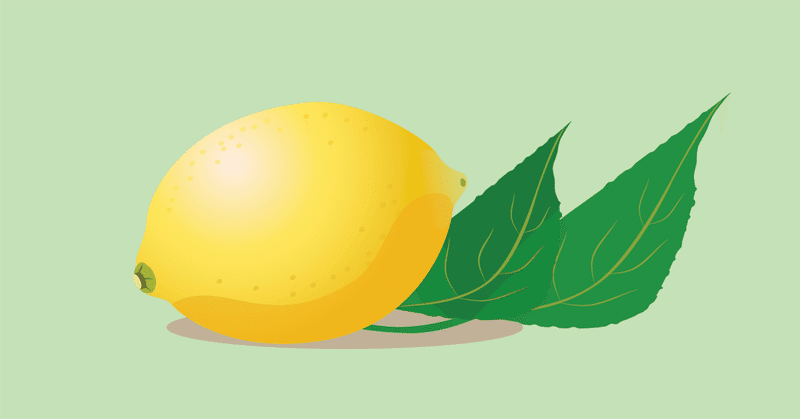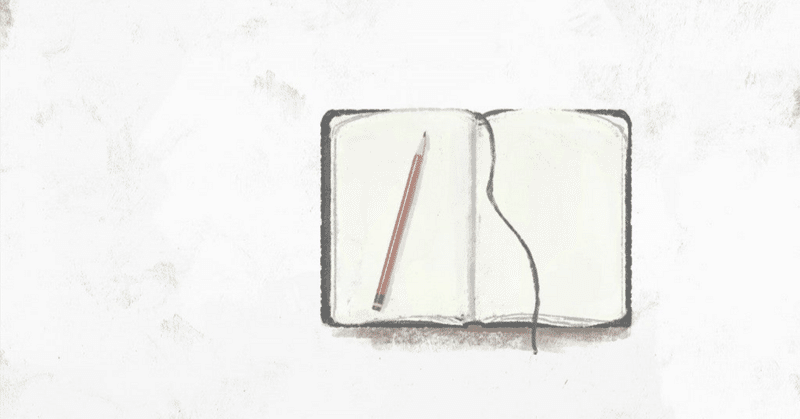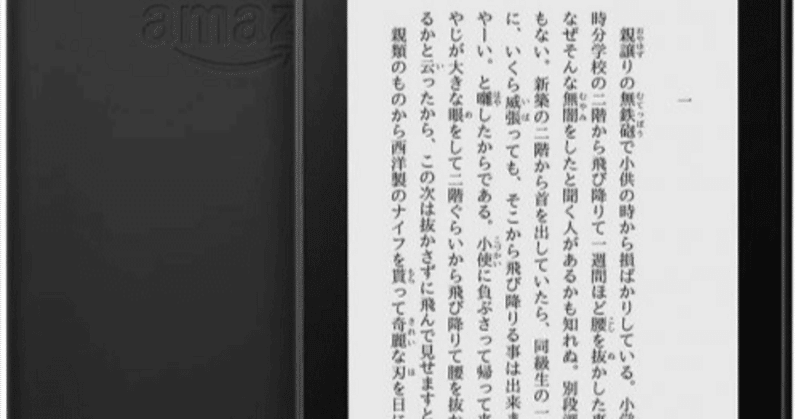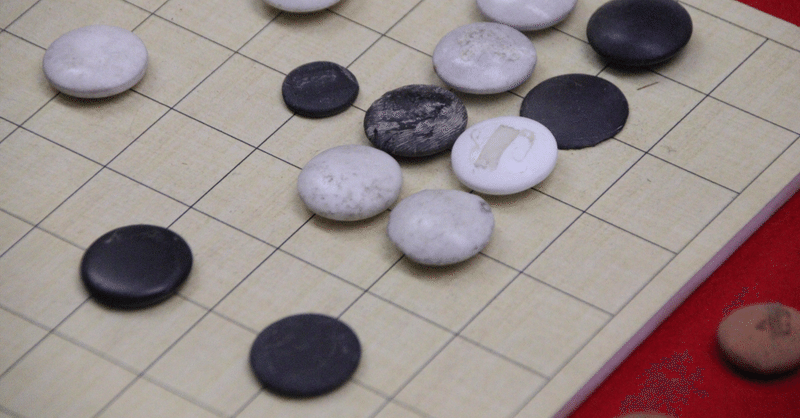#漢字
山の記憶、「山」の記憶
今回は、川端康成の『山の音』の読書感想文です。この作品については「ひとりで聞く音」でも書いたことがあります。
◆山と「山」
山は山ではないのに山としてまかり通っている。
山は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通っている。
体感しやすいように書き換えると以下のようになります。
「山」は山ではないのに山としてまかり通っている。
「山」は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通って
音の名前、文字の名前、捨てられた名前たち
今回は、名前を付ける行為について、私の思うことをお話しします。最後に掌編小説も載せます。
◆音の名前
ウラジーミル・ナボコフは、Lに誘惑され取り憑かれた人のように感じられます。Lolita という名前より、Lに取り憑かれている気がします。あの小説の冒頭のように、 l をばらばらしているからです。
つまり、Lolita を解(ほど)き、ばらばらにするのです。名前を身体の比喩と見なすとすれば