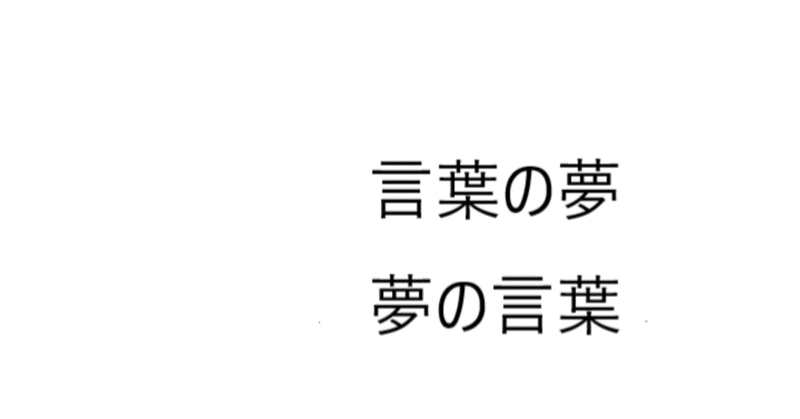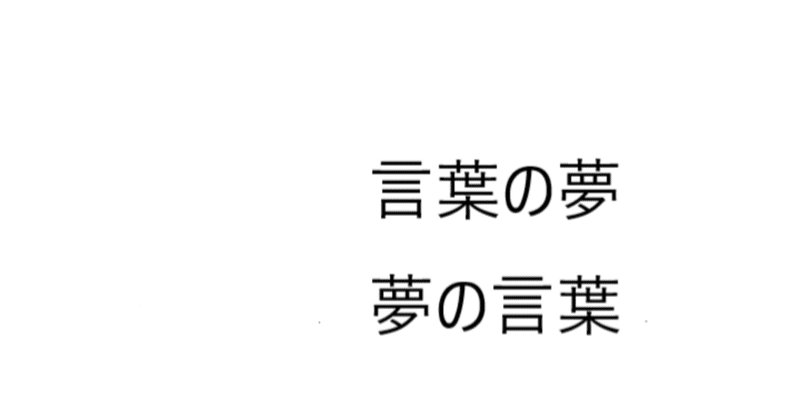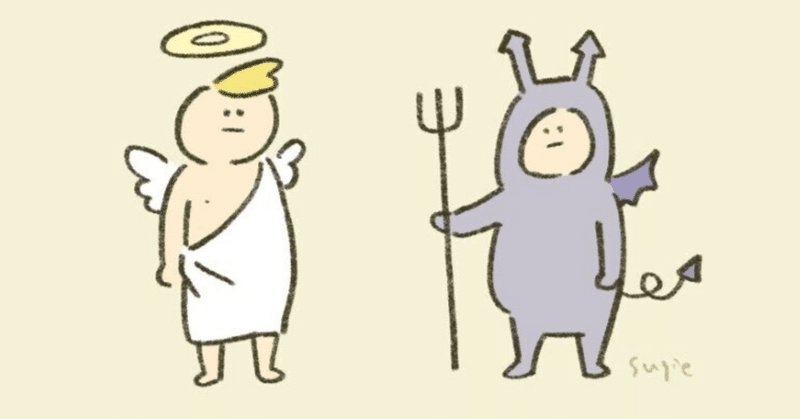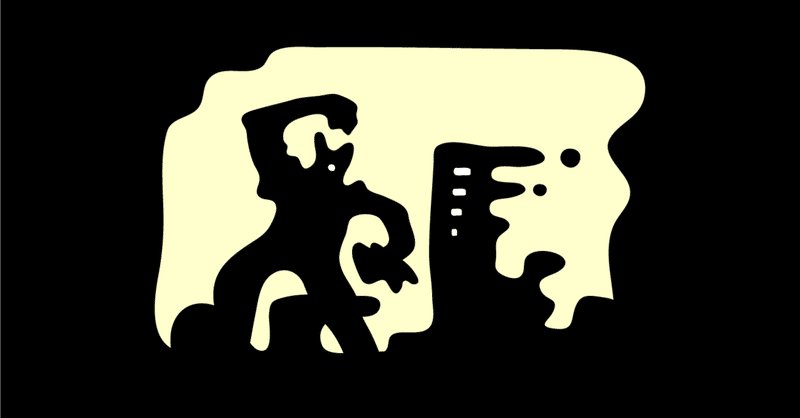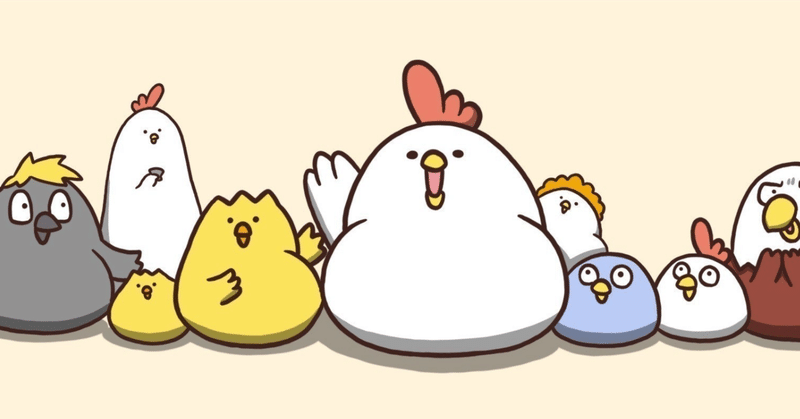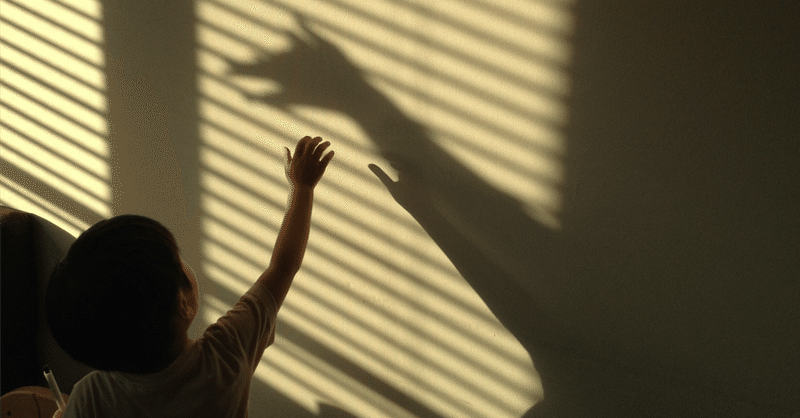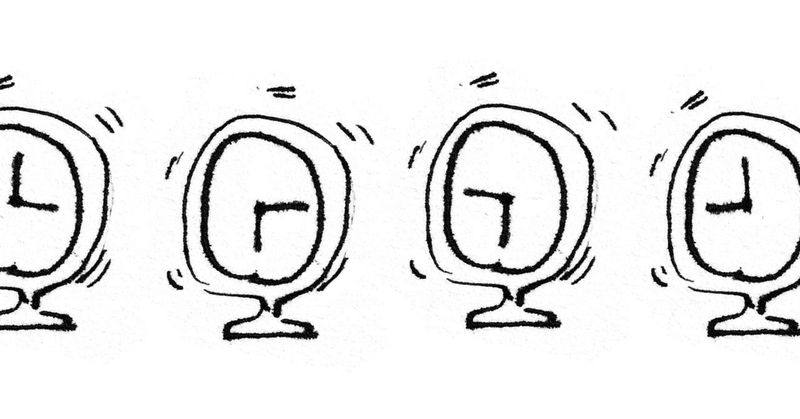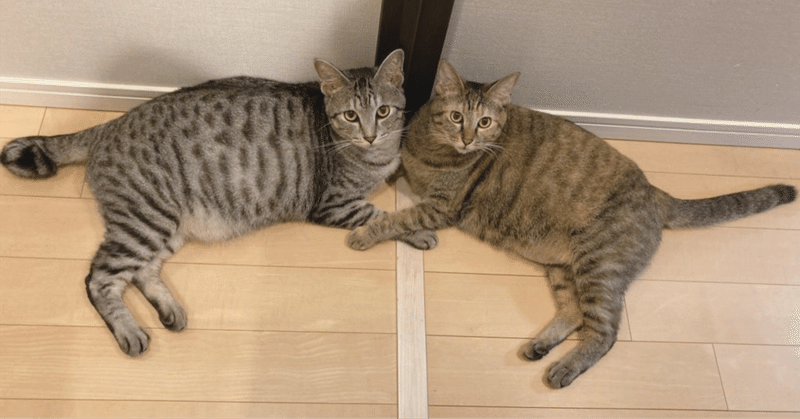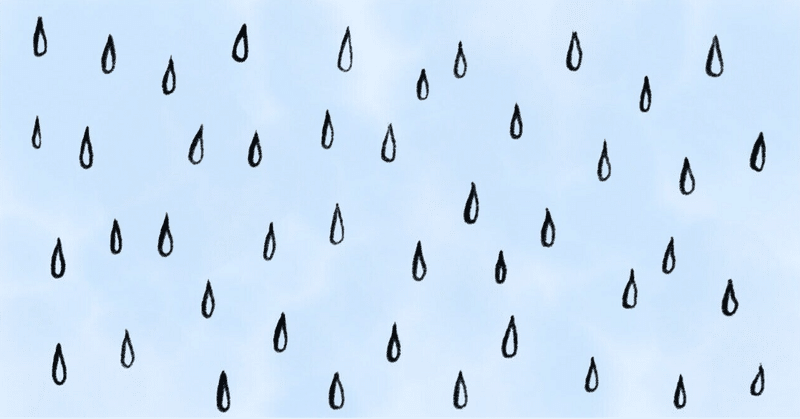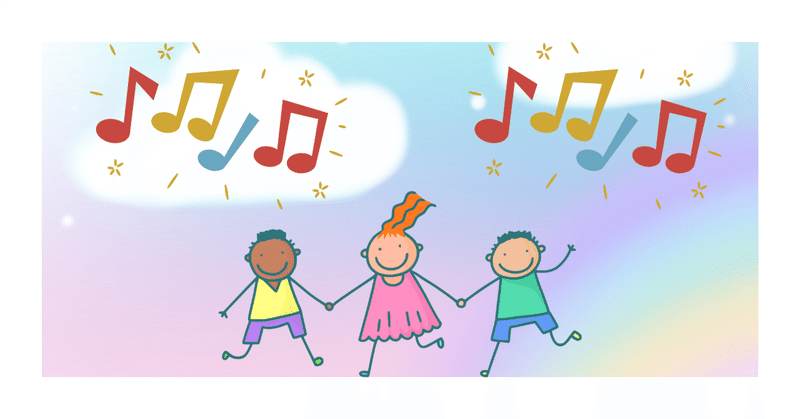2023年11月の記事一覧
直線上で迷う(線状について・01)
直線上で迷うことがあります。嘘ではありません。誰もが経験していることです。私もしょっちゅう経験しています。
証拠があります。ハードエビデンス(hard evidence)、動かぬ証拠というやつです。
たとえば、こんなふうにです。動画をご覧ください。
ごめんなさい。
動かぬ証拠ではなく、動く証拠(soft evidence?)でした。
*
小説には始まりと終わりがあ
迷う権利(線状について・03)
人は直線上で迷う。ただし、「私は直線上で迷っている」と口にするのはタブーである――。
これまで、そうしたことを書いてきました。さらに言うと、次のようにも書きました。
人生や世界や宇宙が、くねくねごちゃごちゃしているから、それをすっきりさせる工夫が線状化や直線化である。
*
人は直線上で迷う生き物であるにもかかわらず、「私は直線上で迷っている」と人前で口にしてはならないし、
振り(線状について・04)
誤っても謝らない、つまりブレない人が上に立つ社会は生きづらい。生きづらいどころか恐ろしい。ブレないリーダーの体裁や辻褄合わせに、人びとが付きあわされて、ブレたり迷うことができなくなる。迷う権利を行使できなくなる。
前回は、そういう話をしました。
*
誤っても謝らない。ブレない、揺れない、振れない、迷わない――。
これは、詳しく言うと次のようになります。
誤っても誤った
振りまわされる(線状について・05)
この記事では、ミシェル・フーコーとノーム・チョムスキー、およびジャック・ラカンの動画と、古井由吉と蓮實重彦の作品と著作からの引用文を題材にして、生きていないものの身振りに「振れる」行為について考えてみます。
Ⅰ 人の身振りに振られる
最近、ぼーっとしながら見ている動画あります。ぼーっと見ていると、なんとなく楽しいのです。
ミシェル・フーコー、ノーム・チョムスキー
以前はミシェル・フーコ
見えない反復、見える反復(反復とずれ・02)
人において、反復と「ずれ」(差違)は別個に起こるものではないし、対立するものでもないのではないか。そんな話をします。ややこしそうに聞こえるかもしれませんが、歌や詩を例にして具体的に話すつもりです。
見えない反復、見える反復
唱歌「故郷(ふるさと)」(作詞:高野辰之、作曲:岡野貞)です。
この歌では、ある反復が起こっているのですが、それは聞き取れるでしょうか? つまり、反復をずれとして聞き