
鹿島茂『多様性の時代を生きるための哲学』: 社会的コントロールへの抵抗
書評:鹿島茂『多様性の時代を生きるための哲学』(祥伝社)
フランス文学者で古書コレクターとしても知られる、鹿島茂の対談集である。
本書は、鹿島の主催する書評サイト「ALL REVIERWS」の会員限定コンテンツとして同サイト掲載された、課題本著者との対談の第2集で、思想哲学系の著書とその著者が紹介されている。
対談相手は、東浩紀、ブレイディみかこ、千葉雅也、石井洋二郎、宇野重規、ドミニク・チェンの6人だ。
私が読んだことのあるのは、東、千葉、ブレイディの3人で、東浩紀と千葉雅也は、フランス現代思想を基調とした哲学者。
ブレディみかこは、イギリスでの生活体験をもとにした社会学書と小説で有名。
石井洋二郎という人は知らなかったが、フランス文学者で、フランスの社会学者ピエール・ブルデューなどの翻訳者として高く評価された人らしい。
宇野重規は、「民主主義」をテーマにした著作の多い政治哲学者で、例の「日本学術会議任命拒否問題」で、菅義偉前首相から任命を拒否された、6人の学者のうちの一人だ。
ドミニク・チェンは、日本の情報学研究者で起業家、ということになる。

書評サイトのしかも対談だから、さほど難しい内容ではなく、哲学や情報学といった、日常的にはあまり縁のない学問を扱ってはいても、しごく平易に語られていて、わかりやすい。
本書は、著者インタビューではなく、あくまでも対談であり、鹿島が半分くらい喋っているが、鹿島はバルザックなどを専門とするフランス文学者であり、元々は抽象的なものではなく具体的なものを求めて、哲学ではなく文学の方へ進んだような人なので、話が抽象的な議論にさしかかると、たとえ話や具体的な話を持ち出して、話をわかりやすく噛み砕いてくれるのだ。

したがって、うんうんなるほどと納得しながら楽しく読み進めることができるのだが、しかし私の場合、こうした著作こそ「要注意」だと考え、あえて眉に唾して読むことにしている。
双方が「そうですね、そうですね」とうなずき合いながら、意気投合しての対談というのは、おおむね「(呑み込まれて)語られていない部分」があり、むしろ、そここそが肝心だと思うからだ。
つまり、鹿島の趣味である「コレクション(蒐集)」の話に喩えて言うと、コレクターが見せびらかしてくれるコレクション(蒐集品)とは、表に出しても差し障りのない程度のものであって、本当にすごい(ヤバイ)コレクションは、しばしば隠され(秘蔵され)がちなものだ、といったようなことなのだが、一一もしかしてこの比喩は、コレクター以外には、ピンと来ないだろうか?
○ ○ ○
ともあれ、そんな私が本書で面白いと思ったのは、本書の帯の背面に刷られている、次のような言葉の指し示すものである。
『「選ぶ」というよりは「選ばされて」いるのに、それが自分の意思だと思い込んでしまう。
これがブルデューの「必要趣味」の本質』(石井洋二郎)
『個人主義になればなるほど、多数者の意見に流されやすくなるという逆説を主張したのは、トクヴィルの慧眼だったと思います。』(宇野重規)
ブルデューの「必要趣味」というのは、次のようなものだ。
「趣味」というものは本来、自由に自身の「好み」で選ばれるもののはずなのに、実際には、多くの人はその「選択範囲」を、所属階層などの外在条件によって、半ば自覚できないまま限定されており、言うなれば「それを選ぶしかないから、それを選ぶ」「それが、自分の立場では最も好ましく必要なものと感じられるから、それを選ぶ」といった選び方によって、選ばされている、そんな「趣味」のことだ。
言い換えれば、カネも教養(文化資産)も持たない低所得者層の「趣味」と言えば、例えばヨーロッパでの「サッカー」や、アメリカでの「バスケットボール」などが思い浮かぶだろう。もちろん、これらの趣味が悪いというのではなく、貧乏人は生活環境的に、おのずと「選択の余地」が限られており、例えば、仮に優れたセンスを秘め持っていたとしても、「オペラ鑑賞」や「乗馬」を趣味にするような機会など与えられない、といったようなことである。
つまり、本来的な意味での「趣味」とは、経済的あるいは時間的に必要な「余裕」等々などに恵まれているために「何者にも制約されることなく、主体的に選びとられたもの」であり、さらに言えばそれは「これを趣味に持てば、人を感心させることができるだろう」といった「承認欲求」などからさえ自由であり得て、初めて、素の自分の「好み」だけで選びうるもの、それが本来の「趣味」だということになる。
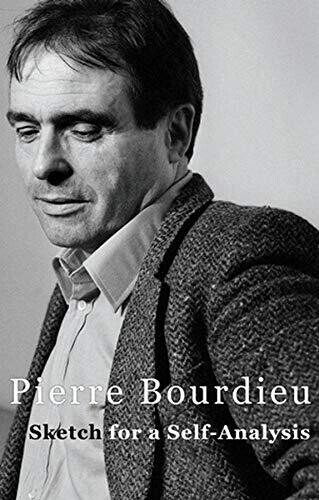
一方、トクヴィルの言う『個人主義になればなるほど、多数者の意見に流されやすくなる』とは、どういうことか。
「集団主義」の面倒くささ(制約)から解放された「個人主義」の社会になると、そこでは「個人」の力量が自己責任的に問われて「集団」に守ってもらえないという不安が出てくるので、かえって多くの人は「多数派の中の個人」でありたがる、というようなことだ。「みんなの言うように、私もそう思う」という立場が、いちばん気楽で「安心」できる立場なのである。
したがって、これらのことからわかるのは、私たちが意外に「個性的ではない」、そうではあり得ない、ということだ。
「集団の統制」を受けない「個人」であることはできても、「集団の制約」の中へ自ら望んで入っていってしまいがちな存在であり、その意味で「個性的」ではあり得ない。「個人」でありながらも「その他大勢」的な存在になってしまいがちなのである。
無論「自分は、その他大勢であることが好きだし、事実、その他大勢の一人なんですよ。私になんか、特別な価値はありません」と、自覚的に認められる(承認欲求の無い)人はいい。
だが、実際には、多くの人は、自身が、交換可能な(無個性な)「その他大勢」であるとは認めないだろうし、それで良いとも思わないだろう。だからこそ、他人から「あなたは、その他大勢ですよ」と言われたら、あるいは「あなたは、典型的なモブです」などと言われたら、腹を立てもするし、「そうではない」と反論するのではないだろうか。一一つまりそれこそが「平均的な人間」心理なのである。
しかし、現実には「個性的な人」などというのは、滅多にいるものではない。そもそも個性派が大勢いたら、もはやそれを「個性派」とは言わないだろう。
いくら「世界で一つだけの花」だとか言っても、誰だって「誰からも注目されない花」で良いとは思っていないし、事実、今の世の中は、「承認欲求」に翻弄されて、カネにもならない「イイね」をもらうためには、言いたいことも呑み込んで、見知らぬ他人に媚びることも当たり前になってしまっている人が、決して少なくはないはずだ。
では、「個性的」でありたいと思う私たちは、一体どうすれば、そうなれるのだろうか。
それは、自己の「承認欲求」の強さを直視して、それをねじ伏せるしかないと思う。つまり「孤立」に耐えるということだ。
多くの人は、自身が「個性的」なままに、その「個性」を「多くの人」つまりは「多数者」や、もしくは「有力者=権威者」に受け入れてもらおう(承認されよう)とするし、それが可能であると思っている。
例えば、多くの人が認める「権威あるもの」を自身の「趣味」として、その「趣味」を誇ることで、自分が「個性化」できると思っている。だが、それは本当だろうか?
私はそうとは思わない。
と言うのも、そういう「おいしい話」というのは、誰もが手軽に飛びつきやすいものだからであり、その結果として、そうした人自身は、その「趣味」において「個性的」なつもりなのだろうが、他人から見れば「よく見かける人たち」の一人でしかない、からだ。つまり「その他大勢=モブ」である。
では、「権威」に抗って「反権威」的なもの選べば良いのかというと、これもそう簡単な話ではない。
というのも、こうした「反権威」というのは、所詮「逆張り」の域を出ず、その意味で「必要趣味」の域を出ないもの、つまり、本物の「趣味」の発露ではない、ということになるからだ。
しかし、そうなると私たちは、「世間受けの良い権威」は無論、「多少なりとも世間から評価されるであろう反権威」さえ選ぶことができず、立ち往生してしまわざるを得ない、ということになる。
そこで私の考えた戦略は「権威的なものと反権威的なものの両方を選ぶ(可能なかぎり、ぜんぶ選ぶ)」ということだ。
どちらの「権威」も同じように認めることによって、私を外から権威づけるものとしての「権威」を相対化して否定し、「既成の権威」に頼らず、むしろその「権威」に、相応の「保証を与えてやる立場」に立つのである。「保証される立場」ではなく、「保証する立場」という、滅多に立ち得ない、自由で「特権的な立場=貴族的な立場」に立つのだ。

(アレクシ・ド・トクヴィル)
私が、「哲学」も扱えば「マンガ」も扱う(あるいは「文学」も扱えば「社会問題」も扱う)のは、こうしたことからだ。
ことさらに、何かの「権威」にすがりついて、その「権威」で自身を飾るのではなく、「どれも、相応に評価する(評価を与える主体)」の位置に、自分を置くのである。
「世間が認めるメジャーな権威の側に立って、マイナーな権威を見下す」ような「単細胞な権威主義」でもなければ、「マイナーな権威の側に立って、選民主義的に、メジャーな権威の権威主義を嘲笑する」という「搦め手の権威主義」でもない。
いずれにしろそれらは、「自分」の外の「権威」に依存している「権威(尊厳)なき人間」でしかない、とする立場に立つのである。
そして、私がこうした立場に立って「権威批判」を繰り広げる根拠とは何かというと、それは「自立(自律)した個人」としての「権威なき私の趣味」であり「権威なき私の美意識」である、とでも言い得るだろう。
無論、こうしたものは、「他者」からは容易に認められる(承認される)ことはない。なにしろ、「既成の権威」という、わかりやすく「世間的な根拠(保証)」を持たないのだから。
しかし、「世間的な根拠(保証)」に依存しないからこそ、私は「個性的」たり得るのであり、それを支えるものとは、私がこれまで築き上げてきた、私独自の「美意識」であり「価値観」ということしかないのである。言い換えれば、「私自身が、私を保証する根拠」なのである。
したがって、こんな私は「特定の立場」を選ぶ必要がなく、その場その場で、自身の「美意識」に照らして、判断することになる。
それはしばしば、外からはわかりにくい「(どこにも根拠のない)立場」に見えるかもしれないが、私の中では、むしろ完全に一貫したものであり、外の「権威」に忖度したり配慮したりする必要のない、自由な立場だと言えるだろう。
私は、「世間的な権威」も「世間的な反権威」も、共にその価値を認めるし、必要があれば、どちらも遠慮なく批判する。それは、「世間(多数派)」の「わかりやすい価値観」に迎合する必要のない、自由な立場なのである。
一一と、こうしたことを考えられる、オリジナリティのある「哲学オタク」なんてものがが、果たしてどれほどいるだろうか?
『石井 ところで私は『ブルデュー『ディスタンクシオン』講義』の最終章にあたる〈総括講義〉に「もっと怒りを!」というタイトルをつけていますが、これはゲーテの臨終の言葉とされている「もっと光を!」というフレーズをもじったものです。彼が本当に死ぬ間際にこんなことを言ったかどうかはあやしいみたいですけどね。ちなみに、日本語の「光」hikariをフランス人が発音すると「怒り」ikariになるんですが、まぁそれはそれとして、ブルデューはとにかくずっと怒っていた人という印象があります。もちろん実際にお会いしてみると、ご本人は怒りっぽいどころか、とても温和で紳士的な方でしたけれど、彼は格差の拡大に代表される世の不正に対する怒りをずっと失わなかった。これは非常に重要なことではないかと私は思います。彼のようにストレートな怒りを表わす知識人が、本当にいなくなってきました。だからこのタイトルは、彼の心情に対する深い共感の表明なんです。
鹿島 たしかに、そうですね。
石井 もちろん怒りはあくまでも生の感情ですから、ただそのまま吐き出すだけではなく、理由を冷静に、かつ適切に言語化しなければいけません。彼は学問的な言葉を使って、それをじつに緻密な形で実践したと思います。いまの社会はいろいろなところでいろいろな不正が起きてきて、理不尽なことにあふれています。私は自分ではどちらかといえば温和な人間だと思っていますが、そんな私でも怒りを禁じ得ないことはたくさんある。それをひとつひとつ着実に言語化していかなければいけないと、つくづく思います。
鹿島 そうですね。ブルデューの『ディスタンクシオン』を読むと、「すべてあらかじめ決定されているのだから行動しようがないじゃないか」という決定論だという批判を向ける人も多いです。実際、そういうふうに読めないこともない。ただブルデューは、「ハビトゥス」は常に動いているもので、固定されたものではないと言っています。しかも自分たちが「ハビトゥス」によって規定されることを意識化しないかぎりそこから抜け出せないものではあるけれど、意識化することが何より必要だと繰り返し述べているんですね。』(P176〜177)
私たちは、常に「世間的な価値観としての権威」の影響下にあり、それに従うにしろ、それに逆らうにしろ、つまり、どっちにしろ、そのコントロールから完全に自由であることなどできない。
しかし、それは絶対的に「固定」された制度などではなく、常に、揺らぎ変化している部分を含みもつものであるからこそ、そこにはつけ込む隙もあれば、そこを突くことも可能であり、状況を多少なりとも変えていくこと(抵抗戦)も、決して不可能ではない。
しかし、それをするためには、いかに私たちが「世間的な価値観としての権威」に縛られているか、を意識することが必要不可欠である。
その認識に立って、「権威的価値観のズラし」に取り組まないかぎり、その人が自分に感じている「権威」とは、必ずや、借り物の「幻想」に過ぎないのである。
(2022年10月31日)
○ ○ ○
○ ○ ○
