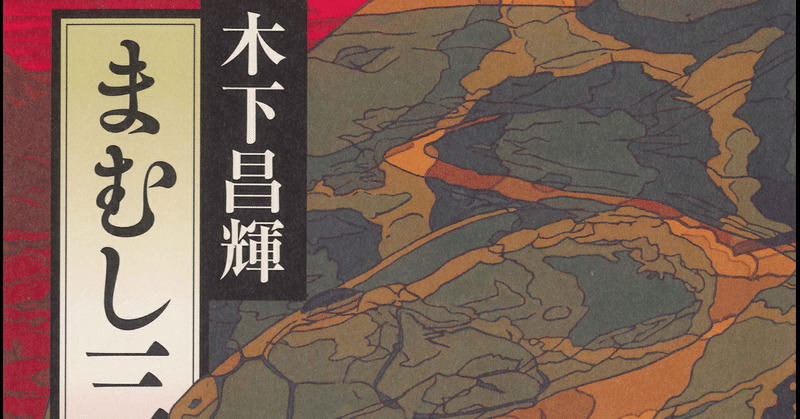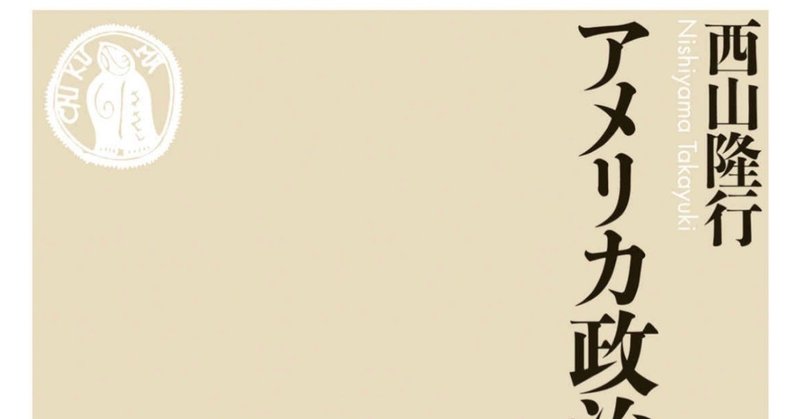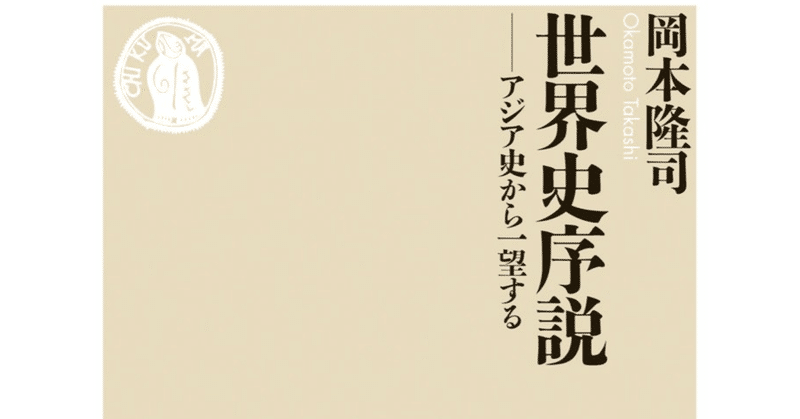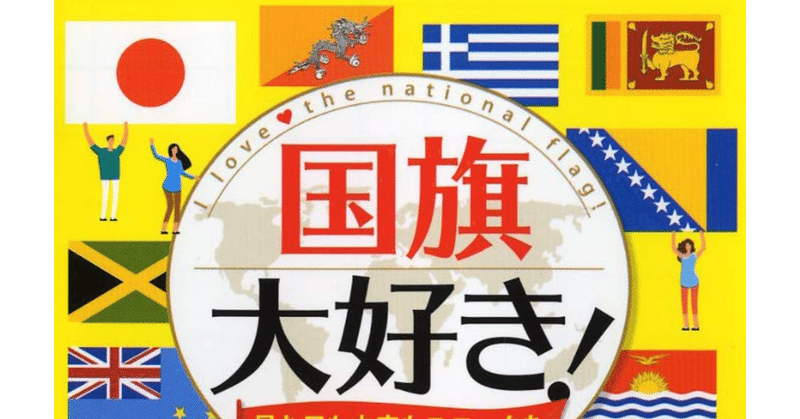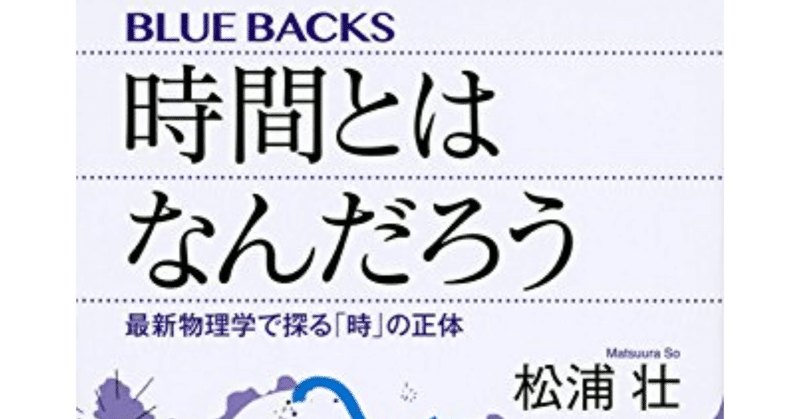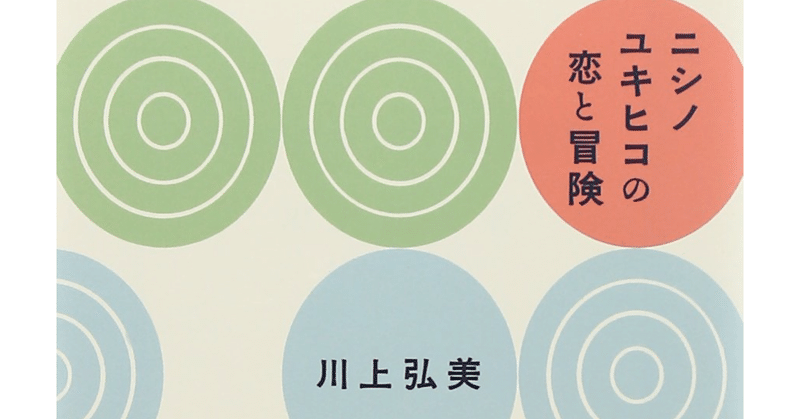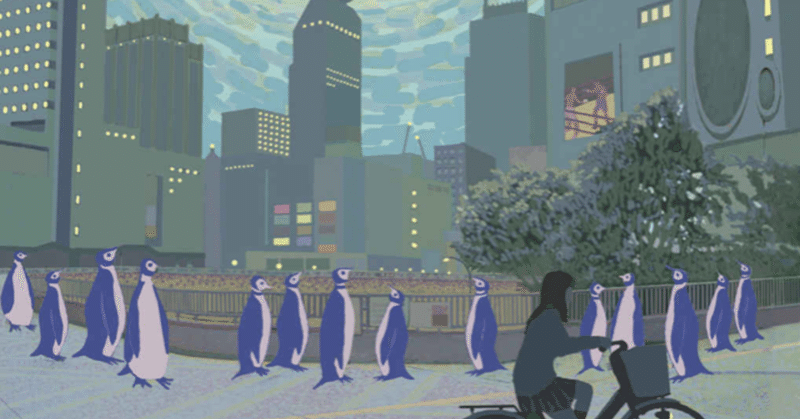記事一覧
【読書感想13】ニシノユキヒコの恋と冒険/川上弘美
特に恋愛を書かせたら川上弘美の右に出る人はいないと思うので、読んでみた。読んでみて、すごくよかったなぁと思って解説を読んだら、自分の受け止めは女性読者の受け止めとは全然違うのかもしれないと思った。僕は、恋愛においては男も女も主体性を持って行動しているもんだと思い込んでいたけど、もしかしたら、誰も主導権を持ってなどいなくて、雰囲気や、勢いや、事の成り行きがほとんどのことを決しているのかもしれない(少
もっとみる【読書感想12】アフター・ヨーロッパ --ポピュリズムという妖怪にどう向き合うか/イワン・クラステフ
以下要約とコメント。
・近年EUが直面した複数の危機のうち、難民危機だけが本質的な危機である。
・EUには3つのパラドックスがある。すなわち、中欧のパラドックス、西欧のパラドックス、そしてブリュッセルのパラドックスである。中欧の人々はEUが好きだがリベラルは嫌いだ。西欧ではリベラルでコスモポリタン的な若者が政治的な運動を組織するに至っていない(SNSで集まり、一瞬不満を爆発させて終わってしまう)。
【読書感想11】 つくられた卑弥呼―“女”の創出と国家/義江 明子
卑弥呼×ジェンダーということで、発想は素晴らしい。よく知られているが漠然としか知られていないものを、これまでと異なる切り口で構成し直すのは、よい考察の一つの類型である。
そして、最終章は悪くない。「神秘の巫女、卑弥呼」像がたかだか明治に新しく作られたものであることを示そうとした狙いは良い。けど、明治以前は本当にそう描かれていなかったのか、いまいち説得的でない。また、明治40年に出された論文(本書の
【読書感想8】いま世界の哲学者が考えていること/岡本裕一朗
「人がより良く生きるために」という観点から、IT、バイオテクノロジー、資本主義、宗教の復権、環境問題について最新の議論の状況をまとめた本。著者自身の結論が述べられているわけではなく、対立する議論の両論を紹介するに留まっているため、自分が問題意識を持っている分野に関しては内容が浅い、物足りないと感じた。しかし、それまであまり意識していなかった分野については、こういう視点もあったのか、と気付かされた。
もっとみる【読書感想7】アイネクライネナハトムジーク/伊坂幸太郎
去年の9月に三浦春馬主演で映画化されるらしいので読んでみた。斉藤和義に作詞を求められたことがきっかけで誕生した短編集とのこと。プロボクサーと美容師の偶然の出会いなどを中心に6本立て。あとがきで著者が言うには「恋愛もの」は慣れていなかったとのことだが、伊坂幸太郎らしい、意外だが気の利いた展開が見られる。映画は、劇場で見るほどではないかな、と思った。
伊坂幸太郎の他の本はこちら
Twitterはこ
【読書感想6】声の網/星新一
星新一の長編。近未来の社会で人類の知能を超えたコンピュータが人類を支配するまでを描く。あるマンションの1Fから12Fまでの住人に起こる出来事を順に観察していくという形式で書かれているので、いつもの星新一のショートショートに近い形で読むことができ、非常に読みやすい(読了までにかかった時間は恐らく3〜4時間程度)。以下の記事でおすすめされていたので読んでみた。
1970年に初版が出たということだ