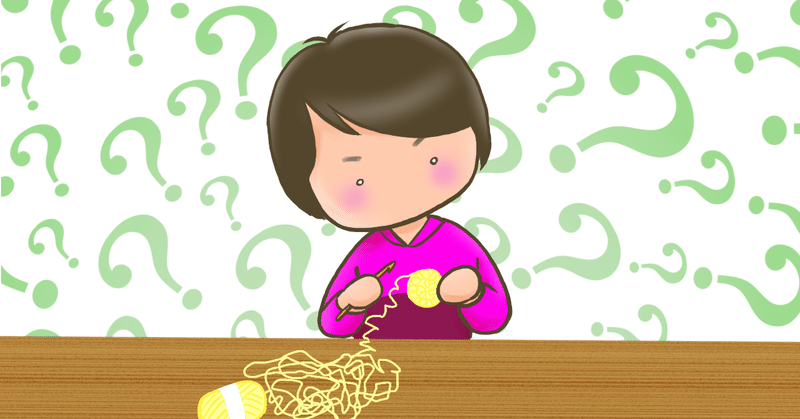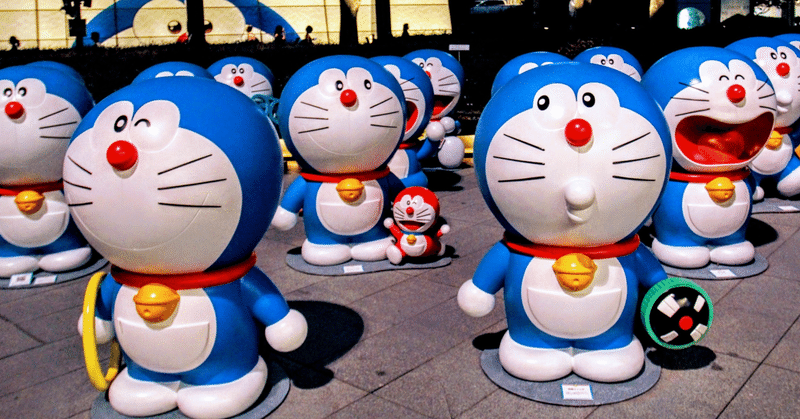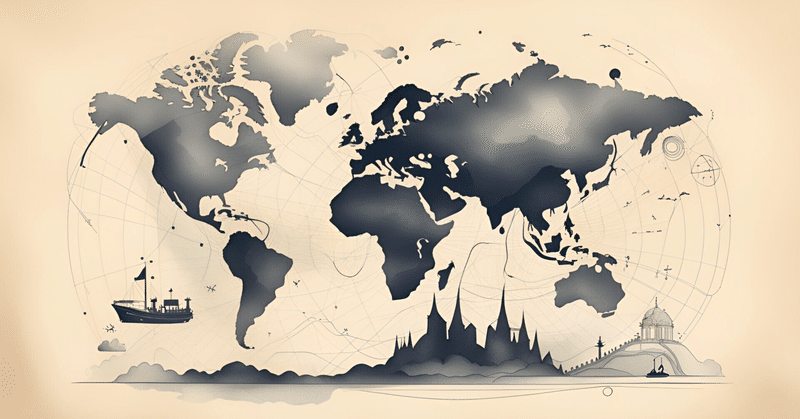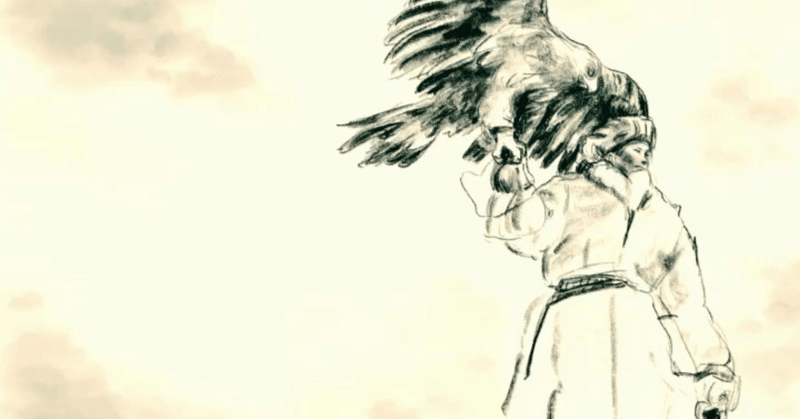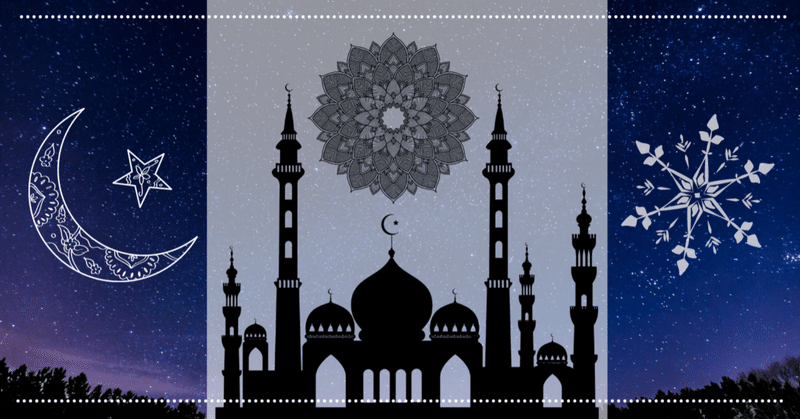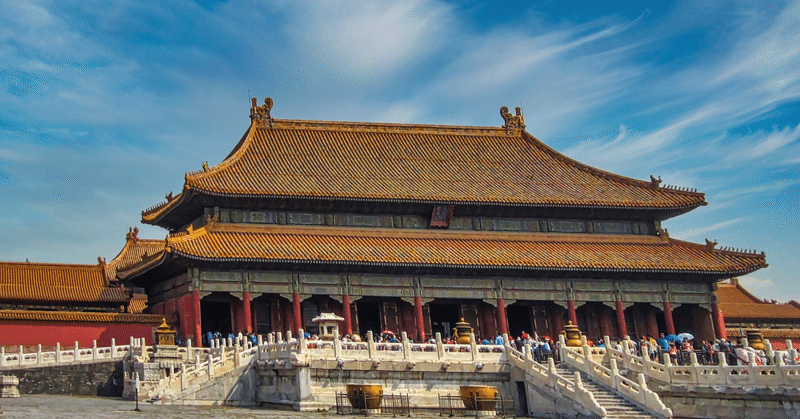2024年2月の記事一覧
真を写す、信を発する ~撮影者なりの世界~
写真の歴史と発信の歴史とを合わせて考える。
これが本記事のテーマです。
この世の中の「風景」「事物」などを
平面に写して残す! 残したい!
そういう欲求は、
人類が進化しつつある太古の昔から
すでに生まれていました。
フランスのラスコーや
スペインのアルタミラという洞窟では、
クロマニョン人が描いた「壁画」が残されています。
人や犬や牛、猪や鹿などが生き生きと描かれ、
この壁画によって、私た
「経営=経験×営繕」と仮定して
「経営=経理×営業」が、平成の主流。
ならば令和は
「経営=経験×営繕」だと仮定して
書いてみたのが本記事です。
元々「経営」とは
◆「経」=変わらないもの
◆「営」=変えていくもの
という意味からできた仏教用語。
それがビジネス用語として
「会社を経営する」などのように
使われ始めた経緯があります。
特にバブル崩壊後、
デフレ傾向の平成日本では、
「お金」のことを考えるのが経営だ、と
捉えら