
書きかえられてしまったシンデレラの本当の人生
ビビデバ
Bibbidi-Bobbidi-Boo
シンデレラには、350~1500の、異なるバージョンが存在する。
数に幅がありすぎるのは、把握しきれないほど多いことと、これもシンデレラの亜種か?と判断がつかないことが原因。
初代・シンデレラはギリシャ人。
本家本元の物語は、紀元前(何年かは諸説ある)のギリシャで、ストラボンによって書かれた。
ロドピスという名の少女。トラキア生まれ。奴隷として、エジプトへ連れて行かれる。鷲が彼女の金色の靴をくわえて飛び去る。ファラオの膝の上にそれを落とす。天からの「しるし」であるととらえた王は、持ち主を探す。ロドピスを見つける。2人は結婚する。ヒロインは奴隷の身分から王族になる。
ヒロインの社会的地位が結婚により昇格する、という軸。ほとんどのシンデレラ類似物語の中心に、これがある。

これ以前に。ヘロドトスの『歴史』2巻に、奴隷で売春婦の、同名女性が登場する。ロドピス/ロードピスなる人物は、おそらく実在した。

このことは後半で詳しく書く。一旦、物語としての『シンデレラ』を解説していく。
セカンド・シンデレラは中国人。
どのようにして、紀元前のギリシャから9世紀の中国まで物語が伝わったのかは、定かになっていない。
9世紀の中国。葉限という名の少女(カタカナで表すとイェンシェンに近い音)。首領の娘だったが両親を亡くす。継母からひどいあつかいを受けながら暮らす。金色の目をもつ魚だけが友達。日々、ごはんをあげていた。大切な友達を継母に処分される。魚の骨が彼女の願いを叶える。金色の靴を手に入れる。片方落としてしまった靴が、ある島の王の手に渡る。誰にもはかれたくないかのように、サイズが変わる不可思議な靴。王は、はける人物を探す。葉限を見つける。2人は結婚する。
鷲よりさらに守護者的な存在(擬人化された魚)と、靴に魔法の力がある的なアイディアが、足されている。重要な要素だ。魚なのは、ロドピスの靴が、魚のうろこ模様だったことからかもしれないが。

よくよく考えてみると。この娘は、素敵な靴がほしいと、そんなささいなことしか願っていない。いや、なくした友達の分身をほしがっただけかも。何でも1つ思いどおりになるというのに。
心やさしく謙虚な人だからこそ、より大きな幸福を手にすることになったと、そのような教訓を表現しているようにも思う。
私たちが知っているシンデレラの誕生。
17世紀イタリアで、短編小説集『ペンタメローネ』に、『チェネレントラ』という物語が掲載された。中国版と同じく、意地悪な継母と義理の姉妹・魔法・行方不明の靴が出てくる。しかし、大きな違いが1つ。このヒロインは、王と強制的に結婚させられたに近いのだ。
その後、フランスのシャルル・ペローの『ペロー童話集』に、現在最も知られているシンデレラの物語が載った。『Cendrillon ou La Petite pantoufle de verre』(サンドリヨン、または小さなガラスの靴)。これには、フェアリー・ゴッドマザーも、かぼちゃの馬車も、ガラスの靴も出てくる。

以降400年以上続く、シンデレラの姿の完成だ。ディズニーがアニメに起用したバージョンだ。

ガラスの靴。
1893年、英国民俗協会は、シンデレラの345の変種をまとめた。その作業中、大勢が、なぜガラスなんだーーという疑問をもった。
たしかに。ガラスなどという実用的でない素材で靴がつくられたというのは、どういう了見なのだろうか。

一部の学者らは、vair(フランス語で毛皮を意味する言葉。ベールだ)と verre(フランス語でガラスを意味する言葉)が、混同されたのだと。また、他の学者らは、イタリア版の亜種にすでにガラスの靴があったと主張。
1697年の類似作品に、赤いサテンの靴が出てくる。毛皮の靴とは、現実的な話、サテンの靴のことなのかなと。

私の足のサイズは22.5cmだ。甲が高く横幅がかなり狭いため、実寸よりも小さく見える。これで、まわりから小さいと言われるくらい。1000人試して誰もはけないなどのエピソードから、シンデレラの足は、少なくとも22cm以下なのだろう。
余談。
所有者に適合するかどうかのテストが、靴ではなく指輪で行われる、似た作品も存在するという。『不思議な樺』というタイトルの、フィンランドやロシアで見られる物語だそう。
ヒロインが厳しい生活を強いられていることは、彼女のさまざまなあだ名の中に、表れている。
英語 cinder、仏語 cendre、独語 asche、伊語 cenere はいずれも、燃え殻や灰を意味する。多くが、これらの派生系である。和名の『灰かぶり姫』然り。
日々の下働きで、ほこりまみれになっていることから。cinder と彼女の本名 Ella を足して。Cinderella だ。

グリム兄弟がまとめた『グリム童話』にある、シンデレラの物語は、『Aschenputtel』というタイトルだ。
より暗い内容なのが特徴。
超自然的な助けは、母親の墓に生えている願いの木からおとずれる。ペロー版のように父親は不在ではなく、意図的に娘の苦しみを無視する。義理の姉妹は、つま先を切断して小さな靴を無理やりはく。血がにじんでチートが判明する。

プロットは、どこからともなく突然現れるわけではない。現実の出来事や実際の感情から、引き出されるものだ。
「意地悪な継母」は、他の多くのおとぎ話にも登場する。
歴史的に。継母が非常に一般的だったのは、離婚と再婚のせいではない。多くの女性が、出産中に亡くなっていたためだ。
また、継子はたしかに、夫の最初の結婚を連想させるだろうが。愛憎劇は、遺産をめぐる争いが生むものでもある。


トレメイン夫人。
彼女は、おそらく生活のために、シンデレラの父親と再婚せざるを得なかった。娘たちが結婚適齢期に近づいていることも、それを決意した要因だったかもしれない。
当時の社会を考える。
思いきり家父長制。彼女が貴族階級だったと想定すると、外で働くことは不可能だっただろう。(実家からの援助や夫の遺した資産で、食いつないでいたのだと思う)
根っからの性悪に見えるが。貴族の常識や道徳や価値観しか、もちあわせていなかった。たとえ学ぶ気概があったとしても、他の環境や情報にアクセスする術がなかった。そんな時代だ。
私は今、個々人の生まれもった性質についてではなく、社会の構造的な問題について、話している。例)極端な手段の少なさ
裕福な男性にみそめられるために体の一部を切り落とすという話が、どのように、怖い話なのか。少し伝わっただろうか。

左がアナスタシア。右がドリゼラ。
ディズニー……。悪意がありすぎやしないか。描き方がかわいそう。
これからどうなってしまうのーーというのは、ヒロインだけの不安ではなかった。継母も義理の姉妹もまた、残りの人生におびえていた。いわば、死に物狂いだった。
「悪いことばかり起きるんじゃないかなんて 心配ばかりで また星占いなんか見ている」「憎しみを越えて 諦めを渡り 愛の次はどこ」
ディズニーの『シンデレラ』は、1952年につくられた。
1950年代のアメリカの概念。仕事を通じてではなく結婚を通じて、女性はアメリカン・ドリームを達成すると。(何も悪いことではない)
この具現化に適切で、残酷な描写は少なくファンタジー要素が多いのが、ペロー版だったのだ。

オリジナルのシンデレラのモデル、実在したであろう女性、ロドピスの話をする。
これは、1人の女性が、奴隷から高級娼婦へと転身した話になる。
ある裕福な男性が、ロドピスに惚れこんだ。彼は彼女を買い取り、奴隷暮らしから解放した。ところが。ロドピスは、彼と一緒になることを望まなかった。
想像してみてほしい。生まれてはじめて、思い通りに人生を歩めるチャンスをつかんだのだ。
彼女は、これからは安心して眠れると胸をなでおろすのではなく、リスクをとってでも挑戦することを選んだ。
彼女が、異国(エジプト)で高級娼婦として成功したことが、『歴史』に記されている。ヘロドトスは、彼女の不屈の精神や独立心の強さを示唆する表現を、複数回している。
「神が与えたものではない」(自力の意味)。当時の感覚からして、かなりの賛辞だろう。

奴隷の身分から解放してくれた男性が、フェアリー・ゴッドマザーだと、していいだろう。ゴッドファーザーだが。
門限などない。真夜中こそ稼ぎ時だった。ガラスの靴?。エジプトだからサンダルだっただろう。魔法なんてない。自分の身ひとつしかなかった。
言うて体を売ってたんだろ、などと思うなかれ。その時代、女に、他にどんな仕事があったと言うのか。さらに。上位の高級娼婦(ヘタイラ)にとっては、性行為など、基本のきだった。
ギリシャ人の著者が、彼女のリアルなストーリーを、安易なおとぎ話に変えてしまった。
残念ながら、こういうことだったようだ。
現代。

そんな鈍感な人はいないと思うが。私は、売春をしてでも成り上がれと、言っているのではない。
国内だけでなく海外でも大人気の、素敵な歌に、代弁してもらおう。
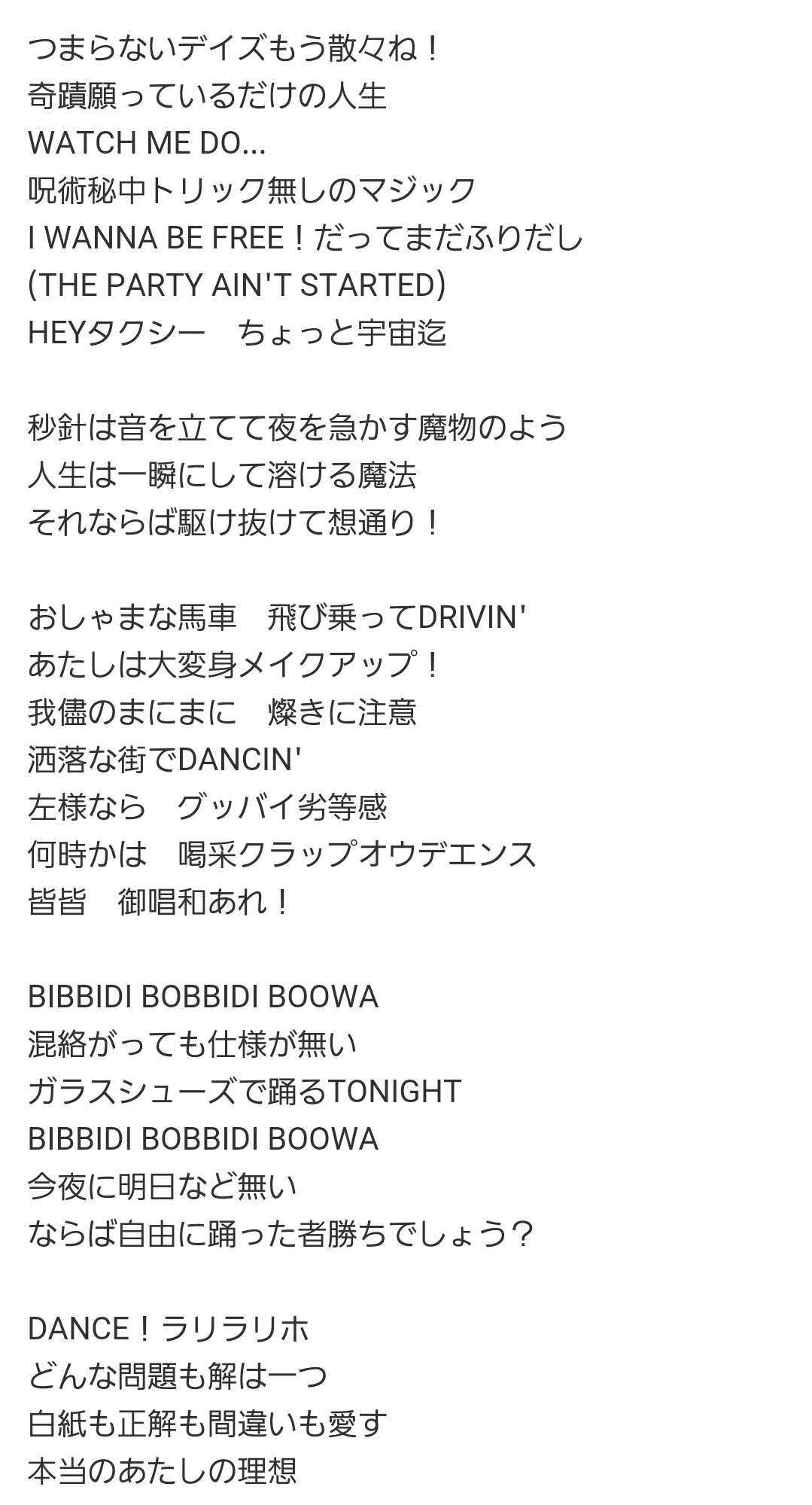




ナイル川デルタにある小さなピラミッドが、ロドピスの墓なのではないかと、推測されているそうだ。
地元の言い伝えによると。人気ヘタイラのロドピスが亡くなった時、悲しみに暮れる愛人たちが費用を分担して、建造したのだと。
真っ赤な嘘かもしれない。だが。性別は関係なく、誰かにとっては、わかりみでしかない話なはず。つくづく思うが、大昔と今で、変わらないことは全く変わらない。

