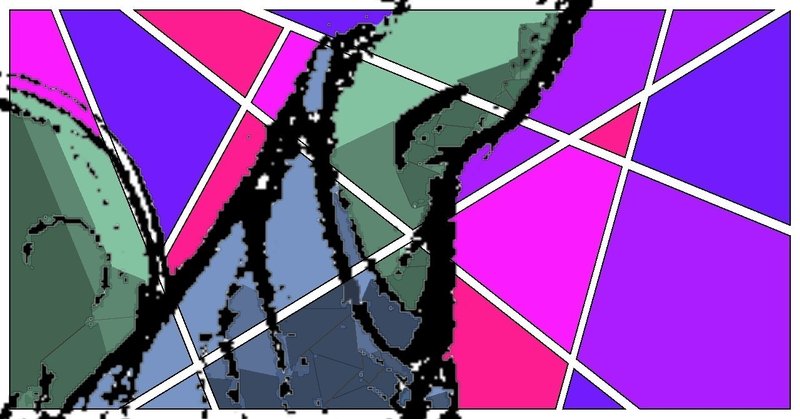
四枚ダンス
「ヨマイです。よろしく」
「ヨマイさん…」
「一枚二枚三枚『四枚』です」
「珍しい名前ですね」
ピアニスト小野雄一という男を一言で形容するなら『ババ抜き弱そう』
彼の弟、小野誠二の計略で私とこの男は『舞踏×音楽』の共同作品を作る事になった。しかし私は音楽に疎い。この男は何が出来るのだろう?
「ピアノと、作曲をたまに」
「経歴を聞いても?」
「東藝の器楽科に在籍してました。卒業してからはピアノ教室で先生したり、ボカロPやったり、V系バンドやったり、ジャズやったり、ゲーム音楽作ったり、時々サロン呼ばれたり、コンクール出たり…雑多な感じです。ヨマイさんは?」
「私は日芸を中退して、以来ずっと舞踏の独学です」
「なるほど」
「……」
「……」
下手なお見合いみたいな空気だ。この展開を予想してか、本日不在の小野誠二は公民館の音楽室を会合場所に設定していた。
「何か弾いて貰えませんか?私も何か舞うので」
「はい。何弾けばいいですか?」
彼は鞄から楽譜の束を取り出した。私は短そうなものを適当に選ぶ。
「…他のにしません?」
「これでお願いします」
どうやらその曲は弾きたくないらしい。ならこの楽譜が正解だ。彼はしぶしぶ椅子に座り、楽譜を並べ溜息をする。少しの音を鳴らして「あ~、このピアノ、管理微妙、かも…」と小声で保険を打ち、指慣らしを終えた彼はピアノを弾き出した。
Bartók Béla
『Allegro barbaro』
凄まじい速度の曲調だ。きっと難度が高い楽曲なのだろう。情報量が過密だ。そもそもの曲調も、彼の演奏も。曲は私の知覚が追い付く前に終了した。私は時計を見る。2分30分くらいの曲だろうか…体感時間が狂っていた。
「どうでしたか」
「…素晴らしい芸術は鑑賞者の時間を簒奪します。長いようで、短いような、不思議な体感でした。魅力ある演奏だったと思います。さっきみたいな曲を一時間弾くことは出来ますか?」
「それは無理です。ありがとうございます」
今度は私の番だ。私は上着を脱ぎ、部屋の中央に突っ立ち、聴座を作る。換気扇の音、秒針、心音…私は窓の外の子どもたちの喧騒を捉えた。
その喧騒を空間に重ねる。私は子どもたちの中心に居座る。子どもたちが私の身体を駆け抜けてゆく。時にすり抜けるように、時にガサツに、時になじるように…私の身体はそよぐ。幼い喧騒は私の記憶と重なり、景色になる。時雨時の放課後、蝉の鳴くプール、粉雪の交差点…瞳は何も見ていない。空間の輪郭が溶け出す。私も輪郭を失う。形状を失った私は足の裏から少しずつ人間を組み上げていく。皮を感じ、肉を感じ、骨を感じ、血を感じる。頭を象った私は、私の意思を感じ、そこで一区切りとした。
…さて、終わりだ。どう言うだろう。意味不明と笑うだろうか?
「あ~…ちょっとよく…いや…僕語彙力無いんであれですけど…少し怖かったです。でも心地よかったんですよね?子ども好きなんですか?」
「子ども?」
「窓の外に聴覚傾けて、変わった気がしたんで。影響あったのかなと…違ったらすみません」
私の舞を観た人は皆自分の主観から感想を言う。私が戯れたイメージを私の視点から捉えて言語化した人は彼が初めてだった。この人と作品を作ってみたいと思った。私は誰かの視点に立って物事を見る事が出来ない。自我が強い、悪く言えば自分本意の我儘な人間だ。優一は他者の視点に立つことが出来る。フットワークの軽いパースフェクティヴ、それは表現者として優れた才能である。
二人の孤独な作品作り、矛盾するような共同創作が始まった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
