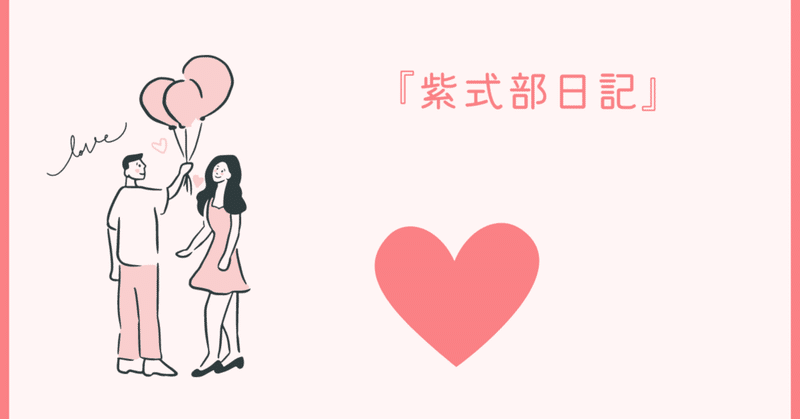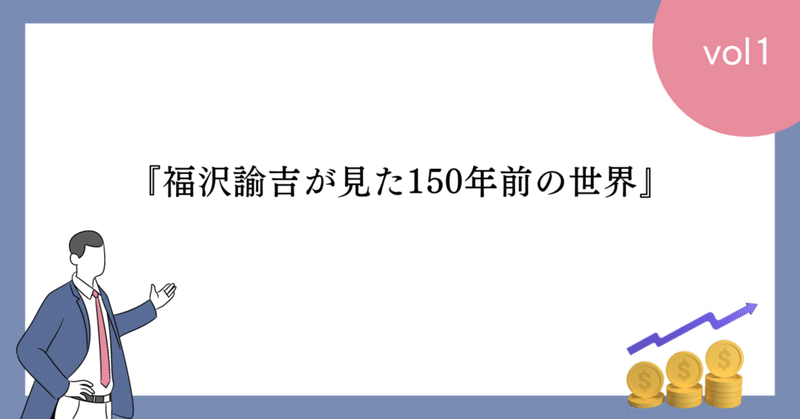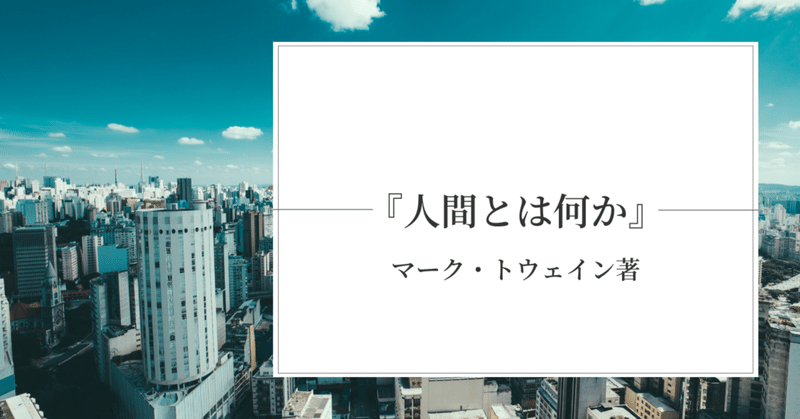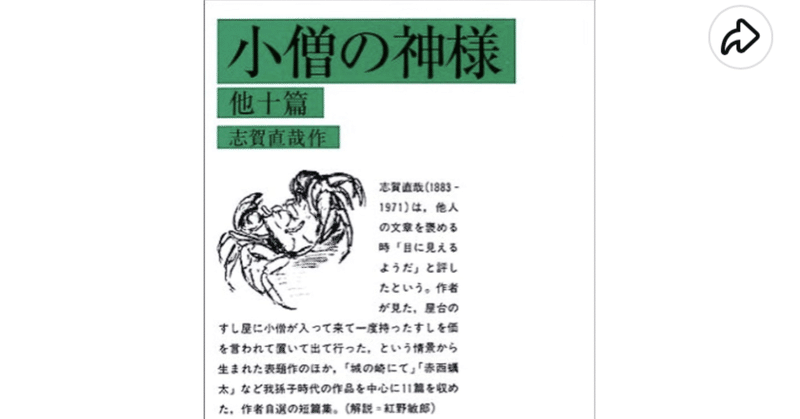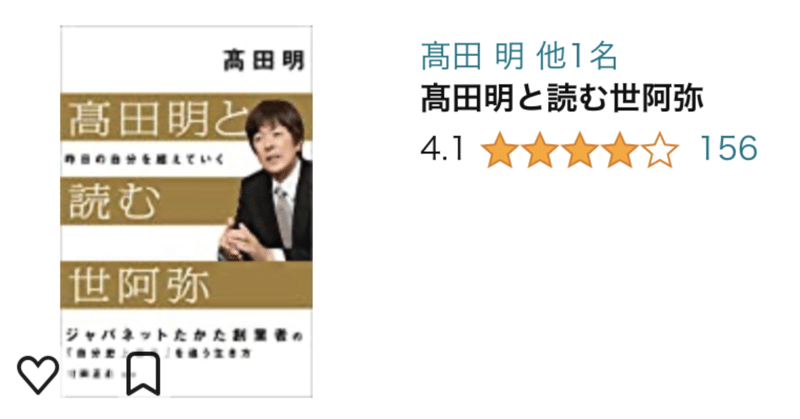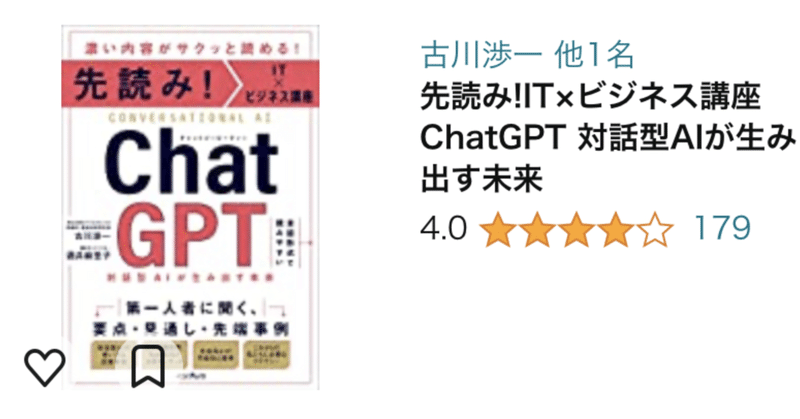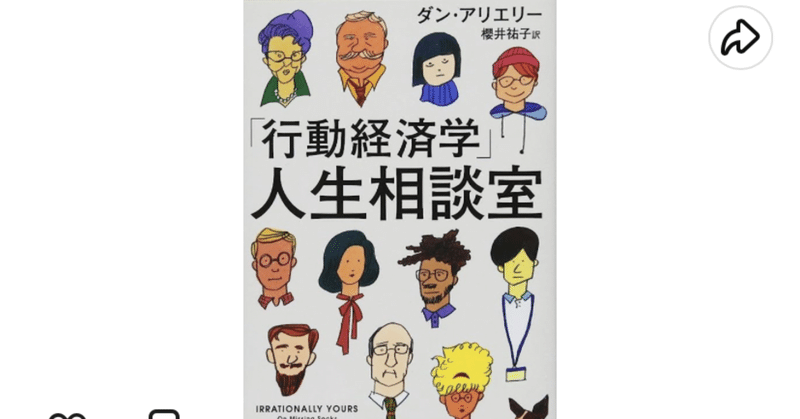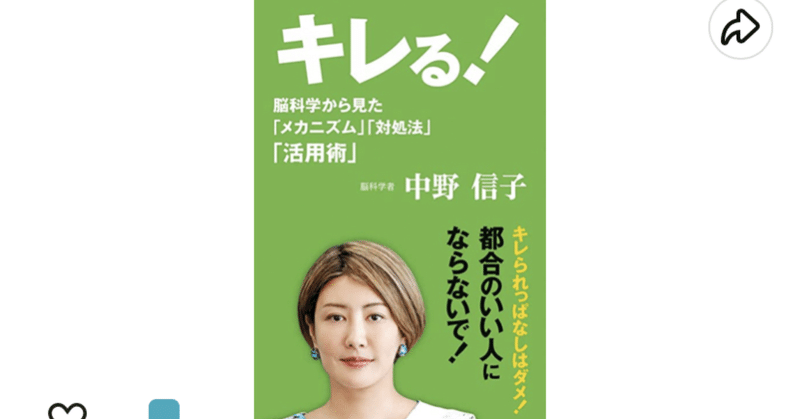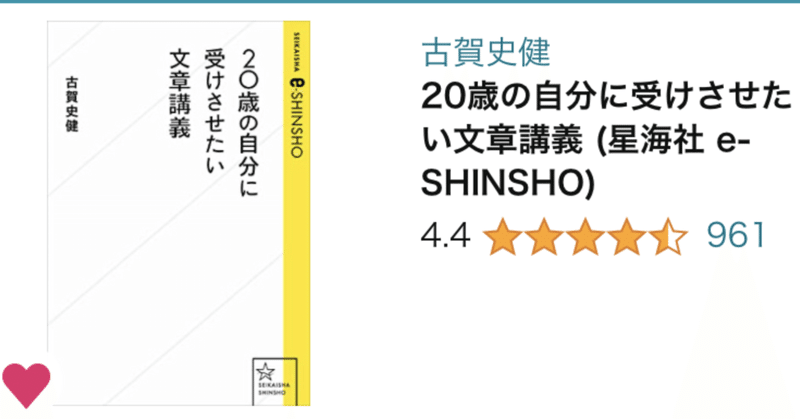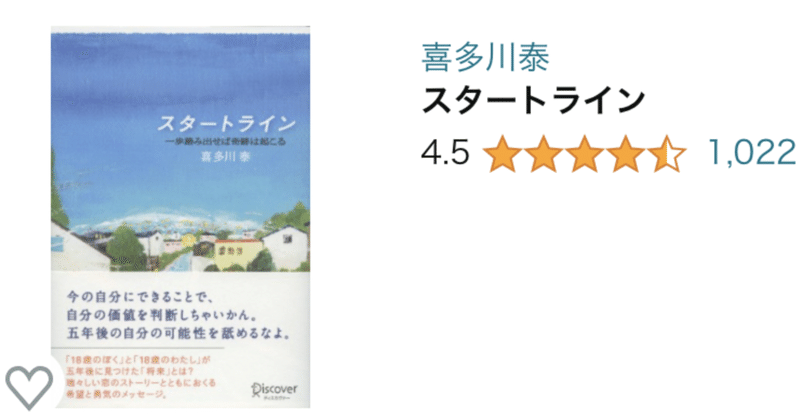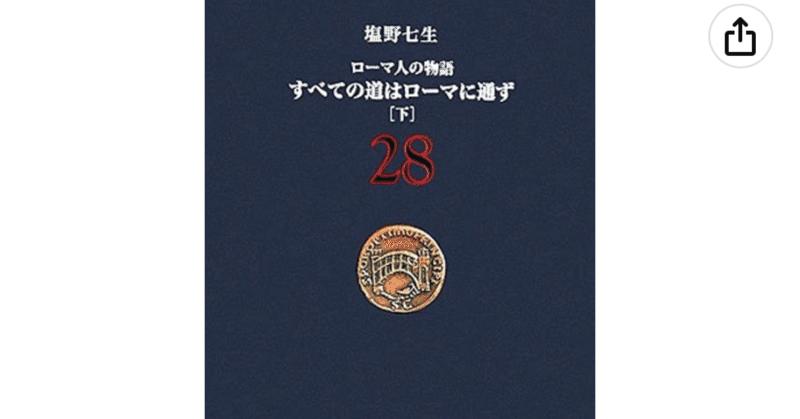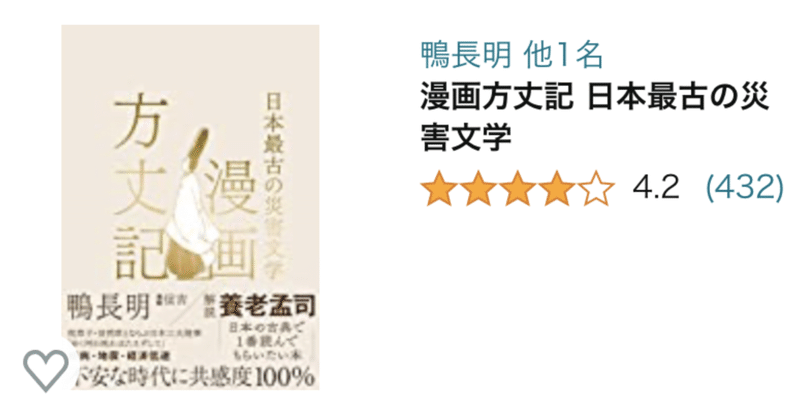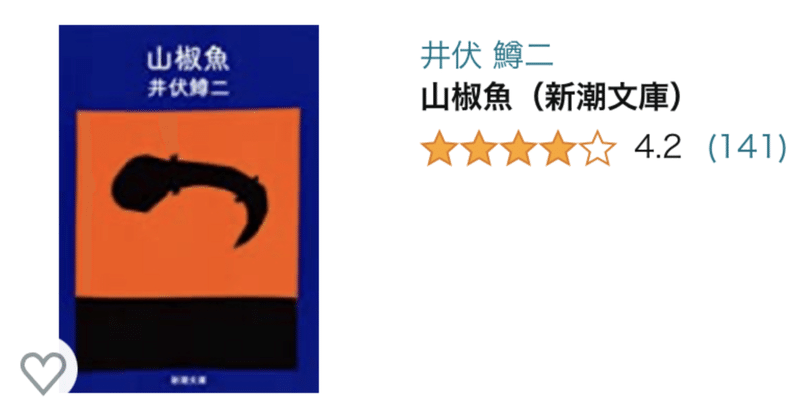#読書
【読書ノート】『新編 人生あはれなり 紫式部日記』
『新編 人生あはれなり 紫式部日記』
小迎裕美子 紫式部
紫式部日記をわかりやすく解説した本。華やかな日常を過ごしていと思いきや日々、将来の不安や人目を気にするストレス、目立ちたくないという願望など、現代の女性にも共感できる人間関係や仕事、嫉妬などが描かれている。
『源氏物語』の登場人物も取り上げていて、人物像を知る上で役にたつ。
平安中期の三大才女(紫式部・清少納言・和泉式部)の微妙な関係
【読書ノート】『福沢諭吉が見た150年前の世界』『西洋旅案内』初の現代語訳
『福沢諭吉が見た150年前の世界』『西洋旅案内』初の現代語訳
福沢諭吉著
武田知弘訳
福沢諭吉が書いた『西洋旅行案内』の現代語訳兼解説本。
明治維新前後の混乱期にアメリカやヨーロッパ訪問使節団に潜り込み、当時の西洋社会の様子が詳細に記されている。
福沢諭吉が、どういう人物だったのか知ることができる大変興味深い内容。
黒船来航、ペリー来日で、蒸気船を見よう見まねで、造られた咸臨丸に乗って太平
『20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海社 e-SHINSHO)』
『20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海社 e-SHINSHO)』原稿
古賀史健著
著者はフリーランスライター
1973年福岡県生まれ。かねて映画監督を夢見るも、大学の卒業制作(自主映画)で集団作業におけるキャプテンシーの致命的欠如を痛感し、挫折。ひとりで創作可能な文章の道を選ぶ。出版社勤務を経て24歳でフリーに。30歳からは書籍のライティングを専門とする。
「話すこと」と「書くこと」は
『ローマ人の物語 28』
「ローマ人の物語 28」
塩野七生著
「ローマによる平和」を人々が享受できた背景には、社会基盤の充実があった。本書では、インフラのなかでも、水道、医療、教育が取り上げられている。
印象に残ったこと
①水道、浴場
ローマの水道は、流し放しだった。そのため、塩素などの消毒をしなくても、水質は良好だったらしい。
公衆浴場は、男女混浴だった。(ハドリアヌス帝が、男女別浴に変えてしまったが。)