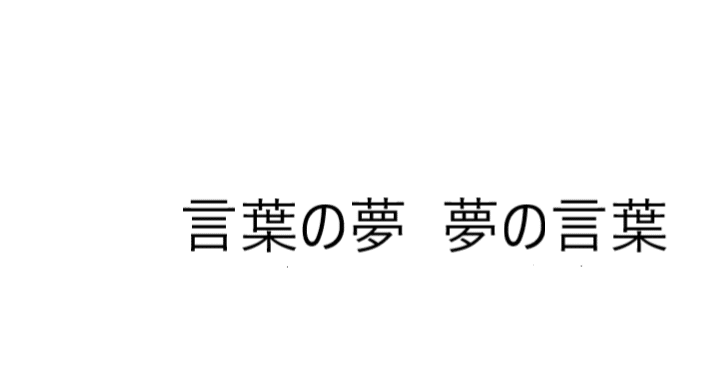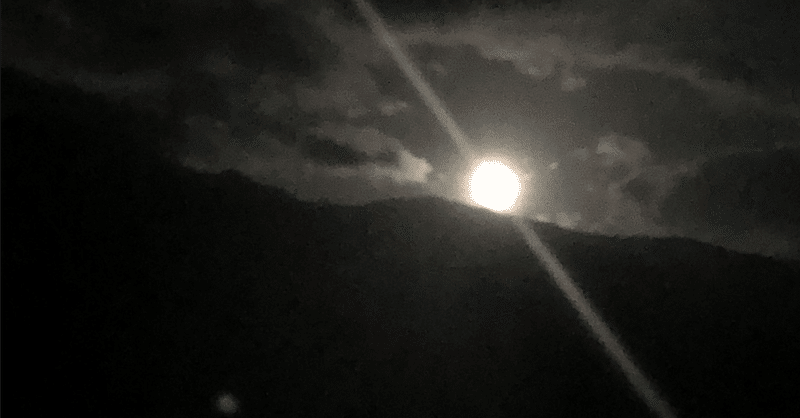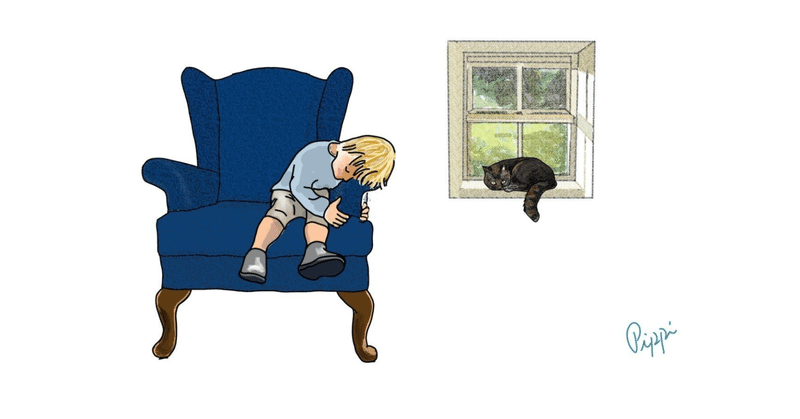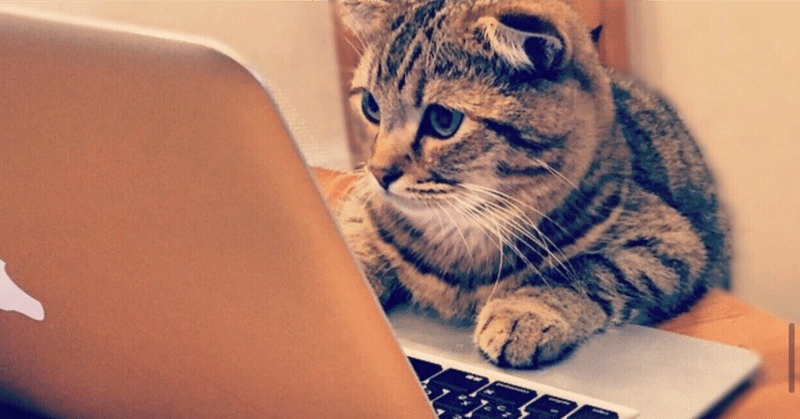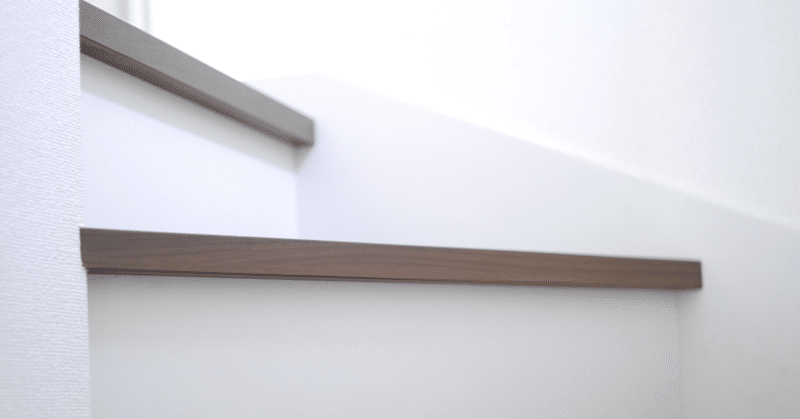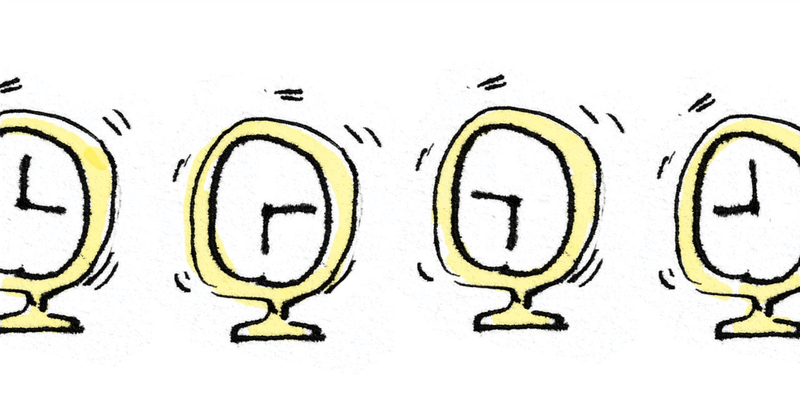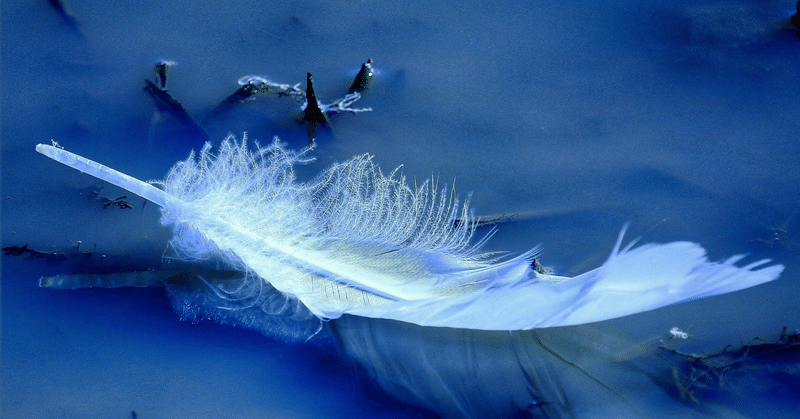#読書感想文
山の記憶、「山」の記憶
今回は、川端康成の『山の音』の読書感想文です。この作品については「ひとりで聞く音」でも書いたことがあります。
◆山と「山」
山は山ではないのに山としてまかり通っている。
山は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通っている。
体感しやすいように書き換えると以下のようになります。
「山」は山ではないのに山としてまかり通っている。
「山」は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通って
人間椅子、「人間椅子」、『人間椅子』
今回は「立体人間と平面人間」の続きです。それぞれが別の方向をむいた言いたいこと(断片)がたくさんあり、まとまりのない文章になっています。申し訳ありません。
お急ぎの方は最後にある「まとめ」だけをお読みください。
人間椅子から「人間椅子」へ
江戸川乱歩の『人間椅子』の文章は朗読に適していると思います。音読してすらすらと頭に入ってくる文体で書かれているのです。特に難しい漢語が使われているわけ
「鏡」という「文字」、鏡という「もの」(「鏡」を読む・01)
「「鏡」を読む」という連載を始めます。江戸川乱歩の『鏡地獄』の読書感想文です。体調というか病状が思わしくないので、この連載は不定期に投稿していくつもりでいます。
◆「鏡」という「文字」、鏡という「もの」
江戸川乱歩の『鏡地獄』の最大の奇想は、鏡ではなく「鏡」という「文字」を真っ向からテーマにしたことだと私は思います。この短編のテーマは、鏡という「もの」ではなく、「鏡」という「文字」だと言いたい
「ここには何もない」という「しるし」
space・空間・空白、sense・方向・意味、order・順序・序列
*「空白・区切り・余白」の捏造
蓮實重彥『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』所収の「Ⅰ肖像画家の黒い欲望――ミシェル・フーコー『言葉と物』を読む」を読んでいて頭に浮ぶのは、英語の「space」と、その語義である「空間」と「空白」です。
簡単に言うと、
・「空間」とは現実の立体に「ある」もの、または「感じられる」もの
で、
わける、はかる、わかる
本記事に収録した「同一視する「自由」、同一視する「不自由」」と「「鏡・時計・文字」という迷路」は、それぞれ加筆をして「鏡、時計、文字」というタイトルで新たな記事にしました。この二つの文章は以下のリンク先でお読みください。ご面倒をおかけします。申し訳ありません。(2024/02/27記)
*
今回の記事は、十部構成です。それぞれの文章は独立したものです。
どの文章も愛着のあるも
長いトンネルを抜けると記号の国であった。(連想で読む・02)
「「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」(連想で読む・01)」の続きです。
連想を綴る この三文は私にいろいろな連想をさせ、さまざまな記憶を呼びさましてくれます。
・「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」
約物である句点も入れると二十一文字のセンテンスをめぐっての連想を、前回は書き綴りました。
今回は、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号