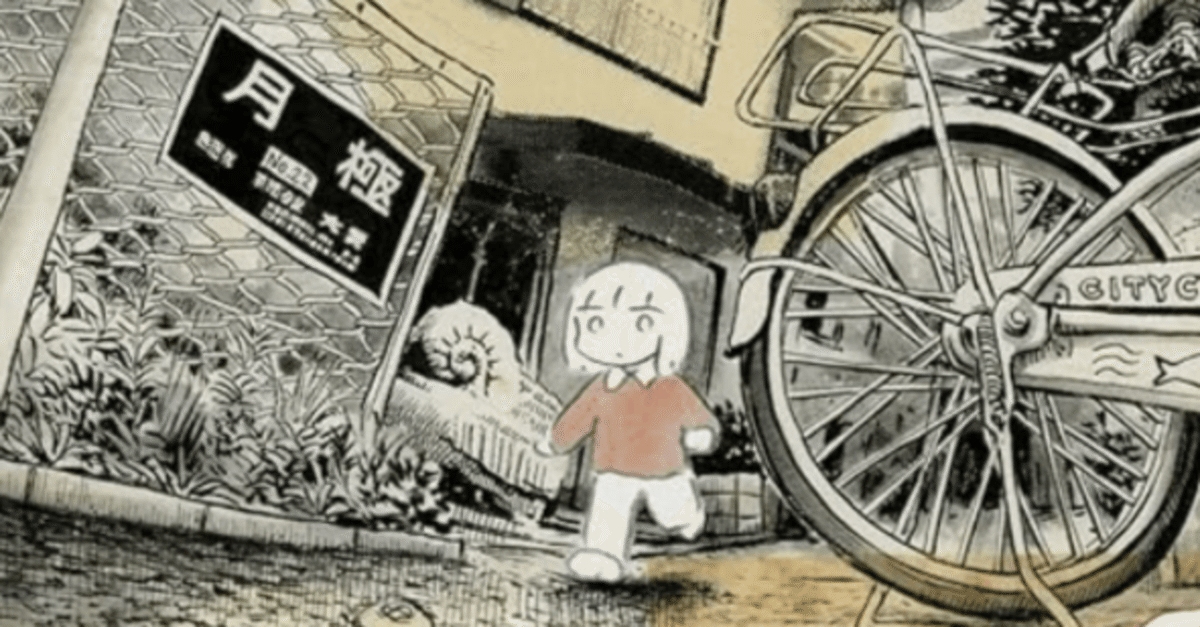
ユリイカされない panpanya : 『ユリイカ 2024年1月号 特集=panpanya』
書評:『ユリイカ 2024年1月号 特集=panpanya』(青土社)
ひさしぶりに大阪梅田まで出て紀伊国屋書店に寄ったところ、雑誌『ユリイカ』の本年1月号「特集=panpanya」が出ていた。
以前なら週に2回は紀伊國屋を覗いて新刊をチェックしていたから、こんなに買い遅れることもなかったのだが、まあ「新刊の買いすぎは、隠居の身には好くない」ので、これは仕方のないことだ。
だが「おくづけ」を見てみると「第2刷」となっているのが、ちょっと悔しい。昔なら、書店を渡り歩いて「第1刷」を探して買ったはずだが、もう「初版第1刷」にこだわるのはやめたのだ。今は「読めればそれでいい」のである。「そー思とこ、そー思とこ」(by「おっ!サン」)。
ちなみに、「初版第1刷」にこだわるようなやつが「雑誌評を、書評と書くのはどうなのよ?」と思った人もいただろうが、私は、基本雑誌は読まず、本号についても特集部分しか読まないので、「雑誌」というよりも「批評アンソロジー」を読んだつもりなので、他のレビューとも表記を合わせるつもりで、あえて「書評」とした。
そんなわけで、「第2刷」を定価で買ったから、評価が辛くなったというわけではない。私を知っている人ならご承知のとおり、私は基本「辛口」なのであり、本号は「第1刷」か「第2刷」かに関わりなく、いささか期待外れだったのだ。

まず、本号には、panpanya本人の「書き下ろしマンガ」は無く、インタビューと往復書簡があるのみ。
したがって、あくまでも「他の人がpanpanyaを論ずる」というのが中心で、panpanyaのマンガを味わうことはできない。
また、panpanya自身も、相手のいるインタビューや往復書簡では、自分を作りきれていないところがあって、そこが面白いとも言えるのかもしれないが、私としては、覗きたくない楽屋が、チラリと覗けてしまったようで、あまり嬉しくなかった。
同じ意味で、現実のpanpanya周辺の人たちが語る「panpanyaと私」みたいなエッセイには基本興味がないし、何よりよろしくなかったのは、各方面の学者さんによる「panpanya論」が、総じて、つまらなかったことである。
本書所収の「panpanya論」が、総じて、どのようにつまらなかったのかというと、大雑把に言えば、多くの学者さんは、panpanyaを、自分のフィールドに引き込んで説明することで、その「理解」を示そうとした点である。
たしかに「そういう見方もある」し「あり」だとは思うのだが、それは「ためにする解釈」であって、「牽強付会」の印象の否めないものが、ほとんどなのだ。
無論「panpanyaを論じてください」と『ユリイカ』編集部からの注文が来れば、好きな作家なのだから、喜んで引き受けてしまう気持ちは、よくわかる。しかし、好きだから「適切に論じられる」という保証などない。
「好きだから好きだ」と言うだけなら素人だってやっていることだから、プロの学者が「評論」を頼まれたら、おのずと「好きだ」ではなく、「私は、panpanyaの魅力をここに見出し、その意味するところはこれこれだと思う」という「理屈」をつけないわけにはいかない。しかし、学者だから評論家だからといって、そう何でもかんでも、いつでも「適切に分析」できるわけではないから、どうしても、無理矢理に理屈をつけて「評論」としての体裁だけを整えてしまうことになりがちなのだ。だが、そうしたものこそが、まさに「つまらない(凡庸な)評論」に他ならない。
で、そんなものが多いのである。なんでそんなものしか書けないのかというと、「panpanya解読」のための、独自性のある切り口もまだ見つかっていないのに、無理をして「分析しました」という「体裁」を整えて、素人を煙に巻こうとするからである。
「将来的には、そんな切り口が見つかって、panpanyaファンが、おおと驚くような評論が書けるかもしれませんが、今はそれを書く準備がありませんので、残念ながら今回は辞退させていただきます」というような謙虚さが無い。与えられたチャンスには食らいついていかないと損だ的な、ケチな考えで原稿を引き受けてしまうから、こじ付けがましい無理矢理な評論になってしまうのである。
しかしまあ「他人の評論にケチばかりつけている」とか「そんなのアンフェアだ」などと言われるのも業腹なので、いちおうは私も、以下に、私なりの「panpanya論」を書くつもりだ。だが、その前に言っておくと、ケチばかりつけるのは、決してアンフェアではない。「つまらないものはつまらないと言う」のは、正しいことだ。だが、それだけでは、つまらないというだけの話なのだ。
で、私は、つまらないのは嫌だから、いちおう、本号掲載の「評論」とは違った切り口から、panpanyaを論じたいと思う。
○ ○ ○
Panpanyaへのインタビューを読んでいて、その回答ぶりに感じるのは「この人は、こういうお祭りに対して、冷めているなあ」ということである。
つまり「うわーっ!、あの『ユリイカ』で特集を組んでもらったぞ!」という雰囲気がまったくない。「まあ、ありがたいことです」的な、冷めた雰囲気がひしひしと伝わってきて、盛り上がっているのは「うわーっ! 好きなpanpanyaの、特集号への原稿依頼が来たぞ!」という、周囲の人たちばかりなのである。

だが、これはまあ、想定の範囲内だろう。
Panpanyaは、もともと「メジャー」とか「スター」とか「みんなからチヤホヤ」とかいったことに、あまり興味を持たない人だ。それは、作品の内容からして明らかではないだろうか。
要は「うち捨てられたもの」「忘れ去られたもの」「誰からも注目されない、日常の中に紛れて存在しているもの」などに、異常なまでに固執するのがpanpanyaという人なのだから、「メジャー」とか「スター」とか「みんなからチヤホヤ」なんてことには、ほとんど興味がないだろうし、そんな人だからこそ、当初はわざわざ、たくさんは作れない「手製同人誌」にこだわったりもした、ということのはずなのだ。

で、そんな人であれば、「メジャー」とか「スター」とか「みんなからチヤホヤ」なんてことに憧れて、大騒ぎしている人たちについては「ふーん、そうなのか。でも、私は興味がないなあ」といった低体温的な反応になるのも、むしろ当然のことであり、この『ユリイカ』の特集だって、特に「うれしい」わけではなく、おのずと「ありがたいことです」というふうになってしまうのだろう。
で、その結果として、本号に寄稿した、当人以外の人たちとの「温度差」が、際立ってしまう。
普通なら「書き下ろしマンガ」の1本くらい入れるだろうと思うのだが、panpanyaの場合、そういうはしゃぎ方はしない。そういうのが似合わないというのは、ファンの人にならわかってもらえると思う。
もちろん、こう書くと、冷静沈着なpanpanyaは「いや、新刊の準備に忙しくて、その暇がなかったんです」とか、無難なことを言うのだろうが、私はそんなもんには騙されない。本当に、人並みに嬉しくてはしゃいでいたなら、無理をしてでも、書き下ろしの1本くらい描いたはずだと思う。「普通」は、そんなもんなのである。
で、肝心の、私の「panpanya論」というのは、panpanyaのこうした「ズレ」を問題にする。
つまり、panpanyaの本質は「ズレ」にある、ということだ。
例えば、panpanyaは、自分の作品についてよく指摘される「背景は描き込むが、主人公は異様にシンプル」といった特性について、多くの論者が、そこに「意味や意図」を読み込もうとするのに対して、「いや、登場人物をイキイキと描きたいという気持ちが無いからです」というような、素っ気ない説明をする。要は「そんな大層な意味はなくて、興味と直観の赴くままに、自然体やっているだけですよ」的な言い方なのだが、しかし、これも真に受けてはいけない。
たしかにこの言葉が「意図的な嘘」ではないとしても、「何かを隠している」という感じは否めない。
それは、panpanyaが「方法論」的に、自身のプロフィールを隠したり、主人公のプロフィール(性別・年齢・氏名・職業などなど)を意図的に「限定しない」ことによって「見えないようにしている」のと同じことである。

で、どうして、panpanyaは、こんなことに執着するのかと考えてみると、要は彼(と私は見ているが、真相は知りたくない)は、「意味の凝固したもの」が好きではないのだ。
彼が好むのは、むしろ「意味の解体」というよりは「軟化的変容」なのだと、私はそう感じる。
Panpanyaの場合、人が注目しない「珍しいもの」を探すのではなく、人が注目しない「ありきたりなもの」の中に、その「ありきたりなもの」だという「認識」を揺るがすような「視点」を持ち込み、その「ありきたりに思えたもの」を、「異様なもの」「見たことがないもの」に変容させることを楽しんでいると、そう言えるのではないだろうか。
例えば、panpanyaのマンガについて、真っ先に指摘されるのは、特に初期作品では「日常世界から、地続きの異界へ(そして、日常への回帰)」といったことなのだが、「幻想系作品」では、ある意味で「ひとつのパターン」にもなっている、こうした「異界彷徨譚」においても、panpanya的な個性とは、現実世界と異界の「どっちか」ではなく、「どっちでもあり、どっちでもない」という「不安定性=ズレの継続性」といったことにあるのではないだろうか。
「日常が嫌だから、異界へ行く」でもなければ「異界も良いけど、やっぱり現実世界が大切」というわけでもない。「どっちも好きだし、どっちもないと困る」ということであり、それは「どっちかに固定されるのが嫌」ということなのではないか。
つまり、panpanyaの「動き」というのは、常に「ズレ」の生産なのだ。
日常から始まれば、異界にズレていくし、異界に入れば、異界らしい異界さからズレて、妙に日常的な感覚がそのまま生かされたり、最終的には、そこからもズレて日常にも戻ってくるのだが、その戻ってきた日常というのは、すでに「元の日常」とは似て非なるものであって、決して「確固たる日常」ではない日常といった、「ズレ」を含んだものに変容しているのである。
だから、その「新たな日常」からは、いつでも「異界」に行けるし、むしろ、わざわざ「異界」に行かなくても、その日常は、すでに「異界」を含んでいるので、panpanyaは「日常の中に、異界を見出すようになる」のである。つまり、あの「カステラ風蒸しケーキ」だとか「グヤバノジュース」とかいったものは、「日常」の側のものではなく、「日常の中の異界」であり「異界への入り口」なのだ。それにこだわる(追求していく)ことで、panpanyaは、日常の中で異界を楽しむことができるようになった、というわけである。

だから、そんなpanpanyaにしてみれば、『ユリイカ』だ『現代思想』だ、メジャーだ、マンガ賞受賞だといったことには、ほとんど触手が動かない。
まあ、現実問題としては「ありがたいこと」ではあるのだが、そういうものというのは「日常世界における、非日常的に陳腐な幻想」に過ぎないとしか思えないので、本気で喜ぶことができない。喜べないというよりも、「楽しめない」代物なのである。
他人が「これは凄いものだ」と決めた、そんなものを、同じように「凄い!」と思えるような人間だったら、panpanyaは「カステラ風蒸しケーキ」だとか「グヤバノジュース」なんかには見向きもせず、「有名店のお菓子」や「ブランド商品」を、人並みに楽しんだことだろうし、それを他の先生方に「お中元」「お歳暮」として送ったりもできただろう。
だが、panpanyaは、そういうことを、世間の了解に沿って信じることができないし、楽しむことができない。
もしもpanpanyaが「お中元」「お歳暮」といったものに興味を持ったとしたら、それはそれが「奇習」にでも見えた時であり、そうなれば、「どんな、お中元やお歳暮が、面白いだろうか」などと考えて、きっと、ろくでもないものを生み出すのであろう。
ここで、主人公(語り手・視点人物・ボブカットの女の子?)が「お中元・お歳暮」という慣習に興味を持って、レオナルド(?)と話している場面を想像してほしい。
「お中元お歳暮とは何だろう?」
「いや、それは日頃のご愛顧に対する御礼としてのプレゼントとかいったものでしょう」
「それなら、いつしても、何をプレゼントしても良いということになるよな」
「まあ、そうですね」
「モノですらある必要もない」
「まあ、そうですが……」
と、こんな感じになるのではないだろうか。
では、この「お中元・お歳暮」を、「panpanya特集号」だとか「panpanya論」に置き換えて考えてみたとき、本号のような「型どおりの特集号」や「型どおりの作家論」など、出てくる余地がないし、それでは「わかってないなあ」ということになるのではないだろうか。
ともあれ、panpanyaがそういう人なのに、それをわかったつもりで論じてる人たちは、総じて、panpanyaから学びもせず、世間並みに「器が小さい」。だから、面白くないのではないだろうか。
私が、この特集号で、わりあい面白かったのは、『最後から二番目の真実』ならぬ、最後から2番目に収録されている作家論、川崎公平の「真面目な異界めぐり panpanyaのマンガ作品における行動原理についての覚書」であった。
この論文で指摘されているのは、panpanyaのマンガの面白さは、作者であれ主人公であれが、「過剰に真面目」に突き進んでいくところから生まれている、という点である。一一私は、この指摘は、かなり本質を突いたものだと思う。

Panpanyaの作品の面白さは、「適当」とか「良い加減」ではなく、「徹底的に真面目」に追求され、突き進んでいってしまうところにある。
決して、「適当なところで手をうつ」とか「引き返す」ということをしないから、結局のところ、「異界」をこえて、その先の「奇妙な日常」にまで突き抜けて行ってしまうのだ。
「異界彷徨譚」を好む小説家である奥泉光が、以前、『黒死館殺人事件』で知られる、戦前のミステリ作家・小栗虫太郎を論じて(だったと思うが)「徹底的なものが面白い」と言っていたと記憶する。私はこの言葉に、いたく共感したのだ。
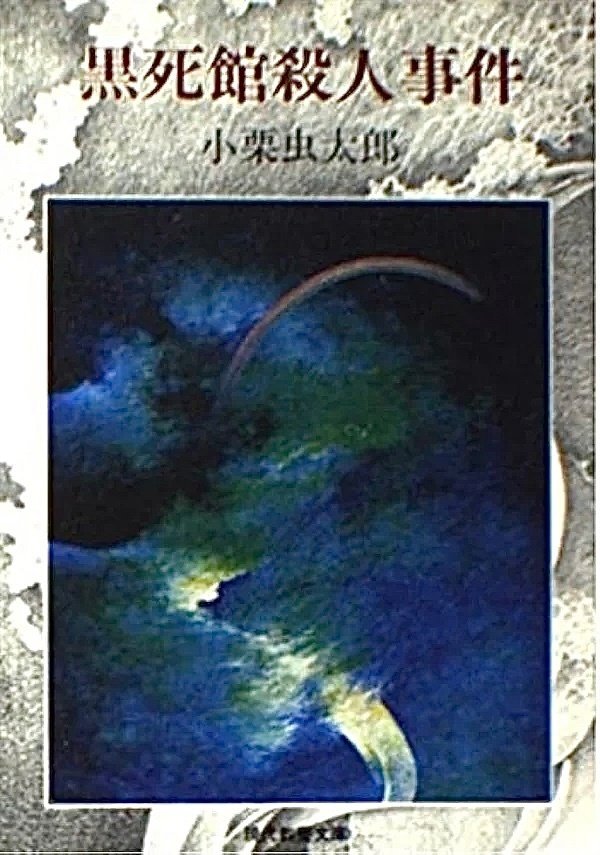
しかし、こうした徹底性とは、ある意味では「異常性」であり「狂気」だとも言えよう。
『黒死館殺人事件』の主人公である名探偵・法水麟太郎が滔々と語るペダントリー(衒学=実用性を欠いた学識)こそが、「黒死館」という「異界」を現出させる呪文だというのは、よく言われるところなのだが、言うなれば、この法水麟太郎的な「狂気」を、panpanyaもまた持っているのではないだろうか。
で、この川崎公平のpanpanya論が「面白い」のは、他の論者たちが当たり前のように「このように、私はpanpanyaを理解しています」というスタンスで書いているのとは違い、ただ一人「その徹底した真面目さが異様であり気持ち悪い」と、おおむねそんなふうに評している点だ。
他の論者が、自身を、人気者のスターであるpanpanyaの理解者であり「そちらの側の人間である」とアピールしようと躍起になっているのに、この川崎公平だけは、素直に「気持ち悪い」と論じてしまっている。
これが意味するのは、川崎のここでの議論は「誉めるための(為にする)論評」ではなく、自身の実感を、正直な語ったものだということなのではないだろうか。だからこそ、説得力があった。
実際、panpanyaみたいな感性の持ち主が大勢いたら、panpanyaという作家がスターになることもなかっただろう。
Panpanyaという作家は「当たり前なものの中に、当たり前ではないもの」を見出す「天才=狂人=幻視者」だったのだが、panpanyaのファンというのは、たいがいは、その真逆に、panpanyaという作家の「珍奇さ」に注目して面白がっているのではないだろうか。
その種の誤解があってこそ、こんな変な作家が、『ユリイカ』で特集される程度には、広く支持されたのではないかと思うのだ。「私はわかっている」という、そんなありふれた「誤解」において。

(2024年3月5日)
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
