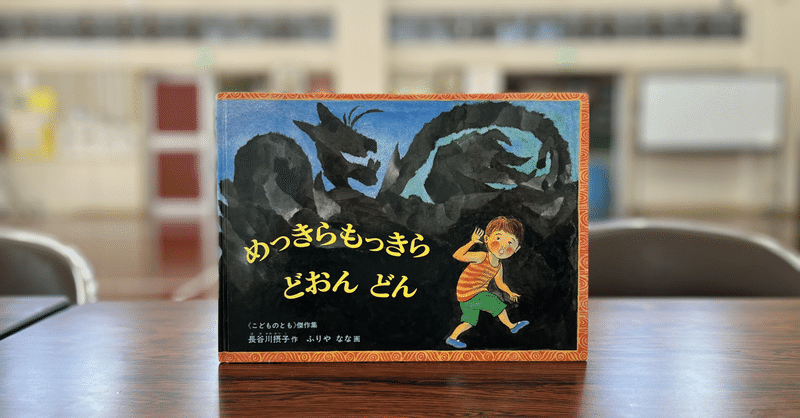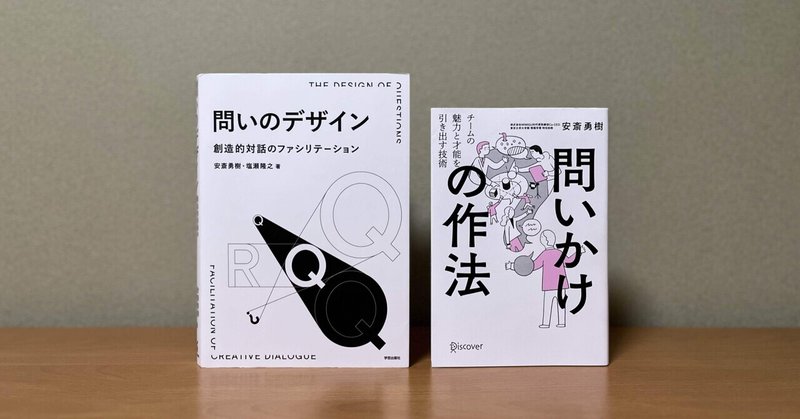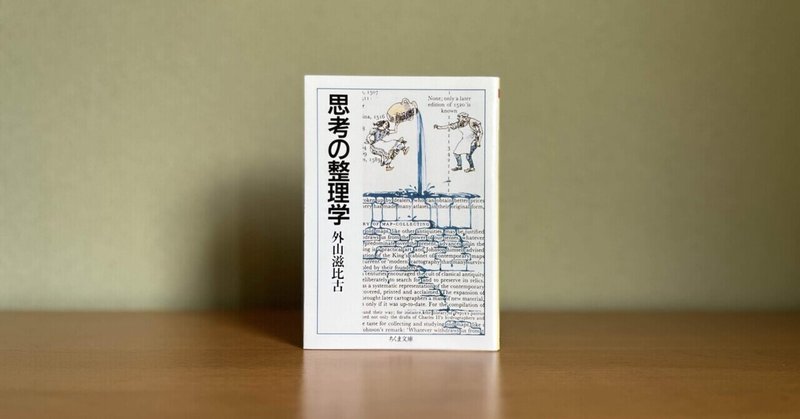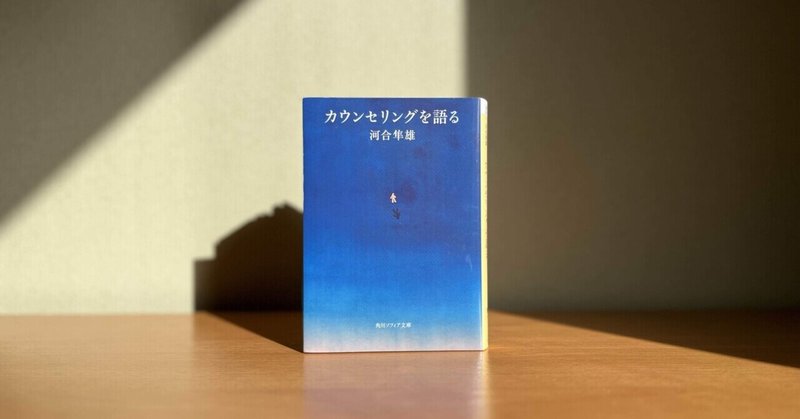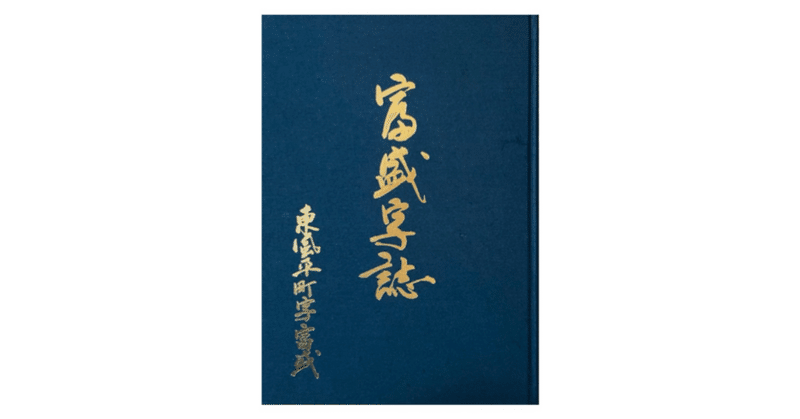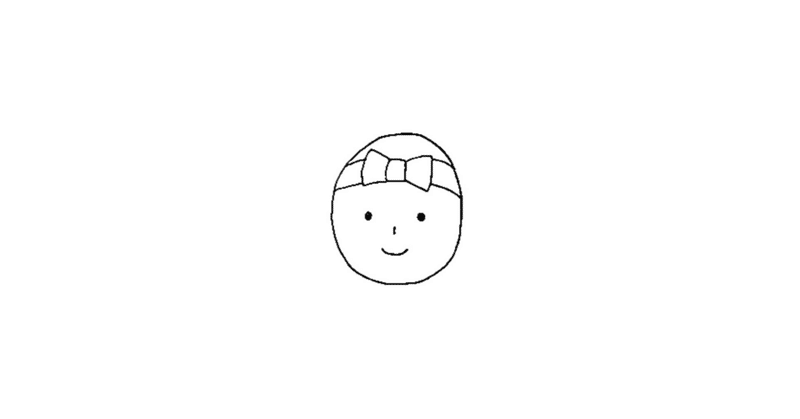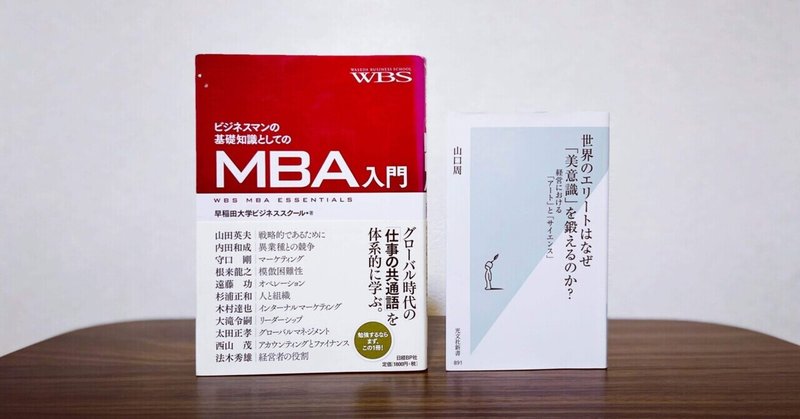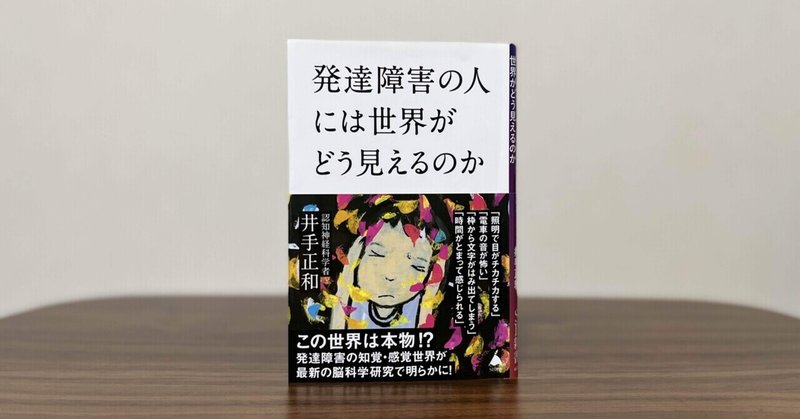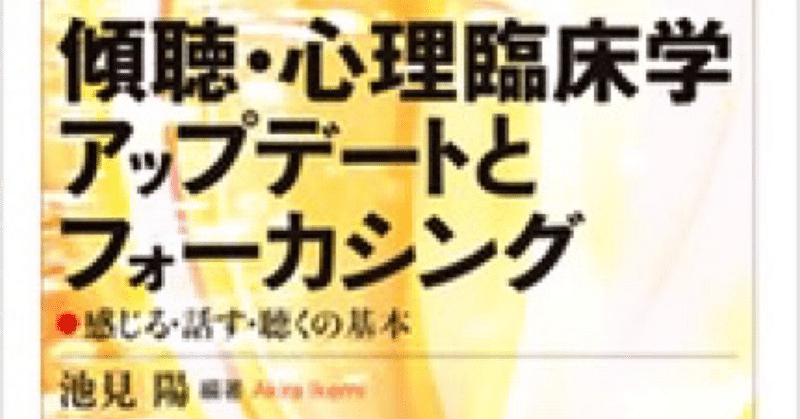#最近の学び
「悲しむことは生きること 原発事故とPTSD」を読みました
沖縄に移住する前から、蟻塚先生にこっそり憧れていた。沖縄に移住後、健康診断を受けた病院が、蟻塚先生が定期的に診察に来ている病院だと知った時は、ひとり興奮した。遅ればせながら、先生の著書を初めて読む。
1.心的外傷(トラウマ)とPTSD心的外傷(トラウマ)は、以下のようなストレス反応を引き起こす。
(1)再体験
(2)回避
(3)過覚醒
(4)否定的な認知や気分
辛い記憶を思い出すフラッシュバッ
久高島イザイホーと祭祀
沖縄県久高島へ行った時、安座真港の売店で購入した「日本人の魂の原郷 沖縄久高島」。この本を探していたから、売店で見つけた時は、思わずお店の人に喜びを伝えてしまったほどだ。
1.久高島の祭祀15世紀以降、琉球王朝がノロ制度を導入する前から、久高島の祭祀は存在していた。有名なイザイホーだけでなく、久高島では旧暦に従い豊富な祭祀が行われる。祭祀の名称も、ノロなどの役職も、耳慣れない言葉ばかりで混乱して
「発達障害の人には世界がどう見えるのか」を読みました
「なぜ?」
何に困っているか。
それが分かれば、できることが見えてくる。
「なぜ?」が分からないと、人は不安になる。
「発達障害者の方々の知覚の『なぜ』を明らかにすることで世の中に貢献したい」と思った著者。
発達障害について、ひと言で説明することは難しい。それは、ひとりひとり特性や困りごと、体験している世界が異なるから。
そして、発達障害は、脳機能の特性によるもの。
本人の性格や人間性に