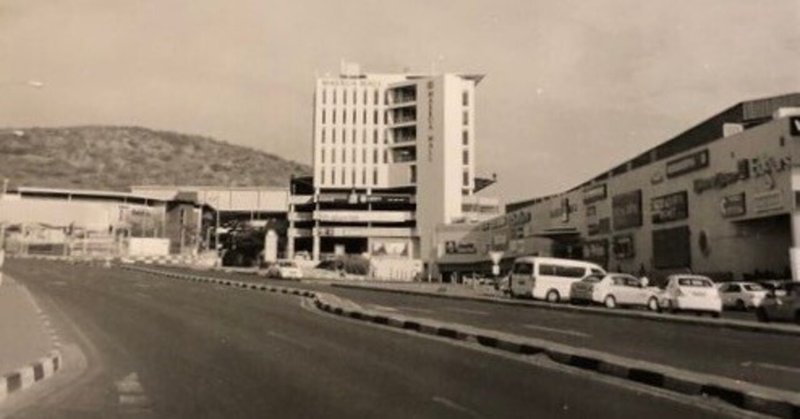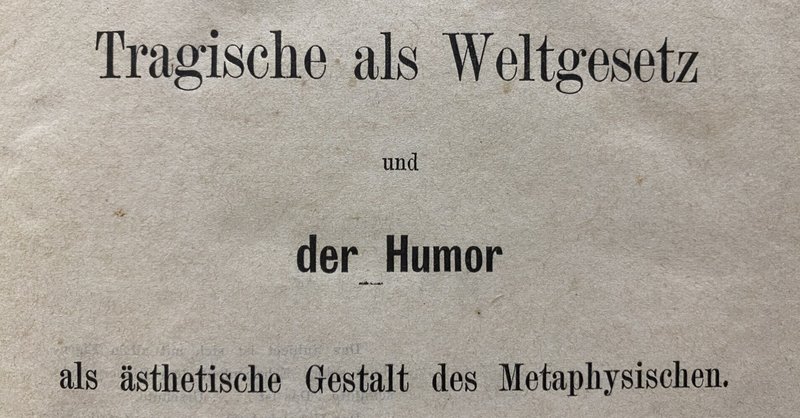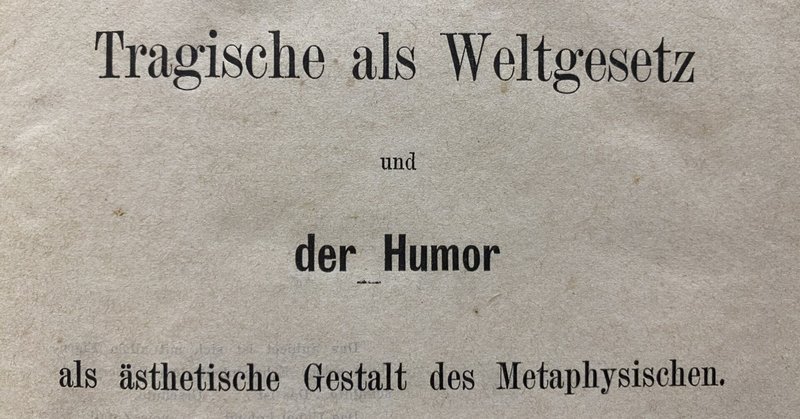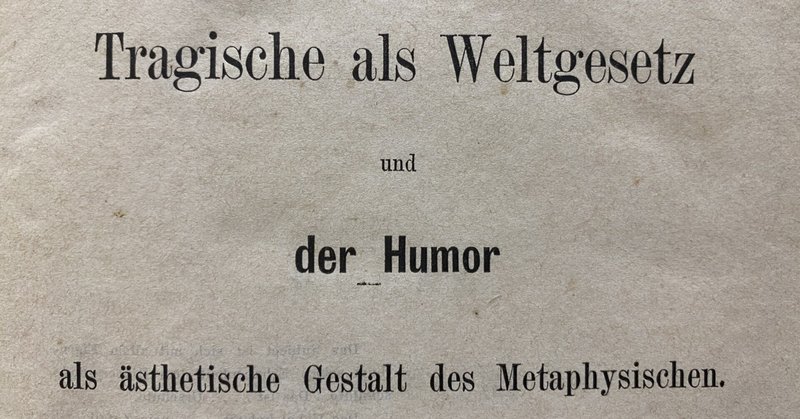記事一覧
(翻訳)バーンゼン『世界法則としての悲劇的なもの』(5):第一章「悲劇的なもの」 第三節(続き)
第一章 悲劇的なもの第三節 日常生活の悲劇(Tragedy of common life)に関する下位の心理学のために(続き)
衝突する義務の混乱は、計算しがたい関係の組み合わせを径の上に容易に押し出す。その径は、希望に関して欺き・欺かれて待ち暮らすことが、過去における最も重苦しい時間が指示した目的の、より快適な道による実現を信じさせた間は、通行できないと思われた径である。しかし、少なくとも半
(翻訳)バーンゼン『世界法則としての悲劇的なもの』(4):第一章「悲劇的なもの」第三節
第一章 悲劇的なもの第三節 日常生活の悲劇(Tragedy of common life)に関する下位の心理学のために
法の違反が新たな違反によってしか償われない無数の場合や、真の誠実さが、見せかけの欺瞞によって最も満たされる場合(すなわち、他人を最も邪に欺こうとしていると疑われる時には最も実直であり、逆に、他人に対して子供染みた無邪気さに至るまで実直であるように見える時は、大抵は沈黙している
(翻訳)バーンゼン『世界法則としての悲劇的なもの』(3):第一章「悲劇的なもの」第二節
第一章 悲劇的なもの第二節 倫理的なものの根本的本質における悲劇的なものの条件
我々は、ヘーゲルの思想の弁証法(Gedankendialektik)が悲劇的な個別的主体において意志の弁証法(Willensdialektik)へと移行するのを見たが、同じことが普遍的な倫理的意志規定の分野においても起きている。その二つの領域、道徳(Moral)と法(Recht)は実在弁証法的矛盾に同様に貫かれてい
(翻訳)バーンゼン『世界法則としての悲劇的なもの』(2):第一章「悲劇的なもの」 第一節
第一章 悲劇的なもの第一節 悲劇的なものの特徴的な前提
悲劇的なものの様々な現れ方を分類しようとする時、最も手近な分類根拠として、主たる関係者(訳者注:悲劇の主人公)の性格及び、彼の運命との接触の形式が挙げられる。我々は単なる運命の単純な悲劇的なものを認めないため、偶然との衝突の形式はまずもって二次的なものとして、衝突する個性の内容を優先しなければならない。悲劇的英雄については故なく語られるわ
(翻訳)バーンゼン『世界法則としての悲劇的なものと形而上学的なものの形態としてのユーモア』(1):序言~緒論
訳者前書き 下掲及び続稿は、ドイツの哲学者ユリウス・バーンゼン(1830-1881)の掲題書(原題:Das Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische Gestalt des Metaphysischen)の邦語訳。バーンゼンは、ショーペンハウアーの影響の下、その悲観主義を継承しつつも独自の立場を打ち立てた思想家、また「性格学」(