
北村紗衣的 「被害者アピール」の淵源 : ヘレン・プラックローズ、 ジェームズ・リンゼイ 『「社会正義」はいつも正しい』
書評:ヘレン・プラックローズ、ジェームズ・リンゼイ『「社会正義」はいつも正しい 人種、ジェンダー、アイデンティティにまつわる捏造のすべて』(早川書房・2022年)
北村紗衣との腹立たしい出会いに始まる、現代フェミニズムやキャンセルカルチャーに関わる私の旅は、まだまだ続く。
最初は「何なんだ、これは?」と感じられた、想像を絶する新状況が、読書をするたびに徐々に視野のひらけてくるという体験は、本当に気持ちの良い、知的冒険の旅とでも呼ぶべきものだ。知ること、理解することの快楽は、勉強であると同時に、難問攻略の娯楽でもあり得るのだ。
そんなわけで、今回の1冊、いつにも増して面白く読めた。
何が面白かったのかと言えば、まず第一には、私の「ポストモダン思想(フランス現代思想)」理解が、大筋で正しかったということが、わかったことである。

しかし、こう書いたからと言って、本書の趣旨である「ポストモダン思想」批判に、私が以前から加担していたということではない。本書著者たちの加勢を得てから、「昔から、ポストモダン思想なんてインチキだと思っていたよ」などと、いきなり自慢するなどという、ありがちなことをしたいのではない。
もちろん、難解なフランス現代思想のことを、ろくにわかってもいないのに、難しげジャーゴンを振り回して、わかったふりをしているだけの「二流以下のその他大勢」については、ときどき批判しはしたけれども、「ポストモダン思想」そのもの、あるいは、ポストモダン思想の中心人物たちを批判したことは、一度もない。
では、なぜ批判しなかったのかと言えば、端的に「わからなかった」からだ。「わからない」ものは、本来、批判できる道理はないのである。
それなのに、「わからなかった」からといって、自分の頭の悪さを棚に上げて、その著者や著作をくさし貶めるというのは、心根の卑しい所業だ。
批判するからには、当然、ある程度「わかっている」必要があるのだが、私の「ポストモダン思想」理解は、そのレベルには達しておらず、入門書的なものやポストモダン思想を援用した批評書を読むのが精一杯だったので、持続して興味は持っていたものの、まだまだ私には、「ポストモダン思想」の価値を云々できる段階にはないと、そう思っていたのである。
その証拠のひとつが、『エクリチュールの零度』ついての、私のレビューである。
同書の著者は、ポストモダン思想の代表的な論客ロラン・バルトで、彼の代表的な著作のひとつが、同書なのだ。
で、このレビューで私が何を書いているのかというと、要は「まったく歯が立たなかった。いずれ再挑戦したい」と、ただそれだけだったのである。
さて、本書『「社会正義」はいつも正しい』には、何が書かれているのだろうか。
それは、近年、学会や言論界などで幅を聞かせている〈社会正義〉を名乗る「理論」、これに対する批判である。
本書のタイトル『「社会正義」はいつも正しい』では、この〈社会正義〉が「社会正義」と「」付きで書かれているが、本文中では、左に示したとおり、〈〉付きで〈社会正義〉と表記されている。
これは、いわゆる一般的な意味での「社会正義」のことではなく、「社会正義」を名乗る、特定の「理論」のことを指している。だから、それを信奉する本人たちには、その「理論」を使って社会を分析し、かつ運動することが「社会正義」の実現につながるという意味なのだが、それは、立場を異にする人にとっては、「社会正義」でも何でもなく、単なる「自称・社会正義」にすぎないということになる。
ただここでは、一般的な「社会正義」と、彼らの自称しているところのそれとを区別するために、彼らのそれについては、〈〉付きで〈社会正義〉と表記して区別しており、本稿でも、本書のそうした表記に準拠して、それを〈社会正義〉と表記したい。
なお、さらに面倒くさいのは、そうした〈社会正義〉の理論を、彼らは単純に〈理論〉とも言うので、これも一般的な「理論」のことではなく、あくまでも「彼らの理論」を意味するものとして、〈理論〉と表記している。
つまり、彼らの言葉遣いで言えば「社会を正しく導くためには、〈理論〉に従って、社会現象を理解し、それに沿って世の中を変えていかなければならない。それが、社会正義だ」というような言い方になる。一一当然、この「」内のセリフにおける「社会正義」とは、ほとんど〈社会正義〉において考えられた「社会正義」であり、要は〈社会正義〉を意味していて、一般的な意味でのそれを指すものではないのだ。
で、こうした〈社会正義〉の〈理論〉が、どのようにして生まれてきて、どのように展開し、現在どのような問題を社会にもたらしているのかを紹介して、それを批判しているのが、本書である。
そして、この〈社会正義〉の出自を「ポストモダン思想」に求めるのが、本書の基本線であり、「ポストモダン思想」の問題点が、最悪のかたちで展開されてしまったものが、現在の各種の〈社会正義〉であり、その〈理論〉だと主張されることになる。
では、その歴史的展開とは、いかなるものかというと、大雑把に言って、次のような3段階に分けられるものだ。
(1)ポストモダニズム(ポストモダン思想・フランス現代思想)
(2)応用ポストモダニズム(ポストコロニアリズム理論、クィア理論、批判的人種理論など)
(3)応用ポストモダニズムの展開(第3〜4波フェミニズム、ジェンダー・スタディーズ、障害学、ファット(肥満体)・スタディーズなど)
それぞれを簡単に説明しておこう。
(1)の「ポストモダニズム」というのは、フランスで1960年から70年代にかけて勃興し、日本では10数年遅れて「ニュー・アカデミズム(ニューアカ)」として流行した、先のロラン・バルトや、ミッシェル・フーコー、ジャック・デリダといった人たちによる、いわゆるフランス現代思想のことである。「構造主義」とか「ポスト構造主義」などと区分されることもあるが、おおむねそれをひっくるめての「ポストモダン思想」だ。
(2)の「応用ポストモダニズム」とは、要は(1)を援用して、社会の中で実際に役に立てようとした、各種の思想だと言えるだろう。つまり、「社会変革運動」と結びついた(1)である。
しかし、ここで重要なのは、本来の(1)は、そんなに簡単に「運動」と結びつくようなものではなかった、という点である。
というのも、本書著者たちも言うとおり、本来の(1)は、デリダの思想を象徴する言葉である「脱構築」からもわかるとおり、その本来の目的とは「堅牢な権威・権力装置」を突き崩すというところにあって、積極的な「構築=社会運動」を意図したものではなかったからだ。
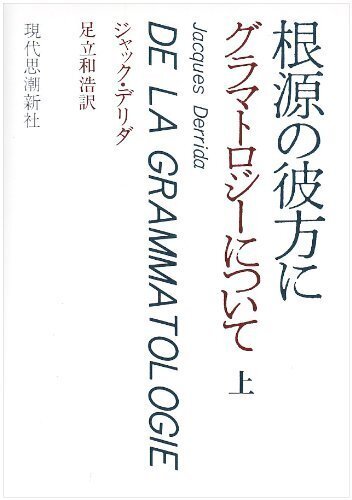
では、なぜ「壊した後で、新たに良いものを作る」という当たり前の考え方を採らず、ひとまず「壊す=脱構築する」ということを目指したのかというと、それは、本書著者たちも満足に理解できていないところなのだが、人間というものは、放っておいてもまた「社会制度」を「構築」する動物であり、「構築」されたものは、必ず「完璧なもの=理想どおりのもの」ではあり得ない、ためだ。つまり、「ポストモダン思想」の目指すものは「壊し続けること」だったのである。
だから、それを「社会運動」という「構築行為」と組み合わせて「実用化する」という発想は、ポストモダニズムにおける「脱構築」的なラディカリズムを、その本質において裏切る、現実への妥協、あるいは「中途転向」でしかないのである。
したがって、(2)は、たしかに(1)の血を半分はひいてはいるのだけれども、(1)からすれば「最悪に出来損ないの子孫」でしかないのだし、無論、そんな「ポストモダニズムの肝心な部分(心)」を捨ててしまって「策に走ってしまった堕落形態」でしかないものを、「正当なる嫡子」だなどと呼ばれたくはないはずなのだ。
(3)の応用ポストモダニズムの展開とは、要は、(2)の「実用主義的」な理論を、各種運動の中に取り込んでいったものであり、例えば、もとからあった「フェミニズム」に、(2)の考えを取り込んでいったのが「第3〜4波フェミニズム」で、それとは別に「女性」問題に限定しない「ジェンダー・スタディーズ」が建てられた。
そのほかにも、「障害学、ファット・スタディーズなど」の、それまでは単純に「劣性」だと考えられていたものを、逆に特異な固有性として積極的に肯定するような、各種のアイデンティティ運動が現れたのである。言うなれば、「黒人こそが美しい」という主張と同様なものとして「肥満体こそが美しい」的なアピールが(2)を援用することで可能となったのである。
したがって、(2)で実用化された思想を、あれにもこれにもと利用したのが(3)だと考えればよい。
これら(3)の展開を、彼ら自身は「弱者・少数者のための社会正義実現思想運動」だとして〈社会正義〉と呼び、その中心的な考え方を、唯一正しいものとして、シンプルに〈理論〉と読んだのである。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcanth/80/4/80_513/_pdf
そんなわけで本書は、こうした〈社会正義〉の蔓延に至る「歴史的経緯」、その中心的な思想運動のいくつか紹介・説明した本だと言えるだろう。
その上で、こうした〈社会正義〉というのは、「弱者・少数者=被抑圧者=苦しみを知る者」のアイデンティティにこそ正義があり真理があるとして、多数派を抑圧者であると前提的に決めつけるような、いささか被害者意識の強い「宗教カルト」めいた「独善的かつ傲慢」な性格を持つものであり、人間社会を、各種の「属性」においてばらばらに「分断」してしまいかねない「危険なもの」であると、そう著者は批判するのである。
そしてその上で、私たちが保持すべきは、「リベラリズム」の「他者への寛容」であり「話し合いによる漸進主義的社会改良」しかないと、そのように主張するのだ。
○ ○ ○
さて、そんなわけで、本書に対する、私の基本的な考え方はというと、その結論としての「リベラリズム」であり「話し合いによる斬新主義」という点では、完全に一致しているから、その意味では、本書の立場を支持するものだと言えよう。
ただし、私が問題視し、本書の大きな弱点だと考えるのが、上の(2)に部分でも少し説明したところだが、本書著者は、(2)の「応用ポストモダニズム」を、(1)の「ポストモダニズム」の「嫡子」であると考え、(1〜3)を全部ひっくるめて「ポストモダン思想」と呼んで、これを否定批判している点である。
上にも説明したとおり、(2)は(1)の「血を引いている」というのは確かな事実なのだが、しかし、(1)の思想の、最も肝心なものを捨てており、言うなれば(1)を裏切ったも同然の(2)と(3)を、(1)の系譜に属するというだけで、ひと括りにして批判するのは、あまりにも恣意的であり間違っていると、私は考えるのだ。
例えば、これは、「物理学研究」のひとつとして、物の構造を探究していった結果の「核物理学」が、結果として「原子爆弾」を産んでしまったからといって、「核物理学」自体も、原爆開発者と「同罪だ」というのは違うだろう、というようなことだ。
「物理学的な研究」というものは、原則的には「真理の探究」であって、初めから「(社会的な)応用」を意図したものではない。結果として、それが「社会の役に立つことを望む」のは当然だとしても、普通は「この宇宙の成り立ちとしての真理を知りたい」という「知的好奇心」から、それらの「探究」はなされるのである。
それが昨今では、安易に「実用化できる研究」が重視されるために、日本の「基礎研究」はダメになってきているというのは、よく言われるところなのだが、「研究」というものは本来、そうした「社会的実用性」など抜きにした「知的探究」行為であり、それを保証するのが「大学における研究」という制度だったのだ。
で、これと同じことで、(1)の「ポストモダン思想」というのも、「真理の探究」として生まれてきたものであり、その基本的な構えとは「絶対確実なものは存在しない(簡単には信じない)」という、徹底した懐疑主義である。
「絶対的に確かそうに見え、現実であり真理であると僭称するもの」に対して、徹底的に疑義を突きつけ、相対化してみせたところに、その価値があったのだ。
そうした相対化の対象となったのが、具体的には、戦後の学術界で絶対的な権威を誇った「マルクス主義」であるとか、「大学における徒弟制度的な位階権威」、あるいは、それに依存した「正統学説」といったものだった。
それらは「正統教理」を僭称して、それ以外のものを抑圧排除しがちだったからこそ、「ポストモダン思想」は「絶対なものなど、何ひとつない」と言って、そうしたものの「脱構築」を目指したし、当然のこととして、自分たちの「脱構築」的な思想もまた「絶対的なものではあり得ない」との自覚に立って、すべては「差異」におけるズラし的な運動の中にあって、絶対的な「平衡状態」は無い、としたのだ。
これは、(1)と(2)の間あたりに位置して、(1)を擁護したジュディス・バトラーの言葉で言えば「行為遂行的」ということになるだろうし、日本における「ニューアカ」を代表する浅田彰の言葉で言えば「逃走(逃げろや逃げろ)」ということになろう。
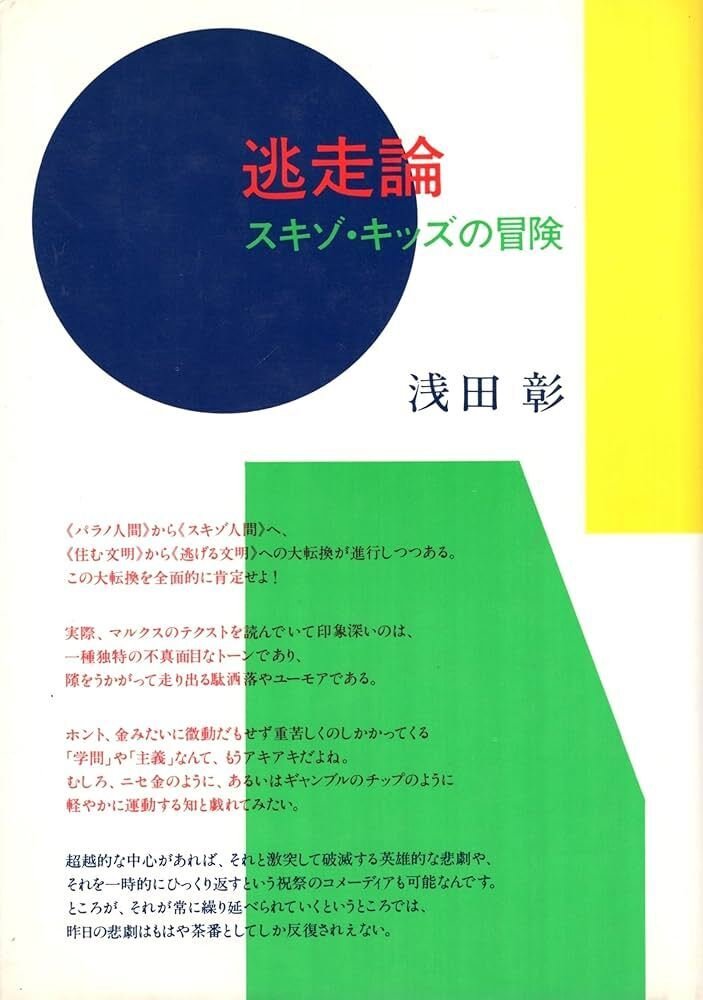
つまり、ひとつの立場に安住してしまったら、それはやがて「硬直したひとつの制度」になるしかないから、そうした頽落に陥らないためにも、つねに走り続け、変わり続けなければならないというのが、「ポストモダン思想」のキモなのである。
そして、このことを(1)の要約的な説明で、わかりやすく教えてくれたという点において、本書は、私にとって、とても「ありがたく、面白い」ものだったのだ。一一「なんだ、俺って、意外にポストモダン思想のことを理解していたんだな。もちろん、個々の細かい部分は別にして」ということだったのである。
そしてさらに、私が(2)や(3)に敵意を抱いて批判する理由も、(1〜3)の説明でハッキリした。
要は、私は(1)のポストモダン思想を支持する「解体屋」として、(2)と(3)の「安直な居直り」は許し難い、と感じていたということなのだ。
(1)の成果を、すっかり歪めて「悪用」したのが(2)と(3)だから、私はそれらを許せないと考えたのである。
したがって、そんな立場の私からすれば、本書著者の立場というのは、結局のところ、(1)が理解できなかったことの「恨みつらみ(ルサンチマン)」を、(2)と(3)という「(1)の頽落形態」を、(1)とひとまとめにすることで、「結局おまえらは、そういうダメな奴らなんだ」と批判したものでしかない、ということになるのである。
一一「子供が馬鹿なら、親も馬鹿に決まっている」あるいは「子供の犯罪は親の犯罪でもあり、同罪だ」という理屈だ。
たとえ子供が、親の教えに背いていたとしても、「血が繋がっているかぎり」は「同じだ」と、恣意的にひと括りにすることで、自分が(1)に太刀打ちできなかった過去に由来する「ルサンチマン」を、ここぞとばかりにぶつけているのだ。
だから、著者たちは本書でリベラルぶってはいるけれども、彼らの実際の態度は、決して「リベラリズム」のそれではなく、むしろ(2)や(3)にも似た、「実用実績主義的」な〈理論〉に近いものだと、そう感じられたので、私は著者を「似非リベラル」として批判するのである。
○ ○ ○
さて、このような、(1)ポストモダン思想理解や、(2)(3)の応用ポストモダニズムへの批判を、本書の整理に学ぶ前に、私が知らずに実践していた「ポストモダン」的な批判というのが、「トランスジェンダリズム(性自認至上主義)」問題における「推進派」と「反対派」の双方に対する、私の「両睨みの批判」であったと思う。
「トランスジェンダリズム」とは日本語で言えば「性自認至上主義」であり、「性自認」とは、文字どおり「性別に関する自己認識」のことである。
つまり「私は自分を、男だと感じている」とか「女だと感じている」とか「どちらでもない」とか「男の時もあれば、女の時もある」といった、当人の「実感的認識」のことだ。

それで、「トランスジェンダリズム=性自認至上主義」とは、要は「性別というのは、当人が感じているそれで良いじゃないか。何も、動物学的・解剖学的な差異を、男と女の区別とする必要はない」とする「自認主義」なのである。
当然、当たり前の人は「そうなった場合、外見や身体の構造では、男女の区別がつかないず、個々の主張を鵜呑みにしなければならなくなるが、それでは色々と不都合が出てくるのではないか」と考える。
例えば「体が男のままの自認が女である、トランス女性が女風呂に入ってきたら、多くの女性は困る(怖い)」などといった問題だ。
では、こうした「現実問題」に対して「トランスジェンダリズム=性自認至上主義」推進派は、どのように考えているのかというと、要は「現行の解剖学的性別というのは、所詮、人間が考え出した制度でしかなく、絶対的に存在するものではないのだから、それを社会構築的な幻想なのだと正しく理解し、問題のある今の幻想は、当然解除すべきだ。それでも私たちは、新たな、より正しい現実に慣れて、そのうち男女の外形的な区別なんか、髪の色と同様に気にならなくなるし、問題ではなくなる。だから、正しい認識に立った制度構築を実現して、それに慣れてください」ということなのだ。
だが、こうした「原理論」的な説明では、長らく「性別とは、解剖学的男女のこと」だと信じてきた人たちには、呑み込みにくいところであるし、最後まで呑み込み得ない人も多数出てくるだろう。
「だって、現実に、男女は違っているし、その違いを男女と呼んでいるのだから、それを無いと言われても、現実になるじゃないかとしか言えない」ということになるからだし、現にそうなって、トラブルにもなっている。
したがって、ここで「ジェンダー(性別・性区分)とは、フィクションに過ぎない。構築された制度のひとつに過ぎない」と考える「トランスジェンダリズム推進派」と、「いや、解剖学的な性別は、人間は無論、他の動物にもある事実だ」と考える「トランスジェンダリズム反対派」の、ほとんど解消し得ない対立が生じているのだ。
で、この問題に対する私の立場(考え方)というのは、「ジェンダーは、社会構築的なフィクションでしかない」と考える、という点では「推進派」と同じである。
ただし、私と「推進派」を絶対的に隔てるのは、私の場合は「ジェンダーは、社会構築的なフィクションであるとしても、多くの人には、それが現実としか感じられないのだし、そうした現実的なフィクションの上に、私たちは今の社会や文化を築いてきたのだから、その意味では、フィクションでしかない社会制度や文化もまた、一種の(二次的な)現実なのであり、それはそれとして尊重せざるを得ないものである。したがって、フイクションだから、さっさと取り払って、真理と取り替えてしまえば良いというような、簡単な話ではない」と、そう考える点だ。
つまり、私も「トランスジェンダリズム推進派」も、「解剖学的なジェンダー」というのは、「人間が選んだ、ひとつの制度であり取り決め」でしかないと考える点では一致しているのだ。「ひとまず、こういう線で区分したほうが、人間がこの世界の中で生きていくには便利だから、これで行こう」と決めた(実用的で好ましい解釈として採用した)ものでしかないのだが、それがいつの間にか「当たり前な現実(事実)」だと思い込まれるようになったものだ、という考え方なのである。
だが、問題はこの先で、「トランスジェンダリズム推進派」は、その「過渡的に採用された区分によって、男でも女でもないといった、曖昧な自認を持つ人たちは、出来損ない扱いにされ不当に差別されてきた。だから、その差別をなくすためには、解剖学的男女二元論を廃棄して、それぞれに自認を尊重すれば良いのだ」と、そう考える点である。

ある意味で、そのようにシンプルに考える彼らは「それはたしかに、制度変更の当初は、混乱や抵抗はあるだろう。しかし、それも慣れるまでの話でしかない。あなた(私・年間読書人)のように、じっくりと話し合い、理解を広めながら漸進的に変えていくというのは、たしかに話としてはわかるのだけれども、こうした抜本的変更というのは、決して容易には納得してもらえるようなことではないから、納得してもらってからと言っていたら、いつまで経っても制度変更は行えず、いつまで経ってもトランスジェンダーの人たちに堪えてもらわなければならないことになる。つまり、彼らにばかり負担を強いることになるのだから、やはりここは、多少の混乱や抵抗があったとしても、先に制度を改革して健全化し、その後で、みんなにそれに慣れてもらうという方向性しかない。まずは、弱者保護を優先すべきなのだ」と、このように考えるのである。
で、私が、この「制度改革を強行してから、みんなには慣れてもらう。そうすれば、これ以上、トランスジェンダーの人に苦痛を強いる必要はない」という、いかにももっともらしい考え方を批判する理由は、要は「男女二元論」というのが「社会構築的なフィクション」なのであれば、それに対応した「トランスジェンダー」という認識もまた「社会構築的なフィクション」だと考えるからなのである。
つまり、どちらも「フィクション」であって「現実」ではない。だから、どちらか一方が正しいのでも間違っているのでもないので、「正しい方に変えれば良い」という考え方は、根っこのところで間違っている、と考えるからである。
つまり、「トランスジェンダリズム推進派」の考え方が(3)的なものであるのに対し、私の考え方は(1)のポストモダン的にラディカルなのだ。
だから、(3)の考えは、程度の差こそあれ「世間一般」的に不徹底なものであり、「社会構築的な制度的幻想」に捉われたものでしかなく、彼らの主張は、無自覚にも「フィクションを別のフィクションに置き換える」ということでしかない、ということにしかならないのである。
そして私の考えでは、人間とは「フィクション無しでは生きられない動物」なのだから、「フィクション」を利用するのはやむ得ないとしても、ある「社会構築的なフィクション」を「別の社会構築的なフィクション」に置き換える場合には、どっちが「有効なフィクション」であるとは、簡単には見定められないのだから、しっかり話し合い、可能なかぎりの合意の得た上で「新しいフィクション」に置き換えるべきであると、そう考えるのである。
そうすれば、「みんなで話し合って、こっちの方がよりマシだろうと思って使ってみたけど、前の方が良かってね」という話にもなっても、「誰がこんなひどい制度を押し付けやがった」という「責任問題」による混乱と対立を無用にもたらし、遺恨を残すことにもならないだろうと、そういう考え方なのである。
私のこうした考え方は、具体的には「トランスジェンダリズム問題」を扱った、次のような書籍のレビューの中で、すでに展開されている。特に(3)『マテリアル・ガールズ』についての2本のレビューにおいてだ。
(1)アビゲイル・シュライアー『トランスジェンダーになりたい少女たち SNS・学校・医療が煽る流行の悲劇』
(2)斉藤佳苗『LGBT問題を考える 基礎知識から海外情勢まで』
(3)キャスリン・ストック『マテリアル・ガールズ フェミニズムにとって現実はなぜ重要か』
(5)女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会編『LGBT異論 キャンセル・カルチャー、トランスジェンダー論争、巨大利権の行方』
(6)笙野頼子『発禁小説集』、杉田俊介編著『対抗言論』Vol.3
以上のそれぞれのレビューでの、私の議論について簡単に紹介しておくと、次のようになる。
(1)は、「トランスジェンダリズム推進派」の強引なやり口を紹介しており、「推進派」のやり口を批判する著者に、私は同意している。
(2)は、著者・斉藤佳苗の属する「トランスジェンダリズム反対派」のやり口もまた、「推進派」並みの「一方的な理屈=敵の悪魔化」による批判でしかなかったため、私は両者を「馬鹿と阿呆の絡み合い」と批判した。
(3)は、本書は(2)の種本で、(2)の著者と同様に「反対派」の著者によるもので、本書著者は、「推進派」の依拠するジュディス・バトラーの思想を理解できないまま、「推進派」がそれに依拠しているからといって、党派的かつ安易にバトラー批判してしまっている。そこが問題なのだ。
しかしまた、バトラーを援用する「推進派」自身が、そもそもバトラーを正しく理解してはおらず、ただ単に、自分たちに都合の良い部分だけの「つまみ食い」しているに過ぎない。
これは、最初に説明した、「応用ポストモダン」派の「ポストモダン思想」の「悪用」と同様の態度だから、そういうインチキな「推進派」も批判されなければならない。
そんなわけで、「トランスジェンダリズム問題」については、その「推進派」も「反対派」も、ともにバトラーを正しく理解しようともしておらず、ただバトラーの権威を利用する「推進派」も、その利用されている権威を否定すれば相手も倒せると考えて、正確に理解しようともしないで批判する「反対派」も、どっちも「目先の党派的利益しか考えていない偽物(インチキ言説)だ」ということになるのである。
(4)は、両派の意見を集めた特集記事で、その個々について論評した。
(5)は、「反対派」の中では、比較的「リベラル」寄りに「穏健な立場」に経った「反対派」の論集である。
なぜそうなったのかといえば、この論集のメインとなる対談の対談者2名が、「トランスジェンダリズム推進」による直接的な被害からは距離のある「高齢男性」であったから、女性のアイデンティティ・ポリティクスにとらわれず、比較的客観的であり得たためであろう。
(6)は、「女は、事実として女であるから、女の存在を相対化して、女消し(メケシ)をたくらむトランスジェンダリズムなど、絶対に認められない」とする「ポストモダニズム完全否定派」の象徴ともいうべき小説家・笙野頼子の「功利主義パフォーマンス」を批判すると同時に、笙野頼子を批判して「虐げられた弱者としてのトランスジェンダーの支援者」である「アライ」を自認する文芸評論家・杉田俊介の、これまた「困難を引き受ける正義の味方」ぶった「自己美化的なパフォーマンス」をも批判した。
つまり、どっちも「党派的な実益狙いのパフォーマンス」ばかりで、誠実に問題の本質を考えようとはしていない、その「運動屋」性を批判したのである。

以上、このように私は、「トランスジェンダリズム」の「推進派」も「反対派」も、そのまま丸ごとでは支持していない。
では、どういう立場なのかというのは、すでに説明したとおり、「フィクションとしての男女二元論」を容易には替えがたい制度として前提し、その現体制に犠牲を強いられている「フィクションとしてのトランスジェンダー」に対する「手当て」をしながらの、漸進的な「男女二元論というフィクションの解体」という、理想的な方向性を堅持する、というようなことになる。
急進的なそれは弊害が多いから、現在の「急進的推進派」のやり方は認めず、「話し合いによる漸進的改革」を提案する、という立場だ。
言い換えれば、私は「ポストモダニズム」的に、「トランスジェンダリズム」の「推進派」も「反対派」も、どちらも基本的には「間違っている」と考えているのだ。
どちらも同じように「フィクションとしてのジェンダー」という「社会構築的な制度」を信じている。信じているからこそ、それを「保守」しようとしたり「改革・交換」しようとしたりするのだ。
だが、私からすれば、そしてジュディス・バトラーの立場からすれば、「トランスジェンダリズム反対派」とは、要は「フィクションとしての男女二元論的ジェンダー」にしがみついて「現実」を見ようとはしない(あるいは、理解する能力のない)「保守派」だし、「トランスジェンダリズム推進派」は「フィクションとしてのジェンダー」というもの重みを理解できないまま、それを「党派的に利用しているだけ」の、小狡い「党派利益主義者」にすぎない、ということになる。
つまり、彼らは全員、どちらも「フィクションとしてのジェンダー」とは何なのかということを理解していないし、真面目に考えようともしていないのだ。
それは、ジュディス・バトラーが『ジェンダー・トラブル』でも説明しているとおりで、そもそも「社会構築的なフィクション」というのは、何も「ジェンダー」に限ったことではないということを、彼らはわかっておらず、そこは無視して、自分たちの利害にかかわる「ジェンダー」ばかりを問題にしている点に明らかなのだ。
初期のホストモダニストや、その趣旨を理解した継承者であるバトラーなどは、私たちの「現実」とは「すべてフィクション」だと、正しく理解している。
例えば「善悪」。この世に「善悪」など、本当は存在しないのである。ただ、それを「あることにする」つまり、そのような「フィクションを設定」しないと、人間はバラバラになってしまい、他の動物の中で勝ち抜いていけないから、「効率よく生きていくために、そういうことにしておきましょう」というのが、「善悪」というフィクションなのである。
同じ意味で、人間が人間として生きていくためには、各種の「社会構築的フィクション」が必要なのであり、ここでいう「社会構築的」とは、「社会が構築するフィクション(制度)」という意味ではなく、「社会を構築するためのフィクション(理念)」という意味なのだが、それを「ポストモダニスト」以外には、誰もわかっていない。
「ポストモダニズム」的な発想を継承したつもりの「応用ポストモダニズム」の人たちも、それを批判している本書著者たちも、無論、世間一般も、私たちの「人間社会」は、「人間都合のフィクション」によって構築されたものなのだということが、全然わかっていないのである。
発達心理学が考えるように、本来の世界は、分割線を持たない無意味な混沌なのだが、生まれてきた子供は、まずそれを「快・不快」よって分割することで認識し、やがて「言葉」によって精緻な境界線を引くことで、多様な意味の塊りを作って、世界を意味あるものとして構築していく。
これは、他の生物でも、程度の差こそあれやっていることだけれども、しかし、その生態や能力に応じて、分割の精度や線引きの仕方が異なってくるから、見ている世界もおのずと違っており、どれが「正解の世界(ありのままの世界)」ということはないのである。
ところが、こうした「ポストモダニズム」的な、決定不可能な相対性ということを理解せず、いつでも多くの人は、「正解」があるかのように「勘違い」してしまう。
「現状が現実そのものだから、基本これで行くしかない」と考える、いわゆる現実主義のつもりである「現状(のフィクション)保守派」も、「社会構築的なフィクション」を打ち砕いて、より「真理に近い社会」を実現すべきと考えて、その「新しいフィクション」を「正義」の名の下に他人にも押しつけようとする「応用ポストモダニズム」の人々も、それぞれに、そもそも「人間の思考」自体が「社会構築的なフィクション」であり、ポストモダン的に言えば、「言説」の外側には出られないということを、わかっていないのだ。
だから、「嘘でも避けられない嘘なのであれば、嘘の中で、よりマシなものを無難に選ぶしかない」というのが、私の「ポストモダン的なリベラリズム」なのである。
だからこそ、本書著者の「呑気なリベラリズム賛美」には、「党派的な誇張」しか感じないのだし、実際、本書著者の一人である、ジェームズ・リンゼイは、その後、より「保守」化して、「陰謀論者」的になっていく。
なぜなら、本物の「リベラリズム」というものは、「理想とは、実現し得るものではなく、よりマシを目指すための目標であって、実在するものではない」といったものなのだが、(本書の最後の2章で)リベラリズムを観念的に美化してしまうようなリンゼイは、そうした「過酷な現実」を直視することが出来ず、わかりやすく友敵論(善悪二元論)的に見るしかなかったのである。
「応用ポストモダニズム」の強引さを批判するために、ことさらに「リベラリズム」を称揚して、まるで自らも「リベラリスト」であるかのように見せかけても、本書に示された「ポストモダニズムへのルサンチマン丸出しの文体」は、単に翻訳者である山形浩生の「個性」や「思想」であるばかりではなく、やはり著者自身が、翻訳者と共有する、「非リベラリズム」的な「不寛容とルサンチマン」を持っている証拠なのだ。
○ ○ ○
そんなわけで、〈社会正義〉は「いつも正しい」わけではなく、大いに間違っている。
看板である建前としての「弱者のため」というのはご立派なものだが、そのやり方には、はっきりとした「独善」が表れていて、とうてい信用できるような相手ではない。
だが、かと言って、それを批判している本書著者たちもまた、丸ごと信用することはできない。当然のことながら、著者たちもまた、自分たちのことを美化しているのであり、その飾り道具となっているのが「リベラリズムの理想」なのだ。
実際、本書著者らが、アラン・ソーカルによる「ソーカル事件」をそのまま真似て、まんまと「二匹目のドジョウ」を手にしたゲリラ的なやり口は、公正な議論を前提とする「リベラリズム」のものではなく、結果オーライで、左右どちらかに振れた、「過激派」的なものだというのは明らかなのだ。
「リベラリズム」が、「ポストモダニズム」から批判されたのも、それが「社会的なフィクション」として、実用される際には、当然のことながら「その理想どおりにはいかず、何かと問題を抱える」ものだからである。
そして、そのひとつの証拠が、リンゼイの「過激派」的な方向への変化だと言ってもいい。「リベラリズム」とは、そう簡単なものではないのだ。
そんなわけで、今となっては滅多にお目にかかれないものになったからこそ、「リベラリズム」は、本書の「結論」部分では美化されて語られている。
だが、それをそのまま、著者たちの立場であると考えるのは間違いで、それは著者たちに批判されている「応用ポストモダニズム」派の看板である「弱者・少数者に寄り添う」というのと同じくらいに、「実態を伴わない理想だからこそ、美しく語り得ているにすぎない」と考えるべきなのだ。
以上が、本書の内容に関するレビューである。
○ ○ ○
さて、ここからは、本書の内容が、北村紗衣とモロに関わってくる部分を紹介しておこう。
「武蔵大学の教授」でフェミニストを自称する北村紗衣は、「応用ポストモダニズム」の悪しき部分を、自覚的に利用しているというのが、ハッキリとわかるはずだ。
実際、本書を読んでいて「まんま、北村紗衣の話だな」と思わされる記述がいくつもあったのだが、ここではその典型的なものを紹介して、北村紗衣的フェミニズムの「問題点」を剔抉しておこう。
『『被害者文化の台頭』でキャンベルとマニングは時代や文化ごとの社会紛争解決の様式の変遷を述べる。人々がどうお互いにつきあい、そうした関係を道徳化し、世界での居場所を確立して、地位と正義を求めるやり方が書かれている。そして指摘するのが、最近の被害者文化の台頭だ。これは尊厳文化や名誉文化とはちがう。彼らによると、名誉文化では誰かからの支配も拒絶するのが重要だ。だから人々は侮辱にきわめて敏感だし、少しでも不敬だと思ったら、即座に腹を立てるか暴力にすら訴える。この種の文化では自足性(※ 自尊心・プライド)が中核的な価値となる。これは何百年も西洋世界を支配し、いまだに一部の非西洋文化や、西洋でも一部のサブカルチャー、例えばストリートギャングなどの間で根強い。それに取って代わったのが尊厳文化だ。尊厳文化も自足性を重視するが、ちがった形での回復力を奨励する。尊厳文化では、人々はほとんどの侮辱は無視すべきだと言われる。そして悪口や罵倒にはあまり反応せず、ほとんどの問題は個人同士で解決し、深刻な紛争は自分でケリをつけるよりも法的手段で(※ 客観的かつ合理的に)解決するように言われる。
キャンベルとマニングが見ている新しい被害者文化は、名誉文化の侮辱に対する敏感さを持つが、それに対して強さを示するより弱さをひけらかす。尊厳文化での、紛争解決(※ のよう)に自分でケリをつけようとはせず、当局に頼るやり方は維持しつつ、なるべく侮辱は無視するとか、まずは平和的解決を求めるといった部分(※ やり方)は捨て去る。被害者文化では、(※ 社会的に優位な)地位は被害者にされたと見られることで生じ、したがって、同情的な第三者からの支援を引き出せるようになる。結果として、それは他人の同情を買おうとし、その路線に沿って助けてくれと公に訴える。だから(※ 被害者文化を内面化した者は)多くの(※ 社会的な)相互作用(※ の中)に、権力不均衡と被害者性を読み取りがちになる一一ときには、それをでっち上げることもある。
(中略)
被害者性の称揚と、権力が(※ 女性や黒人、少数派などの非主流アイデンティティを)抑圧し周縁化する方法に(※ 批判的に)こだわる〈理論〉アプローチは、手に手を取って進んでいる。被害者は〈理論〉を掲げて、それを奉じる人々たちに対する(※ 特権的な)地位を獲得する。道徳的な狙いは、態度や言説に含まれる目に見えない危害形態から、周縁化された人々を守ることだ。そうした問題を見つけるためには、ルキアノフとハイトの指摘する大いなるウソ三つを通して社会を(※ 主観的に)読み取る必要がある。それ(※ 三つのウソが信じ込ませようとする悪意)に対処するためには、名誉文化の強さ称揚や尊厳文化の侮辱からの回復を捨て去り、キャンベルとマニングが被害者文化と呼んだものを受け容れねばならない(※ と主張されることになる)。』(P293〜294)
なお、ここで言う『ウソ三つ』とは、『人々が傷つきやすいという信念(つらさは、死ななくてもその分だけ人を弱くする)、感情的な理由づけへの信念(自分の気持ちに忠実に)、我々vsあいつらという念(人生はいい人と悪い連中との戦いだ)の三つ』(P293)という「主観的な根拠」のことだ。
少しわかりにくいが、要は「つらさは人を鍛える」とか「客観的な事実はどうか」とか「人間関係は、単純な善悪の二項対立ではない」などとは考えず、子供のように主観的に決めつけて良い、という考え方(ウソ)のことである。

ともあれ、この部分は、そう多くの説明を必要とはしないだろう。
ここで語られている「意見を異にする相手と直截に実力対決(論争)するのではなく、他所へ向けて、自身の弱者性・被害者性をアピールをして、同情を買うことで支援者を募り、その「数の力」で敵を袋叩きにする」という手法は、北村紗衣が「呉座勇一に関するオープンレターによるキャンセル」においてやったこと、そのままだからだ。
そして、このように「汚いやり方」が「得策」であると「学習」したので、以降、北村紗衣は、殊更に「悲劇のヒロイン」を演じることになるし、そのたびに、「全体観のない、頭の悪い人たち」が、それを鵜呑みにし、自身を「弱者の味方」だと思い込んで、北村紗衣のような、臆面もない「演技派」に加勢してしまうのである。
北村紗衣の自己喧伝としての「弱者性」や「被害者性」とは、前記のとおり、事実か否かに関係なく、いつでも「自己申告」的なものでしかない。
そうした「自認」を具体的に挙げれば、次のようなものがある。
(1)女性であること。
(2)発達障害であること。
(3)いじめ被害者であったこと。
(4)自殺を考えたことがあるということ。
(5)祖父が昔、治安維持法で逮捕された共産党員であったこと。
それぞれについて、簡単に説明しよう。
(1)北村紗衣の「フェミニスト批評」とか「フェミニズム批評」というのは、要は「男とは自明にミソジニー(女性蔑視・嫌悪)を持っており、そのために、すべての女性は今も不利益を被っている」というものであり、要は「女である自分は、男に対する場合にはいつでも被害者であるから、男であるという理由だけで、誰であろうと批判する権利を持つ」ということだ。
だが、言うまでもないことだが、世の中の「権力関係(権力勾配)」というのは、何も「男女関係」に限られるわけではない。例えば、「女性大学教授と無名の一般人男性」では、明らかに「女性大学教授の方が、社会的影響力(発言力)」において「権力」を持っている。また、北村紗衣のような「(日本)本土の女性」と「沖縄の女性」では、「米軍基地を沖縄に押しつけている」と事実において、北村紗衣は「権力」を行使している「加害者たる本土人」の一人であると言えるだろう。
このように、「女性」だからといって、必ずしも「被害者」ではなく、時と場合によって、その状況に関わる「他の属性」をも勘案しなければ、どちらが「被害者か加害者」かは、いちがいには判別できないのである。
(2)発達障害は「特質」であって、必ずしも「弱者性」でも「被害者性」は意味しない。
発達障害者は、時に、そうでない者よりも、ある種の優れた能力を発揮するし、北村紗衣自身、自身の事務能力の高さを語っている。
「被害者性」については、例えば、発達障害を理由にいじめを受ければ「被害者」になるが、いじめを受けなければ被害者にはならず、むしろ逆に発達障害による不規則行動などによって、一方的に迷惑をかけられた人がいれば、それはそちらが被害者である。無論、この場合の発達障害者は、犯意(故意)が無いという事実において「犯罪者」ではないが、他者に「害を与えている」という「事実」は消えず、それへの対処が求められることにもなる。

(3)いじめ被害者は、被害者である。ただし、北村紗衣の場合は、始終「いじめ加害者」になっているし、しかもそれは、自分一人の言動によるだけではなく、インフルエンサーとしての影響力を行使し、取り巻きやファンを「ファンネル・オフェンス」として使役するという、完全に自覚的「加害者」であることが、しばしばある。
(4)40代にもなってから今更のように「自殺を考えたことがある」などと、わざわざ公に向けてうち明けるのは、新刊『女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選』(2024年11月刊行)を刊行するにあたっての布石であり、この「バズるタイトル」の正当化にしか見えない。
また同時に、「弱者性」の自己アピールによって同情を惹き、信じやすい支援者を集めるための、いつもの手でもあろう。
(5)これは北村紗衣当人の話ではないが、「祖父が治安維持法で逮捕されたことのある共産党員」だというのは、暗に、その孫の自分も「国家権力」から狙われている「被害者」だというアピールであり、実際、北村紗衣は「警察」嫌いを公言している。
しかし、それでいて、「裁判所」という国家機関に頼って「名誉毀損賠償裁判」を提起するのは、ご都合主義的な「国家機関利用」でしかなく、本気で自分の対国家的被害者性を信じているわけではない証拠でもあろう。
また、このように「共産党」性をアピールするからこそ、山内雁琳に対する「賠償訴訟」においては、「共産党系弁護士8人による弁護団」を組むなどという、贅沢なことも可能となる。
要は、節操なく、利用できるものは何でも利用するというのが、北村紗衣の基本スタンスなのだ。
このように、北村紗衣は「被害者性」や「弱者性」をアピールすることで、同じように、自身の「被害者性」や「弱者性」を認めてほしいと願う人たちを惹き寄せ、多分に主観的・願望的なものでしかない「被害者同盟・弱者同盟」を組織して、その「数の力」で、主観的に「強者」認定した「たった一人」を袋叩きにするための「正当性」を担保しようとするのだ。
『(承前) 多くの点で、西洋の大半で起きているこの被害者文化と甘やかしを見れば、社会正義(本当の意味でのもの)のアクティビズムは自分の成功のために自縄自縛に陥った(※ 弱者を助け、減したつもりで、自称弱者を大いに増やした)のではないかと思われる。マイクロアグレッション(※ 故意や悪気なく、結果として他者を傷つける言動)だの、他人への代名詞をまちがえる(彼/彼女はジェンダーを決めつける抑圧的な代名詞で、その人の選んだ新造の代名詞でその人を呼ばねばならないという発想)だのにばかりこだわる人は、本当に心配すべき現実の問題がないだけなんだ、という糾弾を(※ 彼らに向けて)する人は、こうした問題がどれほど本当に苦痛として体験されているかを軽視している(※ と、彼らは自ら主張する)((※ たしかに)ルキアノフとハイトが示すように、若者の自殺は増えている。とはいえ、この増加の原因は(※ 主観的弱者として傷つきやすい人が増えたということだけではなく)もっと複雑(※ な要因を持つの)かもしれないが)。しかし一見ちょっとした社会上の悪口や、気に入らない思想や態度について心配できる社会というのは、その成員のほとんどが、おそらくは直接的に命に関わる状況に置かれていない社会だとは言える。
(※ 例えば)被害妄想じみた育児と「安全偏重」の議論で、ルキアノフとハイトは親たちがしばしば、ジフテリアやポリオといった致死性の病気根絶や、危険な製品や活動の減少を喜ほうとしない点を指摘する。こうした改善で子供の死亡率は減したというのに。かわりに不安な親たちは、いまだに潜在的には危険かもしれない(※ と、極めて主観的に、瑣末な)どうでもいいことにこだわる。さらに力点は、肉体的な危害から心理的な不快感にシフトし、「感情的安全性」の期待が生み出された(※「安全」ではなく「安心安全」まで求める)。同様にキャンベルとマニングは、人々はどうも、人種差別と偏見の証拠を探そうとするときに、それが最も見あたらない場所を(※ 疑心暗鬼的に)探そうとするようだと指摘する。
(※ 以下の太字は、キャンベル&マニング『被害者文化の台頭』からの引用文)
私たちが連想したのは、一九世紀のフランスの社会学者エミール・デュルケムだった。彼は読者に「聖人の社会」では何が起きるか想像してみてくれと述べた。答は、それでも世界に罪人は残るというものだ。というのも「素人ならどうでもいいと思える失点」がそこでは大騒ぎになるからだ。(※ 本書著者による引用終わり)
私たちは、〈社会正義〉の文脈内で、ポストモダン思想の発達について似たような議論をした。〈社会正義〉は、人種差別、性差別、ホモフォビア的な態度や言説に注目して大騒ぎするが、それが起きたのはまさに、そうした態度や言説が激減した時期だった。応用ポストモダン転回が起きたのは一九八〇年代末、まさに公民権運動、リベラル・フェミニズム、ゲイプライドのおかげで二〇年にわたり、驚くほど急速に人種、ジェンダー、LGBTの平等性が法、政治面で進んだあとで、もはやあまりやることが残っていない状態になった頃だったのは偶然ではない。黒人差別法が解体し、帝国が崩壊して、男性の同性愛が合法となり、人種と性別に基づく差別が犯罪となったので、西洋社会はあらためて、周縁化された集団に対する長い抑圧の歴史に気づかされて恥ずかしく思い、そうしたまちがいを正し続けたいと考えた。最も重要な法的戦いはすでに勝利に終わっていたから、取り組む対象として残っていたのは、性差別、人種差別、ホモフォビア的な(※ 日常的に細かな)態度や言説だけだった。ポストモダニズムは、権力の言説と社会構築による知識に注目していたので、それ(※ 当たり前のことを当たり前で済まさない)に取り組む絶好の立場にあった。
だが人種差別、性差別、ホモフォビアはその後も減少を続けたので、それを検出するためには、状況やテクストのさらなる深読みと、ますますややこしい〈理論的〉な議論が必要になってきた。〈社会正義〉アプローチで見られる、ますますこじつけめいた言説の〈理論〉分析は、社会的不公正激減の直接の反映(※ 差別が減って暇になったおかげ)なのだ。』
(P295〜296、※は引用者による補足)
ここも、文中に挟んだ補足文で、おおむねご理解いただけると思う。
著者たちがここで言いたいのは、要は『公民権運動、リベラル・フェミニズム、ゲイプライドのおかげで』ハッキリとした差別が激減して、安心できるようになった後で、初めて、「正義派」ぶった〈社会正義〉グループが登場して、その「差別は、あらゆるところに隠されている」という〈理論〉を掲げ、安心して「あら探し」を始めたのだ、ということである。

そして、そうした不寛容な「(あら探しの)やり過ぎ」のために、私たちの生活は、無意味に窮屈になってしまったとして、著者たちは、〈社会正義〉派が、それまでの「リベラル」による「対差別」行動による実績を簒奪したと、批判しているのだ。
一一平たく言えば、「おまえらが差別を減らしたのではなく、ほとんど差別がなくなった後にしゃしゃり出てきて、大きな反発もない中を安心して、どうでもいいあら探しをし、それで、これ見よがしに、やってますアピールをしているだけだ」と言っているのだ。
さらに平たく言えば、〈社会正義〉のやっていることとは、先人が一生懸命に掃除をした後からやってきて、障子の桟のホコリを見つけて「まだまだ不十分だな」などと上から目線で言うのと、似たようなことをやっているだけだと、そう批判しているのである。
つまり、北村紗衣のやっている、「映画」作品などに対する「フェミニズム批評」というのは、所詮この類いの「男性を批判するための、為にするあら探し」でしかないから、多くの人が「つまらない」と感じるし、また、北村紗衣にはそれしかできないから、「ワンパターン」の「ワン・トリック・ポニー(一つ芸の仔馬)」だと言われるのである。
こういうのもある。
『 最も重要な点かもしれないが、クィア〈理論〉は先行するリベラル・フェミニズムやLGBTアクティビズムと根本的に異なる。異性愛者やジェンダー・コンフォーミングでない(※ 従来の、男女二元論的なジェンダーに準拠しない、少数派の)人々を解放する唯一の方法がクィア〈理論〉だという主張は、それ以前や以降の普遍的でリベラルなアプローチの成功を見ればまちがっているのがわかる。〈理論〉以前のリベラル・アクティビズムと思考は、私たちに共通する多くの特徴と共有された人間性、そして普遍的なリベラル原理に訴えることで、特定の性、ジェンダー、セクシュアリティの人々への偏見を持った態度を変えようとした。トランス・アクティビズムだって、トランス問題をめぐる科学の発展に伴って、こうした面に焦点をあてることはできたはずだ一一クィア〈理論〉が積極的に普遍的や規範的なものをすべて打破しようなどとしていなければ(※ 要は、クィア理論は、リベラリズムの「同じ人間じゃないか」という「思いやり」を不可能にした)。
ところがクイア〈理論〉は一一(※ それまでの方法をダメにしたわりには)まったく役立たずなことに一一性、ジェンダー、セクシュアリティの概念そのものを修正または解体させようとするので、変えようとしている当の社会の人々の大半には不可解で(※ 意味不明な戯言として)どうでもいいものに思われてしまい、ヘタをするとそうした人々から積極的に敬遠されてしまいがちだ。クイア〈理論〉に依拠したクイア活動家たちは、(※ 自分たちの見方が絶対に正しいという)異様なほどの傲慢さと攻撃性一一ほとんどの人にとって容認しがたい態度一一で活動しがちで、しかも特に標準的セクシュアリティとジェンダーを嘲り、それ(※ その無作法と傲慢さ)を指摘する人々を後進的で(※ そっちこそが)無作法だと言いつのる。人は一般に自分の性、ジェンダー、セクシュアリティ(※ などの自認)が本物ではないとか、まちがっているとか、よくないものだと言われるのを快く思わない一一これはクィア〈理論家〉たちが誰よりもわかっているはずのことなのだが。』(P137〜138)
この部分が、北村紗衣にどう関係してくるのかというと、私は北村紗衣の「フェミニズム批評」は、「対象の中に、無理にでも男の差別意識を見つけるだけのワンパターン」でしかなく、「そのほかといえば、せいぜいクィア批評などに言及するが、それも腐女子的な視点から男性同士のイチャイチャ関係を妄想する程度のものでしかない」と指摘してきたのだが、ここで、どうして北村紗衣が、本格的な「クィア理論」の紹介をしないのかと言えば、単にそれをよく知らないというのではなく、クィア理論を正確に紹介してしまうと、北村紗衣の依って立つところの「ジェンダーにおける男女二元論」が、クィア理論によって相対化されてしまい、「被害者である女性の立場から、自明な加害者だと決めつけた男性を、問答無用に批判する」ということが出来なくなってしまうから、ということなのであろう。
つまり、北村紗衣のような「古くさいフェミニズム」の「古くささ」とは、自分の「弱者としての優位なポジション」を揺るがさないように、「ポストモダン」的な「クィア理論」は拒絶するということなのである。
要は、「真実とは何なのか」という本質問題には興味がなく、「どういう考え方を採れば、自分が得なのか」しか考えていない、ということなのだ。
したがって、北村紗衣の「フェミニズム」というのは、「応用ポストモダニズムの展開」のひとつらしく、「自分に都合のよい部分だけを切り取って利用するだけで、主張の一貫性など気にしない」ものなのだ。
「男たちの言動については、過剰解釈的なまでに深読みをして(あら探しして)注文をつける」のに、「自分の言動」については「私は弱者で被害者だから」と「自己免責」してしまっている、ということなのである。
一一まったく、「北村紗衣のフェミニズム」とは、斯くも幼稚かつアホくさい「頽落したフェミニズム(の残骸)」だと、そう呼ぶべきものなのだ。
○ ○ ○
そんなわけで、本書は、昨今流行りの「正義の味方ぶったあら探し」が「どこから来て、何をしているのか」ということを、よく説明してくれている。
著者自身の「弱点」としての「ポストモダニズムに対する無理解と、それに由来する認知の歪み」はあるにせよ、いろいろと教えられるところがあって、とても面白く勉強にもなった。
本書の内容を「鵜呑みにしてはいけない」が、「わかりやすい参考書」としては、強くお薦めしておきたいと思う。
(2024年12月11日)
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
