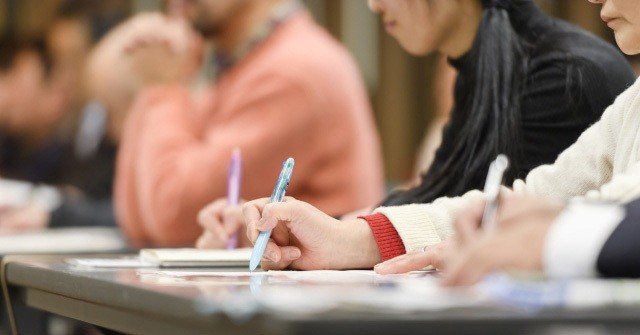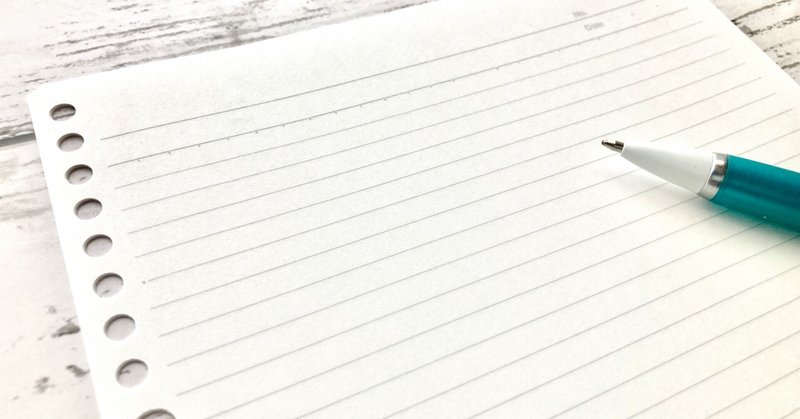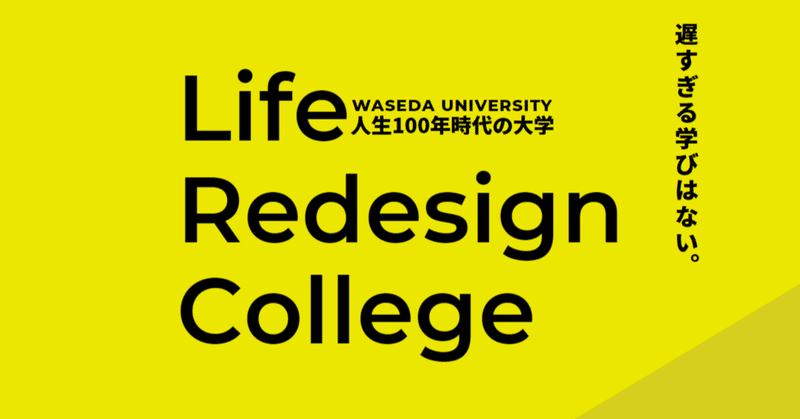#生涯教育
歴史的な転換点となるのか?通信制大学の在り方を根本から変える、ZEN大学と京都芸術大学のチャレンジ
どのような大学や学部の設置認可の申請が出されているのかを見ると、その時々の大学業界や世の中の動きが見えてきます。次年度設置の新学部関連でいうと、工学系の学部設置の動きが加速しており、あと以前このnoteでも取り上げた福井県立大学の恐竜学部が話題です。
一方、新設の大学関連でいうと「通信制大学」が注目すべきトピックのように思います。しかもこれ、単に大学数が増えるだけじゃなく、在り方そのものも大きく
知ることって楽しい!を、もっと手軽に体験!「フクロウナビ」新機能&新企画追加のお知らせ
2022年末に立ち上げた大学や研究機関の学術・研究系コンテンツを紹介するナビサイト「フクロウナビ」を、このたびちょっとだけリニューアルしました。今回は、こちらについご紹介させてもらいます。
大学や研究機関のコンテンツを横断して紹介するナビサイト
そもそもフクロウナビってナニ?という人もたくさんいると思いますので、まず簡単に説明をさせてもらいます。
多くの大学や研究機関は、研究者や研究成果、学
生涯学習どころか大学の学び全体を底上げする?佛教大学が取り組む、公開講座の学習履歴可視化の意義を考える
ここ最近の学び直し関連では、リスキリングが注目されているものの、生きがいとしての学びも、平均寿命が伸びている日本社会にとっては非常に重要です。今回、見つけた佛教大学の取り組みは、この生きがいとしての学びを活性化させる有効な一手になりそうなうえ、大学教育とは何かを考える良いきっかにもなりそうだと感じました。
公開講座のジレンマを学習履歴の可視化が救う?
プレスリリースの内容は、佛教大学オープンラ
自由だけど縛りもある。早稲田が新たに取り組むシニア向け教育は、生涯教育の”雛形”を作り出せるか。
「人生100年時代」の学びはどうあるべきかは、今後さらに加熱していくテーマです。今回、目に止まったのは、早稲田大学の社会に向けた教育拠点「WASEDA NEO」の新たなシニア向け教育プログラム。この教育プログラムを見ていると、やはりというか、18歳に向けた教育と根っこのところから違うものなのだと、あらためて実感しました。
取り上げるのは、50歳以上のプレシニア・シニア世代向け講座「早稲田Life
狙い目は「リカレント教育」と「生涯教育」の真ん中あたり?これから求められる、スキルではなく、楽しみながら知的体力を身につける社会人講座。
先月、APU学長の出口治明先生のリカレント教育についての動画が、文部科学省の公式Youtubeチャンネルに掲載されました。見よう見ようと思いながら、ずっと見られていなくて(12分程度の動画なのに!!)、やっと拝見させてもらいました。
動画内容は、出口先生らしく、エビデンスに基づいた内容で、とても説得力がありました。なかでも、日本とドイツやフランスとでは、年間労働日数を200日で考えると1日あたり
大学の在り方を根本から変える! 大学4年間を“学び続けるための最初の4年間”だと捉え直す。
大学関連の仕事をしているとリカレント教育の重要性が年々高まっているのを感じます。18歳人口が減る大学にとって、社会人学生は新たな財源になるし、国はできるだけ多くの人に効率よく働いてもらいたい。人材が流動化し、実力主義になってきている世の風潮とも合致している。すべての思惑が合っているんだから、そりゃあ重要だと、みんなが言うのも頷けます。
でも、これだけ求められているのに、リカレント教育が盛り上がっ